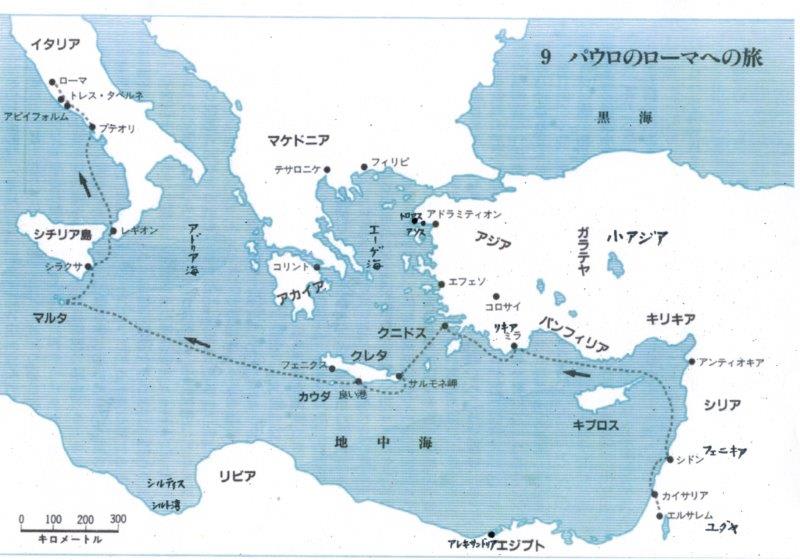2021/8/1 ローマ人への手紙12章1-2節「ともに喜びともに泣く 一書説教 ローマ書」[1]
新約聖書六巻目のローマ人への手紙は、16章ある長い手紙です。一度読んだだけでは分からなくても、多くの忘れがたい言葉が鏤められているのもローマ書です。私も、8章の終わりは葬儀で読んでもらいたい箇所[2]。この12章1、2節は神学校で学ぶ時に大いに励まされた言葉です。勿論、私だけでなく、全てのキリスト者がこう言われています。
12:1ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。…
この「ですから」はローマ書の大きな鍵です。ここまでの全ての内容、11章まで語ってきた言葉をすべてぎゅっと詰め込んでの「ですから」なのです。ここまで長く語ってきたのは、主の一方的なあわれみですから、勧めはとてもまれでした。ここからはそのあわれみを踏まえて、神に自分を捧げた生き方、神の恵みに溢れた生き方を畳みかけて語ります。その流れで5節、
大勢いる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、一人ひとりは互いに器官なのです。
と語って、互いにキリストにある体の器官として助け合いなさい、という勧めが、この手紙の最後まで続きます。
ですから大雑把に分けると、ローマ書は11章までが神のあわれみ、キリストの福音について教え、12章からがキリスト者の生き方についての勧めだと言えます。
ところで、14章15章で語られるのは「信仰の弱い人を受け入れなさい」「力のない人たちの弱さを担うべき」だという勧めです。具体的には、何を食べても良いと思う人と、野菜しか食べない人、ある日を別の日よりも大事と考える人と、どの日も大事だと考える人。これは「例えばの話」というより、実際にそうした分断がローマの教会で大きな問題だったのです。当時の各地の教会も、伝統的な聖書の律法文化に生きていたユダヤ人と、聖書を全く知らない異邦人の摩擦が続いていました。お互いに、律法主義だ、自由すぎる、と対立していた。その事をパウロも伝え聞いて、心を痛めながら、今出来る事として執筆したのがローマ人への手紙です。
この対立や分断こそ、パウロが長い手紙を書いて取り扱い、福音を知ってほしかった事です。その具体的な不和を扱うに当たって、前半11章もかけて福音を辿り直したのです。福音は、ユダヤ人もギリシア人も、信じるすべての人に救いをもたらす神の力だ[3]。ユダヤ人もギリシア人も、すべての人が罪の下にある[4]。ユダヤ人が異邦人をさばくことは出来ない[5]。この罪の徹底ぶりと、それに勝るキリストの贖いを「異邦人」を29回も繰り返してずっと語るのです。
すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリスト・イエスにある贖いを通して、価なしに義と認められるからです。[6]
これは本当に私たちの高慢を打ち砕く事実であり、絶望を喜びへと変える福音です[7]。この神のあわれみは、ユダヤ人もギリシア人も、どんな人も等しく大きく包んでいます。キリストのあわれみの中に、私たちすべてがあるのです。それが、福音がもたらす光です。
ローマの教会は分裂や裁き合う問題がありました。それはローマ教会だけでなく、この世界の誰もが苦しんでいる現実です。神から離れ、神ならぬ何か、人に分裂をもたらすか、分断の傷を癒やすことが出来ない、何か神ならぬものを礼拝しているための現実です。そこにキリストが来て下さいました。そして私たちのためにいのちを捧げて、私たちを生かしてくださいました。それは、神が私の罪を赦す(=怒らない?)だけではなく、私たちが生き方丸ごと、神への聖なるささげ物として献げる、新しい生き方を始めて下さったことです。
福音は、罪の赦しだけでなく、私たちを新しくしてくれる、神のあわれみです。ローマ書の1~11章が福音の教理で、12章からは生活、という分け方よりも、1章から最後までが福音の教理であり、私たちの生活の土台である神のあわれみを教えています。私たちが自分たちの罪を告白し、キリストを信じる信仰に立つことは、私たちと神との関係だけでなく、私たちの生き方を強めます。問題の絶えない現実で生きることへと力づけてくれます。ユダヤ人とギリシア人、教会の内外の違いや分断、人間関係のさばき合いや批判を、ローマ書は取り扱って、私たちに、謙りと希望を与えてくれます。お互いに認め合い、尊重し合う関係へと招く[8]。そういう福音を見せてくれるのです。[9]
一章に
「福音は信じるすべての人に救いを得させる神の力」
とあります。パウロも
「私があなたがたに会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなたがたを強くしたいからです」
と語っています[10]。そして結びの祈りでも神を
「あなたがたを強くしてくださる方」
と呼んでいます[11]。神は、私たちを強くしてくださる方。
それは私たちが、罪を犯さなくなり、正しく生き、正しくない相手を打ち負かせるという強さではありません。むしろ、7章でパウロは自分の葛藤、無力さを赤裸々に言い表しています。そんな正直で謙虚な告白が出来る力です。罪を認める力と、罪の赦しと希望に大喜びする力。自分と考えの違う相手をも認められる力です。復讐を主に委ねられる力です。違いはあっても、霊的な成長を追い求める力です。そして、その中にある最も美しい言葉の一つが、あの
「喜んでいる者たちとともに喜び、泣いている者たちともに泣きなさい」
でしょう。意見が違っても互いの喜びを(水を差さずに)喜び、互いの悲しみを(つけ込んだりせずに)共に泣く。そう変えていただくのです。
福音は私たちの魂の救いだけでなく、私たちの生き方を救い、さばきや争い、内にこもった思いから、神との深い平和を持って生かす力です[12]。ですから「私をお献げします。どうぞ強めて下さい」とその力を求めて祈りましょう。
「どうか、希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であなたがたを満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。どうか、平和の神が、あなたがたすべてとともにいてくださいますように。平和の神は、速やかに、あなたがたの足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか、私たちの主イエスの恵みが、あなたがたとともにありますように。(15:13、33、16:20) 私の福音、すなわち、イエス・キリストを伝える宣教によって、また、世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって──永遠の神の命令にしたがい、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを強くすることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、栄光がとこしえまでありますように。アーメン(16:25~27)」
ローマ書の有名な言葉集(抄)[13]
参考資料:
大竹護「ローマ書~確信していること~」四日市キリスト教会
聖書プロジェクト ローマ人への手紙1と2
脚注:
[1] 久しぶりの「一書説教」です。これまで「聖書同盟」の「聖書通読表」に沿って、テキストとなる書を選んできましたが、8月の「使徒の働き」も「Ⅱ歴代誌」も既にお話ししていますので、9月の「ローマ人への手紙」からお話しします。https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=q0c9b319jurffiu1s6lb5mcid4@group.calendar.google.com
[2] ローマ書8章31~39節「では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに敵対できるでしょう。32私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして、御子とともにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。33だれが、神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。34だれが、私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリスト・イエスが、神の右の座に着き、しかも私たちのために、とりなしていてくださるのです。35だれが、私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。36こう書かれています。「あなたのために、私たちは休みなく殺され、屠られる羊と見なされています。」37しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。38私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、39高いところにあるものも、深いところにあるものも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。」 この箇所についての詳しい説教を友人がしていました。http://www.logos-ministries.org/new_b/rm8_31-39.pdf
[3] ローマ書1章16節「私は福音を恥としません。福音は、ユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。」
[4] 3章9節「では、どうなのでしょう。私たちにすぐれているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も、すべての人が罪の下にあるからです。」。また、2章9~10節(悪を行うすべての者の上には、ユダヤ人をはじめギリシア人にも、苦難と苦悩が下り、10善を行うすべての者には、ユダヤ人をはじめギリシア人にも、栄光と誉れと平和が与えられます。)、10章12節(ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。)も参照。
[5] 2章1節「ですから、すべて他人をさばく者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人をさばくことで、自分自身にさばきを下しています。さばくあなたが同じことを行っているからです。」
[7] パウロは5章まで命令や勧めを一言も語りません。6章の11節で、初めて、「同じように、あなたがたもキリスト・イエスにあって、自分は罪に対して死んだ者であり、神に対して生きている者だと、認めなさい。」と命令形が出て来ます。しかもこれも「何かをしなさい」というより「あなたが何をしようとしまいと関係なく、既に自分が罪の下ではなく、神との関係に活かされている事実に立ちなさい」という勧めですね。そして、その後に、「12ですから、あなたがたの死ぬべきからだを罪に支配させて、からだの欲望に従ってはいけません。13また、あなたがたの手足を不義の道具として罪に献げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされた者としてあなたがた自身を神に献げ、また、あなたがたの手足を義の道具として神に献げなさい。14罪があなたがたを支配することはないからです。あなたがたは律法の下にではなく、恵みの下にあるのです。」と「からだ」を献げるメッセージが続きます。これが12章1節でもう一度繰り返され「あなたがたのからだを神に喜ばれる生きた聖なるささげ物として献げなさい」と言われ、12章以下15章まで膨らまされていくのです。
[8] 14章19節「私たちは、平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。」は、すばらしい勧めです。
[9] ここに、今日の説教題ともした「喜んでいる者たちとともに喜び、泣いている者たちとともに泣きなさい」や「自分で復讐してはいけません。神の怒りにゆだねなさい」などの言葉が出て来ます(ローマ書12章15節、19、21節)。また、13章では「上に立つ権威」に対しての態度が教えられます。
[10] 1章11節「私があなたがたに会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなたがたを強くしたいからです。」
[11] 16章25~27節〔私の福音、すなわち、イエス・キリストを伝える宣教によって、また、世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって──26永遠の神の命令にしたがい、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを強くすることができる方、27知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、栄光がとこしえまでありますように。アーメン〕 この部分が〔〕で括られているのは、欄外注にもあるように、この節を欠いた写本が多くあるからですが、本節がある写本が多数ですから、パウロの書いた言葉であると考えて良いと判断します。
[12] パウロが示す福音は、罪の赦しだけでなく、苦難さえ喜び、希望を与える大きなもの。これを引き下ろしてしまうと、神の恵みが見えなくなる。倫理も、自分たちに出来る程度に引き下ろして、「~しなければならない」にゴール設定をしてしまうと、途方もないビジョンが見えなくなる。パウロは、アダムの罪を償って余りあるキリスト(第二のアダム)の恵みを歌い上げている。
[13] 有名なことば:
1:16「私は福音を恥としません。福音は、ユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。」
2:1「ですから、すべて他人をさばく者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人をさばくことで、自分自身にさばきを下しています。さばくあなたが同じことを行っているからです。」
3:23「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、24神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いを通して、価なしに義と認められるからです。」
4:25「主イエスは、私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられました。」
5:1「こうして、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。2このキリストによって私たちは、信仰によって、居間立っているこの恵みに導き入れられました。そして、神の栄光にあずかる望みを喜んでいます。3それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは、苦難が忍耐を生み出し、4忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、私たちは知っているからです。5この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。6実にキリストは、私たちがまだ弱かったころ、定められた時に、不敬虔な者たちのために死んでくださいました。7正しい人のためであっても、死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。8しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。」
5:19 すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。20律法が入って来たのは、違反が増し加わるためでした。しかし、罪の増し加わるところに、恵みも満ちあふれました。21 それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠のいのちに導くためなのです。
6:3 それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受けた私たちはみな、その死にあずかるバプテスマを受けたのではありませんか。4私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによって、キリストとともに葬られたのです。それは、ちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも、新しいいのちに歩むためです。
6:11 同じように、あなたがたもキリスト・イエスにあって、自分は罪に対して死んだ者であり、神に対して生きている者だと、認めなさい。12ですから、あなたがたの死ぬべきからだを罪に支配させて、からだの欲望に従ってはいけません。13 また、あなたがたの手足を不義の道具として罪に献げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされた者としてあなたがた自身を神に献げ、また、あなたがたの手足を義の道具として神に献げなさい。14 罪があなたがたを支配することはないからです。あなたがたは律法の下にではなく、恵みの下にあるのです。
6:23「罪の報酬は死です。しかし神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。」
7:15「私には、自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。16自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。17ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。18私は、自分のうちに、すなわち、自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。19私は、したいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。」
8:1「こういうわけで、今や、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。2なぜなら、キリスト・イエスにあるいのちの御霊の律法が、罪と死の律法からあなたを解放したからです。3肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を、罪深い肉と同じような形で、罪のきよめのために遣わし、肉において罪を処罰されたのです。」 8章は、宝のような言葉が鏤められている。
9:16「ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、あわれんでくださる神によるのです。」
10:2「私は、彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。3彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして、神の義に従わなかったのです。4 律法が目指すものはキリストです。それで、義は信じる者すべてに与えられるのです。5 モーセは、律法による義について、「律法の掟を行う人は、その掟によって生きる」と書いています。6 しかし、信仰による義はこう言います。「あなたは心の中で、『だれが天に上るのか』と言ってはならない。」それはキリストを引き降ろすことです。7また、「『だれが深みに下るのか』と言ってはならない。」それはキリストを死者の中から引き上げることです。8では、何と言っていますか。「みことばは、あなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。」これは、私たちが宣べ伝えている信仰のことばのことです。9 なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。10人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。」
11:27 これこそ、彼らと結ぶわたしの契約、すなわち、わたしが彼らの罪を取り除く時である」と書いてあるとおりです。28彼らは、福音に関して言えば、あなたがたのゆえに、神に敵対している者ですが、選びに関して言えば、父祖たちのゆえに、神に愛されている者です。29神の賜物と召命は、取り消されることがないからです。30あなたがたは、かつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに、あわれみを受けています。31 それと同じように、彼らも今は、あなたがたの受けたあわれみのゆえに不従順になっていますが、それは、彼ら自身も今あわれみを受けるためです。32神は、すべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人をあわれむためだったのです。
12:9 愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。
12:10 兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手をすぐれた者として尊敬し合いなさい。
12:11 勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。
12:12 望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。
12:13 聖徒たちの必要をともに満たし、努めて人をもてなしなさい。
12:14 あなたがたを迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。
12:15 喜んでいる者たちとともに喜び、泣いている者たちとともに泣きなさい。
12:16 互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のある者と考えてはいけません。
12:17 だれに対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。
12:18 自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。
12:19 愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りにゆだねなさい。こう書かれているからです。「復讐はわたしのもの。わたしが報復する。」主はそう言われます。21 悪に負けてはいけません。むしろ、善をもって悪に打ち勝ちなさい。
13:8 だれに対しても、何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は、律法の要求を満たしているのです。9 「姦淫してはならない。殺してはならない。盗んではならない。隣人のものを欲してはならない」という戒め、またほかのどんな戒めであっても、それらは、「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」ということばに要約されるからです。10 愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ、愛は律法の要求を満たすものです。
14:1 信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見をさばいてはいけません。
14:6 特定の日を尊ぶ人は、主のために尊んでいます。食べる人は、主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。
14:8 私たちは、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものです。
15:1 私たち力のある者たちは、力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。2 私たちは一人ひとり、霊的な成長のため、益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。