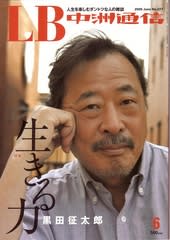歴史はブームの積み重ねである。そして、そのブームの度に「時代は変わる」。特にポップ・ミュージックの世界は常にブームの繰り返しであったといえる。しかしポップ・ミュージック史に残るような仕事(ブーム)をなし得たミュージシャンは数えるほどで、ブームでさえ2年、3年も続くものは数少ない。史上に残る多くの“革命”は1年、短いもので数ヶ月で起こっている。それはおそらく海外でも変わらないことだろう。
ビートルズの登場以降、わずか10年ほどの歴史しか持たない“ロック”というポップ・ミュージック革命は、70年代初頭のニューヨーク、そして中頃のイギリスで起こったパンク・ムーブメント、ニューウエイブという形で再び大変動を起こした。音楽に、鑑賞音楽以上の意味合いを持たせた“ロック”の存在意義そのものがポップ・ミュージックの永久革命を指していたのだから、わずか10年程度であっても、過去の遺物は否定されてしまうのは、また当然なのだ。
日本にも同じような、小さなブームが起こった。それを「東京ロッカーズ」と呼ぶ。グループ・サウンズという日本のロック創世記を経て、70年代前半の日本のロックは極めてアンダー・グラウンドなものだった。歌謡曲が黄金時代を迎え、60年代末のフォーク・ソングが時代を経てポップスとして、ビジネスとして成立した時代である。そんな時代に永久革命を続ける“ロック”が日本のオーバー・グラウンドで受け入れられるわけがない。日本のロックは地下に潜り、海外の「革命」にビビッドに反応しながら小さな爆発を繰り返すしかなかった。
そして、その爆発のひとつが1978年に東京・下北沢などのエリアで行われていたライブ・シリーズ「東京ロッカーズ」だった。70年代前半から活動を続けていたモモヨ率いる紅蜥蜴(後のリザード)、フリクション、ミスター・カイト、ミラーズ、S-KENたちによるその活動は、2008年秋に劇場公開されたドキュメント『ROCKERS』で21世紀に甦った。監督の津島秀明(94年に急逝)が78年当時に「東京ロッカーズ」のライブを撮影した貴重なフィルムは、今も生々しい日本のロックの記憶である。
とはいえ、その記憶が数多くのロック・ファンと共有できるものなのかといえば、それは残念ながらアンダー・グラウンドでの活動ゆえに、多くの共感を呼ぶとは言えないのは確かだ。しかし連綿と続く、日本のロック史の中で忘れてはならない歴史的瞬間であったことも、また確かなのである。
「でも、集合体なんてどこにもなかったよ」
東京ロッカーズという“ブーム”の中心人物のひとりであったモモヨはそう言う。東京ロッカーズとは、あくまでもメジャー、つまり歌謡曲では収まりきれなかった、本格的な日本のロック勃興期に相次いで登場したバンドたちを象徴する言葉にすぎない。東京ロッカーズの時代を前後して、メジャー・シーンでも日本のロックが語られるようになる。
日本のロック史を辿っていくと、ロックというものが一部の富裕層の子弟のものだった側面があることに改めて気づかされる。60年代から70年代にかけて、エレキ・ギターは高価なおもちゃであり、ほんの数年前までは手にしているだけで不良扱いされるような代物だった。70年代末の日本のロック革命とは、一般層にまでエレキ楽器が普及したことと、どこか関係があるのではないか。やはり、70年代末の東京ロッカーズの時代は、日本のロック史にとって何かが変わり、何かが始まる時期だったような気がしてならない。
--今回のコンプリート・ワークス(コンプリートBOX『ブック・オブ・チェンジズ コンプリート・ワークス・オブ・リザード』)はどういうきっかけでスタートしたんですか。
モモヨ 自分がやっていることは所謂、一般的なロックではないことに気がついた。それは何なのか、ずっと考えていた。また全集を作ろうという気持ちもあった。忘れていることもあるし(笑)自分がやってきた仕事なのにやっていないと思い込んでいて今更ながら取り組むこともあったんです。
--気づかずにと(笑)。
モモヨ 私は昔の人間なんで、ビートルズやストーンズと一緒で、同じものを出したくない。変化を常に求めてきたバンド、ミュージシャンなんですね。そうであるが故にモモヨやリザードというものに対し世間が持っているイメージが違っているし、自分も違っている。その正体は何なのかと思ったのが製作意図。これを作らないと曰く言いがたしで終わってしまうものなので(笑)。
--70年代前半から現在に至るまで活動しているにも関わらず、やはり一般的には70年代後半の東京ロッカーズのイメージが強いですね。
モモヨ まあそうですね、基本的には。特に若い子たちにはネットの功罪もあると思うんですけど、東京ロッカーズという「バンド」を率いていたという記述もたまにあるんですよ。それは今の文字文化の怖いところかな。
--今回は昔の話もお伺いしたいと思っているんですが、モモヨさんの音楽的な原点というとドアーズになりますか?
モモヨ ドノヴァンとかドアーズでしょうね。詩を大事にしていたアーティストですね。あとはシド・バレッドのいた頃のピンク・フロイド、ケヴィン・エアーズがいた頃のソフト・マシーン……。
--その辺りはリアルタイムですね。
モモヨ そうですね。当時は国内盤として日本に入ってくるのは1年遅かったんですよ。船便で半年以上遅れて、飛行機便で一ヶ月以上遅れて入ってくる。飛行機便の場合は予約しなければいけないとか、いろいろ面倒なことがあって(笑)。それでも僕は東京に住んでいたから銀座のヤマハで手に入りましたけれど。当時は中村とうようさんの『ニュー・ミュージック・マガジン』が創刊されたばかりで、銀座のヤマハで中村さんと福田一郎さんの解説で新譜視聴会が開かれていたんですよ。客は50人ぐらいしか入らないんですが、その中のひとりでした(笑)。
--モモヨさんは高校時代からバンド活動を始めていますね。
モモヨ 自分は音楽をやるつもりはなかったんですけどね。17歳のときに「日本語のロックを考える会」みたいなところへ行ったら、ある日誰かが楽器を持ってきて、日本語のロックを作るんだとか言って、急にベースを渡されて弾かされたというのが人前で初めて弾いた経験でしたね。その時のヴォーカルが灰野敬二で(笑)。(中略)私は結構秘密結社を作るのが好きで(笑)、結社を作ってアパートとかを借りていると灰野君が泊まりに来るわけです。家賃3000円の3畳間で何もついていないところが結構あったんです。
--そういう方々との接点というのはどこにあったんですか。
モモヨ それは先ほどの新譜視聴会のようなところや、当時行われ始めた100円コンサートのようなところですね。最初は参加者も少ないですから、そこに来ているのはみんな同じ奴なわけです。
--なるほど。日本のロックの始まりですね。
モモヨ 私は当時、16、17歳でしたから一番子供でやたらに可愛がられた記憶はありますね。
--もともとモモヨさんは『現代詩手帖』に投稿されたりして、どちらかというと「ことば」の人だったわけですよね?
モモヨ 興味はありましたね。ただ音楽をやれるとは思わなかったし、日本にロックはなかったしさ(笑)。でも高校(早稲田大学高等学院)を辞めたときには音楽(ロック)と詩を合わせていくんだという気持ちでいましたけどね。現代詩をやっていくと煮詰まっていくわけですよ。それで、例えば萩原朔太郎も晩年、前橋でマンドリン・クラブを作っているんですよ。自分たちの現代詩も歌われるべきではないのかということを唱えたんですね。私の母も前橋出身で、前橋に行くと朔太郎記念館があったりして、私にとってはたぶんその影響も大きいんじゃないかな。
--70年代前半というと高田渡さんのようにブルーズのメロディを使って日本の現代詩を歌うというシンガーもいましたね。
モモヨ そうですね。そういう試みは多くありましたけど、私が好きだったのは……高校がフランス語をやるんですよ。だからフランス語だけ異様に発達していて、19世紀末の象徴主義文学とかにのめり込んでいたところがあるんですね。今でいえば澁澤龍彦ですね。そういう……要は理屈が多かったんですね(笑)。
--なるほど(笑)。
モモヨ 18、19歳の頃に当時東芝の石坂(敬一)さんからアンファンテリブル(恐るべき子供たち)的な扱いをされてたりね(笑)。
--74年(昭和49年)に開かれた郡山のワンステップフェスティバルには参加しているんですか?
モモヨ 前哨戦でやった日劇のコンサートには出ています。日劇で何日かやってから郡山へ行っているんですね。「日劇ロックカーニバル」と言ったかな……ワンステップの本番の時には、仙台のディスコでハコバンをやっていました(笑)。何かあったら呼ぶから近所にいろ、みたいな感じだったと思うんですけど(笑)。
--あのフェスティバルは日本のロックのひとつの出発点ともいえるんじゃないかと思うんですが?
モモヨ うーん、でも自分の個人的な歴史の場所が違うからね。俺が思うのは、例えばビートルズのファンクラブが主催して、「マジカル・ミステリー・ツアー」を映写して、遠藤賢司とバレンタイン・ブルーと一緒にやったんだけど、そこで日本語とロックの可能性を初めて感じましたね。だから実際に日本のロックが始まったといえるのは裕也さんがやっていた100円コンサートの時代からじゃないかな。
--ワンステップは60年代から70年代前半までに登場していたバンドが総結集したという印象ですね。
モモヨ そうですね。一区切りという印象はありますね。あのフェスティバルで人気が出たバンドもいたけれど、その2、3年後には止めたし。
--だからこそ数年後ではありますけれど、東京ロッカーズの動きというのは新しい時代を感じますね。
モモヨ いや、本当は止めようと思ったいた時代なんですよ(笑)。区切りつけようか、と。PANTAと一緒に京都へ行ったりして、それで人気が出て「あれ?」という感じ。
--思いがけない事態に?
モモヨ でしたよ。でも面白かったですよ。京都で紅蜥蜴の人気が出て、呼ばれるんですけど、「じゃあ今度は東京に変なバンドがいるから一緒に連れて行く」と。
--一連の東京ロッカーズのツアーは、実際には紅蜥蜴(リザード)プラスαだったという話ですね。
モモヨ 最初は特にね。名前もなかったしね(笑)。あの当時、一番の意識の革新は、レコードって自分たちでは作れないと思っていたのが、あの辺から「(メジャーの)レコード会社でレコードを作るよりも自分たちで作った方がいい」という風に変わって行ったことですね。
--所謂インディーズですね。東京ロッカーズを受けて、80年代はまさにそういう時代になりましたね。
モモヨ レコード会社神話が崩れたんです。
--ただモモヨさんとリザードの活動は80年代にかけてどんどん収束していってしまいますね。
モモヨ たぶん一番精力を傾けたのはシステムの解体だったと思いますよ(笑)。
--本当に時代の狭間だったんだなと感じますね。モモヨさんや東京ロッカーズのムーブメントの功績というのは、音楽性はもとより、そういうシステムの革新だったと思います。
モモヨ そのままでいるということに興味をなくすんですよ。
(LB中洲通信2009年2月号~4月号 「東京ロッカーズ、その時代」)
※一部加筆・修正
ビートルズの登場以降、わずか10年ほどの歴史しか持たない“ロック”というポップ・ミュージック革命は、70年代初頭のニューヨーク、そして中頃のイギリスで起こったパンク・ムーブメント、ニューウエイブという形で再び大変動を起こした。音楽に、鑑賞音楽以上の意味合いを持たせた“ロック”の存在意義そのものがポップ・ミュージックの永久革命を指していたのだから、わずか10年程度であっても、過去の遺物は否定されてしまうのは、また当然なのだ。
日本にも同じような、小さなブームが起こった。それを「東京ロッカーズ」と呼ぶ。グループ・サウンズという日本のロック創世記を経て、70年代前半の日本のロックは極めてアンダー・グラウンドなものだった。歌謡曲が黄金時代を迎え、60年代末のフォーク・ソングが時代を経てポップスとして、ビジネスとして成立した時代である。そんな時代に永久革命を続ける“ロック”が日本のオーバー・グラウンドで受け入れられるわけがない。日本のロックは地下に潜り、海外の「革命」にビビッドに反応しながら小さな爆発を繰り返すしかなかった。
そして、その爆発のひとつが1978年に東京・下北沢などのエリアで行われていたライブ・シリーズ「東京ロッカーズ」だった。70年代前半から活動を続けていたモモヨ率いる紅蜥蜴(後のリザード)、フリクション、ミスター・カイト、ミラーズ、S-KENたちによるその活動は、2008年秋に劇場公開されたドキュメント『ROCKERS』で21世紀に甦った。監督の津島秀明(94年に急逝)が78年当時に「東京ロッカーズ」のライブを撮影した貴重なフィルムは、今も生々しい日本のロックの記憶である。
とはいえ、その記憶が数多くのロック・ファンと共有できるものなのかといえば、それは残念ながらアンダー・グラウンドでの活動ゆえに、多くの共感を呼ぶとは言えないのは確かだ。しかし連綿と続く、日本のロック史の中で忘れてはならない歴史的瞬間であったことも、また確かなのである。
「でも、集合体なんてどこにもなかったよ」
東京ロッカーズという“ブーム”の中心人物のひとりであったモモヨはそう言う。東京ロッカーズとは、あくまでもメジャー、つまり歌謡曲では収まりきれなかった、本格的な日本のロック勃興期に相次いで登場したバンドたちを象徴する言葉にすぎない。東京ロッカーズの時代を前後して、メジャー・シーンでも日本のロックが語られるようになる。
日本のロック史を辿っていくと、ロックというものが一部の富裕層の子弟のものだった側面があることに改めて気づかされる。60年代から70年代にかけて、エレキ・ギターは高価なおもちゃであり、ほんの数年前までは手にしているだけで不良扱いされるような代物だった。70年代末の日本のロック革命とは、一般層にまでエレキ楽器が普及したことと、どこか関係があるのではないか。やはり、70年代末の東京ロッカーズの時代は、日本のロック史にとって何かが変わり、何かが始まる時期だったような気がしてならない。
--今回のコンプリート・ワークス(コンプリートBOX『ブック・オブ・チェンジズ コンプリート・ワークス・オブ・リザード』)はどういうきっかけでスタートしたんですか。
モモヨ 自分がやっていることは所謂、一般的なロックではないことに気がついた。それは何なのか、ずっと考えていた。また全集を作ろうという気持ちもあった。忘れていることもあるし(笑)自分がやってきた仕事なのにやっていないと思い込んでいて今更ながら取り組むこともあったんです。
--気づかずにと(笑)。
モモヨ 私は昔の人間なんで、ビートルズやストーンズと一緒で、同じものを出したくない。変化を常に求めてきたバンド、ミュージシャンなんですね。そうであるが故にモモヨやリザードというものに対し世間が持っているイメージが違っているし、自分も違っている。その正体は何なのかと思ったのが製作意図。これを作らないと曰く言いがたしで終わってしまうものなので(笑)。
--70年代前半から現在に至るまで活動しているにも関わらず、やはり一般的には70年代後半の東京ロッカーズのイメージが強いですね。
モモヨ まあそうですね、基本的には。特に若い子たちにはネットの功罪もあると思うんですけど、東京ロッカーズという「バンド」を率いていたという記述もたまにあるんですよ。それは今の文字文化の怖いところかな。
--今回は昔の話もお伺いしたいと思っているんですが、モモヨさんの音楽的な原点というとドアーズになりますか?
モモヨ ドノヴァンとかドアーズでしょうね。詩を大事にしていたアーティストですね。あとはシド・バレッドのいた頃のピンク・フロイド、ケヴィン・エアーズがいた頃のソフト・マシーン……。
--その辺りはリアルタイムですね。
モモヨ そうですね。当時は国内盤として日本に入ってくるのは1年遅かったんですよ。船便で半年以上遅れて、飛行機便で一ヶ月以上遅れて入ってくる。飛行機便の場合は予約しなければいけないとか、いろいろ面倒なことがあって(笑)。それでも僕は東京に住んでいたから銀座のヤマハで手に入りましたけれど。当時は中村とうようさんの『ニュー・ミュージック・マガジン』が創刊されたばかりで、銀座のヤマハで中村さんと福田一郎さんの解説で新譜視聴会が開かれていたんですよ。客は50人ぐらいしか入らないんですが、その中のひとりでした(笑)。
--モモヨさんは高校時代からバンド活動を始めていますね。
モモヨ 自分は音楽をやるつもりはなかったんですけどね。17歳のときに「日本語のロックを考える会」みたいなところへ行ったら、ある日誰かが楽器を持ってきて、日本語のロックを作るんだとか言って、急にベースを渡されて弾かされたというのが人前で初めて弾いた経験でしたね。その時のヴォーカルが灰野敬二で(笑)。(中略)私は結構秘密結社を作るのが好きで(笑)、結社を作ってアパートとかを借りていると灰野君が泊まりに来るわけです。家賃3000円の3畳間で何もついていないところが結構あったんです。
--そういう方々との接点というのはどこにあったんですか。
モモヨ それは先ほどの新譜視聴会のようなところや、当時行われ始めた100円コンサートのようなところですね。最初は参加者も少ないですから、そこに来ているのはみんな同じ奴なわけです。
--なるほど。日本のロックの始まりですね。
モモヨ 私は当時、16、17歳でしたから一番子供でやたらに可愛がられた記憶はありますね。
--もともとモモヨさんは『現代詩手帖』に投稿されたりして、どちらかというと「ことば」の人だったわけですよね?
モモヨ 興味はありましたね。ただ音楽をやれるとは思わなかったし、日本にロックはなかったしさ(笑)。でも高校(早稲田大学高等学院)を辞めたときには音楽(ロック)と詩を合わせていくんだという気持ちでいましたけどね。現代詩をやっていくと煮詰まっていくわけですよ。それで、例えば萩原朔太郎も晩年、前橋でマンドリン・クラブを作っているんですよ。自分たちの現代詩も歌われるべきではないのかということを唱えたんですね。私の母も前橋出身で、前橋に行くと朔太郎記念館があったりして、私にとってはたぶんその影響も大きいんじゃないかな。
--70年代前半というと高田渡さんのようにブルーズのメロディを使って日本の現代詩を歌うというシンガーもいましたね。
モモヨ そうですね。そういう試みは多くありましたけど、私が好きだったのは……高校がフランス語をやるんですよ。だからフランス語だけ異様に発達していて、19世紀末の象徴主義文学とかにのめり込んでいたところがあるんですね。今でいえば澁澤龍彦ですね。そういう……要は理屈が多かったんですね(笑)。
--なるほど(笑)。
モモヨ 18、19歳の頃に当時東芝の石坂(敬一)さんからアンファンテリブル(恐るべき子供たち)的な扱いをされてたりね(笑)。
--74年(昭和49年)に開かれた郡山のワンステップフェスティバルには参加しているんですか?
モモヨ 前哨戦でやった日劇のコンサートには出ています。日劇で何日かやってから郡山へ行っているんですね。「日劇ロックカーニバル」と言ったかな……ワンステップの本番の時には、仙台のディスコでハコバンをやっていました(笑)。何かあったら呼ぶから近所にいろ、みたいな感じだったと思うんですけど(笑)。
--あのフェスティバルは日本のロックのひとつの出発点ともいえるんじゃないかと思うんですが?
モモヨ うーん、でも自分の個人的な歴史の場所が違うからね。俺が思うのは、例えばビートルズのファンクラブが主催して、「マジカル・ミステリー・ツアー」を映写して、遠藤賢司とバレンタイン・ブルーと一緒にやったんだけど、そこで日本語とロックの可能性を初めて感じましたね。だから実際に日本のロックが始まったといえるのは裕也さんがやっていた100円コンサートの時代からじゃないかな。
--ワンステップは60年代から70年代前半までに登場していたバンドが総結集したという印象ですね。
モモヨ そうですね。一区切りという印象はありますね。あのフェスティバルで人気が出たバンドもいたけれど、その2、3年後には止めたし。
--だからこそ数年後ではありますけれど、東京ロッカーズの動きというのは新しい時代を感じますね。
モモヨ いや、本当は止めようと思ったいた時代なんですよ(笑)。区切りつけようか、と。PANTAと一緒に京都へ行ったりして、それで人気が出て「あれ?」という感じ。
--思いがけない事態に?
モモヨ でしたよ。でも面白かったですよ。京都で紅蜥蜴の人気が出て、呼ばれるんですけど、「じゃあ今度は東京に変なバンドがいるから一緒に連れて行く」と。
--一連の東京ロッカーズのツアーは、実際には紅蜥蜴(リザード)プラスαだったという話ですね。
モモヨ 最初は特にね。名前もなかったしね(笑)。あの当時、一番の意識の革新は、レコードって自分たちでは作れないと思っていたのが、あの辺から「(メジャーの)レコード会社でレコードを作るよりも自分たちで作った方がいい」という風に変わって行ったことですね。
--所謂インディーズですね。東京ロッカーズを受けて、80年代はまさにそういう時代になりましたね。
モモヨ レコード会社神話が崩れたんです。
--ただモモヨさんとリザードの活動は80年代にかけてどんどん収束していってしまいますね。
モモヨ たぶん一番精力を傾けたのはシステムの解体だったと思いますよ(笑)。
--本当に時代の狭間だったんだなと感じますね。モモヨさんや東京ロッカーズのムーブメントの功績というのは、音楽性はもとより、そういうシステムの革新だったと思います。
モモヨ そのままでいるということに興味をなくすんですよ。
(LB中洲通信2009年2月号~4月号 「東京ロッカーズ、その時代」)
※一部加筆・修正