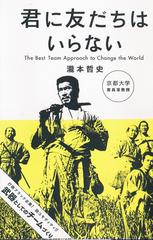<ピストルズ、そしてパンクは、普通の人々に力を与えた。パンクは、人々が音楽をつくる後押しをしただけでなく、自分自身の服をデザインし、ファンジン(同人誌)を始め、ライブを準備し、デモを行い、レコードストアを開店し、レコードレーベルを設立することをも奨励した。ディック・ヘブディジがその著『サブカルチャー――スタイルが意味するもの』で指摘したように、パンクのファンジン『sniffin' glue』には、「おそらくサブカルチャーが生み出したうちで最も見事なプロパガンダ――パンクのDIY哲学の決定的な表現――が含まれている、それは、ギターのネック上におけるスリー・フィンガー・ポジションの図解、そしてそのキャプションにはこうあった」
「これがコードの1つ、あと2つ覚えろ。
そして自分のバンドを組め」>
<「私にとっては、一か所にとどまるのは退屈だ。50過ぎた連中がパンク風のレザージャケットを着てうろうろして、それがなんだっていうんだ。大事なのは、分類不可能なままでいるということだよ。そうすれば、他人がきみを所有するということはない」>(リチャード・ヘル)
(マット・メイソン『海賊のジレンマ ユースカルチャーがいかにして新しい資本主義をつくったか』フィルムアート社2012年)
「これがコードの1つ、あと2つ覚えろ。
そして自分のバンドを組め」>
<「私にとっては、一か所にとどまるのは退屈だ。50過ぎた連中がパンク風のレザージャケットを着てうろうろして、それがなんだっていうんだ。大事なのは、分類不可能なままでいるということだよ。そうすれば、他人がきみを所有するということはない」>(リチャード・ヘル)
(マット・メイソン『海賊のジレンマ ユースカルチャーがいかにして新しい資本主義をつくったか』フィルムアート社2012年)