<新しい道路が必要なら、その必要を考えて作ればいい。「新しい道路を作る」ということは、「この町をこの先どうしていくか?」ということを考えることなんだから。
ところが日本の行政は、そういう風には考えない。そういうことを考えようとして、「いやー、地域住民の利害というのはいろいろありませからねー」で、「既にあるもの」に触れようとしない。そして、当然、そんな風に言われてしまう住民たちは、「自分の現在」のことしか考えない。
そして、「大きなイヴェント」が設定されて、「地域の活性化」というのは、結局のところ、「大きなイヴェントをやれば人が集まるから、それをいい機会にして、地域外の大資本に進出してもらってここら辺をハデにしてもらおう」という金儲けのことだ。(中略)べつに日本人は、今になって急にバカな金の使い方をするようになったんじゃない。それはもう、30年以上も前からのことで、今になってもそのことが分からないオヤジたちはゴマンというという、それだけのことなんだ。
日本人は、いつまでも大イヴェントの黒船が来るのを待っている。「黒船が来ないんだったら、こちらで黒船を作ってしまおう。そうすれば地域の活性化になる」と言って、本当に自分たちが必要なもののことを考えようとはしない。「自分たちの必要」よりも、「なんだから分からないがスゴイ」と言える黒船の方が大切なんだろう。バブルがはじけるのも当然だし、「バブルがはじけた」ということの意味も分からない人間がゴマンといるのも、これまた当然のことだろうね。>
<さて、日本で政治家は「政策」というものを考えない。しかし、現実問題として、日本には「国の方針」というものがあり、「国の決めた制度」というものがある。こういうものは、「政策の結果」です。一体こういうものがなぜあるのか? 誰がこういうことを考えたのか?
「政治家が政策を作らない国で、一体誰が“政策”を作るのか?」と言ったら、その答は「官僚」。
官僚というのは、国家という組織の歯車です。決められた命令に合わせて、それを実行するように動く。官僚は政策に従って動くものであって、政策を決めるものではない。官僚と政治家の関係はコンピューターと人間の関係とおんなじで、コンピューターは人間の指示に合わせて計算をし、官僚も、政治家の出す政策に合わせて動くものだ。ところが、日本の場合はそうじゃない。日本の政治家は、「政策をもって官僚に向かう」のではなくて、「官僚に政策を教えてもらうもの」だからだ。コンピューターが人間を指示している――それが日本。
データがたりないコンピューターは、分からない質問に対しては「回答不能」と答える。日本の官僚も、おんなじように、分からないことには「無言」で対応する。(中略)これは、データ不足のコンピューターの「回答不能」とおんなじだ。
コンピューターに回答させたかったら、その分のデータをインプットしてやればいい。「このコンピューターは悪者だ」と言ってぶっ壊したってどうにもならないんだけども、でも「コンピューターを利用する」という発想に慣れていない日本人たちは、どうも、これが理解出来なくて、「コンピューターを壊す」という方向にしか行けなかったみたいだ。そして、そうなっても当然ぐらいに、日本の官僚たちは、「意志を持ったコンピューター」になりかかっていた。(中略)
新しいデータをインプットされないコンピューターは、新しい事態に対応出来ない。だからどうするか? 対応出来ない「新しい事態」の存在を、認めないようにする。現実はどんどん変わって行っても、それに対応する機構が全然変わらなかったのには、こういう理由があったからだね。>
(橋本治「貧乏は正しい!ぼくらの東京物語」小学館1996)
先週放送されたNHKスペシャルの「シリーズ東日本大震災 追跡復興予算19兆円」の余波が続いている。
動画もまだどこかで観られると思うので探して見て下さい。非常に腹立たしく理不尽な話であることは言うまでもないのだけれども、改めて何が腹立たしいかといえば、霞ヶ関が震災、そしてその復興をイヴェントにしてしまったということだと思う。
一時期、反原発派は主義主張のために原発災害の被害の拡大を待っているかのような誹謗中傷がされていたけれども、まさに霞ヶ関こそ3.11という黒船に便乗して復興を大イヴェント化しているといえる。
地域(経済)振興や復興をイヴェントでしか捉えられない連中にとっては、大震災とその復興は(外圧を除けば)まさに黒船中の黒船、大イヴェント中の超巨大イヴェントだったのだと思う。
これが、本当にこれから25年も続くのだろうか?
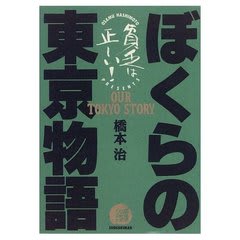
ぼくらの東京物語―貧乏は正しい!
<ハシモト式人生の教科書第3弾 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。><本書では、トーキョーの変貌と地方のトーキョー化の裏に潜む日本の本質を暴き出す。足下の定まらない急激な都市化の過程で、トーキョーは何を失い、日本人は何を捨てたか。そして、ぼくらは何を取り戻すべきか。これを読めば、人生が変わる。 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。>
登録情報
単行本:318ページ
出版社:小学館 (1996/01)
ISBN-10:4093723133
ISBN-13:978-4093723138
発売日:1996/01
商品の寸法:19.2 x 13.4 x 2.6 cm
ところが日本の行政は、そういう風には考えない。そういうことを考えようとして、「いやー、地域住民の利害というのはいろいろありませからねー」で、「既にあるもの」に触れようとしない。そして、当然、そんな風に言われてしまう住民たちは、「自分の現在」のことしか考えない。
そして、「大きなイヴェント」が設定されて、「地域の活性化」というのは、結局のところ、「大きなイヴェントをやれば人が集まるから、それをいい機会にして、地域外の大資本に進出してもらってここら辺をハデにしてもらおう」という金儲けのことだ。(中略)べつに日本人は、今になって急にバカな金の使い方をするようになったんじゃない。それはもう、30年以上も前からのことで、今になってもそのことが分からないオヤジたちはゴマンというという、それだけのことなんだ。
日本人は、いつまでも大イヴェントの黒船が来るのを待っている。「黒船が来ないんだったら、こちらで黒船を作ってしまおう。そうすれば地域の活性化になる」と言って、本当に自分たちが必要なもののことを考えようとはしない。「自分たちの必要」よりも、「なんだから分からないがスゴイ」と言える黒船の方が大切なんだろう。バブルがはじけるのも当然だし、「バブルがはじけた」ということの意味も分からない人間がゴマンといるのも、これまた当然のことだろうね。>
<さて、日本で政治家は「政策」というものを考えない。しかし、現実問題として、日本には「国の方針」というものがあり、「国の決めた制度」というものがある。こういうものは、「政策の結果」です。一体こういうものがなぜあるのか? 誰がこういうことを考えたのか?
「政治家が政策を作らない国で、一体誰が“政策”を作るのか?」と言ったら、その答は「官僚」。
官僚というのは、国家という組織の歯車です。決められた命令に合わせて、それを実行するように動く。官僚は政策に従って動くものであって、政策を決めるものではない。官僚と政治家の関係はコンピューターと人間の関係とおんなじで、コンピューターは人間の指示に合わせて計算をし、官僚も、政治家の出す政策に合わせて動くものだ。ところが、日本の場合はそうじゃない。日本の政治家は、「政策をもって官僚に向かう」のではなくて、「官僚に政策を教えてもらうもの」だからだ。コンピューターが人間を指示している――それが日本。
データがたりないコンピューターは、分からない質問に対しては「回答不能」と答える。日本の官僚も、おんなじように、分からないことには「無言」で対応する。(中略)これは、データ不足のコンピューターの「回答不能」とおんなじだ。
コンピューターに回答させたかったら、その分のデータをインプットしてやればいい。「このコンピューターは悪者だ」と言ってぶっ壊したってどうにもならないんだけども、でも「コンピューターを利用する」という発想に慣れていない日本人たちは、どうも、これが理解出来なくて、「コンピューターを壊す」という方向にしか行けなかったみたいだ。そして、そうなっても当然ぐらいに、日本の官僚たちは、「意志を持ったコンピューター」になりかかっていた。(中略)
新しいデータをインプットされないコンピューターは、新しい事態に対応出来ない。だからどうするか? 対応出来ない「新しい事態」の存在を、認めないようにする。現実はどんどん変わって行っても、それに対応する機構が全然変わらなかったのには、こういう理由があったからだね。>
(橋本治「貧乏は正しい!ぼくらの東京物語」小学館1996)
先週放送されたNHKスペシャルの「シリーズ東日本大震災 追跡復興予算19兆円」の余波が続いている。
動画もまだどこかで観られると思うので探して見て下さい。非常に腹立たしく理不尽な話であることは言うまでもないのだけれども、改めて何が腹立たしいかといえば、霞ヶ関が震災、そしてその復興をイヴェントにしてしまったということだと思う。
一時期、反原発派は主義主張のために原発災害の被害の拡大を待っているかのような誹謗中傷がされていたけれども、まさに霞ヶ関こそ3.11という黒船に便乗して復興を大イヴェント化しているといえる。
地域(経済)振興や復興をイヴェントでしか捉えられない連中にとっては、大震災とその復興は(外圧を除けば)まさに黒船中の黒船、大イヴェント中の超巨大イヴェントだったのだと思う。
これが、本当にこれから25年も続くのだろうか?
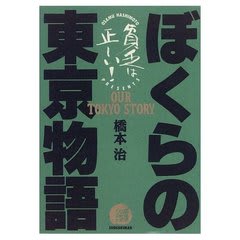
ぼくらの東京物語―貧乏は正しい!
<ハシモト式人生の教科書第3弾 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。><本書では、トーキョーの変貌と地方のトーキョー化の裏に潜む日本の本質を暴き出す。足下の定まらない急激な都市化の過程で、トーキョーは何を失い、日本人は何を捨てたか。そして、ぼくらは何を取り戻すべきか。これを読めば、人生が変わる。 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。>
登録情報
単行本:318ページ
出版社:小学館 (1996/01)
ISBN-10:4093723133
ISBN-13:978-4093723138
発売日:1996/01
商品の寸法:19.2 x 13.4 x 2.6 cm


















