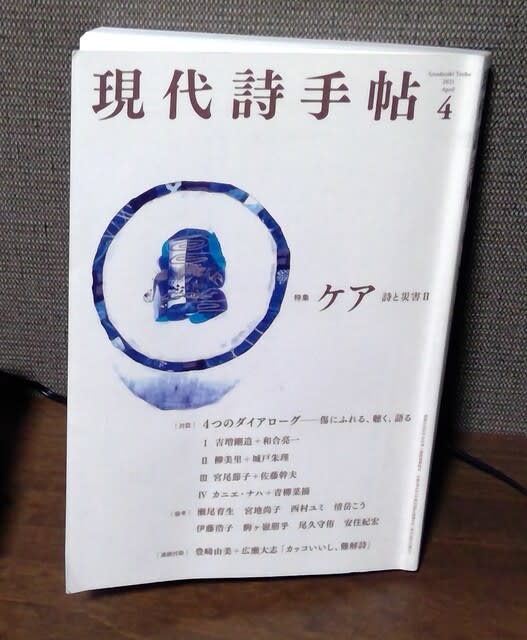
引き続き、特集の、4つのダイアローグ以外の個別の論考、報告を紹介する。被災地に住み、哲学・思想、心理・精神・ケア、そして、詩に関心を持つ人間にとって、今号の特集は、どれも、深い関心を呼び起こされざるを得ないもの、ということになる。
【瀬尾育生「疫学的な日々、数的な日々」】
イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンペンが、今回のコロナ禍についてイタリア政府のとった緊急措置命令を批判したらしい。瀬尾育生氏は、アガンペンの語った言葉が、時局的に間違っていたのかもしれないと述べながら、むしろ、擁護する姿勢を見せる。
「なぜならここでアガンペンの発言のもっとも根底にある直観は、イタリア政府が疫学的な理由から人と人との、共同体と共同体の接触回避を、政治権力によって強制したことは、私たちの中のナニカトテモ大切ナモノを損なう、ということだからである。…そのナニカトテモ大切ナモノとは、ヨーロッパが歴史的に大切にした「倫理的な実体」にかかわっているのである。」(64ページ)
アガンペンは、次のように語っているという。
「《…いつまで続くのかもわからぬまま、このようなしかたで生きることに慣れていく国にあって、人間関係はどのようなものになるのか。生き延びる以外の価値をもたない社会とはどのようなものなのか?》」(65ページ)
アガンペンの語りを引きながら瀬尾氏が語る怖れは、現時点での大きな問題として広く共有されるべきものであろう。
「この一年のあいだ私を捉えてはなさない直観を言葉にすれば、それは「生存」と「生活」の逆接、ということになる。それ以前の世界において「生存」と「生活」は順接だった。「経済」もまた「必要」の上に「欲望」を積みあげたところで、成り立っていた。それを根底から変えたのは「ウイルスという異物観念」が現実のものになったことだ。今われわれは、「生存」のためには「生活」をあたうかぎり切り詰めざるを得ず、「生活」を拡大・充実させようとすれば、「生存」を危険にさらすしかないという逆接を、体験している。」(70ページ)
人間の「生存」は、誰とも会うことなく、話すこともなく、個室に閉じこもっていても可能であるかもしれないし、ベッドにひとり括りつけられ、放置されたままでも可能なのかもしれない。しかし、「生活」は、ひとと会い、言葉を交わし、何らかのかたちでコミュニケーションを取ることなしには成り立たない。「生活」なしに文化はない。このままでは、ヨーロッパの育んだ大切な歴史が損なわれてしまう、とアガンペンは怖れる。もちろん、瀬尾氏も、わたしたちも、西洋の、というだけでなく、人間の歴史が失われてしまうことを怖れるところは同様である。
ヨーロッパの「倫理的な実体」とは具体的に何なのか、ここを読むだけでは掴みづらいところだが、単に人間の生命を繋ぐ生存のレベルのみではない、人間の生活、歴史、文化そのものと言っていいだろうし、もう少し絞り込めば、理性、自由、友愛、人権の尊重に繋がっていくような何ものか、ということではあろう。
この瀬尾氏の論考は難解かもしれないが、私なりには確かにそのとおりと得心できるものである。
【宮地尚子「詩の「恥ずかしさ」について」】
宮地氏は、精神科医で、高校時代までは詩を書いていたという。
「今年一月二十九日に劇場公開された映画『心の傷をいやすということ』は、二〇〇〇年に亡くなった神戸の精神科医・安克昌さんが阪神・淡路大震災の心のケアに奔走したことを家族の関わりとともに描いたものです。私は安さんの友人として取材を受けたり、精神科医としてドラマの精神医療交渉をさせていただいた…」(72ページ)
筑波大学教授で精神科医の齋藤環氏(オープンダイアローグの紹介者)によれば、この映画には、あの中井久夫も登場するらしく、ぜひ、観たいと思っているところである。
「基本的には、私は聞くことの専門家だと思っています。…生き延びた人にしか手記は書けない。体験を話すことはできない。けれども、亡くなった人の分まで、私たちは遺された言葉を読み返したり、そこから新たな作品を生み出したりすることはできる、と思ったのです。「聞く」ことは非常に重要です。今は皆発信や「即答」ばかりですが、ていねいに聞き取って、少しためを作り、それをエコーのように再び伝えていくことは非常に豊かなことだと思います。時空間をずらしながら。」(76ページ)
確かに、「即答」しないことの大切さはあるに違いない。
【西村ユミ「ケア=詩の生成のかたち」】
西村ユミ氏は、看護師のケアという実践についての研究者であるという。谷川俊太郎氏とも交流があるらしい。深く聴き取り、詳細に記述することを行っている。
「「意識の表面にある言語と、そうではなくもっと未分化な何かの動きとして意識下にあるもの」「言語以前の存在」、これに迫ろうとするのが詩だ。詩人である谷川俊太郎さんと対談をした際、このように教えてもらった。「言葉自体の根っこや、言葉が発生する源がそこにはある」。このようにも話された。これを聞いて、谷川さんの詩と私の考えるケアには、通底する何かがあるように思った。
私は看護師のケアという実践を研究している。実際に医療現場で働く看護師に同伴して調査し、そこで気になったことを聴き取り、その言葉を手がかりに、ケアの成り立ちを詳細に記述するというものである。」(78ページ)
【清岳こう「心を開くことば―「ことばの移動教室」を通して」】
詩人清岳こう氏は、宮城県の高校教師であるが、被災地の小・中・高校を訪問し、「ことばの移動教室」を立ち上げ、『震災 宮城・子ども詩集』をまとめた。
「二〇一一年三月の東日本大震災のとき、私はちょうど仙台の高校で二年生の担任を務めていました。」(84ページ)
「…四月に「ことばの移動教室」を立ち上げ、六月から半年間で被災地の小学校、中学校、高校をのべ四十数回訪問し、四百人ほどの児童・生徒と交流しました。」(84ページ)
「生徒たちが書いた詩は、二〇一二年三月に『震災 宮城・子ども詩集』にまとめました。「津波に襲われた故郷、でも、やはり、故郷の海は美しい」の言葉とともに。以後、この詩集をもとに、詩の朗読会や、書やダンス、音楽など様々なコラボレーションも実施しました。」(85ページ)
【伊藤浩子「喪うということについて」】
詩人伊藤浩子氏がここで描いているのは、前号3月号に執筆された土方正志氏の出版社荒蝦夷から上梓された『みちのく怪談コンテスト傑作選 2011』の世界である。たしかに、こういう目撃譚は多い、のかもしれない。
「…わたしたちが「喪われた対象」との再会を望むのは、ごく自然なことに思われる。
…実際問題として、東北地方の太平洋側の海岸を歩いているときに、人魂を見たとか、亡きひとの幽霊を見たという報告が実に多いと聞く。…真偽を問うことに意味はない。それよりはいくら荒唐無稽であってもそこには遺族たちの、死者との再会を果たしたいという切なる願いが込められていると解釈したいし、彼らにとってはそれが心的現実であったろう。」(90ページ)
【尾久守侑「stateを保存する」】
尾久守侑氏は、精神科医にして詩人である。
「新型コロナウイルス感染症が流行して以降、精神科の「診断基準」などというものとはまた別に、人が調子を崩す仕組みというものを診療を通して考えていて、最近、それがようやく自分のなかで明確になってきた。…まず最初にその一部を一般的に公開してみたい。」
「「コロナ様の身体症状」というのはすなわち、高体温や呼吸苦、胸痛、全身倦怠感などの症状である。…そもそも何ウイルスにも感染していない、身体的には全く健康体なのにこのような身体症状が出現する人というのがいる。…
この身体の反応は、S・フロイトの頃はヒステリーと呼ばれており、日本では数十年前までは神経衰弱と呼ばれていた。」(93ページ)
【駒ヶ嶺朋乎「パンデミックと人間」】
駒ヶ嶺朋乎氏は、詩人で、脳神経内科/総合内科専門医とのこと。
まず冒頭にアルベール・カミュの『ペスト』からの引用を置く。ここに再引用はしないが、いま、『ペスト』を参照するというのはあり得べきことである。(と言いながら、私はまだ読んでいない。)
駒ヶ嶺氏の行論は、上の瀬尾氏の論考と通じるものである。
「パンデミックを取り巻く問題で、感染症学的なことはごくわずかだった。この一年で誰もが大きな傷を受けたのは、相互監視社会が急速に立ち上がったことだった。」(97ページ)
「文化や芸術活動を贅沢品で本来は不要なものだと位置づけるのはまるで旧時代の亡霊かと思う。人を日々生かしているのは医療のようなインフラではない。明日生き延びるべきか迷う命をかくまい、なお伸びやかに育てるのは、芸術や表現活動、人の繋がりだ。」(98ページ)
【安住紀宏「巨魚(イサナ)にかえる Reborn Art Festival―吉増剛造「詩人の家」/「roomキンカザン」」】
安住紀宏氏は、宮城県石巻市出身であり、その1でも触れたとおり、リボーン・アート・フェスティバルのイベントとしての、吉増氏の石巻市鮎川地区滞在について報告する。鮎川地区は、捕鯨の基地として知られ、金華山を目前にする牡鹿半島先端部の町である。
「「roomキンカザン」は、吉増が会期中に寝泊まりしていたホテルニューさか井の部屋自体亜を展示スペースとして開放したものだ。この一室で吉増は会期中に詩作を進めていたそうだが、原稿用紙だけでなく、なんと、窓や鏡にも詩を書いていた。神の島とみなされている金華山を望む窓を、まるでレンズの内側から叩くようにして、こう記している。
窓に白い言が
顕って来ていた 白い言が 窓に
巨魚よ
巨魚
汝
世界樹に
登れ!」(100ページ)
巨魚は当て字で、鯨=勇魚で、イサナと読ませる。
「顕って」は、安住氏も触れていないが、「ふって」と読ませるのだろうか?天啓のように、空から降りてくる、降ってくる、そして、ここに顕現する。鯨は逆に、海から出て木の上に浮かび上がる。
【鵜飼哲「「災間期」の言葉の分解と官能」】
鵜飼哲氏の論考は、「赤坂憲雄、藤原辰史『言葉をもみほぐす』(岩波書店)の紹介である。
赤坂憲雄氏は、学習院大学教授、元東北芸工大学教授の民俗学者で、「東北学」を唱えた。藤原辰史氏は、京都大学准教授、専門は、農業思想史・技術史とのこと。
以上、読み応えのある論考が並んだ。「特集・ケア 詩と災害Ⅱ」についての紹介は、ここまでということになるが、実は、この号の紹介は、もう一回。その3まで続けたいと思う。難解な詩と分かりやすい詩についてである。


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます