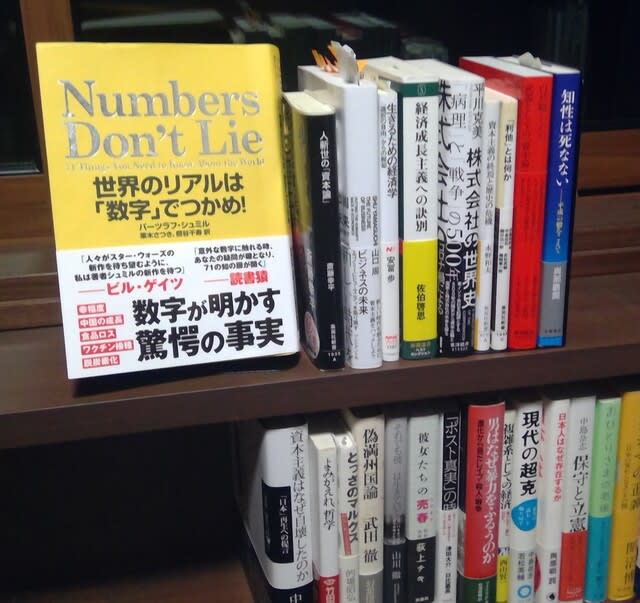
英文タイトルの「Numbers Don’t Lie」とは、言うまでもなく「数字はウソをつかない」。副題は「71Things You Need to Know About the World」とのことで、訳せば、「世界について知っておくべき71のこと」となるだろうか。
バーツラフ・シュミル氏は、カナダのマニトバ大学特別栄誉教授で、エネルギー、環境変化、人口変動、食料生産、栄養、技術革新、リスクアセスメント、公共政策の分野で学際的研究に従事されているとのこと。1943年、東ヨーロッパ「鉄のカーテンの東側」のチェコ生まれ、アメリカ、カナダと移り住んだ方のようである。
冒頭、「日本語版に寄せて」に、以下のように書かれている。引用はしないが、「仕方がない」とか「頑張ってください!」とか、原文でも日本語で書かれているという。かなりの日本通、現在の日本の課題にもかなり詳しい方のようである。
「1978年以来、折に触れ日本を訪ね、この10年ほどは年に一度はかならず東京を訪問している。…
さまざまな偉業を達成してきた日本に、わたしはいまなお関心を寄せずにはいられない。細部(ディテール)、意匠(デザイン)、美、食を重んじてきた伝統には敬服しているし、組織や技術において数々の実績をあげてきたことも称賛している。
しかし、日本の歴史を振り返り、そこから派生した数々の問題点についてはずっと指摘してきたし、近年の日本の政治的意思決定や将来については懸念も抱いている。」(9ページ)
賞賛すべきところ、懸念するところの双方が、曇りなく見えているということだろう。
さて、「はじめに」で、本書の内容、目的について、著者自身が簡潔にまとめておられる。
「とりあげるトピックは、世界の人々、人工、国々…エネルギー利用、技術革新…。ほかにも、食料の供給や選択、地球環境の状況とその悪化という問題にも触れていく。」(12ページ)
まさにいま、問題とすべきところが取り上げられているということだ。
「まず初めに申しあげたいのは、事実(ファクト)をはっきりさせる、それが本書の目的だということ。とはいえ、それは一筋縄ではいかない。たしかにインターネットには数字があふれているが、日付も出所も不明なデータを適当に引っ張ってきただけのものがあまりにも多いうえ、単位が不確かなものも散見する。」(12ページ)
「たとえば、…GDP(国内総生産)は、…名目GDPだろうか?それとも…実質GDPなのだろうか、それから…ドルへの換算はたんに実勢為替レートを利用しているのだろうか?それとも…購買力平価に基づいているのだろうか?」(12ページ)
上記引用の省略箇所には、名目GDP、実質GDP、購買力平価などについて簡潔にわかりやすく説明が付されている。問題提起としては、省略したままで読み取れると思うが、実際に書物にあたれば、なお読み手に分かりやすく親切な書き方になっていることが分かる。
「…本書でとりあげるほぼすべての数字は、4種類の一次資料からのみ引用している。」(13ページ)
この4種類は、文中に、もちろん、明記されている。著者が、信頼できるものとみなす資料から直接引用しているということである。
「数字はウソをつかない(ナンバーズ・ドント・ライ)。その事実のみならず、数字がどんな真実を伝えているのかを、さまざまな例を挙げながら説明したい。」(17ページ)
ということで、全7章、71項目にわたって解説が行われる。
私なりに、何か所かピックアップして紹介していきたい。
まずは、第3章「食」、第24項「食品(フード)ロスはグローバルな大問題―いますぐ行動を!」から。
「…全世界で生産・採取された食料の少なくとも3分の1は廃棄されているのだ。」(123ページ)
なんと、3分の1にも上る分量が廃棄されているという。
「フードロスは栄養物が無駄になるという話だけではすまされない。そうした食料を生み出すために要した大量の労働力やエネルギーも必然的に無駄になるのだ。田畑で耕運機や灌漑用ポンプを使用するといった直接的な労働力やエネルギーだけではなく、そうした機械やその材料として必要な鋼鉄、アルミニウム、プラスチックの製造、肥料や農薬の合成といった間接的な労働力やエネルギーも、ただ浪費されることになる。農業に余計な負荷がかかれば、土壌侵食、窒素の地下水などへの溶出、生物多様性の喪失、薬剤耐性菌などの問題を引き起こし、環境破壊にもつながる。これに加えて、全世界が排出している温室効果ガスの10%程度にもあたる量を、結局は廃棄されてしまう食料の生産過程で排出しているのだ。」(126ページ)
驚くべき浪費というほかない。このままでは、早晩、地球は、人の住めない場所と成り果ててしまう。人の生活の継続自体が、人の生活の継続を妨げるというパラドクス。
現在、斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』(集英社新書)などで関心を呼んでいる言葉である「人新世」について、第4章環境の第34項、「人新世と呼ぶのは時期尚早」で論じている。
「歴史家や科学者の多くが、われわれはいま「人新世(アントロポセン)」を生きていると主張している。つまり、人類が生物圏を支配するという特徴をもつ新たな地質年代「人新世」がすでに始まっているというのだ。…
これに対するわたしの意見は,古代ローマの格言にならって「フェスティーナ・レンテ」、すなわち「ゆっくり急げ」だ。」(169ページ)
人類の地球環境への介入によって、人類の未来が危険にさらされているのは間違いないところだが、しかし一方で、人類が介入できない条件も多いという。これまでの地質年代の決め方から言っても、現在の「完新世」が始まって1万2000年も経過していない現時点では、判断は時期尚早であろうと述べる。
「というわけで、人新世に入っているかどうかは、あと1万年ほど待ってから決めるべきだろう。」(172ページ)
第5章「エネルギー 燃料と電気をめぐる不都合な真実」の第43項「原子力発電 果たされない約束」では、以下のように述べる。
「わたしは10年以上前に、このテクノロジーに対して「いったんは成功をおさめた失敗という評価をくだした。以来、この評価は変わっていない。」(210ページ)
原子力発電は、確かに、いったんは成功したかに見えたという。
「ところが1980年代になると、核分裂を利用した発電プロジェクトは失速した。先進国の電力需要が落ち込むと同時に、原子力発電所の問題が次から次へとあきらかになったからだ。…1979年にはペンシルベニア州スリーマイル島で、1986年にはソ連(現在はウクライナ)のチェルノブイリで、そして2011年には日本の福島で原子力発電所の事故が起こり、いかなる状況においても核分裂に反対する人たちにさらなる根拠を提供したのである。」(211ページ)
スリーマイル、チェルノブイリ、そして福島である。私に言わせれば、これだけで、原子力の問題点は明らか過ぎるほどと言いたいが、著者は、コストの問題も語るし、技術改良への期待も語る。
「そのうえ、原子力発電所の建設費用も見積よりも高い状態がずっと続いていて、使用済み核燃料の最終処分方法についても許容できる状態が見つからず、失望させられる状況が続いている。」(211ページ)
「いま、わたしたちにできることはたくさんある。なにより、まず原子炉の設計を改善し、放射性廃棄物の問題をおろそかにしないことだ。そうすれば原子力発電のシェアを大きく拡大し、二酸化炭素の排出を抑えられる。しかし、そのためには先入観をもたずに事実の検証を行い、地球規模のエネルギー政策に対して真の意味で長期的な手法を採択しなければならない。だが、いずれの動きも全く見られないのが現状だ。」(213ページ)
一見、著者は、原子力発電を否定しておらず、推進しているようにも見えるが、「放射性廃棄物の問題」を解決するような「原子炉の設計の改善」は可能だろうか?
むろん、それが可能なのであれば、それはそれで可としてもいいわけであるが。
ここは、原子力にあからさまにノーと言わないための著者一流のレトリック、というふうに言ってしまってもいいと私は思う。他の再生可能エネルギーの利用も、そんなに単純に推進できるばかりではないなかで、一つの選択肢として一応は検討の遡上に載せておくべきだということではあるのかもしれない。
さて、私にとって、ここは新しい発見と思わされたところが、第7章機械第62項「奇跡の1880年代」である。
「じつのところ、人類史でもっとも創意工夫に富んだ時代は1880年代だったのではないかと、わたしは考えている。そもそも電気と、動力を生み出す内燃機関の発明ほど、現代世界の基盤をつくった画期的かつ根本的な発明はないはずだ。」(290ページ)
「電磁波の研究が進んだのも1880年代…」(291ページ)
だという。
詳細は、直接あたってほしいが、
「10年以上前、わたしは著書『20世紀をつくりだす(Creating the Twentieth Century)』のなかで、この奇跡の10年間に生まれた日用品を紹介する形で、アメリカ人の日常生活を追ってみた。
たとえば現代のある朝、1人の女性がアメリカの都市で目を覚まし、…」(292ページ)
から始まる一節は、なかなかに面白く読ませられた。1960年代、私が子どもの頃に、家の茶の間のテレビで見せられたアメリカのホーム・コメディ、憧れのアメリカン・ウェイ・オブ・ライフが思い起こされる。5~60年代のアメリカの繁栄は、188年代に準備されていたことだったというのだ。
同じく第七章第71項「真のイノベーションとは」で、著者は、
「現代社会はイノベーションにとりつかれている。」(328ページ)
という。しかし、イノベーションを、何の疑念も差し挟まずに崇めたてまつるのはまちがいだと言う。
「そうした失敗に終わったイノベーションの第一のカテゴリーに分けられる代表格は、やはり高速増殖炉だろう。発電しながら消費した以上の核燃料を生成するという触れ込みだったものの、結局、長々と莫大なコストを食うばかりでほとんど稼働せず、イノベーションの失敗例となって終わったのである。」(329ページ)
「ほかにも、…水素(燃料電池)自動車、磁気浮上式鉄道(リニアモーターカー)、核融合エネルギーなどがある。」(329ページ)
現代社会がとりつかれているのは、イノベーション、そして、GDP、である。
「さらに、経済指標としてGDPを利用することにも納得がいかない。なぜならGDPは、国内で1年間に取引された商品やサービスの付加価値の総額に過ぎないのだから。生活の質が向上して経済が成長した場合だけではなく、国民や環境に悪影響が及んだ場合にも、GDPが増加する可能性はある。…さらに熱帯地方で違法な森林伐採が増え、森林破壊が進み、生物多様性が失われ、木材の売り上げが伸びても、やはりGDPは増大する。このようにGDPを指標にしたところであまり当てにならないとわかっていながら、世間はいまだにGDPの成長率に一喜一憂し、高ければ高いほどありがたがっている。」(331ページ)
私に言わせれば、著者は「現代社会は、イノベーションを止めて、GDP信仰を止めなければならない」と主張している、のだと思う。ところが、「おわりに」では次のように言う。
「たとえ、かなり信頼が置けるものであろうと、それどころか、申し分ないほど正確なものであろうと、数字はかならず多角的な視点から見なければならない。情報に基づいて絶対的な価値を評価するには、相対化や比較化という視点が必要なのだ。」(332ページ)(下線部は、引用元では傍点)
あくまで、客観視し、俯瞰しようとする。それはそれで、必要な姿勢ではあるだろう。というか、相対化や比較化の視点は必須のことにまちがいはない。
経済成長などもはや幻想でしかない、むしろ、害悪しかもたらさない、などと断定してしまっては、いたずらに読者を失う愚におちいるのみであるのかもしれない。
さて、この書物の訳者のひとりは、熊谷千寿氏である。気仙沼市唐桑町出身、在住の翻訳家。英米のミステリ小説が専門といっていいと思う。この本を購入したのは、彼のフェイスブックでの紹介を見てのことである。しばらくお会いできていない。そろそろ連絡してみよう。
熊谷(くまがい)千寿(ちとし)氏 講演会 『翻訳家の仕事』
ロバート・ハリス 熊谷千寿訳 ゴーストライター 講談社文庫
熊谷千寿氏コーナー 唐桑コミュニティ図書館


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます