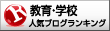原発ドキュメンタリーの変化
福島原発の事故から1年目の3・12を過ぎ、テレビや新聞や雑誌をはじめとする各媒体が原発事故を取りあげる機会が減ってきている。1年間にわたる「禊ぎ」が済んでしまえば、この列島に住む人々にとって、原発事故による健康被害という災厄ですらも、徐々に忘却のなかで薄れていってしまうのだろうか。セシウムをはじめとする放射性物質による汚染が消えたわけではないのに、それに慣れてきて意識しなくなっている現状に、私たちは危機感を覚えていいはずである。
そんななか、映画館で公開される震災や原発問題を扱ったドキュメンタリーの質も少し変わってきている。これまでのように震災被害や原発事故をテーマとして直接扱うものから、長い時間軸のなかで原発や原子力エネルギーと人類との関係を再考させるものが増えてきた。そこで示されるのは、原発事故が起きようと原爆が投下されようと、災厄の後でもその土地で生き続ける人々がいるという事実である。
チェルノブイリと「ゾーン」
たとえば、1986年の4月にウクライナで起きたチェルノブイリの原発事故から12年後のこと。チェルノブイリの原子力発電所から30キロメートルの圏内は、環境に漏れた放射性物質によって人間が住めない高放射線量の地域となり、政府が厳重に出入りを制限する、通称「ゾーン」となっていた。これはタルコフスキーの映画『ストーカー』の物語ではなく、実際のウクライナの一地方の話である。
ドイツのドキュメンタリー作家のニコラウス・ゲイハルターは、少人数のスタッフとともにゾーンへ入って撮影を行い、『プリピャチ』という作品にしている。『プリピャチ』とは30キロ圏内にあるために、完全なるゴーストタウンと化した街の名である。ゾーンは鉄条網によって立入禁止になっているのだが、映画はゾーンに出入りする原発のエンジニア、警備員、自主的に圏内へ戻った居住者、ゾーンを出入りする元プリピャチの住人といった、汚染された土地に留まって働いたり生活したりしている人々に取材を重ねる。
『プリピャチ』によれば、チェルノブイリの原子力発電所では、事故を起こした4号炉の「石棺」は終わったものの、廃炉にともなう膨大な量の作業が行われている途上である。しかし、そこで働くエンジニアや従業員たちには十分な報酬が払われていない。カメラの前で現場責任者が「食料は無料だが、ここの給料では普通に食べていくことすらできない」と漏らすとき、あまりのことに戦慄すら覚える。彼らには安全基準を遵守しながら、廃炉という数十年に及ぶ作業を貫徹する能力が本当にあるのだろうか。
事故を起こした4号機の隣では、他の原子炉が稼動し、相変わらず原子力発電を行っている。廃炉や発電を行うエンジニアに十分な待遇をせずに、はたして安全など守れるのだろうかと疑ってしまう。あれだけの大事故を起こした後でも、相変わらず、どこか上層では彼らの金銭が掠め取られているのかもしれない。インタビューで「政府は線量を計らないし、公表もしない」と語るチェルノブイリ近郊の住民の証言があったり、また近郊の関連の産業で働く男は「放射能の影響は心配していない」と強がって言ったりする。それらの言葉を聞くたびに、10年後のフクシマの未来図が透けて見えてくるかのようだ。私たちの戦いは長期的なスパンにおいて、徐々に脱原発を達成していくことはもちろんだが、放射性物質に汚染されることに馴らされてはいけないということ、それらを忘却しないよう、くり返しくり返し想起しなくてはならない、というところへ入ってきているのだ。
そうはいっても、『いのちの食べ方』ゲイハルターであるだけに、『プリピャチ』は単純な反原発ドキュメンタリーではない。立ち入ることのできない原発事故後の30キロ圏内の映像と、ゾーンに出入りする人々へのインタビューで構成するのだが、主眼は別のところにありそうである。バウハウスの建築デザインを思わせる、計算され、美しい構図で映し出されるゾーン内の原子力発電所内部のモノクローム映像は、不穏なまでに美しい。その機能美の極限にある原子力テクノロジーが持っている禍々しさが、そこには言語を介さない形で直接的に表象されているのだ。
原発投下という「実験」
私たちにとって人体に影響のある放射性物質と放射線量の問題は、つまるところは目に見えない、におわない、語感で感じることができない特性にある。だが、診察する医師にとっては、少し問題のあり処が違ってくる。フランス人監督の手によるドキュメンタリー『核の傷 肥田舜太郎医師と内部被爆』では、自らが広島の被爆者であり、長年被爆者の治療にあたってきた医師・肥田舜太郎が次のように語る。
「病院へ行って調べても、放射線の影響だということは絶対わからない。調べる方法がない、証明のしようがない。だから僕たちは〝同じ症状がこんなに起こった〟という、数で話をするしかないんです」。肥田医師は、『核の傷』撮影時には85歳で現役の医師であり、2012年現在では、唯一存命している95歳の被爆医師である。『核の傷』が観る者に与える感銘は、医師として原爆投下後の戦いに身を捧げた、この医師の生のあり方に多くを負っている。 
原爆が落ちた場所から数キロメートルのところにいて、20代で被爆した肥田医師によれば、アメリカが広島に原爆を落としたのが午前8時15分だったことは偶然ではなかった。広島市に住む人たちが、屋外や遮蔽物のないところへ出ている時間が何時なのか、偵察をした上で周到に時間を決めたという。そして、原爆投下直後にアメリカはABCC(原爆障害調査委員会)を設立し、文字通り人体実験を行っていった。
このドキュメンタリーでは、広島フィルム・コミッション、アメリカ国立公文書記録管理局、平和博物館を創る会、ヒューストン医師会などにアクセスして、原爆投下直後の広島のカラー映像や、アメリカの機関ABCCによって調査された被爆者たちの身体映像が次々に映し出される。その悲惨な姿も十分にショキングだが、それ以上に衝撃的なのは、ABCCが原爆の犠牲者たちの検査だけをして、治療を決して行わなかったという史実の方である。治療をすれば、原爆を落としたことの非を認めることになるからだ。
「まずは火傷とか、怪我など、外側を診ます。その後入院させていろいろ検査する。死ぬと全部解剖して、全部切り刻む。脳から内臓全部瓶の中にいれて、消毒液をいれて、バンバン本国へ運ぶわけ。解剖したら体がからんどうになるから、その中に藁くずを入れて、仮縫いして家族にもどしていた」と、肥田医師はいう。これは私たちと無関係な過去の事象ではない。放射能の人体に対する影響の知識や、放射線の人体にとっての限界量は、これら広島や長崎の被爆者に対して行われた「実験」を通して得られたものであるからだ。
このような非道が行われていたのにもかかわらず、アメリカと日本の政府は「被爆者で病気やけが人は一人もいない」という報告書を国連に出していたらしい。「科学」を名乗る集団が、そのような嘘の報告書づくりに加担するのだ。どこかで見た光景である。戦後30年経って、次第に内部被爆の影響が判明するなかで、肥田医師は国連に被爆者の実態を訴えるが、証拠がないと言われた。そこで、さまざまな団体と共同で1万人の被爆者から証言を集めて、国連にようやく被爆者の実態を認めさせたという。
いつも不思議に思うのは、どうしてこのような公然とした虚偽がまかり通り、人々は見てみないふりをし、当事者ですらそれがなかったことのように忘却できるのか、ということだ。『核の傷』では、スターングラスという放射線物理学者がインタビューで、誰もが抱くその疑問に見事に答えている。「(アメリカ)政府は放射線の影響を公にしたくなかったのです。影響が解明されるまでの5~15年間に原子炉建設がいくつも計画され、ウラン発掘に巨費が投じられていました。石油や石炭がやがて不足して、原子力が必要になると考えたからです」。
スターングラスによれば、原発の風下に住む人々が癌で死んでいくことは明白な事実である。「アメリカや欧州で出版された数々の資料によると、原発が稼動しているとき癌発症率は急激に上昇して、閉鎖後は減少します」という。それでは何故、誰も原発を閉鎖しようとしないのか。そこには、私たちの生活を支えるエネルギーの問題、地域の雇用、経済への影響、政府や電力会社や建設会社の思惑が複雑に絡まっている。そして、最後には何となく慣れてきて「健忘症」がおとずれる。ひょっとしたら、私たちは豊かな生活を享受し、その代償として健康を害し、死んでいくのにふさわしい愚者にすぎないのかもしれない。原発や核兵器を止められない人類など存続するに値しないが、それでは、地球上の自然や他の動植物に申し訳ない気もするのである。
② 山形国際ドキュメンタリー映画祭2009
③ 『鏡の中のマヤ・デレン』『聖なる騎士たち:ハイチの生きた神々』 ④ 『アメリカ ―戦争する国の人びと―』『One Shot One Kill―兵士になるということ―』
⑤ 座・高円寺ドキュメンタリー・フェスティバル