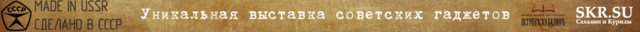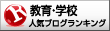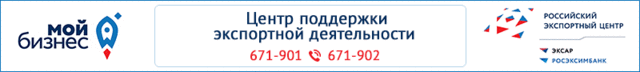2018年7月21日
読売新聞の読書委員を同じ時期に務めて以来、親しくされている梯久美子さんと三浦しをさん。先日、三浦さんの新刊『ののはな通信』(KADOKAWA)をめぐってお二人が対談された際に、梯さんが原民喜の評伝を執筆中と明かされたところ、三浦さんも子どものころに「夏の花」を読んで以来、原民喜がお好きだとのことで、意気投合されました。梯さんの新著『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(岩波新書)の刊行を記念し、あらためてお二人に、原民喜への思いを語りあっていただきました。原民喜の人間性と作品を愛おしむ対談となりました。
「夏の花」との出会い
梯:最近は広島でも原民喜や「夏の花」を知らない若い人がけっこういるそうなんです。私たちの世代は「夏の花」が教科書に載っていましたし、原爆文学といえば原民喜だと思っていました。
今はTwitterなどで「原民喜」で検索すると、本屋大賞を受賞し映画化もされた『
羊と鋼の森』に原民喜の言葉が引用されているという話題がほとんどです。これがまた原さんらしい、いい言葉なんですけどね。
三浦:それは「夏の花」からの引用ではないんですよね?
梯:「沙漠の花」というエッセイの中で、文体について述べている部分が、登場人物の調律師がめざす音として紹介されています。
「明るく静かに澄んで懐しい文体、少しは甘えてゐるやうでありながら、きびしく深いものを湛へてゐる文体、夢のやうに美しいが現実のやうにたしかな文体……私はこんな文体に憧れてゐる。だが結局、文体はそれをつくりだす心の反映でしかないのだらう」
原民喜を原爆作家だと意識せずに、この言葉に惹かれる若い方が多いようで、〝原爆作家″という肩書を外しても、時代をこえて人の心をひきつける力が原の文章にはあるんだなぁと、あらためて思います。
三浦:本当にそうですね。梯さんは、何をきっかけに原民喜をお読みになったんですか?
梯:中学か高校のときに読んだ「夏の花」ですね。それ以外の作品に出会ったのは、ずいぶんあとのことです。
三浦:たしかに、「夏の花」は原爆を描いたすごい作品ですが、原民喜はそれ以外の小説にもすばらしいものがある。そこが大事なポイントですよね。今回の梯さんのご著書は、原民喜の人生や作品についてよく知ることができて、もう一度、原民喜を読みかえそうと思えるものでした。
私は「夏の花」と出会う前、小学校2年生のときに『はだしのゲン』のアニメを学校の体育館で観たんですよ。それが衝撃だったんです。明日にもみな原爆で死ぬんだと、本当に怖くて夜も眠れなくなりました。後年、高校生ぐらいになって、アメリカ人の作家、ティム・オブライエンの『ニュークリア・エイジ』という、冷戦時代、主人公が核の恐怖に怯え、庭にシェルターを掘るという小説を読んだときに、「この気持ち、めっちゃわかる!」と思いましたから。
『はだしのゲン』を見てから2年間ぐらい、原爆が怖くてたまらない毎日でしたが、そんなときに家の本棚にあって好きで読んでいた『少年少女のための日本文学宝玉集』という本に、「夏の花」が入っていたんです。
梯:(本の実物を)あ、持ってきてくれてたんだ!
三浦:(古くて)崩壊してきてるんですけど(笑)。母が子どものときに読んで、結婚するときに持ってきたんでしょうね。原爆の恐怖から抜けきれないときに、この本で「夏の花」を読んで、ショックではあったんですが、原民喜の文章を通じて、「あぁ、そうか、実際に体験した人がいるんだから、どういうことがあったのかをもっと知りたいな」と思えるようになったんです。それ以降、戦争文学といわれるものを読むようになりました。
その後、高校の教科書に「夏の花」が載っていたのをきっかけに新潮文庫版を買ったら、原爆の前に病気で亡くなった奥さんのことを書いた小説も載っていて、それがすごくよくて。
梯:私も奥さんとの日々を描いた作品が、実は一番好きです。
三浦:当然のことではあるんですが、この人は原爆に遭ったから書けたわけではなくて、もともと小説に真剣に取り組んできたからこそ、自分が体験した原爆についてあのように書くことができたし、私の中の怖かった気持ちを、その先へと導いてくれたんだと感じました。原爆作家としてだけでなく、多面的な魅力のある小説家だと思います。
身近にいそうな青年
梯:原民喜の文章からは不思議なくらい昭和の匂いがしない。なんというか、ものすごく「今っぽい人」なんです。「コミュ障」(コミュニケーション障害)という言い方がありますが、今だったらそんなふうに呼ばれるタイプでしょう。
繊細すぎて人と接することが極端に苦手。中学校の5年間、教室で一度も口をきかなかったというぐらい、とにかく世間が怖い人だった。戦前に広島から慶応大学に進学するというのは、かなり頭がよい、いいとこのお坊ちゃんなんですが、相当生きづらかったと思います。
三浦:梯さんの御本を読むと、大学も留年しまくってますよね。普通、親もそこまで学費を払えないじゃないですか。卒業しても就職しないで、ずっと実家に援助してもらって、そうとうダメ人間なんですよね。そこもまた、いいんだよなぁ(笑)。
梯:ずっと就職しないままで、生涯、所属できたコミュニティは同人誌だけですから。主な寄稿先だった『三田文学』も同人誌ですし、商業的な雑誌に書いたのは『群像』ぐらいで。
三浦:商業雑誌に書くようになったのも戦後になってからですよね。今でいうオタクで、すごくよくわかる。
梯:表紙の写真も、昔の人という感じがしないでしょう? ちょっとお洒落な感じで。
三浦:梯さんの本にはけっこうお写真が載っていて、子どもの頃も、すごくかわいいいんですよ。奥さんとの写真も、仲が良かったのが伝わってくる。その写真の原民喜もまたかっこよくて、働かずに小説書いてても、この旦那なら応援しちゃうだろうなって思います(笑)。優しいですしね。
梯:本人は結婚したくなかったんですが、いつまでもニートみたいなのはまずいと、親が相手を見つけて結婚させたんですよね。
三浦:就職もしていないのに(笑)。
梯:左翼運動で一度つかまっていますし、東京でわけのわからないことをしていると、実家は心配したんでしょう。原民喜は太宰治に似ているんです。年は原民喜のほうが4歳上ですが、地方のお金持ちの出身で、東京の大学に出てきて、実家にコンプレックスがある。原民喜の実家は原商店という繊維商で、軍に軍服などを納めていたので、そのうしろめたさがあったようです。そして左翼運動に参加して、挫折するんですよね。
同級生の山本健吉は運動でけっこうえらくなっていくんですが、山本健吉の回想を読むと、原民喜が街頭連絡をする姿を偶然見かけたら、前のめりになって道を歩いて、見るからに挙動不審で(笑)。結局は捕まって拘置され、心の傷が残ってしまったようです。
それで卒業しても就職しないから、親が結婚しないと仕送りを止めるといってお見合いさせたんですね。
三浦:ダメ人間を助長するような条件だ(笑)。
梯:でも、この奥さんがあたりだったんですね。
三浦:すごくいい奥さん。お写真も載っていますが、とてもきれいな人。わりとポンポンものを言う人で、原民喜をうまくフォローするし、あなたは絶対にいいものが書けると励まし続けるんですよね。ふつう、できませんよ、そんな一文も稼いでいない旦那に!(笑)
梯:読書家で文学好きの人だったようで、夫の才能を信じて応援するんですよね。
三浦:この御本に奥さんの俳句も載っていますが、すごくいい感じです。
梯:結婚したころの原民喜は同人誌にしか発表していなくて、まだ作家でもなんでもなく、結婚して三年目に本を出すんですが、それも自費出版なんです。
三浦:聞いててつらいわ、ほんとに(笑)。
梯:民喜が唯一話しのできる相手が奥さんで、お医者さんのところに行って説明するのも、奥さんに付き添ってもらう。
三浦:佐藤春夫に自分の小説を見てほしくて会いにいったときも、奥さんが全部通訳して。
梯:佐藤春夫が、小学生が母親に連れられて叱られにきたようだったと書いていますからね。その奥さんが、結核で入院してしまう。そして、戦争が始まると、原は実家の会社の株の配当などで食べていたので、株の値段が下がって生活が大変になる。それで、初めて学校の嘱託講師として働き始めるんです。
三浦:学校が嫌いで、しゃべるのが苦手な人が、どうしてそんな無茶を!
梯:学歴はありますからね。他にできる仕事がないので、週に三日だけ。奥さんが家にいなくてさびしいから、仕事のない日はお見舞いに行く。妻のベッドの側ですごす時間が唯一の安らぎなんです。その奥さんが結婚11年半で、33歳で死んでしまうんです。
三浦:つらすぎますよね……。
梯:原民喜は夫婦で千葉に住んでいましたが、昭和19年9月に奥さんが亡くなって、実家に帰ることにするんです。すでに東京の空襲が始まっていて、千葉はB29の通り道で空襲警報が頻繁に出ていたので、疎開のつもりで広島に帰ったら、そこで原爆に遭ってしまう。
静かに頑固な抵抗者
梯:原民喜は原爆作家として有名ですが、そこに至るまでは、幼少期を描いた幻想的な小説、それから詩や童話を書いていました。
三浦:原爆に遭う前から、奥さんとのやりとりや子どものころのことを書いていても、幻想的というか、夢の世界というか、あの世のことを書いているような作品が多いですよね。私小説とは手触りが違う。もとから、他の人には聞こえない声を聴くことができる繊細な人で、いつも黙って、他の人にはわからない何かに耳を澄ませていたんだと思います。
梯:大好きなお父さんもお姉さんも早く亡くなってしまい、妻も33歳の若さで亡くなっています。愛する人に先立たれる運命を背負った人で、死者が身近なんですね。亡くなった人に心の中で語りかけながら、ものを考えたり、書いたりしてきた。
すごく怖がりで、慶応の予科のころから始めた俳句の号が「杞憂」。「杞憂」はもともと、中国の古代の人が天が落ちてくるのではないかと心配したことから、心配しないでいいことを心配するという意味ですよね。それと同じように原民喜は、そういう幻想にずっと囚われていた。
三浦:彼にとっては幻想ではないんですよね。千葉から広島に帰るときも、広島がこのまま無事なはずは絶対ないと思っている。戦争が始まったときから来るべきものが来たと思っていて。大政翼賛的な小説もぜんぜん書いていないですし。
梯:昭和19年の『三田文学』に、戦地の兵隊さんを慰問するための特集号があって、みんなすごく勇ましくてヒロイックなものを書いているのに、原民喜は違うんです。
三浦:今読むとヤバいなというものをみんな書いているのに、原民喜だけ一人、ぜんぜん空気を読んでいない。
梯:わかっていてあえてそうしたんだと思います。戦地にいる弟に宛てた手紙の形式なんですが、学校帰りの先生が駅のツバメの巣を見ているとか、貝を剥いて売っているおじさんを見たとか。
三浦:牛が「もーお」と鳴いて、兵隊さんが牛の耳を撫でたとか、なんなのこれ?!ですよ(笑)。原稿をもらった編集者も、「慰問特集なんだが」と困惑したでしょうね。
梯:詩のような日常のスケッチですが、これは当時としてはかなりの抵抗だったんだと思うんです。
戦時中、抵抗詩を書いた人として金子光晴などの名前がよく挙げられますが、以前、吉本隆明さんの聞き書きの本を作ったとき、吉本さんは、当時の抵抗詩は、秋山清という詩人がアッツ島の玉砕をうたった詩ぐらいだというんですね(「白い花」1944年)。兵士が突撃する直前に家族や故郷への思いを秘めて地面に咲いている小さな花に目をやって死んだだろうという詩で、それが当時できた最高の抵抗表現だったと。
原民喜の牛の耳がどうしたというのも、『三田文学』でできることのぎりぎりを確信犯的にやったんだと思います。
三浦:検閲だってあるでしょうからね。
梯:原民喜があえてやった空気の読まなさかげんは、今読むとすごいものがあると感じます。かなり頑固な方だったんじゃないでしょうか。
三浦:そうじゃなきゃ、実家からの仕送りでずっと小説を書こうだなんて思わないですよ。そうとうな覚悟と頑固さがある。自分はこれしかできないし、これをやりたいんだと、心に期するものがあったんだと思います。
梯:小学生のころから作家になりたいと言っていましたから。お兄さんの影響やおうちの文化的な背景も大きいですね。
三浦:兄弟で家庭内同人誌を作って。最初の同人誌の名前が『ポギー』でしたっけ。かわいい(笑)。
最期を迎えた場所に
梯:ここ(神保町)は原民喜ゆかりの土地なんです。原民喜が亡くなったときに住んでいたのは吉祥寺駅の南側ですが、その前はこの近くに今もある能楽書林に住んでいました。原民喜は昭和21年の春に広島から再び上京して、住むところがなくて転々とし、酷い目に遭うんですね。
三浦:コミュ障の原民喜が、戦後の混乱している東京、生き馬の目を抜くような状況で、いいお部屋を探せるわけがない!
梯:だまされて汚いところを仲介され、権利金もちゃんと払ったのに、前に住んでいた担ぎ屋のおばさんが荷物を置きっぱなしにして出ていってくれない。
三浦:出ていってくれと強くも言えなくて、なぜか同居。ほとんど不動産屋の詐欺ですよ。
梯:奥さんの弟が文芸評論家の佐々木基一なんですけど、彼の回想に、原民喜がひとりで何かをすると、ろくなことにならないと書いてある(笑)。
三浦:優しいし、放っておけない感じの人だから、お友達はいい人たちばかりですね。
梯:戦後、『三田文学』が復刊したときに編集長を務めた能楽書林の二代目の丸岡明さんという方が、『三田文学』の発行元も能楽書林で引き受けていた時期があったんです。その丸岡さんが、自分ところのビルが焼け残っているから、そこに住んだらどうかと世話してくれた。
原民喜のゆかりの場所はいろいろとあって、鉄道自殺をしたのは西荻窪と吉祥寺の間で、私、その場所をほぼ特定しまして。
三浦:その話をぜひ聞かせてください。
梯:私は亡くなった人のことを書くときにはお墓参りをすることにしていて、原民喜のお墓は広島に行くたびにお参りしているんですが、今年は命日に彼が亡くなった場所でお花を供えたいと思って、西荻窪に行きました。3月13日の午後11時30分に西荻窪駅を出た電車に轢かれているんですが、訃報の新聞には吉祥寺に向かって出発し、200メートルほど進んだところに横たわっていたとある。私、地図を読むのが得意なんで、縮尺から、このあたりかな、と見当をつけたんです。今は高架になっていますが、昔は築堤で……
三浦:ちくてい? ああ、土手みたいなもの?
梯:鉄道用語では築堤っていうんですよ。すみません、私、鉄道オタクなので(笑)。その築堤の上を電車が通っていて、原さんがそこにのぼって線路に横たわるのを若い女性二人が目撃していたんですね。証言によれば階段か梯子をのぼったという。昔あった設備は形を変えても残っていることが多いんです。原民喜が亡くなったと思われるあたりに行ってみたら、点検用なのか、今も階段がありました。
本の最初に書きましたが、原民喜が亡くなる前日に訪ねた鈴木重雄という『三田文学』の後輩が、庭のクロッカスを掘って鉢に入れたのを原さんに渡したのだけれど、置きざりにして帰ってしまった。翌日死ぬと決めていたからでしょう。それで命日にクロッカスを供えようと思ったんですが、クロッカス、今はほとんど売っていないんですね。自宅の近くや西荻窪の花屋さんをいくつも探したけれど、鉢植えでも見つからなかったので、次善の策としてヒヤシンスを用意しました。
三浦:違うけど、まぁ、球根だし(笑)。
梯:麻ひもで小さな花束にして、ビニルなどはかけないで持っていって。その階段のまわりは、人が入れないように囲われていて、土の出ているところがあったので、お花を供えられてちょうどよかったです。
今回、この本が出て、イベントに来てくださいという話も、広島、神保町、西荻窪、千葉と、不思議に原民喜に関係のある場所の書店さんから声をかけていただいているんです。
この世とあの世の境で
三浦:原民喜が千葉に住んでいたのを知らない人も多いですよね。作品にも出てくるのですが、「千葉だ」とあまり意識されていなくて。
梯:実は奥さんと10年近く住んでいて、一番幸せなときだったんですよね。
三浦:その時代を書いたものは、ほんとうにいいんですよ。戦後、奥さんと一緒に住んでいた千葉のおうちのあたりに行ってみたときの小説があるんです。そうしたら駅前もそのままで、家もそのままで。それをさらっと書いているんですが、情景が浮かぶようで、そのときの原さんの気持ちを思うと、何回読んでも泣いてしまう。
梯:奥さんの臨終の場面について、お前が亡くなった話を、いつかお前とできるような気がすると書いている作品もありますよね。すべてを話せる魂の通じあった相手は奥さんしかいないから、愛する人を看取ったという特別な経験や気持ちを、当の死者である奥さんにこそ話したい。幽冥の境があいまいというか……。
三浦:今まさに死んでいこうとしている奥さんを見ているときも、すでに自分の魂もあの世にあるようで、客観的とも冷静とも冷酷とも違う、なにか不思議な浮遊感なんですよね。
梯:原民喜について書いてみたいと思ったのは、彼の遺書を読んだからなんです。義弟の佐々木基一宛の遺書が、あまりにも静かで、美しくて……。
「ながい間、いろいろ親切にして頂いたことを嬉しく思ひます。僕はいま誰とも、さりげなく別れてゆきたいのです。妻と死別れてから後の僕の作品は、その殆どすべてが、それぞれ遺書だつたやうな気がします。 岸を離れて行く船の甲板から眺めると、陸地は次第に点のやうになつて行きます。僕の文学も、僕の眼には点となり、やがて消えるでせう。」
すでに死者の側に立って書いているような文章ですね。鉄道自殺という壮絶な死に方をし、原爆にも遭っている人が、こんな遺書を書いていることに惹かれました。
三浦:晩年に遠藤周作と一緒に出会って仲良くなった女の子に宛てた詩も遺されていて、それがすばらしくて。大岡信さんが紹介されているので知って、そのときは原民喜がどういう亡くなり方をしたのか知らない中学生ぐらいだったんですが。
梯:中学生であれを読んだんですか。さすが!
「濠端の柳にはや緑さしぐみ……」で始まる「悲歌」という詩ですね。濠端というのは、このあたり(神保町・九段下)ですね。原民喜が42歳、『三田文学』の後輩の遠藤周作が25歳のときに二人は出会って、この人、一人で生活できるのかな? というような危なっかしい原民喜を、遠藤周作は何かと世話をやいていた。近所に行きつけの「龍宮」という飲み屋があって、連れだって行ったり。ある日、原民喜と遠藤周作と、もう一人『三田文学』の仲間の三人が、能楽書林の近所を歩いていたときに……あ、これ、ネタばれになっちゃうかな。
三浦:もういいよ、梯さん! あとは御本を読んでもらおうよ!(笑)
そこで、ほほえましい、とてもいいエピソードがあって、21歳の女の子と仲良くなるんですね。その彼女に、ほんとうに美しい詩を遺して。お友だちに宛てた遺書にも「お元気で」と必ず書いてあって、この人はなんて優しい人なんだろうと思います。
自ら選んだ死をどう考えるか
梯:原民喜が自死した事実をどんなふうに伝えるかは、評伝を書く上で難しいことでした。この本は、原民喜の作品に、原を知らない若い人たちに出会ってほしいと思って書いたんですね。新書で出したいと思った理由も、そのへんにあります。高校生ぐらいから読んでほしいのですが、原民喜の思いに寄り添って書くと、若い人たちに自殺を肯定すると受け止められるのではないかと悩みました。普通に時系列で書いて、さらっと「こんなふうに亡くなりました」で終わることもできたのですが、でもやっぱり、自死のことを避けてはいけないんじゃないかと思って。
三浦:私も、そう思います。
梯:それで、彼の自死をあえて序章にもってきました。こんなふうに亡くなった人なんだ、ということを頭に置いた上で、原の人生をたどってほしいと思って。もうひとつ、書くことによって、彼がどうしてそういう死に方をしたのか理解することが、私自身にとって必要だったんですね。書き手には、書いてみることで初めてわかるということがある。
三浦:きっとこうにちがいないとか、自殺は絶対的に悪だとか、結論ありきで書けることではないですし。
梯:はっきりと一言で言えるような結論は出ませんが、原民喜は絶望して死んだ感じでもないんですね。
三浦:はい、そうは思えないですね。
梯:亡くなる前の年に朝鮮戦争が始まり、また核戦争が起きるんじゃないかという恐れやおびえも詩や手紙に書いているので、この世に絶望していたという考え方もできなくはないのですが、でも、たくさんある、どの遺書にも、希望が書いてある。すべて、相手の幸福を祈る言葉でしめくくられています。『群像』の大久保房男さんにもネクタイをかたみわけで残して、「あなたはたのしく生きて下さい」と。
三浦:ネクタイといったって、原民喜は貧乏で、そんなに服を持っているわけではないのに、その中でいいものを選んで、これは誰々に、と、かたみわけができるように準備して、お元気で、と伝えて。どうなんでしょう……原民喜が自殺したことを、今の若いかたたちが知っても、彼の遺した作品や言葉を読めば、それに引きずられることはないんじゃないかと思います。
梯:「鎮魂歌」という作品には、くりかえし、自分のために生きるな、死者の嘆きのためだけに生きよ、と書いています。原は奥さんがすべてで、妻と死に別れたら、美しい悲しい詩集を一冊だけ書き残すために一年間だけ生き残ろうと書いていました。
それが、原爆が落ちたときに厠にいて、家も頑丈で倒壊せず、ケガひとつなく助かってしまった。それで、2日目の夜、野宿していた神社の境内で、原爆が落ちた瞬間からそれまでのことを雑嚢に入れていた手帳に鉛筆で記録します。そこに「コハ今後生キノビテコノ有様ヲツタヘヨト天ノ命ナランカ」と書いてあるんですね。
三浦:そのあとの6年間で、彼はそれをやりきったと思ったんだと思います。そして、現にやりきったと思うんです。だって、今、彼の作品は残り、私たちは読み継いでいるんですから。
梯:今回の本では、原民喜が戦後をどう生きたかも書きたかったんです。戦後、復興の掛け声の中、日本人はみんな、とにかく前を向いて生きなくてはならなかった。何百万人も亡くなっているのに、悲しみにひたっている余裕はなかった。私が戦争の取材でお会いした方にも、悲しみを封印して生きてきた方がたくさんいらっしゃいました。
死者を置き去りにして、猛烈な勢いで前だけを見て進み、悲しむべきときに悲しんでこなかった弊害が、戦後の日本にはあるような気がするんです。原はそういう世の中にあらがって、嘆き、悲しみ、祈りを書き続けた。悲しみの中にとどまり続けることは、実は力のいることだと思います。
三浦:俺は昨日のことを考える、という姿勢をつらぬいた。
梯:原民喜は生きる力は弱かったかもしれないけど、自分は死んだ人の側に立とうと、どこかで決めて、それをつらぬく強さがあった。原の自死について、新潮文庫の解説で大江健三郎さんが「書かねばならぬものの、すくなくとも大かたを書き終えるまでは、決して死ななかったのである」と書いていて、私なんかが言うのもなんですが、これを読んで、ありがとう!と思いました。そういうことだったんだと思います。
友人たちとの魅力的な関係
梯:遠藤周作宛の遺書も全集に掲載されていますが、数年前に現物が発見されて、長崎市の遠藤周作文学館に見にいったんです。ほんとうに美しい遺書で、女の子に遺したのと同じ詩を、遠藤周作にも書いています。
三浦:三人でいつも一緒に遊んだり散歩したりしていたんですよね。
梯:次の時代を生きる人に希望を託したことがわかる詩です。
三浦:梯さんが終わりのほうに引かれている「永遠のみどり」も、とてもいい詩で。最後に、原民喜の言葉が長めに引用されているのも、今の時代にすごく通じることが書いてあると思います。
梯:「死について」というエッセイから引用したんですが、あの言葉、好きなんです。死とは何か、なぜ死んだのかという裏テーマのようなものがあったので……
三浦:朗読しなくていいからね!
梯:読みそうになっちゃった(笑)。
三浦:そこはみなさんに、梯さんの御本で読んでいただくということで。あと、この本を読んで思ったのは、遠藤周作の株があがる!
梯:遠藤周作、いい人なんですよ。
三浦:遠藤周作、作品は読んでいたんですが、実はあんまり好きじゃなかったんです。若干、冷たい感じがするなというのと、ちょっと教条的じゃないかとずっと思っていたんですが、ごめん周作、私が間違ってた!
中学生ぐらいで読んで、そのころは何もわかってないし、思春期の反発心まんまんで、そういうふうに読んでしまったんだと思います。遠藤周作の中にある影や淋しい部分を作品から感じとれていなかったのかもしれない。もう一回読もうと思いました。
梯:この本を読んだ方はみなさん、遠藤周作ってこんな人だったのかっておっしゃるんです。年も違うし、環境も違う、終戦後すぐの東京じゃないと出会わなかった人たちの、不思議な友情ですよね。
三浦:この中に、いろんなお友だちが出てきますが、同じ広島出身の熊平武二さんという人が気になって。最初に同人誌に誘ってくれた、いい子なんですよね。原民喜のお友だちは、その後もずっと原民喜の面倒をみる人が多いですが(笑)、熊平さんはどうなったんですか?
梯:北原白秋に序をもらった詩集を一冊出したあとは、実家が熊平製作所という今もある大きな会社で、次男ですがお兄さんと一緒に家業に従事したそうです。しをんちゃんは、熊平くんにご執心なんだよね(笑)。
三浦:はい(笑)。原民喜との2ショットの写真が載っているんだけど、なんだかすごくいいなと思って。二人のムードがとてもいい感じで、仲のいいお友だちなんだなというのが伝わってくる。
梯:熊平くんのほうが文学的には早熟で、この人の影響を受けて、いろんなものを読むようになったんです。原さんは、いいお友だちがいっぱいいた。
三浦:本人の人柄がいいから、まわりにもいい人が集まってくるんですね。
梯:戦前の文学青年の友情物語としてもおもしろいですよね。原さんは、親切にしてもらってもお礼を言わないんですって。作家たちは、親切にしたら見返りを期待していると思われないだろうかとか気にする自意識の強い人が多かったりしますが、でも彼からはぜったい見返りがないから、安心して親切ができる(笑)。
今の世の中、原民喜のような人に共感する人が、いっぱいいると思うんです。
三浦:きっといますよ。
梯:時代を超えて、共感できる人と知りあうことができるのが文学のよさですが、原民喜は原爆文学の名作を書いた人というのから一度離れて、自分と似たような、あるいは隣にいるような人が原爆に遭ったんだと、そちらの道を通って原民喜に出会ってもらえたら嬉しいです。
三浦:原爆に遭った人たちは、「特別な人」ではない。私たちと同じように、喜びや悲しみの中で生活していた人たちなんですよね。原民喜の作品を読むと、それを知り、想像し、考えることができる気がします。
梯:ありがたいことに、作品を通じて今でも原民喜とコミュニケーションすることができる。原民喜を初めから戦争文学としてとらえる必要はないと思うんですが、この本が広い意味で戦争とは何かを考えるきっかけになればいいなと思っています。