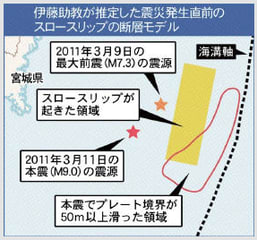東京電力福島第1原発事故による避難区域を12日、初めて視察した原子力損害賠償紛争審査会の能見善久会長ら委員8人は、6市町村の避難区域の住宅や商店、事業所などの現状を確認した。
原発事故から2年2カ月が経過した福島県内では、双葉町と川俣町山木屋を残して避難区域再編が進み、住民の帰還に向けて損害賠償の新たな課題が出ている。しかし、審査会の現地視察はこれまでに一度もなく、県が4月に実施を求めていた。審査会はこれを受け、賠償指針に関する協議には避難区域の現状把握が必要として初めて訪れた。視察した能見会長は「長期間の避難で、住宅は想像できないような大きな損害が出ていた。また、戻れる人と戻れない人に差があり、地域コミュニティーが分断されていた。賠償やほかの施策も含め、皆さんが元の生活に戻ることを実現できればいいと感じた」と語った。
(2013年5月13日 福島民友ニュース)
原発事故から2年2カ月が経過した福島県内では、双葉町と川俣町山木屋を残して避難区域再編が進み、住民の帰還に向けて損害賠償の新たな課題が出ている。しかし、審査会の現地視察はこれまでに一度もなく、県が4月に実施を求めていた。審査会はこれを受け、賠償指針に関する協議には避難区域の現状把握が必要として初めて訪れた。視察した能見会長は「長期間の避難で、住宅は想像できないような大きな損害が出ていた。また、戻れる人と戻れない人に差があり、地域コミュニティーが分断されていた。賠償やほかの施策も含め、皆さんが元の生活に戻ることを実現できればいいと感じた」と語った。
(2013年5月13日 福島民友ニュース)