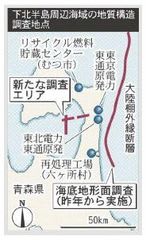東京電力福島第1原発の汚染水を減らすため、地下水をくみ上げて海洋に放出する東電の「地下水バイパス計画」について、県漁業協同組合連合会(県漁連)は「組合員の理解が得られていない」として、同意を見送った。これを受け茂木敏充経済産業相は、14日の閣議後の記者会見で「国としても説明を尽くしていきたい」との考えを表明した。
当然だ。国も、東電とともに説明責任の一端を担っていることを、あらためて認識してもらいたい。
同原発では、山側から海側に向かって流れる地下水が、途中で原子炉建屋に流れ込む。原子炉を冷やした水と混じり、放射性物質に汚染される。その量は1日400トン。汚染された水は敷地内に保管されているが、放射性物質を低減させる水処理や保管容量には限界があり、汚染水対策は急務だ。
原発敷地内で増え続ける汚染水が、いずれ海に漏れ出す危険性が懸念される。4月に同原発を調査した国際原子力機関(IAEA)の調査団も、汚染水問題を「直面する最大の課題」と指摘した。
汚染水の増加が、廃炉作業を進める上での障壁ともなり、海への新たな汚染の拡大を生むようなことは、何としても避けなければならない。
東電のバイパス計画は、地下水が原子炉に流れ込む前に、建屋上流部からくみ上げ、放射性物質を検査した上で、海に流す計画だ。原子炉に流入する地下水の量が1日100トン抑えられ、発生する汚染水を減らすことができるとしている。
東電の検査では、地下水には微量の放射性物質が含まれるが、濃度は低く周辺の河川と同じレベルとして、東電は県漁連に放出の同意を得たい考えだ。
県漁連は当初、放出に同意する方向で組合員の意見集約を図ろうとしていたが、13日の組合長会議では、東電の説明に対し、風評被害の拡大への懸念や安全性への不安の声が相次いだ。会議は非公開だったが、東電の計画に対し、国がどのように監視していくのかなど、国の関与に対する疑問を晴らすような説明はなかったという。
県漁連は6月以降に再度協議する方針だが、国や東電には、原子炉で汚染水になる前に、地下水を放出する計画自体への誤解と不信を払拭(ふっしょく)することが求められる。原発事故で自粛している漁の再開を望み、手探りの試験操業に取り組んでいる漁業関係者の心情を酌む努力が、東電にも国にも不十分と言わざるを得ない。国の「事業者任せ」と映る姿勢は、何としても改めてもらいたい。
計画を進める上で、地元の了解が前提になるのはもちろんだが、新たな風評被害を生まないために、漁業関係者以外の人たちにも、理解を求める説明などに取り組んでほしい。
2013年5月15日 福島民友新聞社説
当然だ。国も、東電とともに説明責任の一端を担っていることを、あらためて認識してもらいたい。
同原発では、山側から海側に向かって流れる地下水が、途中で原子炉建屋に流れ込む。原子炉を冷やした水と混じり、放射性物質に汚染される。その量は1日400トン。汚染された水は敷地内に保管されているが、放射性物質を低減させる水処理や保管容量には限界があり、汚染水対策は急務だ。
原発敷地内で増え続ける汚染水が、いずれ海に漏れ出す危険性が懸念される。4月に同原発を調査した国際原子力機関(IAEA)の調査団も、汚染水問題を「直面する最大の課題」と指摘した。
汚染水の増加が、廃炉作業を進める上での障壁ともなり、海への新たな汚染の拡大を生むようなことは、何としても避けなければならない。
東電のバイパス計画は、地下水が原子炉に流れ込む前に、建屋上流部からくみ上げ、放射性物質を検査した上で、海に流す計画だ。原子炉に流入する地下水の量が1日100トン抑えられ、発生する汚染水を減らすことができるとしている。
東電の検査では、地下水には微量の放射性物質が含まれるが、濃度は低く周辺の河川と同じレベルとして、東電は県漁連に放出の同意を得たい考えだ。
県漁連は当初、放出に同意する方向で組合員の意見集約を図ろうとしていたが、13日の組合長会議では、東電の説明に対し、風評被害の拡大への懸念や安全性への不安の声が相次いだ。会議は非公開だったが、東電の計画に対し、国がどのように監視していくのかなど、国の関与に対する疑問を晴らすような説明はなかったという。
県漁連は6月以降に再度協議する方針だが、国や東電には、原子炉で汚染水になる前に、地下水を放出する計画自体への誤解と不信を払拭(ふっしょく)することが求められる。原発事故で自粛している漁の再開を望み、手探りの試験操業に取り組んでいる漁業関係者の心情を酌む努力が、東電にも国にも不十分と言わざるを得ない。国の「事業者任せ」と映る姿勢は、何としても改めてもらいたい。
計画を進める上で、地元の了解が前提になるのはもちろんだが、新たな風評被害を生まないために、漁業関係者以外の人たちにも、理解を求める説明などに取り組んでほしい。
2013年5月15日 福島民友新聞社説