第三部 未知への挑戦(9) 低減への模索 和歌山方式で試験栽培

平成25年3月6日。福島県農業総合センター果樹研究所主任研究員の阿部和博(50)は、和歌山県橋本市にある和歌山県果樹試験場かき・もも研究所のほ場を訪ねた。主幹の大部分を切り落として柿を栽培する「低樹高と短期成園化栽培」の現場を見たかった。2年連続で加工自粛となった県北地方の「あんぽ柿」の放射性セシウムを低減する方法を探るためだった。
阿部は、ほ場に目を見張った。本県の柿畑とは異なる景色が広がっていたからだ。山の斜面に根元から伐採された柿の切り株が並び、高さ50センチほどの幹から枝が水平に伸びていた。「主幹の大部分を切り落とせば、樹木の内部に蓄積された放射性物質を大幅に減らせる。あんぽ柿を再生できる技術かもしれない」
■ ■
和歌山県内では、山あいの傾斜地で柿を栽培している農家が多い。かき・もも研究所は、高齢化する生産者の農作業の負担を軽くしようと、主幹を切除し、低い位置で柿を育てる栽培方法に着目した。22年から農林水産省の農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業として本格的に試験栽培を始めた。
まだ試験段階だが、20年冬から先行して栽培している樹木では、23年から柿の収穫が始まっている。収穫量は徐々に増えているという。「今後、数年で伐採前の収量に戻る見通しだ」。栽培を担当する研究員の熊本昌平(36)は手応えを感じている。
温暖な和歌山県の栽培法が、本県の気候になじむのか─。「柿の木は寒さに強いため、福島県でも栽培できるのではないか」と熊本はみている。
視察を終えた阿部は25年3月下旬から、福島市や伊達市保原町のほ場で合わせて12本の柿の樹木を主幹から切り、和歌山方式の研究に乗り出した。「放射性物質濃度を半分以下から検出されない程度にする」と目標を掲げる。今後、成長して生える枝や葉の放射性物質濃度を調べ、2年後以降に実る柿の濃度を確認する。
■ ■
実際に農家が導入するには課題もある。主幹を切り落とすことで放射性物質を取り除くことができても、少なくとも2年間は収穫できない。3年後以降も成木するまでの数年間は収穫量が落ち込む。「主幹を伐採したら収量が落ちたまま戻らないかもしれない」。伊達市霊山町で約50年にわたり原料柿を生産し、あんぽ柿に加工している男性(82)は不安を口にする。
県北地方で24年に実った多くの柿は、あんぽ柿に加工しても食品衛生法の基準値(1キロ当たり100ベクレル)を下回る濃度だった。だが、ごく一部の地域で基準値を上回る可能性があり、伊達や桑折、国見など7市町で加工自粛となった。
セシウム濃度がなかなか下がらない一部の地域の対策をどうするか─。阿部は「低減対策の選択肢を増やすことは重要だ。手をこまねいていては、何も改善されない」と苦悩する農家を救う糸口を見つけようとしている。
栽培の研究が進む一方で、加工再開に向けた模索も続いている。(文中敬称略)

2013/05/22 11:12 福島民報

平成25年3月6日。福島県農業総合センター果樹研究所主任研究員の阿部和博(50)は、和歌山県橋本市にある和歌山県果樹試験場かき・もも研究所のほ場を訪ねた。主幹の大部分を切り落として柿を栽培する「低樹高と短期成園化栽培」の現場を見たかった。2年連続で加工自粛となった県北地方の「あんぽ柿」の放射性セシウムを低減する方法を探るためだった。
阿部は、ほ場に目を見張った。本県の柿畑とは異なる景色が広がっていたからだ。山の斜面に根元から伐採された柿の切り株が並び、高さ50センチほどの幹から枝が水平に伸びていた。「主幹の大部分を切り落とせば、樹木の内部に蓄積された放射性物質を大幅に減らせる。あんぽ柿を再生できる技術かもしれない」
■ ■
和歌山県内では、山あいの傾斜地で柿を栽培している農家が多い。かき・もも研究所は、高齢化する生産者の農作業の負担を軽くしようと、主幹を切除し、低い位置で柿を育てる栽培方法に着目した。22年から農林水産省の農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業として本格的に試験栽培を始めた。
まだ試験段階だが、20年冬から先行して栽培している樹木では、23年から柿の収穫が始まっている。収穫量は徐々に増えているという。「今後、数年で伐採前の収量に戻る見通しだ」。栽培を担当する研究員の熊本昌平(36)は手応えを感じている。
温暖な和歌山県の栽培法が、本県の気候になじむのか─。「柿の木は寒さに強いため、福島県でも栽培できるのではないか」と熊本はみている。
視察を終えた阿部は25年3月下旬から、福島市や伊達市保原町のほ場で合わせて12本の柿の樹木を主幹から切り、和歌山方式の研究に乗り出した。「放射性物質濃度を半分以下から検出されない程度にする」と目標を掲げる。今後、成長して生える枝や葉の放射性物質濃度を調べ、2年後以降に実る柿の濃度を確認する。
■ ■
実際に農家が導入するには課題もある。主幹を切り落とすことで放射性物質を取り除くことができても、少なくとも2年間は収穫できない。3年後以降も成木するまでの数年間は収穫量が落ち込む。「主幹を伐採したら収量が落ちたまま戻らないかもしれない」。伊達市霊山町で約50年にわたり原料柿を生産し、あんぽ柿に加工している男性(82)は不安を口にする。
県北地方で24年に実った多くの柿は、あんぽ柿に加工しても食品衛生法の基準値(1キロ当たり100ベクレル)を下回る濃度だった。だが、ごく一部の地域で基準値を上回る可能性があり、伊達や桑折、国見など7市町で加工自粛となった。
セシウム濃度がなかなか下がらない一部の地域の対策をどうするか─。阿部は「低減対策の選択肢を増やすことは重要だ。手をこまねいていては、何も改善されない」と苦悩する農家を救う糸口を見つけようとしている。
栽培の研究が進む一方で、加工再開に向けた模索も続いている。(文中敬称略)

2013/05/22 11:12 福島民報












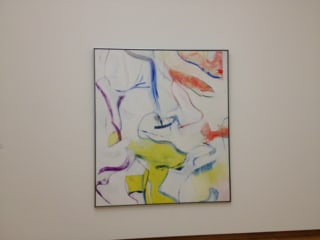
 たび
たび
