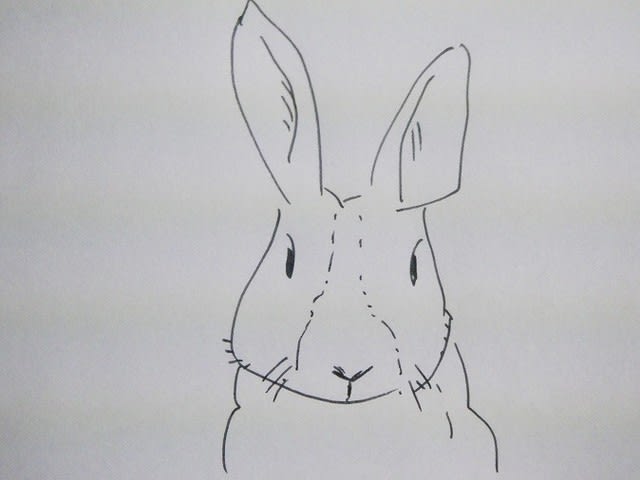博士と助手
「博士おはようございます」
「おはよう」
挨拶を返した博士の目は充血している。いつもの事なのだが、博士は慢性的な寝不足だった。意識を失うまで研究に没頭する日々を送っているためだ。今朝もいつものように血走っている。
「今日の作業はこの服を着ろという事でよろしいですね」
助手は不燃性のつなぎを着ている。
「そうだ。わしも白衣の下は、君と同じ、レーシングスーツを着ておる。そして今すぐマシンに乗ってくれ」
「マシンって何ですか」
「わしが作ったマシンはすでにコースに出してある」
「博士、まず確認したいことがあります。ここは今朝、私が電車とバスに乗って、通勤してきた研究所でよろしいですね」
助手は博士が行うトリッキーな行動を警戒して、至極当然の質問をした。「いいや、違う」
「違うんですね。どういうことでしょう」
「うむ、研究所のドアを開けた瞬間、静電気がぴりっときたじゃろ」
助手は強めの静電気を手に感じたことを思い出した。
「はい。ぴりっときました」
「それは昨日の朝の出来事になる」
「昨日ですか」
「そうじゃ。わしが発明した電気麻酔で君を眠らせた。そのまま積載車に乗せて、マシンと一緒にわしの運転でここまで来た。なんのかんので一晩かかったぞ」
「何のためにそんなことを……」
「おもしろいかなと思って。そんな些細なことより、君にはわしが丹精を凝らしてエンジンから作ったF1マシンに乗ってもらうぞ」
博士は困惑する助手を置いてけぼりで説明を始めた。
「エンジンは冷やす必要があるのは君でも知っておるな」
「はい」
「よろしい。水か油か風か。何かしらを用いて発生した熱を下げる必要がある。そこで発明したのが、回転すると熱を奪う球体だ。この球体はどんな大きさのものでも作れる。転がれば転がるほど温度が下がり続けるのじゃ。するとどうじゃ、冷却システム一式が不要のエンジンが出来たのじゃ。なおかつ、摩擦係数ゼロの金属も作った。わしのエンジンはレッドゾーン無し。どこまでも回るぞ」
「はあ」
「重量的に設計の余裕が出来たんで、マシンには快適装備も乗せたぞ。マッサージ機能付きリクライニングシート。前車に追随するオートドライブも完備した。時速300キロオーバーでも余裕でついて行くから大丈夫じゃ」
「はあ」
「さあ、安心して乗れ。レースエントリーは済ませてある。君は幸せ者じゃぞ。F1のドライバーズシートなんか、なかなか空いとらんのじゃから」
「博士。無理ですよ。レースするんですか」
「そうじゃ、行ってこい。自分の意思で行かないのなら、電気でぴりっとさせて、そのまま、オートクルーズ状態でレースまっただ中で目覚める事になるぞ」
「ええー」
「さあ、行け」
博士の目は最高に真っ赤。
「博士おはようございます」
「おはよう」
挨拶を返した博士の目は充血している。いつもの事なのだが、博士は慢性的な寝不足だった。意識を失うまで研究に没頭する日々を送っているためだ。今朝もいつものように血走っている。
「今日の作業はこの服を着ろという事でよろしいですね」
助手は不燃性のつなぎを着ている。
「そうだ。わしも白衣の下は、君と同じ、レーシングスーツを着ておる。そして今すぐマシンに乗ってくれ」
「マシンって何ですか」
「わしが作ったマシンはすでにコースに出してある」
「博士、まず確認したいことがあります。ここは今朝、私が電車とバスに乗って、通勤してきた研究所でよろしいですね」
助手は博士が行うトリッキーな行動を警戒して、至極当然の質問をした。「いいや、違う」
「違うんですね。どういうことでしょう」
「うむ、研究所のドアを開けた瞬間、静電気がぴりっときたじゃろ」
助手は強めの静電気を手に感じたことを思い出した。
「はい。ぴりっときました」
「それは昨日の朝の出来事になる」
「昨日ですか」
「そうじゃ。わしが発明した電気麻酔で君を眠らせた。そのまま積載車に乗せて、マシンと一緒にわしの運転でここまで来た。なんのかんので一晩かかったぞ」
「何のためにそんなことを……」
「おもしろいかなと思って。そんな些細なことより、君にはわしが丹精を凝らしてエンジンから作ったF1マシンに乗ってもらうぞ」
博士は困惑する助手を置いてけぼりで説明を始めた。
「エンジンは冷やす必要があるのは君でも知っておるな」
「はい」
「よろしい。水か油か風か。何かしらを用いて発生した熱を下げる必要がある。そこで発明したのが、回転すると熱を奪う球体だ。この球体はどんな大きさのものでも作れる。転がれば転がるほど温度が下がり続けるのじゃ。するとどうじゃ、冷却システム一式が不要のエンジンが出来たのじゃ。なおかつ、摩擦係数ゼロの金属も作った。わしのエンジンはレッドゾーン無し。どこまでも回るぞ」
「はあ」
「重量的に設計の余裕が出来たんで、マシンには快適装備も乗せたぞ。マッサージ機能付きリクライニングシート。前車に追随するオートドライブも完備した。時速300キロオーバーでも余裕でついて行くから大丈夫じゃ」
「はあ」
「さあ、安心して乗れ。レースエントリーは済ませてある。君は幸せ者じゃぞ。F1のドライバーズシートなんか、なかなか空いとらんのじゃから」
「博士。無理ですよ。レースするんですか」
「そうじゃ、行ってこい。自分の意思で行かないのなら、電気でぴりっとさせて、そのまま、オートクルーズ状態でレースまっただ中で目覚める事になるぞ」
「ええー」
「さあ、行け」
博士の目は最高に真っ赤。