大阪湾の水質が改善されたのは確かだけれども、河からの栄養素が流れ込んでいないわけではないが、関空などの大規模埋め立てで海流によどみができて栄養素の各藩ができていないからだという。関西TV報道による。

大阪湾に起こった「栄養の偏り」
大阪湾にあった時計回りの緩やかな潮の流れが、神戸空港や関西空港などの大規模な埋め立てによって邪魔されて弱くなり、海水がうまく混ざらなくなっていったのです。その結果、いまでも排水が多い湾の奥では、栄養が多すぎる一方で、西側や南側では栄養が足りなくなってしまったのです。
栄養がなくなった海には、魚のえさとなるプランクトンが増えません。プランクトンがいない海は濁りが無く透明になる為、これを漁業者は「きれいすぎる」と言っていたのです。
かつての豊かな大阪湾を取り戻そうと立ち上がった人たちがいます。

大阪府立大学 大塚耕司 教授
大阪府立大学の大塚耕司教授。手にしているのは、共同研究する企業が作った海の栄養剤です。魚のアラで作ったアミノ酸が入っています。
【大阪府立大学 大塚耕司 教授】
「さかな(のアラ)からとった栄養分を、海にまた戻すと。海から陸にあげて処理した廃棄物をうまく利用してまた元に戻して、漁場を造成する」

岩井克巳さん
一緒にプロジェクトを行っているのは、大阪湾の環境改善を行うNPOの岩井克巳さん。
魚が集まる住処や繁殖場所をつくれないか、1年半前、沖合にこの栄養剤を設置し、定期的に調査を行っています。漁礁に栄養剤が入ったネットが設置されています。周りにはフグやハギの仲間が集まっていました。栄養剤が入った蛸壺にもしっかり大きなタコが住み着いているようです。
【岩井克巳さん】
「蛸壺マンションの方は、タコもはいっていましたし栄養材があるというのは良いインパクとになっているのかなと」
更に大塚教授は今、栄養が偏ってしまった大阪湾の状況を解決するある研究を進めています。
【大阪府立大学 大塚耕司 教授】
「大阪湾も南港など奥の方では大量のアオサが発生して。処理にも困っています。困っているから悪い者をやつけるのではなく、これをいいものに換えてやろうと」

この研究ではまず、栄養が多すぎて湾の奥で大量発生してしまうプランクトンや海藻を回収し、そこからメタンガスという船などに使う燃料を作ります。この時でてくる残りかすには、栄養が多く含まれているため栄養分を取り出し、作った燃料で船を動かして足りないところに栄養をまこうというものです。すでに燃料と栄養分を取り出すことには成功しています。














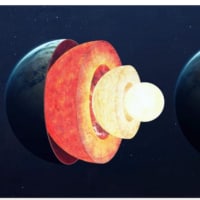

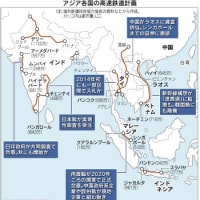
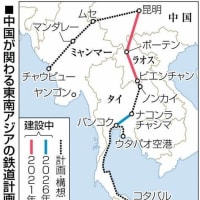

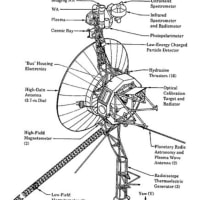
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます