毎日新聞が報道していた:::80年以上前にイタリアの物理学者マヨラナ教授が予言していた幻の「マヨラナ粒子」が実際に存在することを世界で初めて実証したと、京都大などのグループが12日付の英科学誌ネイチャーに発表した。電気を通さない固体の中で、電子があたかもマヨラナ粒子のようにふるまう現象を観測したという。将来的には量子コンピューターなどへの応用が期待される。
マヨラナ粒子は、粒子とも反粒子とも区別のつかない「幻の粒子」と言われ、1937年にイタリアの物理学者、エットーレ・マヨラナが理論的に存在を予言した。電気を帯びず極めて質量の小さな素粒子「ニュートリノ」がその本命と考えられているが、証明には至っていない。一方、特殊な条件下の超電導体などでは、電子がマヨラナ粒子のようにふるまう可能性が指摘され、その決定的証拠をつかもうと各国で研究が本格化している。
笠原裕一・京大准教授(物性物理学)らは、東京工業大のチームが合成した磁性絶縁体「塩化ルテニウム」を用い、その内部を伝わる熱の流れが磁場によってどの程度曲がりやすくなるかを、磁場を変化させながら測定した。
その結果、ある範囲の磁場では、磁場や温度を変えても、曲がりやすさの値が普遍的な値の2分の1で一定になった。熱を運ぶ粒子が電子の半分の自由度を持っていることを意味し、そのような性質があるマヨラナ粒子が現れたと考えないと説明が付かないという。
マヨラナ粒子は外部からの影響に対して強く、粒子が持つ情報を安定的に保てるため、量子コンピューターの素子としての応用に期待がかかる。笠原准教授は「これが普遍的な現象なのか、他の物質でも確かめたい。量子コンピューターの実現につながるか今は全く分からないが、その基盤を発見したと言えるのではないか」と話す。【菅沼舞、阿部周一】
◇ノーベル賞級の成果
木村昭夫・広島大教授(物性物理学)の話 世界で発見レースが繰り広げられる中、大半の研究がターゲットにしていた超電導体とは別の物質、別の方法を用いてマヨラナ粒子の存在を直接的に示したインパクトは大きい。液体ヘリウムで冷却可能な温度(5ケルビン)で観測できたことも、今後の実験や応用に期待を広げる。ノーベル賞に値する重要な成果だ。
【ことば】粒子と反粒子
電子に対する陽電子、陽子に対する反陽子のように、物質を構成する粒子には質量は同じだが電荷が正負逆の反粒子がある。両者は出合うと消滅する。宇宙誕生時は粒子と反粒子が同数できたはずだが、今の宇宙は粒子ばかり。もし宇宙で最も数が多いニュートリノが粒子と反粒子の区別がつかないマヨラナ粒子だとすると、粒子と反粒子の数が非対称になった謎に説明が付くと期待されている。
固体中で電子がマヨラナ粒子のようにふるまうイメージ=笠原裕一・京都大准教授提供















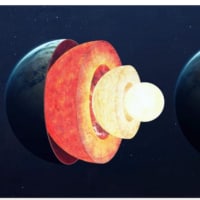

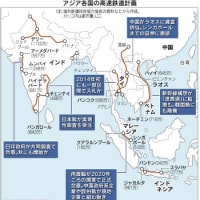
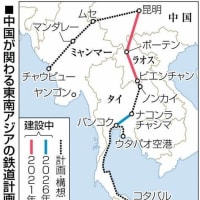

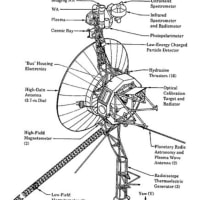
まあ簡単に言うとシナジーということで
1+1=2 だけではなく
1+1=3 という世界を
数理的に表現しようとしたもののように受け止められる。