2019年日経電子版で連載した「ネット興亡記」に、メルカリの山田進太郎社長の話が出ていた。
自分と向き合い続けた山田氏が見つけたカリスマ経営者とは異なる起業の形。そんな山田氏が夢だった米国進出のために「鬼」になったというストーリー。
日本に「フリマ」という新しいeコマースの形をもたらしたメルカリ。2013年の設立から瞬く間に利用者数を伸ばし、毎月使うユーザーは今では1700万人に迫る。近年のスタートアップを代表する存在ともいえるが、創業者の山田進太郎はいきなりフリマという金鉱脈を見つけたわけではない。そこに至るには長い模索の旅があった。
■諦めていた起業の夢
高校時代は地元愛知県の進学校に進むがそこでの成績はクラスでも最底辺。部活はマイナーなハンドボール部を選んだのに補欠。そこから山田の内省が始まった。
「僕はすごく記憶力があるわけでもないし社交的でもない。プレゼンがうまいわけでもない。本当に地味な目立たない学生でした。これが得意だというものがなく悶々(もんもん)としていました。だから、自分はどう生きていくのかをずっと考えていた。普通のサラリーマンでは良い仕事ができない。小説家とか起業とか、何か人と違うことをやらないと、この世に生まれた価値が出せないという感覚でした」
小説家を目指すが手に取った村上春樹の指南本を読んでがくぜんとする。
「僕はこういうふうにはモノを読めないし無理だなと思いました。物書きは人と違う視点で色々なことを捉えて表現できないとダメ。僕にはその能力はないと痛感した」
では起業家はどうか。実は大学1年の時にある人物に会いに行き「こうはなれない」と一度諦めたという。それがソフトバンクグループ創業者の孫正義だった。1996年のことだ。当時39歳だった孫は、新世代のベンチャー経営者として注目を集めていた。
「孫さんはものすごくエネルギッシュで人を巻き込むリーダーシップがある。当然、知識も。僕は当時18歳。あと20年でどうやったらここまで到達できるのだろうと。イメージがわかなかった。こういうスタイルは無理だなと思って、いったん起業を諦めたのです」
だが、自分の生き方を模索する山田は、徐々にカリスマたちとは違う生き方でもいいのではないかと考えるようになった。そこに2つの出会いがあった。
ひとつがドイツの思想家ニーチェが書いた名作「ツァラトゥストラはかく語りき」だった。絶対的な存在である超人を描くニーチェに対する、山田の解釈は独特なものだった。「僕は超人ではない。凡人でいい」だ。
「結局、自分は自分でしかないということです。良いものは良いと認める。その上で自分の良いところを伸ばし、他の人の良いところを使う。自分だけではできないことを他の人と一緒になって、より良い価値をつくっていく」
もうひとつの出会いは、当時渋谷近辺に集まった「ビットバレー」と呼ばれる若手IT起業家の集まりだった。その中心的存在だったのがネットエイジ。渋谷・松濤の歯科医の2階にあったオフィスに山田も足を運んだひとりだった。
グリーの田中良和、ミクシィの笠原健治、ヤフーの川辺健太郎、コロプラ創業者で個人投資家の千葉功太郎……。ビットバレーに集う同世代の若き起業家たちの姿が、山田に一度は諦めた起業の道を選ばせた。
「ビットバレーの起業家には色々なタイプがいました。技術で引っ張る人。センスが良い人。スタイルというのはなんでもいいんだなと思いました」
■米国で戦う覚悟
フリーランスとしてたった一人で活動を始めた山田は「映画生活」というサイトを作るが、20代も半ばにさしかかると米国への移住を考え、サンフランシスコに渡る。ここでインターネットで生きていく腹を固めることになった。
「当時はインターネット以外に飲食とか不動産にも興味がありました。現地の日本人の方と日本食レストランを開こうということになったのですが、その時に考えました。お店で接客できるのは1日100人か200人程度。でも、当時僕のサイトは月間100万人の利用者がいた。少ない人に質の高いサービスを提供するか、それともインターネットで多くの人に提供するか。自分はどちらが好きかを考え、やっぱりインターネットが面白いなと改めて思いました」
「それで日本に帰ることになりましたが、米国に来て『日本人として何ができるか』と考えた。日本でサービスをつくって海外に持っていこうと。世界中で使われるインターネットサービスを作ろうと。腹が据わった。これを一生やっていこうと」
日本に戻った山田はソーシャルゲームの会社をつくった。ヒット作にも恵まれ米ゲーム企業に買収される。それが「世界」への近道だと思ったから売却したのだが、方針があわずすぐに退職した。そんな時に出かけた世界一周の旅で、もう一度自分がなすべきことを見つめ直した。
「やっぱり子供が働いているのが印象的だった。ボリビアからチリに行ったときも(ガイドの)助手席には子供がずっと座っていました。みんな豊かになろうとしているけど全世界が豊かになるなんて現実的には難しい。資源も限られている。では自分に何ができるかを考えました」

世界一周の旅で、自分がなすべきことを見つめ直した(インドで)
それがフリマアプリにつながった。誰かの使い古しでも誰かの役に立つ。そうやってモノを循環させる仕組みを作れば、世界はもう少しだけ豊かになるのではないか。
そして、ここまでの経験で山田は経営者としての「自分のスタイル」に気づき始めていた。
「僕は人を生かすのが得意なのかなと。次に会社をやるときは自分でやること以上のことをやりたいと思っていた。自分にないものを持っている人がいたら、その人の能力を生かせるような状況をつくり出そうと」

2014年に米国参入した際のオフィスで、山田氏と(左)と石塚氏
13年に始めたメルカリは曲折がありながらも短期間でユーザーを獲得していった。新たな仲間たちと山田が目指したのが米国だった。日本でのサービス開始から半年もしないうちに米国で視察に回り、翌14年に参入を決めた。
「日本だけでやるということをそもそも目標としていない。米国で勝てば、それはいきなりボスを倒すようなもの。一番高いハードルだけど、その後に続く欧州市場(を攻略しやすくなること)なども考えると(米国での成功は)日本だけでやる10倍以上のポテンシャルがあると思う。やらないリスクの方がむしろ高いという感覚でした。むしろ、日本を落としてでも米国でうまくいけばそっちの方がいいというコンセンサスは(経営陣の中で)ありました」
■たった一度の「わがまま」
だが、やはりハードルは高かった。米国では思うように取引額が伸びない。思い詰めた山田は行動に出た。米国事業を任せていたメルカリ共同創業者の石塚亮を米国CEO(最高経営責任者)から外し、自らが陣頭指揮をとるよう迫ったのだ。
帰国子女で米国での起業経験もある石塚は、山田本人がメルカリを起業する際に「米国は亮に任せるから」と言って誘った人物だ。日本での立ち上げの功労者でもある。自らの約束を反故(ほご)にし、仲間のプライドを傷つける決断だったはずだ。
「それはあったと思います。でも、どうしてもここで成功したいと。自分自身でやってダメなら諦めがつきます。ある意味、僕のわがままだけど『やらせてほしい』と伝えました。もちろん、彼にも思いはあった。色々と話しました。最後は『全力でサポートするから』と言ってくれました」
カリスマ経営者と自分は違うと思い、「人を生かす」という自分なりのスタイルを見つけた起業家・山田進太郎が見せた「わがまま」。米国はその後も苦戦を続けながらしぶとく戦い続けている。
スマホ世代の代表的なスタートアップと見られるようになったメルカリ。社会的責任を痛感させられた出来事が17年に起きた現金の不正出品問題だった。
「自分たちはすごく小さな存在だと思っていたけど、プラットフォーマーとして報道されていた。世の中のインフラみたいな存在になりつつあると初めて気づきました。ある意味、社会的な公器を目指すようにカジを切りました」
日本発のスタートアップとしての「社会的な役割」として今、最も意識するのがやはり海外への挑戦だ。インターネット産業が始まっておよそ四半世紀。いまだ日本発のグローバル・テックカンパニーは育っていない。
「メルカリがやらないといけないのは海外で成功して外貨を稼ぐこと。これまでは自動車や電機のメーカーが成功しているけど。僕たちはそこを目指したい。成功例が出れば『あそこにできるなら』と、どんどん海外を目指す人が増えてくると思うんです」

新規株式公開(IPO)時は株式市場で話題を集めた(2018年6月、前列左から3人目が山田氏)
山田は18年6月に上場した際、「創業者からの手紙」を公開した。それはこんな一文から始まっている。
「私は、野茂英雄さんの大ファンです。野茂さんがメジャー挑戦を発表された時、日本中でバッシングが巻き起こったのをよく覚えています」
メルカリの米国事業にはいまも投資家やメディアから厳しい声が寄せられる。成功したと言えるにはほど遠いから、反論はしない。ただ、追いかけているものが、批判と懐疑に満ちた視線の中で米国に渡ったパイオニアの後ろ姿であることに、今も変わりはない。















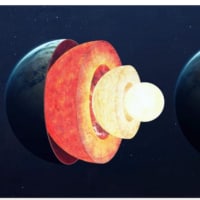


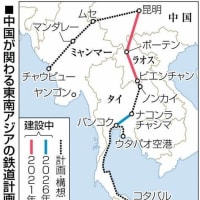

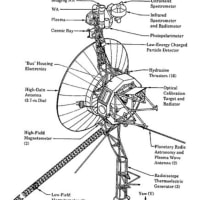
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます