ソニーが家電見本市としてスタートした世界最大のIT見本市「CES」(2020年1月7~10日、米ラスベガス)で、参考出展した「VISION-S(ビジョン エス)、日経のxTechによると、ソニーのおもちゃロボット「アイボ」の開発チームが、様々なパートナーの協力を得て造ったという。
EV車は、内燃機関のガソリンエンジン車などより部品数が少なく、かつ、制御も電機の制御が主だから大分簡単になるから、電機メーカーや、自動車メーカー以外の機械メーカーも作れ、しかも車単体では通用しなくなって、インターネットを活用が不可欠だから、多分野の企業との協業が必要になる。第4次産業革命の作りだした新たな産業分野だと思う!
開発は同社の犬型ロボット「アイボ」を担当するチームが欧州に約20カ月間滞在し、少人数で極秘裏に進めてきた。車線変更などができる自動運転のレベル2以上に対応し、運転席の前には左右一杯に横長の大型液晶画面が置かれ、カーナビの表示だけでなく映画の鑑賞などができる。家庭用に開発した独自技術「360度リアリティオーディオ」も投入し、立体感のある音響映像空間を車内に実現した。まさにソニーならではの仕上がりといえる。
社員の士気向上も狙いの一つ
車両の製造はカナダの自動車部品大手、マグナ・インターナショナルのオーストリア子会社に委託したが、デザインや仕様などは自ら設計した。ソニーが得意とするイメージセンサーなどの技術を自動車メーカーに提供するのが元々の狙いだったが、「彼らと協業するうち、本当にいい技術を提供するには自ら完成車を造ってみるのが早道だとわかった」と、開発現場を担当したAIロボティクスビジネスグループのエンジニアリングマネジャーの小川康文氏は語る。
ソニーでも業績が低迷していた2006年にアイボの生産を中止したところ、同社から離れたエンジニアもいた。吉田社長の下でアイボを2018年に復活させたことで「エンジニアや社員の士気はかなり高まった」という。EVの開発はそうした彼らのモチベーションをさらに高めるための新たな挑戦だったというわけだ。
吉田氏は子会社からソニー本体に戻り、最高財務責任者(CFO)を務めたころから、「何か動くものをやりたいと考えていた」と語る。というのも日本の家電メーカーが世界で強かった時代、競争力の源泉は当時「メカトロニクス」と呼ばれた機械と電気の両方に裏打ちされた技術力にあった。
ソフトウエアやサービスの分野でGAFAに対抗するのはもはや難しいが、彼らが作れない「動くもの」を世に問うことでソニーの存在感を再びアピールできると考えたという。
トヨタは次世代モビリティをスマートシティで実証へ
米国のEVベンチャーのテスラにバッテリーを供給するパナソニックも、今回は展示スペースのほぼ半分以上をモビリティの分野に割いた。小型EVの開発を進める米スタートアップ企業のトロポステクノロジーズと提携、パナソニックが2016年に買収した米業務用冷蔵庫メーカー、ハスマンの冷蔵ケースと組み合わせた配送用の電気自動車などを発表した。
ソニーやパナソニックに加え、モビリティの分野でもう1社注目されたのが中国のEVベンチャー「BYTON(バイトン)」だ。独BMWなどのエンジニアが2016年に設立した会社で、18年からCESに出展、いよいよ今年秋から欧米市場でスポーツタイプのEVを発売する。自動運転機能と次世代通信規格「5G」に対応し、「中国版テスラ」とも呼ばれるが、販売価格は3万6000ドルからとテスラより低めに設定。欧米市場で6万台の事前注文を獲得したという。
迎え撃つ自動車メーカーの方でも新たな発表が相次いだ。自動運転車「e-Palette」を開発するトヨタ自動車は、そうした次世代型モビリティ技術を実証するために、富士山のふもとにある静岡県裾野市に大規模なスマートシティを建設することを発表した。豊田章男社長は「自動車産業は100年に1度の大変革期にある」と強調、自動運転に限らず、家事支援ロボットなど様々なIoT機器を街全体で活用できるプラットフォーム作りを目指す。
「コネクテッド、自動運転、シェアード、電気」の頭文字で表す「CASE」という自動車の新しい方向性を打ち出した独ダイムラーも次のフェーズを狙う。基調講演を務めたオラ・ケレニウス会長は環境対策を最重要課題に掲げ、従来の「リサイクル」に加え、「リユース」「リデュース(使用量削減)」を一層推進していく考えを表明した。ハリウッド映画「アバター」をモチーフにした究極のエコカー「VISION AVTR」を発表するなど、自動車と情報技術との融合に力を注ぐ。
有人ドローンが新たな市場に
さらにモビリティ分野の新たな勢力としてCESの場で存在感を高めているのが有人ドローンだ。昨年に続き、米ベル・ヘリコプターが大型ドローンを展示したのに加え、今年は韓国の現代自動車が米ライドシェア最大手のウーバーテクノロジーズと提携、「空飛ぶタクシー」のコンセプトモデルを出展した。ダイムラーや米インテルもドイツのドローンベンチャー、ボロコプターに出資しており、トヨタも米スタートアップ企業のジョビー・アビエーションとの提携を発表した。
そうした流れを受け、CTA自身も2015年に前身の全米家電協会(CEA)から今日の名称に名前を変えた。シャピロ会長は「CESをもはやコンシューマー・エレクトロニクス・ショーと訳さないでほしい」と訴える。今年の開会初日の基調講演もIT企業ではなく、米デルタ航空のエド・バスティアン最高経営責任者(CEO)だった。これもまさにモビリティの分野である。
誰でもクルマを造れる時代の到来
しかし、こうした技術の進化は既存の自動車産業にとっては大きな脅威となりかねない。ガソリン車の時代からEVの時代になれば、基本となる部品さえ調達できれば誰もが自動車を造れるようになるからだ。ソニーの自動車開発はまさにそれを立証したことになる。
これはテレビがブラウン管から液晶の時代になり、ベンチャー企業でもテレビを作れるようになったのとよく似ている。今後、5Gや3Dプリンターなどの技術が普及すれば、自動車産業のプレーヤーもガソリン車の時代とは大きく変わっていくに違いない。
その意味ではソニーの自動車開発は今年のCESの特徴を表す最も象徴的な出来事だったといえる。ソニーにとってはクルマという新分野への参入だが、自動車産業からみれば、業界以外からの新しいプレーヤーの台頭を意味する。トヨタやダイムラーが街づくりや環境対策といった大きなコンセプトを掲げたのも、新興プレーヤーに対する自動車業界のメンツをかけた対抗策だった。
今回のCESはそうした情報技術とモビリティ分野の技術がせめぎ合う新しい時代の到来を告げるイベントだったと言えよう。























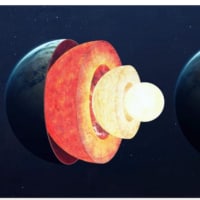


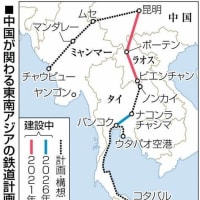

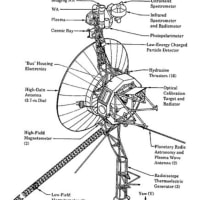
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます