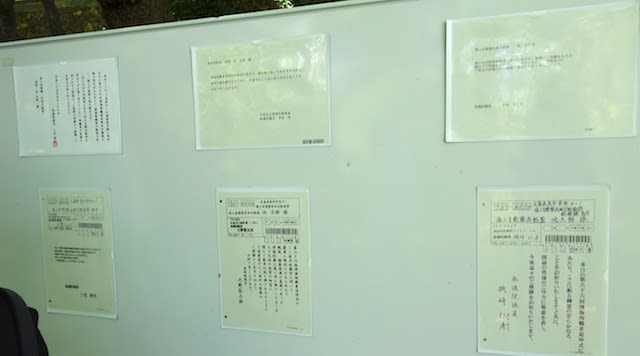掃海艦「はちじょう」除籍に伴う自衛艦旗返納式についてお話ししています。
掃海「艦」の建造に至る過程について、面白い話を見つけました。
専守防衛の我が日本国自衛隊が新しく装備を導入する時、そこにはあくまでも
「カバーストーリー」といいますか、つまり「建前の必要性」が必要になります。
掃海艦が企画されようとしていたころ、日本は西側諸国の一員として
冷戦を「戦って」おり、そのために、P3Cを増やし、イージス艦を整備し、
そう、掃海艦を建造するという必要があったのです。
防衛力整備達成のために必要なのは建前、いや理論武装です。
そこで掃海艦の整備に必要となったのは、ソ連の高い機雷敷設能力、
特にロケット上昇式の深々度機雷に対する「脅威論」でした。
「我が国の重要港湾のほとんどが本州の太平洋岸に集中しており、
通行船舶の輻輳、集中するチョークポイントも、その多くが
外洋につながる深々度海域を多く含んでいるため、もしここに
ソ連の有する深々度機雷が使われたら大変なことになる!
だからこそ深々ど機雷排除機能を持つ掃海艦が必要なのである!」
というのが、この場合の「カバーストーリー」となり、それは
内局にも大変歓迎されたといわれます。
ソ連の軍事的能力の高さは、当時の日本にいて否定できるものではなく、
それさえ言っておけば公式には反論・議論の余地もなくなるというわけです。
そもそもソ連がそんなことをする意図やその可能性があるかについては、
中の人に疑問を持つ向きがないでもなかったらしいのですが、(そらそーだ)
それを論証することもまた不可能、とうわけで、内局の部員の中には
「騙すなら、最後まで気持ちよく騙してね」
と冗談半分、実は本気で囁く者もいたという話でした。
閑話休題、
時は流れ、冷戦構造は終了し、時代の流れから掃海艦は次第に減勢に転じました。
現在建造中の「あわじ」型掃海艦は、「やえやま」型とほぼ同じ大きさでありながら、
艦体を木造からFRP構造に変えたため、基準排水量が3割低減し船体が長寿命化しています。
「あわじ」型のカバーストーリー、いや建造目的は、科学の発展に伴い日々開発される
新型機雷に対応するため、となっています。

さて、国歌「君が代」の演奏とともに、「はちじょう」の自衛艦旗が降下されました。
左手に三角に畳まれた旗を掲げ、副長がラッタルを渡ります。

副長を先頭に、「はちじょう」の乗組員が後に続いて退艦を行います。
この時の音楽はもちろん行進曲「軍艦」。
ところでこれを「総員退艦」と称してよろしいのでしょうか。
そういうと、何か今からよくないことになりそうな気がするのですが・・・。

掃海艦の乗員は全部で60名。
これが掃海艇となると48名となり、多めの一学級(しかも昔の)規模となります。
たったこれだけが一つの艦で、訓練と一日のほとんどをともに過ごすのですから、
掃海部隊が「家族」というような緊密な一体感で結ばれていたとしても当然です。

乗組員は、テントの前に整列し、自衛艦旗を掲げた副長は
前列一番左側でその姿勢のまま待機。
掃海艦からの60名の退艦はあっという間に終了し、行進曲「軍艦」は
中間部に入る前に終わってしまいました。

最後に退艦した艦長が、副長の前に歩みます。

自衛艦が就役するとき、防衛大臣、あるいはその代理から自衛艦旗が艦長に授与され、
艦長はそれを副長に渡し、最初に乗艦させます。
除籍はその逆で、乗員に先駆けて副長が自衛艦旗を艦から降ろし、
それを艦長が受け取って、執行官に返納することになっています。

「はちじょう」最後の艦長の手に副長から自衛艦旗が渡されました。

艦長は受け取った自衛艦旗を左手で掲げ、互いに右手で敬礼を交わします。

しかるのち、二人で正面にむきなおり・・・・、

艦長が受け取った自衛艦旗を持って中央に進み出ます。

まずは中央台の前で敬礼。

除籍の時にまで防衛大臣及びその代理が出席することは普通ないようです。
ということは、防衛省から受け取った旗を、自衛隊に返還するということになるのでしょうか。

横須賀地方総監に、自衛艦旗を返納する艦長。

地方総監はそれを横に控えていた副官に手渡します。
副官はそれを台の横に用意されていた白木の箱に納め・・・・、

持ち去ります。
この箱は、この後、車のハッチバックに置いてあるのを目撃しました。

そののち、地方総監からの訓示が行われました。
「『はちじょう』は、平成6年3月24日、『やえやま』型掃海艦の3番艦として就役した。
以後、23年間の永きにわたり、機雷戦部隊の主力艦として各種任務に従事し、
海上自衛隊の任務遂行に大きく貢献した。
23年間における総行程28万8千190マイル、総航海時間3万9千783時間。
二ヶ月に及ぶ、東日本大震災への派遣を含む災害派遣2回、
生存者捜索救助2回、航空機救難5回、海外派遣3回、
実機雷処分3回などの業績は、歴代艦長以下、乗組員が不屈の精神と誇りを持って、
一丸となって任務邁進した賜物であり、
海上自衛隊における掃海業務の発展に大きな足跡を残したことに
深い感謝と敬意を表する。
さらに、諸君が『はちじょう』最後の乗組員として、
有終の美を飾ったことに対し、その労をねぎらいたい。
まもなく、それぞれが新たな配置に向かうことになるが、
『はちじょう』乗組員であったことを誇りにし、
海上防衛の一旦を担うべくさらに精進努力することを期待する。
最後に、『はちじょう』の輝かしい業績と諸君の健闘に対し、
重ねて感謝と敬意を表するとともに、諸君の一層の活躍を祈念し、訓示とする」
東日本大震災発生時、「はちじょう」はシンガポールでの合同訓練に向けて航行中でした。
震災発生の一報を受け、すぐさま急遽引き返し被災地へ向かったと聞いています。
その時の「はちじょう」と「やえやま」の災害救助活動については、
このブログに詳しく書かれています。

横須賀地方総監に敬礼をした艦長は、振り向いて乗組員に正対し、
「ただいまをもって〇〇を解く。
『はちじょう』乗組員、解散!」
と声をかけ、その後乗組員の
「(敬)礼!」
という号令に対し、敬礼をしたまま左右に体を巡らせて総員を見回しました。
『〇〇』のところは聞き取れずわからなかったのですが、「任務」だったのでしょうか。

「まわれ〜みぎっ!」
もう一度号令が下され、全員が「はちじょう」の方をみて最後に敬礼を送ります。
これは「はちじょう」との別れに際し、その労をねぎらう敬意と感謝の意を表す敬礼です。
艦体に対して敬礼が送られるのは、もしかしたら23年の歴史で最初で最後のことかもしれません。
この時のマストからは、すでに長旗は降ろされていました。

そして、自衛艦旗が降ろされ、乗組員のいなくなった「はちじょう」。
気のせいか、もうすでにそこからは魂が抜けかけているように見えます。

解散した乗組員たちは、艦首側でこれから記念撮影をするようです。
テントの中の方々は三々五々語らったり、写真を取り合ったりしていましたが、
わたしは記念写真を撮る彼らの写真を撮るためにそーっと近づいてみました。

昔護衛艦の引き渡し式でお会いした陸自の方から、
「戦車などを導入するときでも、別にこんな式典はしないので少し驚いた」
という発言を聞いたことがあります。
海自は船舶と基本同じ慣例を導入しているので、導入にも除籍にも海の儀礼にしたがって
荘重ともいえる儀式を行うことは海軍以来の伝統となっています。
しかし、そういえば、海自であってもヘリや固定翼機の導入にあたって、
広く人を招いて式典を行うなどという話は聞いたことがありません。
LCACもかつてのカルガモ艦隊のMSBももちろん SAMも行わないのですから、
こういう一連の式典で遇される艦艇の基準はなんなのだろうとふと思います。
とにかく、これが海軍以来の伝統であり、その度ごとにこうやって
集団写真を撮るわけです。
海軍関係の資料を読んでいたとき、
「海軍というところは何かというと集団写真を撮る団体で」
と元海軍軍人が書いていたのをこの光景を見ながら思い出しました。

掃海艦「はちじょう」、最後の乗組員の、最後の記念写真です。
何枚か真面目な写真を撮り、最後に
「笑ってください」
と注文をつけられて。
皆さん、とってもいい笑顔ですね。(特に3列目右から2番目)
続く。