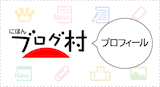2024年5月7日(火)
コツバメ Callophrys ferrea

20240416 前翅長12mmほど
年に一度、早春にだけ現れるシジミチョウ科の蝶
小雨の降る午前中、ピュンとすばやく飛んでスッととまる地味な蝶だ。
翅の表面はスカイブルーだったりしてきれいなのに・・・
開こうとしない。
例えば、コンクリートの路上にとまると

どこにいるかすぐにはわからない。
例えば、枯葉の上でもわからない。

気付かずに近づくとすばしこく飛んで逃げるからややこしいヤツだ。
そして、観察してるととまった後ジワ~ッと横たわるのだ。
太陽の光で体温を上げたいのなら他のシジミチョウみたく翅を広げてとまってくれればいいのに・・・
まるで、稀にいるであろう少し運んではすぐサボる宅配便みたいなヤツだ。

ま、私もそうなのである。
お世話になった横島漁港の底引き網漁の龍神丸さんへ感謝の意を込めて
購入した『びんごの自然誌 第3号』を手に、今日漁協へと出かけたのだが・・・

・本当ならGW前に届けられたはずなのに
・ピュッと急いで届けりゃいいのに、図書館に寄ったり、ため池覗いたり
宅急便ならぬ宅緩便なのでありました。
コツバメ Callophrys ferrea

20240416 前翅長12mmほど
年に一度、早春にだけ現れるシジミチョウ科の蝶
小雨の降る午前中、ピュンとすばやく飛んでスッととまる地味な蝶だ。
翅の表面はスカイブルーだったりしてきれいなのに・・・
開こうとしない。
例えば、コンクリートの路上にとまると

どこにいるかすぐにはわからない。
例えば、枯葉の上でもわからない。

気付かずに近づくとすばしこく飛んで逃げるからややこしいヤツだ。
そして、観察してるととまった後ジワ~ッと横たわるのだ。
太陽の光で体温を上げたいのなら他のシジミチョウみたく翅を広げてとまってくれればいいのに・・・
まるで、稀にいるであろう少し運んではすぐサボる宅配便みたいなヤツだ。

ま、私もそうなのである。
お世話になった横島漁港の底引き網漁の龍神丸さんへ感謝の意を込めて
購入した『びんごの自然誌 第3号』を手に、今日漁協へと出かけたのだが・・・

・本当ならGW前に届けられたはずなのに
・ピュッと急いで届けりゃいいのに、図書館に寄ったり、ため池覗いたり
宅急便ならぬ宅緩便なのでありました。