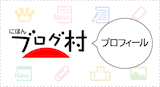2023年6月11日(日)
アカシジミ Japonica lutea

20230603 20mmほど
裏山を登った。
頂上付近は古い城跡が残り、視界が開けてるから楽しい。
「シギゾウムシの仲間もそろそろかな?」というのが下心。
どうせ初見の鳥には会えないからと、高倍率ズームデジカメを持って登らなかったのがいけなかった。
なぜなら、アカシジミがカシ類の葉にとまっていたからだ。
手元の10倍デジカメだと近づかなきゃいけない。
近づくと必ず逃亡する。
何度同じ失敗をくり返せば覚えるのだ! 私の頭はっ!
なので、この1枚撮らせてもらって、さようなら。
出会った他のチョウはモンキチョウのメス(白色型)

さて、アカシジミについて
属名がJaponicaなのに、日本・中国東部・朝鮮・台湾のカシ・シイ・ナラ林に分布してるという。
そして、なんといってもミドリシジミ亜科、つまりゼフィルスと呼ばれるグループで
日本には20数種いるうちの1種なのである。
20240614 追記のアカシジミ

翅が緑の金属色に光るミドリシジミたちにもぜひ会ってみたいものだ。
コナラやクヌギの林冠には、いろんなシジミチョウが乱舞している。
タマムシ類やシジミチョウの仲間は、木の天辺あたりをウロウロしておられるとのことで
延べ竿のような長い捕虫網を使って採集されるという。
私は、ポケットにある「生ごみ水切りネット」しか術がないので会える機会はほぼほぼないんだろうな。
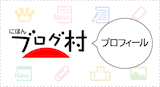
アカシジミ Japonica lutea

20230603 20mmほど
裏山を登った。
頂上付近は古い城跡が残り、視界が開けてるから楽しい。
「シギゾウムシの仲間もそろそろかな?」というのが下心。
どうせ初見の鳥には会えないからと、高倍率ズームデジカメを持って登らなかったのがいけなかった。
なぜなら、アカシジミがカシ類の葉にとまっていたからだ。
手元の10倍デジカメだと近づかなきゃいけない。
近づくと必ず逃亡する。
何度同じ失敗をくり返せば覚えるのだ! 私の頭はっ!
なので、この1枚撮らせてもらって、さようなら。
出会った他のチョウはモンキチョウのメス(白色型)

さて、アカシジミについて
属名がJaponicaなのに、日本・中国東部・朝鮮・台湾のカシ・シイ・ナラ林に分布してるという。
そして、なんといってもミドリシジミ亜科、つまりゼフィルスと呼ばれるグループで
日本には20数種いるうちの1種なのである。
20240614 追記のアカシジミ

翅が緑の金属色に光るミドリシジミたちにもぜひ会ってみたいものだ。
コナラやクヌギの林冠には、いろんなシジミチョウが乱舞している。
タマムシ類やシジミチョウの仲間は、木の天辺あたりをウロウロしておられるとのことで
延べ竿のような長い捕虫網を使って採集されるという。
私は、ポケットにある「生ごみ水切りネット」しか術がないので会える機会はほぼほぼないんだろうな。