
自ら動きだしたくなる「地域づくり」のお話!!
「地域づくりのハナシ」
講師は
高橋信博先生(山形県地域づくりプランナー)でした。
夢へと続く扉を開こう
山形県農林水産部農政企画課のパンフレットから
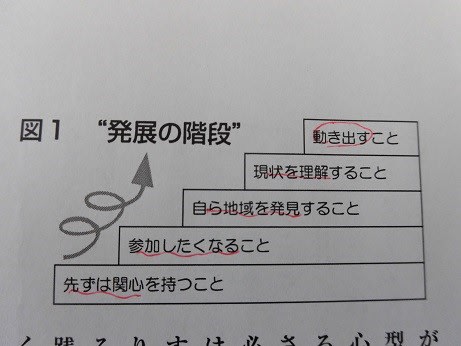
「地域づくり」2015.11月号から
基本の発展の階段です。

「地域づくり」2015.11月号から
一番最初に必要なことは
地域づくりを進めるための「括り」の設定と。
「地域づくり」2015.11月号から
ワークショップの流れ図と
一目で理解できる行動計画表です。

「夢へと続く扉を開こう」から。
白鷹町大瀬地区の「大瀬物り」の事例。
ひとり一人の助け合い・ふれあい・睦み合い
未来にほこる「大瀬の郷」

「夢へと続く扉を開こう」から。
「吉川の未来を創ろう!!」
「地域づくりのハナシ」・・・主催はいわき市
講師は
高橋信博先生(山形県地域づくりプランナー)
貴重な全国の事例を話され、
実行することの大切さを学びました。
高橋先生は
活き活きと暮らすための条件整備とは?
1)人 物 場で
その中の場として、
みんなで話し合う「場」を設け補完できないかと
2)地域が生き残るための生業を作り出すための視点
(産業の振興・雇用)
の2つに基づく集落のマスタープランが大事と。
その視点のお話と
その全国の事例の一端を話されました。
高橋先生は
若いときに「地域づくり」の現場に出会い、四半世紀この道一筋。
そして全国1.000の事例に関係。
↓
地域がなかなか動かない
↓
地域が動き出したくなる計画づくりが大事と
(地域の課題が何で、それがどのようになればよいのか。
それを解決するためにはだれが何をすれば良いのか。
そのために必要な材料は何か。
これらを関係するみんなが納得し整備され動き出す)
↓
自らの計画は自らが描くと。
(図1の 関心→参加→発見→理解→創造)の発展段階
図2で地域づくりを話し合う基本として一番最初に
括り検討カルテの作成が大事と
人材・社会・環境・文化・経済
↓
地域ワークショップ
↓
地域診断の材料を基に
課題の発生→計画と実行(対策)→その後の展開→次のステージへ
その後、
山形県や全国の事例をいくつか話されました。
☆山形県上山町の山元地区の
山元そば祭り(32回開催)
☆愛媛県
遊子の水荷浦の段畑の二度いも(じゃがいも)の事例
☆三重県神瀬の深蒸し茶の事例
☆山形県白鷹町深山地区
深山和紙の事例など
事例の一端を話されました。
いろいろな事例で
成功されているのに感心しました。
高橋先生は
実践につながらない計画はいらないと。
地域が動き出すためには
自ら動き出したくなるような生きた計画づくりが必須だと。
帰りたくなる郷・住みたくなる郷
になる地域づくりをしたいですね。
高橋先生
貴重な実践の記録
ありがとうございました。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます