右に駿河湾、左に朝日岳、国道一号線を戻る。大井川は、赤石山脈北部「間ノ岳」を源流に静岡県中部、電力開発のダムがある井川・畑薙ダム
など、長さ168km。を渡り、安倍川に、歌川広重の五十三次府中、河畔の餅屋の賑わいを描いている。山梨の安倍峠を源流。
直進すると富士市に、それを左折国道52号線「富士街道」を甲府方面に登ってみた。
「富士川街道」は、100強km。 起点、市清水区興津~ 終点山梨県甲府市 国道411号。山梨県南巨摩郡南部町、身延町、富士川町、韮崎市になる。ほぼ、富士川に沿い、この道路と並走する形で「中部横断自動車道」が整備中。(山梨県内では一部区間が供用中)
源流は、南アルプス駒ヶ岳釜無川、秩父山地、甲府盆地の笛吹川、富士山芝川と合流駿河湾に注いでいる。
日本三大急流の一つ、鉄道の無い時は、運搬船1500が往来していたと云う。
古来から洪水に悩まされ、武田信玄の治水対策は有名である。
雨が少なくゴムボートも気の毒

今年は特に、雨が少なく暑く、緑地部分が広がっており、この状態は、珍しいと云う。
草が茂る河川敷

水量の少ない富士川

「南部町」は、山梨県南西部で静岡県に最も接する。富士川中流域の町。町名は、かって土豪「南部氏」の居館があった。
山林が、約87%を占めている。中・近世まで、甲駿街道の宿場町で賑わっていた。
岩手県奥州南部藩の基礎は、この地の出身の「南部三郎光行」によって築かれた。
経済圏は、静岡富士宮に属し、南部茶が特産品に。
1189年源頼朝の奥州藤原氏討伐軍功により、糖部郡北東一帯を与えられ、三戸に本拠地を移し、和賀、稗置地方、1439年津軽の
安東氏討伐、1443年所領拡大をしている。
津軽、青森西部、最後は、盛岡藩で明治を迎えている。
南部町に

南部光行
┏━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━┳━━━┓
行朝 実光2 実長 朝清 宗清 行連
(一戸氏)[三戸南部氏] (波木井南部氏) (七戸氏)(四戸氏)(九戸氏)
┃ ┣━━━┓
時実3 実継 長義
┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┃ (波木井氏)
政光4 宗経5 政行 実政 宗実 義元 長継
┃ (伊勢南部氏) (甲斐南部氏)
┏━━━╋━━━┓ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┓
時長 師行 政長 義行 宗行6 祐行7
[根城南部氏] ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┣━━━┓
信政 義重 茂時10 信長11 仲行 茂行 信行 政連8 祐政9
┣━━━┓ ┃
信光 政光 政行12,,,,,,,(南部当主46代続く)
(八戸氏)(七戸氏) ┃
南部信直 1546-99 南部氏26代当主、秀吉に通じ、小田原征伐・朝鮮出兵に従軍した。領国を訪れた京都の鷹商から、秀吉の権勢を知らされ、家中無骨者揃いで適任者無し、鷹商が、憐れに思い、家臣人数名で使者となり、信直は、秀吉の後援を得ている。
南部氏の安泰は、一介の商人に助けられたという。
南部光行・南部氏の館跡



「南部城」
1180年に南部氏の始祖である南部光行が源頼朝から甲斐国南部牧を与えられ、南部氏館や南部城(詰城)を建てたのが始まりとされている。
この南部氏館は光行が陸奥国へ移住した後も南朝の拠点として使用された。
現在は南部氏館、南部城共に建物は存在しないが、南部氏館跡には古井戸の遺構が残されている。
土塁らしき堀



室町時代になると陸奥国へ移住した波木井氏にかわり、武田氏の一族である穴山氏が治めるようになる。
戦国時代に武田信玄が今川氏を滅ぼすと、当地に南部宿が設けられ、駿州往還の整備と共に軍事上・交通上の要所となる。
南部を治めていた武田氏家臣穴山信君の発給文書には度々南部宿の名前が登場し、伝馬の際は特定の時刻を過ぎた場合は南部宿に泊まるよう記されていたり、通行証の確認を行うなど関所の代わりとしても役割を担っていたと云う。
本堂 浄光寺の境内


鎌倉時代には光行の子・南部実長(波木井実長)をはじめとする波木井氏が当地を治めていた。
実長は日蓮宗に帰依していたことから、当地に浄光寺や妙浄寺といった日蓮宗の寺院が建立されている。
この2つの寺院は現存し、浄光寺には、南部氏の墓石群がある。
南部氏墓石群 地域の集会所なのか



身延山 久遠寺 総門

立派な楼門 参道



「久遠寺」は、1274年日蓮が、やまの西谷に草庵が起源で、1281年身延山久遠寺と命名された。
本尊は、大曼荼羅、1882年江戸池上で没し、遺言で墓を身延山西谷草庵北に置くように云い残している。今でも多数の僧坊が建てられている。
1712年時数133に達したという。
久遠寺参拝、287段の石段を登ると左手に五重塔、正面に大本堂で、日蓮宗の聖地である。
総門、三門、本堂、祖師堂、奥の院と続く、広い境内には、樹齢400年の枝垂れ桜が迎えてくれた。
287の急な階段



佐渡島流罪を許さ蛇日蓮が、「波木井実長公」の招きで身延山に入山し、庵室をかまえた事が起こりとされている。
以来9年に渡り、法華経の読誦と門弟達の指導に努めた日蓮は、1281年身延山に本格的工事をし本堂を建設している。
療養の為、武蔵の国池上で没した。


日蓮 1222-82 戦闘的な日蓮宗の開祖、千葉県、安房の生まれ、安房の清澄寺にて出家、浄土教を批判した。
鎌倉で「立正安国論」を書き上げる。北条時頼に提出したが無視され、伊豆へ流された。他宗の僧から憎まれ、佐渡ヶ島へ流された。身延山で蒙古来襲している。
鎌倉竜の口で打ち首時、雷鳴と稲妻が走り命が助かっている。
本堂


本堂裏手に身延山山頂を目指すロープウエイで約7分に奥の院「恩親閣」があり、ここからの展望は南アルプス、富士山を望む事が出来る。



境内や参道に芭蕉等の句碑が


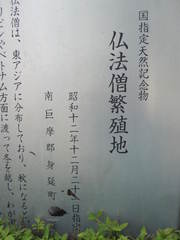
「蓮華寺」 日蓮聖人の高弟の1人であった日持上人が開基の古刹。

次回は、身延山久遠寺の裏手、早川・七面山へ。
など、長さ168km。を渡り、安倍川に、歌川広重の五十三次府中、河畔の餅屋の賑わいを描いている。山梨の安倍峠を源流。
直進すると富士市に、それを左折国道52号線「富士街道」を甲府方面に登ってみた。
「富士川街道」は、100強km。 起点、市清水区興津~ 終点山梨県甲府市 国道411号。山梨県南巨摩郡南部町、身延町、富士川町、韮崎市になる。ほぼ、富士川に沿い、この道路と並走する形で「中部横断自動車道」が整備中。(山梨県内では一部区間が供用中)
源流は、南アルプス駒ヶ岳釜無川、秩父山地、甲府盆地の笛吹川、富士山芝川と合流駿河湾に注いでいる。
日本三大急流の一つ、鉄道の無い時は、運搬船1500が往来していたと云う。
古来から洪水に悩まされ、武田信玄の治水対策は有名である。
雨が少なくゴムボートも気の毒

今年は特に、雨が少なく暑く、緑地部分が広がっており、この状態は、珍しいと云う。
草が茂る河川敷

水量の少ない富士川

「南部町」は、山梨県南西部で静岡県に最も接する。富士川中流域の町。町名は、かって土豪「南部氏」の居館があった。
山林が、約87%を占めている。中・近世まで、甲駿街道の宿場町で賑わっていた。
岩手県奥州南部藩の基礎は、この地の出身の「南部三郎光行」によって築かれた。
経済圏は、静岡富士宮に属し、南部茶が特産品に。
1189年源頼朝の奥州藤原氏討伐軍功により、糖部郡北東一帯を与えられ、三戸に本拠地を移し、和賀、稗置地方、1439年津軽の
安東氏討伐、1443年所領拡大をしている。
津軽、青森西部、最後は、盛岡藩で明治を迎えている。
南部町に

南部光行
┏━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━┳━━━┓
行朝 実光2 実長 朝清 宗清 行連
(一戸氏)[三戸南部氏] (波木井南部氏) (七戸氏)(四戸氏)(九戸氏)
┃ ┣━━━┓
時実3 実継 長義
┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┃ (波木井氏)
政光4 宗経5 政行 実政 宗実 義元 長継
┃ (伊勢南部氏) (甲斐南部氏)
┏━━━╋━━━┓ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┓
時長 師行 政長 義行 宗行6 祐行7
[根城南部氏] ┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ ┣━━━┓
信政 義重 茂時10 信長11 仲行 茂行 信行 政連8 祐政9
┣━━━┓ ┃
信光 政光 政行12,,,,,,,(南部当主46代続く)
(八戸氏)(七戸氏) ┃
南部信直 1546-99 南部氏26代当主、秀吉に通じ、小田原征伐・朝鮮出兵に従軍した。領国を訪れた京都の鷹商から、秀吉の権勢を知らされ、家中無骨者揃いで適任者無し、鷹商が、憐れに思い、家臣人数名で使者となり、信直は、秀吉の後援を得ている。
南部氏の安泰は、一介の商人に助けられたという。
南部光行・南部氏の館跡



「南部城」
1180年に南部氏の始祖である南部光行が源頼朝から甲斐国南部牧を与えられ、南部氏館や南部城(詰城)を建てたのが始まりとされている。
この南部氏館は光行が陸奥国へ移住した後も南朝の拠点として使用された。
現在は南部氏館、南部城共に建物は存在しないが、南部氏館跡には古井戸の遺構が残されている。
土塁らしき堀



室町時代になると陸奥国へ移住した波木井氏にかわり、武田氏の一族である穴山氏が治めるようになる。
戦国時代に武田信玄が今川氏を滅ぼすと、当地に南部宿が設けられ、駿州往還の整備と共に軍事上・交通上の要所となる。
南部を治めていた武田氏家臣穴山信君の発給文書には度々南部宿の名前が登場し、伝馬の際は特定の時刻を過ぎた場合は南部宿に泊まるよう記されていたり、通行証の確認を行うなど関所の代わりとしても役割を担っていたと云う。
本堂 浄光寺の境内


鎌倉時代には光行の子・南部実長(波木井実長)をはじめとする波木井氏が当地を治めていた。
実長は日蓮宗に帰依していたことから、当地に浄光寺や妙浄寺といった日蓮宗の寺院が建立されている。
この2つの寺院は現存し、浄光寺には、南部氏の墓石群がある。
南部氏墓石群 地域の集会所なのか



身延山 久遠寺 総門

立派な楼門 参道



「久遠寺」は、1274年日蓮が、やまの西谷に草庵が起源で、1281年身延山久遠寺と命名された。
本尊は、大曼荼羅、1882年江戸池上で没し、遺言で墓を身延山西谷草庵北に置くように云い残している。今でも多数の僧坊が建てられている。
1712年時数133に達したという。
久遠寺参拝、287段の石段を登ると左手に五重塔、正面に大本堂で、日蓮宗の聖地である。
総門、三門、本堂、祖師堂、奥の院と続く、広い境内には、樹齢400年の枝垂れ桜が迎えてくれた。
287の急な階段



佐渡島流罪を許さ蛇日蓮が、「波木井実長公」の招きで身延山に入山し、庵室をかまえた事が起こりとされている。
以来9年に渡り、法華経の読誦と門弟達の指導に努めた日蓮は、1281年身延山に本格的工事をし本堂を建設している。
療養の為、武蔵の国池上で没した。


日蓮 1222-82 戦闘的な日蓮宗の開祖、千葉県、安房の生まれ、安房の清澄寺にて出家、浄土教を批判した。
鎌倉で「立正安国論」を書き上げる。北条時頼に提出したが無視され、伊豆へ流された。他宗の僧から憎まれ、佐渡ヶ島へ流された。身延山で蒙古来襲している。
鎌倉竜の口で打ち首時、雷鳴と稲妻が走り命が助かっている。
本堂


本堂裏手に身延山山頂を目指すロープウエイで約7分に奥の院「恩親閣」があり、ここからの展望は南アルプス、富士山を望む事が出来る。



境内や参道に芭蕉等の句碑が


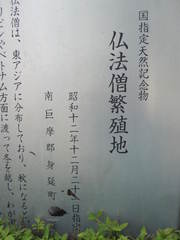
「蓮華寺」 日蓮聖人の高弟の1人であった日持上人が開基の古刹。

次回は、身延山久遠寺の裏手、早川・七面山へ。









