多摩川散歩に戻ります。
「多摩都市モノレール線」
「北立川駅」ー「上北台駅・都東大和市」の空中散歩へ。
多摩動物園前から立川方面



空中散歩



終点 上北台駅ー 桜街道駅ー 玉川上水駅(西武・拝島線、玉川上水)- 砂川七番駅ー 泉体育館駅ー 立飛駅(多摩都市モノレール運営基地)
ー 高松駅ー「立川北駅 /↓立川駅・JR東・青梅線・中央線・南武線」→ 立川南駅ー 柴崎体育館駅・・・(高幡不動駅・多摩動物園)
「終点・上北台は東京都東大和市」
狭山丘陵南部に位置し、旧神奈川県北多摩郡から明治26年東京府に編入している。清水・高木・奈良橋・蔵敷・芋窪・狭山の6村が合併して「大和村」
1655年「野火止用水開削後に開墾されている。幕末には、木綿織物「村山絣」が盛んに。1927年狭山丘陵に貯水池が建設されている。
村山貯水池の資料から、面積321HAが水没し、161戸が移転している。
1939年昭和14年、日立航空機工場・現在は、新興住宅都市として発展している。
JR立川と2階通路でー立川北駅へ





玉川上水駅を発車すると西武拝島線と交差。左手には西武鉄道の玉川上水車両基地が見える。
玉川上水を渡り、相変わらず変わらない住宅街の風景を見ながら走っていく。
砂川七番駅を発車すると間もなく東京都道7号杉並あきる野線(五日市街道)と交差。左にカーブし、南東を向くと右手に泉市民体育館が現れ
泉体育館駅へ。発車すると右へ大きくカーブして南西を向き芋窪街道から分かれ、ここから先は広大な工業地帯となる。
右手に立飛企業が見えると立飛駅、さらにいなげや青果センターなどが見えてくると三角のデルタ線を通る。これは多摩都市モノレールの車両基地
への引き込み線となっている。デルタ線を通過すると列車運転の基点となる高松駅へ。発車すると左にカーブし南を向く。
右手に自治大学校や農林水産省などの施設が見えてくる。
やがて両手から工場は消え、百貨店など商業施設が目立ってくると間もなく立川北駅に到着する。
モノレールで空中散歩
昭和記念公園



「上北台 - 玉川上水」
右手に広い霊園が広がる。都道43号立川東大和線(芋窪街道新道)の真上に位置し、バスターミナルと隣接する上北台駅は、鉄道のない
武蔵村山市の住民の足も担っている。発車すると間もなく右手から芋窪街道旧道が合流し、この先延々と広がる住宅街を両手に見ながら走る。
左にカーブを切ると左手に森永乳業東京多摩工場等の看板などが見えてくる。
桜街道駅は芋窪街道と桜街道という東大和市の市道の交差点の真上にある。しばらく進むと右手には佼成霊園という立正佼成会の霊園が広がり、間もなく玉川上水駅に到着する。この駅の構内に立川市との市境があると云う。
住宅街がどんどん広がって



「たちひ駅」
「ららぽーと立川立飛のプレオープン」
ららぽーと立川立飛のプレオープンは12月10。
オープンでは大混雑、モノレールも超満員でした。
たちひ・ららぽーと・オープン凄い賑わいを





館内





「立川飛行場の歴史」
1922年の 大正11年、 陸軍航空第5大隊が各務原(岐阜県)から立川へ移駐、(立川飛行場のはじまり)「陸軍飛行第5大隊」。
昭和3年、 日本航空輸送(株)が立川飛行場で設立ー国内初の民間航空会社、立川~大阪定期輸送の初運行。
御大典記念大観兵式(航空機百余機が参加)・ 陸軍技術研究所 所沢から移駐
昭和6年、 東京飛行場(現東京国際空港:羽田)完成に伴い、 民間航空会社が立川から羽田へ移動 。
昭和10 陸軍航空廠設立 ー 昭和13 陸軍航空技術研究所設立 ー 陸軍飛行第5連隊が柏へ移駐 ー 昭和15 陸軍航空工廠設立
昭和20 4月 立川大空襲ー8月 終戦 ー米軍基地となる。



「玉川上水」
江戸市中へ飲料水を供給していた上水(上水道として利用される溝渠)であり、江戸の六上水の一つ。
多摩の羽村から四谷までの全長43kmが1653年に築かれた。
羽村取水堰で多摩川から取水し、武蔵野台地を東流し、四谷大木戸(現在の四谷四丁目交差点付近)に付設された「水番所」(水番屋)を経て
市中へと分配されていた。
水番所以下は木樋や石樋を用いた地下水道であったが、羽村から大木戸までの約43kmは、すべて露天掘りであった。
羽村から四谷大木戸までの本線は武蔵野台地の尾根筋を選んで引かれているほか、大規模な分水路もそれぞれ武蔵野台地内の河川の分水嶺を選んで
引かれている。
1722年、以降の新田開発によって多くの分水(用水路)が開削されて武蔵野の農地へも水を供給し、農業生産にも大いに貢献した。
(野火止用水、千川上水)
玉川上水が

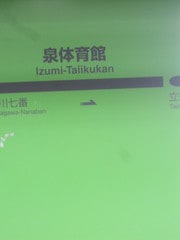

昭和20年 9月ー 米空軍、立川へ移駐(米空軍極東司令部設置)ー 昭和27 立川基地が極東最大の輸送基地となる(朝鮮戦争)。
昭和30年 5月ー 東京調達局、立川基地拡張計画を発表・ 昭和30 9月 砂川事件(基地拡張反対運動)全学連が。
昭和31年 防衛庁長官、測量中止発表ー 昭和44年 米空軍、立川基地の飛行業務を停止 ・防衛庁、自衛隊機及び民間機の立川飛行場使用を申し入れ
昭和46年 国有財産関東地方審議会日米共同使用了承 ・ 昭和47 陸上自衛隊の年度内移駐方針、閣議了承 。
昭和52年の 11月ー 米空軍、立川基地日本へ全面返還 。(陸上自衛隊駐屯地、広域防災基地として一部使用。
大型スーパーの駐車場


1989年の平成元年 4月ー 天皇・皇后両陛下行幸啓(立川飛行場・昭和記念公園)
ー砂川七番ー玉川上水ー桜街道ー上北台が終点



終点ー北上台駅

「多摩都市モノレール延長計画」は、平成10年、 上北台 - 立川北間開業し、平成12年、 立川北 - 多摩センター間・平成24年。
今後の延伸計画は、多摩センター駅から町田方面を望む。延伸案がある。構想路線は現営業区間も含めると「約93km」。
上北台駅から箱根ヶ崎方面、多摩センター駅から町田・八王子方面への延伸について検討されていると云う。
上北台 - 箱根ヶ崎間は、、導入空間となる新青梅街道の拡幅のため用地確保が進められているとも云う。
新青梅街道は上北台駅から神明4丁目までの1.1kmの区間を第一期工事。ー2017年。
箱根ヶ崎駅から武蔵村山市岸までの1.43kmの区間を第二期工事。 2018年度。
三本榎交差点から三ツ木交差点までの1.5kmが第三期工事として計画されているが、中央分離帯におけるモノレールの軌道建設のめどは立っていない。
多摩センター 八王子間は、多摩センターから西進して八王子までの路線については、導入空間の用地確保が。
多摩センター 町田間は、多摩センターから南進して町田までの路線についても、多摩都市モノレール町田方面延伸協議会が設立された。
また、構想は大きい。箱根ヶ崎からさらに延伸し、羽村、秋川を経て八王子までを結ぶ路線と唐木田付近で多摩センター - 八王子間の路線から分岐し、若葉台を経て是政までを結ぶ路線・八王子から小宮・日野を経て甲州街道までを結ぶ路線が。



「芋窪街道」ー距離:7,8k。
起点ー都立川市羽衣町~都道145号立川国分寺線交点。終点ー東大和市蔵敷。
バイパスは、立川市泉町(市民体育館交差点南方) - たちかわ中央公園交差点
立川市泉町(高松駅北交差点) - 都道153号立川昭島線支線(中央南北道路)交点(立川市役所交差点)
都ー 立川市ー国立市ー東大和市。






「郷社・豊鹿嶋神社」
東大和市芋窪にある神社。
蘇我倉山田石川麿が慶雲4年の707年、創建。明治14年、郷社に列格している。
(天智天皇第四姫蘇我倉山田石川麿)
祭神ー武御加豆智命。



「社伝」
社地、一萬三千六百六十四坪、御朱印十三石、本社六尺上屋を設く、拝殿二間に五間半、幣殿二間に二間半、社傳を閲るに、
慶雲四年の鎮座にて、武甕槌命を祭神とし、神體は龍王丸とて、則武甕槌命の太刀なりしといへど、神主も拝することを得ざるよし、
社を造立ありしは、天智天皇第四姫宮なりしとも、又蘇我山田石河麻呂なりしとも記し、この外疑ふべきことをも記したれば、此社傳天文等の棟札あるをもて見れば、舊きよりの鎮座なりしことは知るべし、例祭は九月十五日なり。
神寶ー 武甕槌命鎧ノ袖、五寸許。 黄金石、五寸許。 錦几帳、東照宮御寄進なし給ひしよし、外に尾州亜相公この邊遊覧の折柄、
當社に詣て自ら書して賜ひしといふ歌などありと云。
鐘、大鐘なり、銘に「奉納撞鐘一口、鹿島太神宮神前 建武三子年三月十三日 武州多東郡上奈良橋村 深井三郎源光義妻敬白」按するにここに載たる鐘銘に、多東郡上奈良橋村とあれば、當社草創の頃はこの邊奈良橋村の内にて、後別に一村となりしに、其のちからこの社も今の如く
この地に属せしものなるべし、又深井三郎日鍵義といへる人は、外に所見なし、もし此社の棟札にするせる、本旦那源憲光といへるものも、
深井の子孫なるにや、これらのことその微とすべきものあらざれば今より知りがたし、又此鏡社頭にかけおきしを、いつの頃にかありけん奪はれて今はなし、ただ鐘銘のみをつたえり。
平成4~6年解体時の棟札・1466年大工二郎三郎近吉にて建立、屋根は厚板葺が判明した。



末社。白山祠、子之神祠、山王祠。本社の左右にあり、何れも僅なる祠なり。
神主石井市之進。社地の西方に住めり、此人の先祖石川出羽守は、ここの地頭酒井某と共に、大阪御陣にも出たりなどいへどさせる記録はなし。
石。社前の原上むはら生い茂れり中にあり、要石と稱す、其さまをいはば、長さ二尺五寸許、横四尺許、径り一尺五寸、黒色にしていと潤澤あり、
かかる田間にありては、耕作の妨なりとて、いつの頃か百姓等よりつどひ、穿ちすてんとせしに、地下に至るほど石の形ますます大にして、
たやすく掘得べきにも非れば、是より土人要石と稱せる名を得たりと、村老の口碑にのこれり、按るにこの石適々鹿嶋社前にあれば、
かかる話を附會せしにや、覺束なし。(新編武蔵風土記稿より)



狭山丘陵の一角を切り開いて古くから「鹿島様」と呼ばれて親しまれ、信仰を集め、「鹿島様」と呼ばれ親しまれ、
「本殿」は、一間社流造で、都内に現存する最古、かつ唯一の室町時代建立の神社本殿です。
その規模は桁行(間口)が170.7cm、身舎の梁間(奥行)が152.4cm、向拝の梁間はやや狭くて140.4cmである。
この本殿の建築年代は、社家により天文一九年(一五五〇)に建立されたものと考えられてきました。しかし平成四年から六年にかけての
解体修理時に発見された棟札により、文正元年(一四六六)に大工二郎三郎近吉の手により建立されたことが明らかとなりました。
同時に、古くは屋根が厚板葺であったことも判明しました。(東京都教育委員会掲示より)
拝殿(本殿建設年代は、1550年建立)

「文化財」
本殿・都指定有形文化財ー獅子頭は、東大和市重宝ー本殿の狛犬、東大和市重宝。
末社ー紅葉稲荷神社



木彫り狛犬は,三多摩地方でも、貴重なもの。 獅子舞の獅子頭は雄獅子二頭と雌獅子一頭が組になっていると云う。
二人で一つの獅子頭を操る。
神社では毎年、大晦日から元旦にかけての年明けには、太鼓の音が響く中、直径が5mもあろうかという大きなかがり火がたかれる。
9月、鹿島様のお祭りが、(社例大祭)
荒々しく練り歩るく御神輿が。(青梅街道から参道へ入るのが難しいほど見物人で埋めつくされると云う)
木彫り狛犬は市の重宝指定



「蓮華寺」
蓮花寺とも呼ばれ、開山・開基は不明。
1631年入寂した承雲を中興開祖に。山門の南側に、木立の中の二本のカシの巨木の間に小祠があり、その前に縦1m、横60㎝ほどの石が露出
昔、村人が耕作のじゃまになるので掘り出そうとしましたが、石は下に行くほど大きくなり、いくら掘っても掘り出すことができません。
以来、誰いうことなく「鹿島様(豊鹿島神社)の要石」と呼ぶようになったといいます。
現在、さわると良くないことが起こるといわれ、金網で囲って近づけないようになっている。
真言宗豊山派「蓮華寺」 分院 本堂



まだ残る雑木林、ドングリの実を、保育園の子供達が拾う姿が。

次回は、あきる野市方面へ。
「多摩都市モノレール線」
「北立川駅」ー「上北台駅・都東大和市」の空中散歩へ。
多摩動物園前から立川方面



空中散歩



終点 上北台駅ー 桜街道駅ー 玉川上水駅(西武・拝島線、玉川上水)- 砂川七番駅ー 泉体育館駅ー 立飛駅(多摩都市モノレール運営基地)
ー 高松駅ー「立川北駅 /↓立川駅・JR東・青梅線・中央線・南武線」→ 立川南駅ー 柴崎体育館駅・・・(高幡不動駅・多摩動物園)
「終点・上北台は東京都東大和市」
狭山丘陵南部に位置し、旧神奈川県北多摩郡から明治26年東京府に編入している。清水・高木・奈良橋・蔵敷・芋窪・狭山の6村が合併して「大和村」
1655年「野火止用水開削後に開墾されている。幕末には、木綿織物「村山絣」が盛んに。1927年狭山丘陵に貯水池が建設されている。
村山貯水池の資料から、面積321HAが水没し、161戸が移転している。
1939年昭和14年、日立航空機工場・現在は、新興住宅都市として発展している。
JR立川と2階通路でー立川北駅へ





玉川上水駅を発車すると西武拝島線と交差。左手には西武鉄道の玉川上水車両基地が見える。
玉川上水を渡り、相変わらず変わらない住宅街の風景を見ながら走っていく。
砂川七番駅を発車すると間もなく東京都道7号杉並あきる野線(五日市街道)と交差。左にカーブし、南東を向くと右手に泉市民体育館が現れ
泉体育館駅へ。発車すると右へ大きくカーブして南西を向き芋窪街道から分かれ、ここから先は広大な工業地帯となる。
右手に立飛企業が見えると立飛駅、さらにいなげや青果センターなどが見えてくると三角のデルタ線を通る。これは多摩都市モノレールの車両基地
への引き込み線となっている。デルタ線を通過すると列車運転の基点となる高松駅へ。発車すると左にカーブし南を向く。
右手に自治大学校や農林水産省などの施設が見えてくる。
やがて両手から工場は消え、百貨店など商業施設が目立ってくると間もなく立川北駅に到着する。
モノレールで空中散歩
昭和記念公園



「上北台 - 玉川上水」
右手に広い霊園が広がる。都道43号立川東大和線(芋窪街道新道)の真上に位置し、バスターミナルと隣接する上北台駅は、鉄道のない
武蔵村山市の住民の足も担っている。発車すると間もなく右手から芋窪街道旧道が合流し、この先延々と広がる住宅街を両手に見ながら走る。
左にカーブを切ると左手に森永乳業東京多摩工場等の看板などが見えてくる。
桜街道駅は芋窪街道と桜街道という東大和市の市道の交差点の真上にある。しばらく進むと右手には佼成霊園という立正佼成会の霊園が広がり、間もなく玉川上水駅に到着する。この駅の構内に立川市との市境があると云う。
住宅街がどんどん広がって



「たちひ駅」
「ららぽーと立川立飛のプレオープン」
ららぽーと立川立飛のプレオープンは12月10。
オープンでは大混雑、モノレールも超満員でした。
たちひ・ららぽーと・オープン凄い賑わいを





館内





「立川飛行場の歴史」
1922年の 大正11年、 陸軍航空第5大隊が各務原(岐阜県)から立川へ移駐、(立川飛行場のはじまり)「陸軍飛行第5大隊」。
昭和3年、 日本航空輸送(株)が立川飛行場で設立ー国内初の民間航空会社、立川~大阪定期輸送の初運行。
御大典記念大観兵式(航空機百余機が参加)・ 陸軍技術研究所 所沢から移駐
昭和6年、 東京飛行場(現東京国際空港:羽田)完成に伴い、 民間航空会社が立川から羽田へ移動 。
昭和10 陸軍航空廠設立 ー 昭和13 陸軍航空技術研究所設立 ー 陸軍飛行第5連隊が柏へ移駐 ー 昭和15 陸軍航空工廠設立
昭和20 4月 立川大空襲ー8月 終戦 ー米軍基地となる。



「玉川上水」
江戸市中へ飲料水を供給していた上水(上水道として利用される溝渠)であり、江戸の六上水の一つ。
多摩の羽村から四谷までの全長43kmが1653年に築かれた。
羽村取水堰で多摩川から取水し、武蔵野台地を東流し、四谷大木戸(現在の四谷四丁目交差点付近)に付設された「水番所」(水番屋)を経て
市中へと分配されていた。
水番所以下は木樋や石樋を用いた地下水道であったが、羽村から大木戸までの約43kmは、すべて露天掘りであった。
羽村から四谷大木戸までの本線は武蔵野台地の尾根筋を選んで引かれているほか、大規模な分水路もそれぞれ武蔵野台地内の河川の分水嶺を選んで
引かれている。
1722年、以降の新田開発によって多くの分水(用水路)が開削されて武蔵野の農地へも水を供給し、農業生産にも大いに貢献した。
(野火止用水、千川上水)
玉川上水が

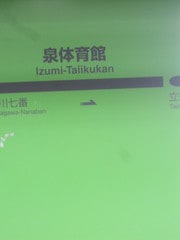

昭和20年 9月ー 米空軍、立川へ移駐(米空軍極東司令部設置)ー 昭和27 立川基地が極東最大の輸送基地となる(朝鮮戦争)。
昭和30年 5月ー 東京調達局、立川基地拡張計画を発表・ 昭和30 9月 砂川事件(基地拡張反対運動)全学連が。
昭和31年 防衛庁長官、測量中止発表ー 昭和44年 米空軍、立川基地の飛行業務を停止 ・防衛庁、自衛隊機及び民間機の立川飛行場使用を申し入れ
昭和46年 国有財産関東地方審議会日米共同使用了承 ・ 昭和47 陸上自衛隊の年度内移駐方針、閣議了承 。
昭和52年の 11月ー 米空軍、立川基地日本へ全面返還 。(陸上自衛隊駐屯地、広域防災基地として一部使用。
大型スーパーの駐車場


1989年の平成元年 4月ー 天皇・皇后両陛下行幸啓(立川飛行場・昭和記念公園)
ー砂川七番ー玉川上水ー桜街道ー上北台が終点



終点ー北上台駅

「多摩都市モノレール延長計画」は、平成10年、 上北台 - 立川北間開業し、平成12年、 立川北 - 多摩センター間・平成24年。
今後の延伸計画は、多摩センター駅から町田方面を望む。延伸案がある。構想路線は現営業区間も含めると「約93km」。
上北台駅から箱根ヶ崎方面、多摩センター駅から町田・八王子方面への延伸について検討されていると云う。
上北台 - 箱根ヶ崎間は、、導入空間となる新青梅街道の拡幅のため用地確保が進められているとも云う。
新青梅街道は上北台駅から神明4丁目までの1.1kmの区間を第一期工事。ー2017年。
箱根ヶ崎駅から武蔵村山市岸までの1.43kmの区間を第二期工事。 2018年度。
三本榎交差点から三ツ木交差点までの1.5kmが第三期工事として計画されているが、中央分離帯におけるモノレールの軌道建設のめどは立っていない。
多摩センター 八王子間は、多摩センターから西進して八王子までの路線については、導入空間の用地確保が。
多摩センター 町田間は、多摩センターから南進して町田までの路線についても、多摩都市モノレール町田方面延伸協議会が設立された。
また、構想は大きい。箱根ヶ崎からさらに延伸し、羽村、秋川を経て八王子までを結ぶ路線と唐木田付近で多摩センター - 八王子間の路線から分岐し、若葉台を経て是政までを結ぶ路線・八王子から小宮・日野を経て甲州街道までを結ぶ路線が。



「芋窪街道」ー距離:7,8k。
起点ー都立川市羽衣町~都道145号立川国分寺線交点。終点ー東大和市蔵敷。
バイパスは、立川市泉町(市民体育館交差点南方) - たちかわ中央公園交差点
立川市泉町(高松駅北交差点) - 都道153号立川昭島線支線(中央南北道路)交点(立川市役所交差点)
都ー 立川市ー国立市ー東大和市。






「郷社・豊鹿嶋神社」
東大和市芋窪にある神社。
蘇我倉山田石川麿が慶雲4年の707年、創建。明治14年、郷社に列格している。
(天智天皇第四姫蘇我倉山田石川麿)
祭神ー武御加豆智命。



「社伝」
社地、一萬三千六百六十四坪、御朱印十三石、本社六尺上屋を設く、拝殿二間に五間半、幣殿二間に二間半、社傳を閲るに、
慶雲四年の鎮座にて、武甕槌命を祭神とし、神體は龍王丸とて、則武甕槌命の太刀なりしといへど、神主も拝することを得ざるよし、
社を造立ありしは、天智天皇第四姫宮なりしとも、又蘇我山田石河麻呂なりしとも記し、この外疑ふべきことをも記したれば、此社傳天文等の棟札あるをもて見れば、舊きよりの鎮座なりしことは知るべし、例祭は九月十五日なり。
神寶ー 武甕槌命鎧ノ袖、五寸許。 黄金石、五寸許。 錦几帳、東照宮御寄進なし給ひしよし、外に尾州亜相公この邊遊覧の折柄、
當社に詣て自ら書して賜ひしといふ歌などありと云。
鐘、大鐘なり、銘に「奉納撞鐘一口、鹿島太神宮神前 建武三子年三月十三日 武州多東郡上奈良橋村 深井三郎源光義妻敬白」按するにここに載たる鐘銘に、多東郡上奈良橋村とあれば、當社草創の頃はこの邊奈良橋村の内にて、後別に一村となりしに、其のちからこの社も今の如く
この地に属せしものなるべし、又深井三郎日鍵義といへる人は、外に所見なし、もし此社の棟札にするせる、本旦那源憲光といへるものも、
深井の子孫なるにや、これらのことその微とすべきものあらざれば今より知りがたし、又此鏡社頭にかけおきしを、いつの頃にかありけん奪はれて今はなし、ただ鐘銘のみをつたえり。
平成4~6年解体時の棟札・1466年大工二郎三郎近吉にて建立、屋根は厚板葺が判明した。



末社。白山祠、子之神祠、山王祠。本社の左右にあり、何れも僅なる祠なり。
神主石井市之進。社地の西方に住めり、此人の先祖石川出羽守は、ここの地頭酒井某と共に、大阪御陣にも出たりなどいへどさせる記録はなし。
石。社前の原上むはら生い茂れり中にあり、要石と稱す、其さまをいはば、長さ二尺五寸許、横四尺許、径り一尺五寸、黒色にしていと潤澤あり、
かかる田間にありては、耕作の妨なりとて、いつの頃か百姓等よりつどひ、穿ちすてんとせしに、地下に至るほど石の形ますます大にして、
たやすく掘得べきにも非れば、是より土人要石と稱せる名を得たりと、村老の口碑にのこれり、按るにこの石適々鹿嶋社前にあれば、
かかる話を附會せしにや、覺束なし。(新編武蔵風土記稿より)



狭山丘陵の一角を切り開いて古くから「鹿島様」と呼ばれて親しまれ、信仰を集め、「鹿島様」と呼ばれ親しまれ、
「本殿」は、一間社流造で、都内に現存する最古、かつ唯一の室町時代建立の神社本殿です。
その規模は桁行(間口)が170.7cm、身舎の梁間(奥行)が152.4cm、向拝の梁間はやや狭くて140.4cmである。
この本殿の建築年代は、社家により天文一九年(一五五〇)に建立されたものと考えられてきました。しかし平成四年から六年にかけての
解体修理時に発見された棟札により、文正元年(一四六六)に大工二郎三郎近吉の手により建立されたことが明らかとなりました。
同時に、古くは屋根が厚板葺であったことも判明しました。(東京都教育委員会掲示より)
拝殿(本殿建設年代は、1550年建立)

「文化財」
本殿・都指定有形文化財ー獅子頭は、東大和市重宝ー本殿の狛犬、東大和市重宝。
末社ー紅葉稲荷神社



木彫り狛犬は,三多摩地方でも、貴重なもの。 獅子舞の獅子頭は雄獅子二頭と雌獅子一頭が組になっていると云う。
二人で一つの獅子頭を操る。
神社では毎年、大晦日から元旦にかけての年明けには、太鼓の音が響く中、直径が5mもあろうかという大きなかがり火がたかれる。
9月、鹿島様のお祭りが、(社例大祭)
荒々しく練り歩るく御神輿が。(青梅街道から参道へ入るのが難しいほど見物人で埋めつくされると云う)
木彫り狛犬は市の重宝指定



「蓮華寺」
蓮花寺とも呼ばれ、開山・開基は不明。
1631年入寂した承雲を中興開祖に。山門の南側に、木立の中の二本のカシの巨木の間に小祠があり、その前に縦1m、横60㎝ほどの石が露出
昔、村人が耕作のじゃまになるので掘り出そうとしましたが、石は下に行くほど大きくなり、いくら掘っても掘り出すことができません。
以来、誰いうことなく「鹿島様(豊鹿島神社)の要石」と呼ぶようになったといいます。
現在、さわると良くないことが起こるといわれ、金網で囲って近づけないようになっている。
真言宗豊山派「蓮華寺」 分院 本堂



まだ残る雑木林、ドングリの実を、保育園の子供達が拾う姿が。

次回は、あきる野市方面へ。









