「奥多摩の鶴の湯」
戦国時代・「武田信玄」の隠し湯の一つ。
水道局の計画の調査は山梨県北都留郡丹波山村から始めて下流青梅町あたりまで行われ、結局第1候補地に決まったのは青梅鉄道の終点御岳駅から少し遡った古里村一帯だったと云う。
古里村は、青梅町も巻き込んで全村をあげて反対し、第2案の小河内村案を進めるられていく。
小河内村は、武蔵の豪族で甲斐の武田の家臣であった小沢一族の流れで、原島氏は、天正年間に鶴の湯温泉を開いた家筋で元は氷川村の
奥の鍾乳洞で名高い日原川の岸を根拠地とした豪士であり昔は丹治氏を名乗った平家の末流と云う。
奥多摩湖の総貯水量は「1億8540万T]世界でも最大級の水道専用貯水池。
小河内ダム。ダムの運用は、35K下流にある羽村取水堰と連携しながら行われたと云う。
多摩川の水を、いったん小河内ダムに蓄え、水量調節しながら放流、羽村で取水し、玉川上水を経由して東京都の浄水場へ送る仕組み。
小河内ダムの最大の成果は、利水できない「ムダな水」を減らしたことだ。1993年に規則が
改められるまでの間、原則として小河内ダムから放流した水は、すべて羽村堰で取水された。
羽村から下流へ水を流すのは、川崎市の二ヶ領用水で灌漑用水が必要となる5月~9月の期間だけで、残りの半年以上は、奥多摩の山々から流れ出した
水が下流へ流れなかったと云う。
近くにある「日原鍾乳洞」は、関東随一の規模を誇る「日原鍾乳洞」は奥多摩町の北西部にあり洞内は全長800m、年間を通じて気温が11℃。
鍾乳洞の中にこんな空間があったのか!と思うスケールが魅力の鍾乳洞で、奥多摩駅から、日原鍾乳洞や本仁田山、川苔山などへハイキングコース。
日原川に架かる巨大なコンクリートアーチ橋が、橋の上には雑草が生い茂り、使われている様子はない。
JRの奥多摩駅と小河内ダム直下の水根積卸場を結ぶ、全長ー6.7kmのダム建設で大活躍した「奥多摩工業専用鉄道」の橋梁である。
奥多摩ふれあい館

「二本百名山・雲取山」
東京最高峰と都民の水源と登山者憧れの2000m級の山「雲取山」は、山頂から都内・関東平野・富士山・南アルプス等眺望抜群である。
「日原鍾乳洞」付近からのコースがおすすめ(歩行時間約5時間強)
「奥多摩昔道」ー奥多摩駅から奥多摩湖を歩こうー
小河内ダム建設で資材運搬専用鉄道として造られ、昭和30年頃まで使われていた。今でも所々にレール・トンネル跡が。
都水道局小河内線は、昭和28年頃煙をはいて走っている。
「日原鍾乳洞」
奥多摩駅から日原街道へ、バス停倉沢から谷に「倉沢のヒノキ」、トンネルを潜りバス停東日原に森林館・稲村岩・ふるさと美術館
バス停鍾乳洞に石山神社・小川大滝・梵天岩・鍾乳洞がある。(都指定天然記念物)


「水と緑のふれあい館」(入場無料)
写真 館内1階エントランスホール・館周辺施設や水道局事業の取組などを映像と音響で楽しめる。



「川野車人形」
天保時代の1830~44年、武州加冶村阿須(現・埼玉県飯能市)の西川古柳(本名:山岸柳吉)により考案された箱車(内部に車輪が3つ組み込まれている)をつかう一人遣いの人形です。
この箱車に座り、ずれないように腰に縛り付け、自分の足で人形の足をつかみ動かす。
左手で人形の頭を操作し、右手で人形の右手を操作する、内部に仕掛けがあり、人形の右手を動かしながら人形の左手も動かすことが出来るようになっていると云う。江戸時代末期に考案された車人形が、明治18年、小宮村(現:あきる野市小宮)の説教節の太夫、岸野清兵衛により川野地区にもたらされ
川野地区には車人形が入る前に、二人遣いの人形芝居が伝承されていたらしい。
現在でも宝暦2年から天明・文政年間にかけて作られた人形の頭部であるカシラが31個残っておりそのうち3個は「金平頭」で文化財としても
貴重なカシラと云う。
車人形が導入される以前の人形は二人遣いで、人形のカシラは小ぶりで動かず、手足もなく、主遣いが頭と人形の右手、もう一人が人形の胴体部をもち、人形の左手を担当していたらしい。
川野には浄瑠璃本が百段ほどありましたが、火災で焼失し現在は約三十段位に、川野に入った車人形は村人の娯楽として
「3月5日箭弓神社の祭礼」に民家で上演され、昭和6年ダム計画が発表されると、人々が昭島や羽村へ移住しはじめ、昭和13年から
ダム工事が着工すると多くの人たちがダム計画地から離れ、川野は過疎化し、昭和27年川野車人形は、都無形民俗文化財に指定されましたが、
昭和32年、ダムが完成以後は人手が少なくなり、上演されなくなってしまう。昭和45年、文化財を見直す機運が盛り上がり、
都と奥多摩町の補助金で人形と衣装の修理が行われ、保存会を結成して、復活のための練習が始まり、地元を離れた人たちが組織し。
「川野会」の援助もあり、現在では3月5日に地元の箭弓神社の祭礼に川野会の人たちも川野生活館に集まり年1回の定期公演がある。
伝承演目ー三番叟・東山朝倉草紙(渡し場・住家:子別れ)・出世景清一代記(「日向」とも)(阿古屋自害の場・獄舎破りの場・人丸姫道行の場)
東海道中膝栗毛(赤坂並木の段)・小栗判官一代記(七色の場)等が上演されると云う。
定期公演ー3月5日午後1時頃~3時頃 奥多摩町川野生活館。


「奥多摩水源と森林」
手入れ不足の森は暗い森に・手入れされた森は明るい森。
森を健康にするためには、
「間伐」生育の悪い木などを抜き切り作業を、間伐を行うと森の中に光が入るため、草や低い木が成長します。
これ等の草木などは雨が地面にぶつかる力を和らげ、土が川へ流れ出るのを防いでくれ、残った木は太く育ち健康な森に。
「道づくり」
間伐した木材を横木と杭で道を作り、歩道を。
「枝打ち」
余分な木の枝を切り落とし、節の無い良質な木材にします。(木を切り倒すのには・手オノとノコギリ)


森づくりは、豊かな水を生む


「ダム造りの資材を運ぶ鉄道から」
氷川駅(奥多摩駅)ー 第一氷川橋梁ー 第一氷川トンネルー 日原川橋梁ー 第二氷川トンネルー 第二氷川橋梁ー 氷川疎水トンネル
ー 第三氷川トンネルー 第一弁天橋梁ー 第二弁天橋梁ー 第三氷川橋梁ー 第四氷川トンネルー 第一小留浦橋梁ー 第一小留浦トンネル
ー 第二小留浦橋梁ー 第二小留浦トンネルー第三小留浦橋梁ー 第三小留浦トンネルー 第四小留浦橋梁ー 第四小留浦トンネル
ー 第五小留浦橋梁ー 第五小留浦トンネルー 第一境橋梁 ー 桧村トンネルー 第一境トンネルー 第二境橋梁ー 第二境トンネルー 第三境橋梁
ー 第三境トンネルー 第四境橋梁ー白髭トンネルー 橋詰橋梁ー 栃寄橋梁ー 白髭橋梁ー 梅久保トンネルー 梅久保橋梁ー 惣獄橋梁
ー 第一板小屋トンネルー 第二板小屋トンネルー清水疎水トンネルー 清水トンネルー 第一桃ヶ沢トンネルー 桃ヶ沢橋梁ー 第二桃ヶ沢トンネル
ー 中山トンネルー第一水根橋梁ー 水根トンネルー第二水根橋梁ー 水根駅 。
線路延長ー6.7km・最急勾配ー30パーミル・1日最大輸送量:1,500T・橋梁ー23箇所、延長1,121m・トンネルー23箇所、延長2,285m。
(難工事であったであろう)


「完成までに長い道のり」
小河内ダムの築造計画は古く大正15年に遡り、当時の東京市会が将来の大東京実現を予想して水道事業上の百年の長計を樹てるべきだとしたことから、調査が開始され、昭和7年、東京市会で小河内ダム築造計画が決定された。
その後、多摩川下流、神奈川県側の二ヶ領用水との間で水利権を巡る調整に時間がかかったこともあって、総合起工式が行われたのは昭和13年。
用地買収が進んだが、戦争中に一時中断、昭和23年再開。
工事は、昭和13年に付け替え道路工事が始まり、順次進み、しかしこれも戦争で18年に中断、23年に再開。
28年に本体の定礎式があり、竣工式は32年11月。
完成に長期を要したが、今都民の水瓶として大きな役割を果たし、大正にはじまる計画の先見性は、現在賞賛されると云う。
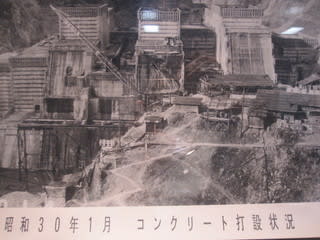

水を育む豊かな森を
森林を適切に管理して、水道の水源を守る。



「湖低に沈んだ旧小河内村伝統文化・鹿島踊り」
小河内の鹿島踊りは、旧小河内村で伝わっていた民族芸能。ダム建設により、移転をした村の住民たちが、散り散りになった人々のつながりを
踊りで残したいと、昭和45年に踊りの保存会を設立。現在も大切に受け継がれていると云う。
美しい着物と豪華な装飾品を身につけた女装姿の青年たちが、風雅に舞う小河内独特の踊り、昭和55年に、国の重要無形文化財に指定。

「小河内神社」は、湖にある小さな神社で、湖に飛び出した半島のような場所にある。
四方を湖に取り囲まれて浮かんでいるよう。
神社は小河内ダムが建設された時に水没した旧小河内村から移された小河内地区の総鎮守で、今は水の護り神として祀られている。
鹿島踊りー原の獅子舞・坂本の獅子舞・川野の獅子舞・峰の獅子舞は9月

次回から多摩川を下って行きます。鳩ノ巣方面へ。
戦国時代・「武田信玄」の隠し湯の一つ。
水道局の計画の調査は山梨県北都留郡丹波山村から始めて下流青梅町あたりまで行われ、結局第1候補地に決まったのは青梅鉄道の終点御岳駅から少し遡った古里村一帯だったと云う。
古里村は、青梅町も巻き込んで全村をあげて反対し、第2案の小河内村案を進めるられていく。
小河内村は、武蔵の豪族で甲斐の武田の家臣であった小沢一族の流れで、原島氏は、天正年間に鶴の湯温泉を開いた家筋で元は氷川村の
奥の鍾乳洞で名高い日原川の岸を根拠地とした豪士であり昔は丹治氏を名乗った平家の末流と云う。
奥多摩湖の総貯水量は「1億8540万T]世界でも最大級の水道専用貯水池。
小河内ダム。ダムの運用は、35K下流にある羽村取水堰と連携しながら行われたと云う。
多摩川の水を、いったん小河内ダムに蓄え、水量調節しながら放流、羽村で取水し、玉川上水を経由して東京都の浄水場へ送る仕組み。
小河内ダムの最大の成果は、利水できない「ムダな水」を減らしたことだ。1993年に規則が
改められるまでの間、原則として小河内ダムから放流した水は、すべて羽村堰で取水された。
羽村から下流へ水を流すのは、川崎市の二ヶ領用水で灌漑用水が必要となる5月~9月の期間だけで、残りの半年以上は、奥多摩の山々から流れ出した
水が下流へ流れなかったと云う。
近くにある「日原鍾乳洞」は、関東随一の規模を誇る「日原鍾乳洞」は奥多摩町の北西部にあり洞内は全長800m、年間を通じて気温が11℃。
鍾乳洞の中にこんな空間があったのか!と思うスケールが魅力の鍾乳洞で、奥多摩駅から、日原鍾乳洞や本仁田山、川苔山などへハイキングコース。
日原川に架かる巨大なコンクリートアーチ橋が、橋の上には雑草が生い茂り、使われている様子はない。
JRの奥多摩駅と小河内ダム直下の水根積卸場を結ぶ、全長ー6.7kmのダム建設で大活躍した「奥多摩工業専用鉄道」の橋梁である。
奥多摩ふれあい館

「二本百名山・雲取山」
東京最高峰と都民の水源と登山者憧れの2000m級の山「雲取山」は、山頂から都内・関東平野・富士山・南アルプス等眺望抜群である。
「日原鍾乳洞」付近からのコースがおすすめ(歩行時間約5時間強)
「奥多摩昔道」ー奥多摩駅から奥多摩湖を歩こうー
小河内ダム建設で資材運搬専用鉄道として造られ、昭和30年頃まで使われていた。今でも所々にレール・トンネル跡が。
都水道局小河内線は、昭和28年頃煙をはいて走っている。
「日原鍾乳洞」
奥多摩駅から日原街道へ、バス停倉沢から谷に「倉沢のヒノキ」、トンネルを潜りバス停東日原に森林館・稲村岩・ふるさと美術館
バス停鍾乳洞に石山神社・小川大滝・梵天岩・鍾乳洞がある。(都指定天然記念物)


「水と緑のふれあい館」(入場無料)
写真 館内1階エントランスホール・館周辺施設や水道局事業の取組などを映像と音響で楽しめる。



「川野車人形」
天保時代の1830~44年、武州加冶村阿須(現・埼玉県飯能市)の西川古柳(本名:山岸柳吉)により考案された箱車(内部に車輪が3つ組み込まれている)をつかう一人遣いの人形です。
この箱車に座り、ずれないように腰に縛り付け、自分の足で人形の足をつかみ動かす。
左手で人形の頭を操作し、右手で人形の右手を操作する、内部に仕掛けがあり、人形の右手を動かしながら人形の左手も動かすことが出来るようになっていると云う。江戸時代末期に考案された車人形が、明治18年、小宮村(現:あきる野市小宮)の説教節の太夫、岸野清兵衛により川野地区にもたらされ
川野地区には車人形が入る前に、二人遣いの人形芝居が伝承されていたらしい。
現在でも宝暦2年から天明・文政年間にかけて作られた人形の頭部であるカシラが31個残っておりそのうち3個は「金平頭」で文化財としても
貴重なカシラと云う。
車人形が導入される以前の人形は二人遣いで、人形のカシラは小ぶりで動かず、手足もなく、主遣いが頭と人形の右手、もう一人が人形の胴体部をもち、人形の左手を担当していたらしい。
川野には浄瑠璃本が百段ほどありましたが、火災で焼失し現在は約三十段位に、川野に入った車人形は村人の娯楽として
「3月5日箭弓神社の祭礼」に民家で上演され、昭和6年ダム計画が発表されると、人々が昭島や羽村へ移住しはじめ、昭和13年から
ダム工事が着工すると多くの人たちがダム計画地から離れ、川野は過疎化し、昭和27年川野車人形は、都無形民俗文化財に指定されましたが、
昭和32年、ダムが完成以後は人手が少なくなり、上演されなくなってしまう。昭和45年、文化財を見直す機運が盛り上がり、
都と奥多摩町の補助金で人形と衣装の修理が行われ、保存会を結成して、復活のための練習が始まり、地元を離れた人たちが組織し。
「川野会」の援助もあり、現在では3月5日に地元の箭弓神社の祭礼に川野会の人たちも川野生活館に集まり年1回の定期公演がある。
伝承演目ー三番叟・東山朝倉草紙(渡し場・住家:子別れ)・出世景清一代記(「日向」とも)(阿古屋自害の場・獄舎破りの場・人丸姫道行の場)
東海道中膝栗毛(赤坂並木の段)・小栗判官一代記(七色の場)等が上演されると云う。
定期公演ー3月5日午後1時頃~3時頃 奥多摩町川野生活館。


「奥多摩水源と森林」
手入れ不足の森は暗い森に・手入れされた森は明るい森。
森を健康にするためには、
「間伐」生育の悪い木などを抜き切り作業を、間伐を行うと森の中に光が入るため、草や低い木が成長します。
これ等の草木などは雨が地面にぶつかる力を和らげ、土が川へ流れ出るのを防いでくれ、残った木は太く育ち健康な森に。
「道づくり」
間伐した木材を横木と杭で道を作り、歩道を。
「枝打ち」
余分な木の枝を切り落とし、節の無い良質な木材にします。(木を切り倒すのには・手オノとノコギリ)


森づくりは、豊かな水を生む


「ダム造りの資材を運ぶ鉄道から」
氷川駅(奥多摩駅)ー 第一氷川橋梁ー 第一氷川トンネルー 日原川橋梁ー 第二氷川トンネルー 第二氷川橋梁ー 氷川疎水トンネル
ー 第三氷川トンネルー 第一弁天橋梁ー 第二弁天橋梁ー 第三氷川橋梁ー 第四氷川トンネルー 第一小留浦橋梁ー 第一小留浦トンネル
ー 第二小留浦橋梁ー 第二小留浦トンネルー第三小留浦橋梁ー 第三小留浦トンネルー 第四小留浦橋梁ー 第四小留浦トンネル
ー 第五小留浦橋梁ー 第五小留浦トンネルー 第一境橋梁 ー 桧村トンネルー 第一境トンネルー 第二境橋梁ー 第二境トンネルー 第三境橋梁
ー 第三境トンネルー 第四境橋梁ー白髭トンネルー 橋詰橋梁ー 栃寄橋梁ー 白髭橋梁ー 梅久保トンネルー 梅久保橋梁ー 惣獄橋梁
ー 第一板小屋トンネルー 第二板小屋トンネルー清水疎水トンネルー 清水トンネルー 第一桃ヶ沢トンネルー 桃ヶ沢橋梁ー 第二桃ヶ沢トンネル
ー 中山トンネルー第一水根橋梁ー 水根トンネルー第二水根橋梁ー 水根駅 。
線路延長ー6.7km・最急勾配ー30パーミル・1日最大輸送量:1,500T・橋梁ー23箇所、延長1,121m・トンネルー23箇所、延長2,285m。
(難工事であったであろう)


「完成までに長い道のり」
小河内ダムの築造計画は古く大正15年に遡り、当時の東京市会が将来の大東京実現を予想して水道事業上の百年の長計を樹てるべきだとしたことから、調査が開始され、昭和7年、東京市会で小河内ダム築造計画が決定された。
その後、多摩川下流、神奈川県側の二ヶ領用水との間で水利権を巡る調整に時間がかかったこともあって、総合起工式が行われたのは昭和13年。
用地買収が進んだが、戦争中に一時中断、昭和23年再開。
工事は、昭和13年に付け替え道路工事が始まり、順次進み、しかしこれも戦争で18年に中断、23年に再開。
28年に本体の定礎式があり、竣工式は32年11月。
完成に長期を要したが、今都民の水瓶として大きな役割を果たし、大正にはじまる計画の先見性は、現在賞賛されると云う。
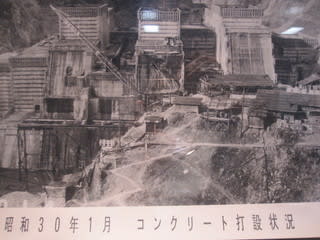

水を育む豊かな森を
森林を適切に管理して、水道の水源を守る。



「湖低に沈んだ旧小河内村伝統文化・鹿島踊り」
小河内の鹿島踊りは、旧小河内村で伝わっていた民族芸能。ダム建設により、移転をした村の住民たちが、散り散りになった人々のつながりを
踊りで残したいと、昭和45年に踊りの保存会を設立。現在も大切に受け継がれていると云う。
美しい着物と豪華な装飾品を身につけた女装姿の青年たちが、風雅に舞う小河内独特の踊り、昭和55年に、国の重要無形文化財に指定。

「小河内神社」は、湖にある小さな神社で、湖に飛び出した半島のような場所にある。
四方を湖に取り囲まれて浮かんでいるよう。
神社は小河内ダムが建設された時に水没した旧小河内村から移された小河内地区の総鎮守で、今は水の護り神として祀られている。
鹿島踊りー原の獅子舞・坂本の獅子舞・川野の獅子舞・峰の獅子舞は9月

次回から多摩川を下って行きます。鳩ノ巣方面へ。









