太田市は、県南東部、中世以来の郷名、江戸期には、「例弊使街道」の太田宿として栄え、「大光院」の門前町で知られている。
太田市と云えば、やはり第二次世界大戦終結まで軍需工業都市として(旧中島飛行機)・戦後冨士重工自動車製造を核とし、県最大工業都市。
古墳では、「天神山古墳」は、東日本最大前方後円墳で、長さ210m、5世紀中期の築造と云う、中世の新田氏の遺跡・金山城跡など、文化財に
恵まれている。
「大光院」-金山町の新田寺院号・浄土宗・山号ー義重山・開山ー然誉呑竜
徳川家康が、始祖とする「新田義重」を祀っている。
1613年建立。呑竜は貧民の子供を弟子の名目で養育したことから「子育て呑竜」と云われている。
太田市「大光院」

「源 義重・新田 義重・上西入道」 1114(1135)-1202年 平安時代末期から鎌倉時代初期の河内源氏の武将。
源義国の長男。新田氏の祖。
武家の棟梁として名を馳せた八幡太郎義家の孫。異母弟に足利氏の始祖源義康がいる。
新田氏本宗家(上野源氏)の初代であり、上野国新田荘を本拠としたため新田義重と称している。
大光院本殿

1613年、徳川家康によって一族の繁栄と始祖新田義重を追善供養するために開かれた浄土宗の寺で、開山には芝増上寺の観智国師の門弟で四哲の一人といわれた「呑龍上人」が迎えている。
上人は、1556年、武蔵国埼玉郡一の割村(埼玉県春日部市)に生まれ、1623年、大光院で入寂した名僧。
大光院に入山した上人は、看経・講義・説法などに力を尽くしたため、上人の徳を慕う学僧が大光院には多数集まり、周辺農民も上人の教えを受け入れたので、寺運は栄え、一方では、乱世後の人心は乱れ、天災等の影響で生活は困難を極めていたため、捨て子や間引きなどの非道が横行していたと云う。
上人は、その非道を憂い、捨て子や貧しい人々の子供を弟子という名目で寺に受け入れ、寺の費用で養育。
このため、「子育て呑龍」と呼ばれ、今に篤い信仰を集めてゐると云う。
大光院 本殿

徳川幕府より寺領300石の御朱印を拝領、浄土宗関東十八檀林の一つとして浄土宗の関東における学問所となっていたと云う。
大光院 東上州三十三観音特別札所、武州太田七福神の弁財天。

大光院宮殿 安産、育児の願かけに女性の参拝が多い 鐘楼



菊人形の歴史は、以外に新しい。1910年、明治43年に、京阪本線の天満橋駅 - 五条駅(現・清水五条駅)間の開業記念事業として東京両国国技館で開催されていた菊人形に着目。
名古屋の黄花園主と契約、大阪府北河内郡友呂岐村(現在の寝屋川市)にあった「香里遊園地」で第1回菊人形を開催、京阪電車で往復乗車の観客には入場無料・関係先に招待券を配布するなどの積極策をとり成功を収めた。
大光院菊花展



1911年も内容を充実して菊人形展が開催されたが前年以下の成績で、香里園遊園地の土地も住宅地として売却されてしまった。
香里園遊園地の代替として枚方駅(現在の枚方公園駅)の側に約1万平方メートルの土地を購入し、岐阜菊楽園の浅野善吉を中心とする菊師らによって
1912年第3回菊人形が開催。
以後1918年、大正7年まで順調に続けられたが、金銭トラブル(電車の乗客数に対してのバックマージンの金額で折り合いが付かなかった)で岐阜菊楽園が請負を辞退。
大光院菊花展



宇治で菊人形展開催を熱望していた料亭の主人「別所吉松」との話し合いの結果、1919年、宇治橋と国鉄宇治駅の間に新たな菊人形館を建てて開催。
枚方時代より優れた菊人形が名人によって製作され、水戸・高松の芸妓の余興を見せたのに好評では有ったが毎年欠損を出し、
1922年の菊人形展終了後に火災で菊人形館が焼失、宇治での開催は不可能に。
そこに南海鉄道の後援で堺大浜で菊人形を興業していた東京相撲協会年寄、春日野・中田の両名から枚方に移したいとの申し入れが有り、大浜の菊人形館を枚方に移築して1923年、菊人形展が枚方に戻って来た。
1924年、本館・余興館・ボート池・滑り台・ブランコなどが整備され、翌年には、枚方遊園は実質京阪電気鉄道の経営となった。
これが「ひらかたパーク」の起源と云う。
大光院菊花展


「新田金山」
県太田市金山町にある標高239mの独立峰である。山頂には「新田神社」や「金山城(国の史跡)」があり、南側下に太田市街地、

以前にも掲載している「金山城跡」
太田駅北約3km金山山頂にある山城ー室町~戦国期。
1584年北条氏の手に渡っている。小田原合戦後廃城に。本丸跡に「新田神社」が明治8年創建された。
戦国時代の山城「金山城」

室町時代以前、1336年に「佐野義綱」が新田庄の新田城を攻め落としたという記録がある。
新田城が新田義貞によって金山に建築されていたのではという説があるが、最近行われている発掘調査ではその時代の遺構や遺物は検出されない。
ただし城郭遺構の保護との兼ね合いのために万全な調査ができていないという一面もあると云う。
金山城碑 城内路



1469年、 新田一族であった「岩松家純」によって築城される。
1528年、「由良成繁・国繁親子」、1584年には、北条氏と主は変わったっている。
上杉謙信の攻撃を退けるなど、関東七名城の一つとされ、1590年、 豊臣秀吉の小田原征伐の際攻撃を受けて落城、こののち廃城となった。
大事な井戸跡 馬小屋

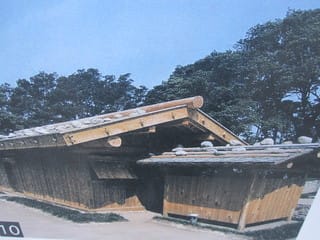
主の城主ー岩松氏・後北条氏高山定重・宇津木氏久。
1934年(昭和9年)「金山城跡」として国の史跡に指定され,現在は、いくつかの遺構をもとに、公園として整備されている。
2006年、日本100名城(17番)に選定。2009年、史跡金山城跡ガイダンス施設・太田市金山地域交流センターが開館している。
石垣・土塁・濠・馬出し・井戸・新田神社、、など。


群馬県利根川「刀木橋」を通り、ここは、埼玉県熊谷市妻沼町(女医1号「荻野吟子」生誕地)
埼玉県熊谷市ー「妻沼聖天山・歓喜院」ー高野山真言宗の仏教寺院・関東八十八箇所第88番結願所。
日本三大聖天の一つとされ、「妻沼聖天山」と 称することが多い。
本尊ー歓喜天御正体錫杖頭(重要文化財)

1179年に、長井庄(熊谷市妻沼)を本拠とした武将「齋藤別当実盛」が、守り本尊の大聖歓喜天(聖天)を祀る聖天宮を建立し、
長井庄の総鎮守としたのが始まりとされている。
1197年、良応僧都(斎藤別当実盛の次男である実長)が聖天宮の別当寺院(本坊)として歓喜院長楽寺を建立し、十一面観音を本尊としたという。
妻沼聖天ー歓喜院(菊花展)

「斎藤 実盛」-平安時代末期の武将。藤原利仁の流れを汲む斎藤則盛(また斎藤実直とも)の子。
越前国の出で、武蔵国幡羅郡長井庄(埼玉県熊谷市)を本拠とし、長井別当と呼ばれた。
武蔵国は、相模国を本拠とする「源義朝」と、上野国に進出してきたその弟・「義賢」という両勢力の緩衝地帯であった。
実盛は始め義朝に従っていたが、やがて地政学的な判断から義賢の幕下に伺候するようになる。
こうした武蔵衆の動きを危険視した義朝の子・「源義平」は、1155年、に義賢を急襲してこれを討ち取ってしまうー(大蔵合戦)。
斉藤実盛は、再び義朝・義平父子の麾下に戻るが、一方で義賢に対する旧恩も忘れておらず、義賢の遺児・駒王丸を畠山重能から預かり、駒王丸の乳母が妻である信濃国の中原兼遠のもとに送り届けた。
この駒王丸こそが後の「旭将軍・木曾義仲」である。
中世には忍城主の庇護を受け、近世初頭には徳川家康によって再興されたが、1670年の妻沼の大火で焼失した。
現存する聖天堂(本殿)は、18世紀半ばにかけて再建されたものである。
妻沼聖天ー楼門



大師堂-関東八十八箇所第88番結願所。仁王門ー1658年創立、明治24年台風により倒壊し、明治27年に再建された。中門ー護摩堂・齋藤別当実盛の像、
ー貴惣門ー参道の1つ目の門。
文化財ー聖天堂(国宝)・ 御正体錫杖頭、貴惣門(重要文化財)・ 紵絲斗帳、鰐口(埼玉県指定有形文化財)など。
妻沼聖天 本堂 舞殿



2003年から2011年まで本殿の修復工事が行われ、平成22年1(2010年)1月18日に本体工事の竣功式を、平成23年(2011年)6月に竣功奉告法会を執行、同月から一般公開が始まっていると云う。平成24年に聖天堂(本殿)は国宝に指定。
妻沼聖天本堂前の銅灯籠 回廊

妻沼聖天本堂全景

「埼玉の日光」と云われている。
聖天堂(本殿) - 拝殿・中殿(相の間)・奥殿からなる廟型式権現造(日光東照宮などに見られる、複数棟を一体とした建築形式)の建物。
大工棟梁は幕府作事方棟梁の「平内政信」の子孫の妻沼の名工「林兵庫正清」で、子の正信の代まで1735年、から1760年にかけて
20数年をかけて再建された。
奥殿は内外ともに彫刻、漆塗、彩色、金具等をもって華麗に装飾する装飾性の高い建築で、奥殿向拝南面羽目板の「鷲と猿」の彫刻は伝説的な彫刻職人の左甚五郎作とする伝承がある。
実際の彫刻棟梁は「石原吟八郎」(吟八)と「関口文治郎」と云う。
また、「司馬温公の瓶割り」などの彫刻があり、拝殿正面唐破風下の彫刻は「琴棋書画」。国宝に指定
弘法大師堂 神木 境内参道



次回は、埼玉県深谷市方面に。
太田市と云えば、やはり第二次世界大戦終結まで軍需工業都市として(旧中島飛行機)・戦後冨士重工自動車製造を核とし、県最大工業都市。
古墳では、「天神山古墳」は、東日本最大前方後円墳で、長さ210m、5世紀中期の築造と云う、中世の新田氏の遺跡・金山城跡など、文化財に
恵まれている。
「大光院」-金山町の新田寺院号・浄土宗・山号ー義重山・開山ー然誉呑竜
徳川家康が、始祖とする「新田義重」を祀っている。
1613年建立。呑竜は貧民の子供を弟子の名目で養育したことから「子育て呑竜」と云われている。
太田市「大光院」

「源 義重・新田 義重・上西入道」 1114(1135)-1202年 平安時代末期から鎌倉時代初期の河内源氏の武将。
源義国の長男。新田氏の祖。
武家の棟梁として名を馳せた八幡太郎義家の孫。異母弟に足利氏の始祖源義康がいる。
新田氏本宗家(上野源氏)の初代であり、上野国新田荘を本拠としたため新田義重と称している。
大光院本殿

1613年、徳川家康によって一族の繁栄と始祖新田義重を追善供養するために開かれた浄土宗の寺で、開山には芝増上寺の観智国師の門弟で四哲の一人といわれた「呑龍上人」が迎えている。
上人は、1556年、武蔵国埼玉郡一の割村(埼玉県春日部市)に生まれ、1623年、大光院で入寂した名僧。
大光院に入山した上人は、看経・講義・説法などに力を尽くしたため、上人の徳を慕う学僧が大光院には多数集まり、周辺農民も上人の教えを受け入れたので、寺運は栄え、一方では、乱世後の人心は乱れ、天災等の影響で生活は困難を極めていたため、捨て子や間引きなどの非道が横行していたと云う。
上人は、その非道を憂い、捨て子や貧しい人々の子供を弟子という名目で寺に受け入れ、寺の費用で養育。
このため、「子育て呑龍」と呼ばれ、今に篤い信仰を集めてゐると云う。
大光院 本殿

徳川幕府より寺領300石の御朱印を拝領、浄土宗関東十八檀林の一つとして浄土宗の関東における学問所となっていたと云う。
大光院 東上州三十三観音特別札所、武州太田七福神の弁財天。

大光院宮殿 安産、育児の願かけに女性の参拝が多い 鐘楼



菊人形の歴史は、以外に新しい。1910年、明治43年に、京阪本線の天満橋駅 - 五条駅(現・清水五条駅)間の開業記念事業として東京両国国技館で開催されていた菊人形に着目。
名古屋の黄花園主と契約、大阪府北河内郡友呂岐村(現在の寝屋川市)にあった「香里遊園地」で第1回菊人形を開催、京阪電車で往復乗車の観客には入場無料・関係先に招待券を配布するなどの積極策をとり成功を収めた。
大光院菊花展



1911年も内容を充実して菊人形展が開催されたが前年以下の成績で、香里園遊園地の土地も住宅地として売却されてしまった。
香里園遊園地の代替として枚方駅(現在の枚方公園駅)の側に約1万平方メートルの土地を購入し、岐阜菊楽園の浅野善吉を中心とする菊師らによって
1912年第3回菊人形が開催。
以後1918年、大正7年まで順調に続けられたが、金銭トラブル(電車の乗客数に対してのバックマージンの金額で折り合いが付かなかった)で岐阜菊楽園が請負を辞退。
大光院菊花展



宇治で菊人形展開催を熱望していた料亭の主人「別所吉松」との話し合いの結果、1919年、宇治橋と国鉄宇治駅の間に新たな菊人形館を建てて開催。
枚方時代より優れた菊人形が名人によって製作され、水戸・高松の芸妓の余興を見せたのに好評では有ったが毎年欠損を出し、
1922年の菊人形展終了後に火災で菊人形館が焼失、宇治での開催は不可能に。
そこに南海鉄道の後援で堺大浜で菊人形を興業していた東京相撲協会年寄、春日野・中田の両名から枚方に移したいとの申し入れが有り、大浜の菊人形館を枚方に移築して1923年、菊人形展が枚方に戻って来た。
1924年、本館・余興館・ボート池・滑り台・ブランコなどが整備され、翌年には、枚方遊園は実質京阪電気鉄道の経営となった。
これが「ひらかたパーク」の起源と云う。
大光院菊花展


「新田金山」
県太田市金山町にある標高239mの独立峰である。山頂には「新田神社」や「金山城(国の史跡)」があり、南側下に太田市街地、

以前にも掲載している「金山城跡」
太田駅北約3km金山山頂にある山城ー室町~戦国期。
1584年北条氏の手に渡っている。小田原合戦後廃城に。本丸跡に「新田神社」が明治8年創建された。
戦国時代の山城「金山城」

室町時代以前、1336年に「佐野義綱」が新田庄の新田城を攻め落としたという記録がある。
新田城が新田義貞によって金山に建築されていたのではという説があるが、最近行われている発掘調査ではその時代の遺構や遺物は検出されない。
ただし城郭遺構の保護との兼ね合いのために万全な調査ができていないという一面もあると云う。
金山城碑 城内路



1469年、 新田一族であった「岩松家純」によって築城される。
1528年、「由良成繁・国繁親子」、1584年には、北条氏と主は変わったっている。
上杉謙信の攻撃を退けるなど、関東七名城の一つとされ、1590年、 豊臣秀吉の小田原征伐の際攻撃を受けて落城、こののち廃城となった。
大事な井戸跡 馬小屋

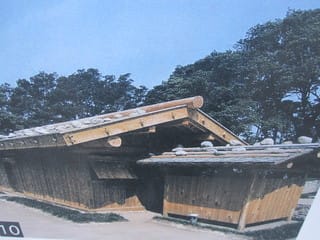
主の城主ー岩松氏・後北条氏高山定重・宇津木氏久。
1934年(昭和9年)「金山城跡」として国の史跡に指定され,現在は、いくつかの遺構をもとに、公園として整備されている。
2006年、日本100名城(17番)に選定。2009年、史跡金山城跡ガイダンス施設・太田市金山地域交流センターが開館している。
石垣・土塁・濠・馬出し・井戸・新田神社、、など。


群馬県利根川「刀木橋」を通り、ここは、埼玉県熊谷市妻沼町(女医1号「荻野吟子」生誕地)
埼玉県熊谷市ー「妻沼聖天山・歓喜院」ー高野山真言宗の仏教寺院・関東八十八箇所第88番結願所。
日本三大聖天の一つとされ、「妻沼聖天山」と 称することが多い。
本尊ー歓喜天御正体錫杖頭(重要文化財)

1179年に、長井庄(熊谷市妻沼)を本拠とした武将「齋藤別当実盛」が、守り本尊の大聖歓喜天(聖天)を祀る聖天宮を建立し、
長井庄の総鎮守としたのが始まりとされている。
1197年、良応僧都(斎藤別当実盛の次男である実長)が聖天宮の別当寺院(本坊)として歓喜院長楽寺を建立し、十一面観音を本尊としたという。
妻沼聖天ー歓喜院(菊花展)

「斎藤 実盛」-平安時代末期の武将。藤原利仁の流れを汲む斎藤則盛(また斎藤実直とも)の子。
越前国の出で、武蔵国幡羅郡長井庄(埼玉県熊谷市)を本拠とし、長井別当と呼ばれた。
武蔵国は、相模国を本拠とする「源義朝」と、上野国に進出してきたその弟・「義賢」という両勢力の緩衝地帯であった。
実盛は始め義朝に従っていたが、やがて地政学的な判断から義賢の幕下に伺候するようになる。
こうした武蔵衆の動きを危険視した義朝の子・「源義平」は、1155年、に義賢を急襲してこれを討ち取ってしまうー(大蔵合戦)。
斉藤実盛は、再び義朝・義平父子の麾下に戻るが、一方で義賢に対する旧恩も忘れておらず、義賢の遺児・駒王丸を畠山重能から預かり、駒王丸の乳母が妻である信濃国の中原兼遠のもとに送り届けた。
この駒王丸こそが後の「旭将軍・木曾義仲」である。
中世には忍城主の庇護を受け、近世初頭には徳川家康によって再興されたが、1670年の妻沼の大火で焼失した。
現存する聖天堂(本殿)は、18世紀半ばにかけて再建されたものである。
妻沼聖天ー楼門



大師堂-関東八十八箇所第88番結願所。仁王門ー1658年創立、明治24年台風により倒壊し、明治27年に再建された。中門ー護摩堂・齋藤別当実盛の像、
ー貴惣門ー参道の1つ目の門。
文化財ー聖天堂(国宝)・ 御正体錫杖頭、貴惣門(重要文化財)・ 紵絲斗帳、鰐口(埼玉県指定有形文化財)など。
妻沼聖天 本堂 舞殿



2003年から2011年まで本殿の修復工事が行われ、平成22年1(2010年)1月18日に本体工事の竣功式を、平成23年(2011年)6月に竣功奉告法会を執行、同月から一般公開が始まっていると云う。平成24年に聖天堂(本殿)は国宝に指定。
妻沼聖天本堂前の銅灯籠 回廊

妻沼聖天本堂全景

「埼玉の日光」と云われている。
聖天堂(本殿) - 拝殿・中殿(相の間)・奥殿からなる廟型式権現造(日光東照宮などに見られる、複数棟を一体とした建築形式)の建物。
大工棟梁は幕府作事方棟梁の「平内政信」の子孫の妻沼の名工「林兵庫正清」で、子の正信の代まで1735年、から1760年にかけて
20数年をかけて再建された。
奥殿は内外ともに彫刻、漆塗、彩色、金具等をもって華麗に装飾する装飾性の高い建築で、奥殿向拝南面羽目板の「鷲と猿」の彫刻は伝説的な彫刻職人の左甚五郎作とする伝承がある。
実際の彫刻棟梁は「石原吟八郎」(吟八)と「関口文治郎」と云う。
また、「司馬温公の瓶割り」などの彫刻があり、拝殿正面唐破風下の彫刻は「琴棋書画」。国宝に指定
弘法大師堂 神木 境内参道



次回は、埼玉県深谷市方面に。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます