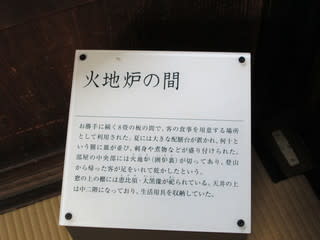角川庭園講座の3回目は「妙法寺」やくよけ祖師。この地に住んで30年にもなるが、初めて訪れた。江戸時代には浅草浅草寺と並び賑わったお寺とのこと。
今でも3のつく日に種々行事があり、縁日や商店街も賑わうそう。
今日は妙法寺集合なので地図を見ながら参加。地下鉄東高円寺駅から15分、この都心にこんな静かな地域があったかと思うほど、広い敷地に大きな建物など、
緑も深く、今はあじさいが満開で綺麗だった。杉並区堀の内にある日蓮宗本山。
仁王門

元々は真言宗の尼寺であったが、1615年 - 1624年(元和年間)日逕上人は、母・日圓法尼の菩提のため日蓮宗に改宗した。
山号は日圓法尼に因み日圓山とし寺号を妙法寺とした。初めは碑文谷法華寺の末寺となったが、1698年(元禄11年)碑文谷法華寺は不受不施派の寺院として
江戸幕府の弾圧を受け、改宗を余儀なされ、身延久遠寺の末寺となった。このころ碑文谷法華寺にあった祖師像を譲り受ける。
日蓮の祖師像が厄除けに利益があるということで、江戸時代より多くの人々から信仰を集めている。現在でも厄除けなどの利益を求め、多くの人が参拝に訪れている。
古典落語「堀之内」の題材にもなるなど、街の顔にもなっている。
1926年(大正15年)妙法寺貫首により、東京立正短期大学・東京立正中学校・高等学校を設立している。

「祖師堂」
日蓮聖人の「祖師御尊像」つまり「やくよけ祖師像」が奉安されている、妙法寺では一番大きなお堂。天井や壁が金箔で覆われた堂内は豪華絢爛。

鐘楼


「天明の水」
祖師堂の西前にある手水舎は、天明2(1785)年、第十七世日研上人の時、渇水のために掘った井戸で、妙法寺の水屋といわれる。
この井戸は、天明の当時から未だに涸れることなく清水をたたえています。
「有吉佐和子の碑」
「複合汚染」「恍惚の人」などのベストセラーで知られる作家の有吉佐和子さんは妙法寺のすぐ近くに住んでいた。境内を通って帰宅されることが多かったらしい。
キリスト教の信者だったが、妙法寺をこよなく愛されていたので、周囲の方のお勧めで「有吉佐和子の碑」が境内に作られた。
杉村春子、山田五十鈴の名が石碑に刻まれていた。
天名の水 有吉佐和子の碑


祖師堂の屋根に金色の魔除けの像


鉄門の上

「鉄 門」
明治11年(1878)英国人コンドル博士設計による貴重な和洋折衷様式の門。鹿鳴館・上野博物館・ニコライ堂などを手掛けたコンドル氏に依頼したのは、時の住職。
当時は、斬新なデザインだった鉄門なので、ものめずらしさに来寺する人も多かったとか。日本寺院の門としては特殊なめずらしい存在。

門前はあじさいが見事


今でも3のつく日に種々行事があり、縁日や商店街も賑わうそう。
今日は妙法寺集合なので地図を見ながら参加。地下鉄東高円寺駅から15分、この都心にこんな静かな地域があったかと思うほど、広い敷地に大きな建物など、
緑も深く、今はあじさいが満開で綺麗だった。杉並区堀の内にある日蓮宗本山。
仁王門

元々は真言宗の尼寺であったが、1615年 - 1624年(元和年間)日逕上人は、母・日圓法尼の菩提のため日蓮宗に改宗した。
山号は日圓法尼に因み日圓山とし寺号を妙法寺とした。初めは碑文谷法華寺の末寺となったが、1698年(元禄11年)碑文谷法華寺は不受不施派の寺院として
江戸幕府の弾圧を受け、改宗を余儀なされ、身延久遠寺の末寺となった。このころ碑文谷法華寺にあった祖師像を譲り受ける。
日蓮の祖師像が厄除けに利益があるということで、江戸時代より多くの人々から信仰を集めている。現在でも厄除けなどの利益を求め、多くの人が参拝に訪れている。
古典落語「堀之内」の題材にもなるなど、街の顔にもなっている。
1926年(大正15年)妙法寺貫首により、東京立正短期大学・東京立正中学校・高等学校を設立している。

「祖師堂」
日蓮聖人の「祖師御尊像」つまり「やくよけ祖師像」が奉安されている、妙法寺では一番大きなお堂。天井や壁が金箔で覆われた堂内は豪華絢爛。

鐘楼


「天明の水」
祖師堂の西前にある手水舎は、天明2(1785)年、第十七世日研上人の時、渇水のために掘った井戸で、妙法寺の水屋といわれる。
この井戸は、天明の当時から未だに涸れることなく清水をたたえています。
「有吉佐和子の碑」
「複合汚染」「恍惚の人」などのベストセラーで知られる作家の有吉佐和子さんは妙法寺のすぐ近くに住んでいた。境内を通って帰宅されることが多かったらしい。
キリスト教の信者だったが、妙法寺をこよなく愛されていたので、周囲の方のお勧めで「有吉佐和子の碑」が境内に作られた。
杉村春子、山田五十鈴の名が石碑に刻まれていた。
天名の水 有吉佐和子の碑


祖師堂の屋根に金色の魔除けの像


鉄門の上

「鉄 門」
明治11年(1878)英国人コンドル博士設計による貴重な和洋折衷様式の門。鹿鳴館・上野博物館・ニコライ堂などを手掛けたコンドル氏に依頼したのは、時の住職。
当時は、斬新なデザインだった鉄門なので、ものめずらしさに来寺する人も多かったとか。日本寺院の門としては特殊なめずらしい存在。

門前はあじさいが見事