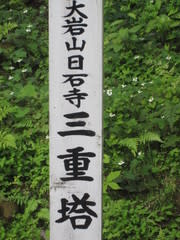富山市から高岡市に入る。市は、県北西部に位置し、富山湾に臨む、海と山の街、加賀藩二代目藩主「前田利長」が高岡城築城した。
利長は、詩経の鳳凰鳴矣千波高岡から二文字を取ったという。城下町として栄え、いろいろの職人を集めている。
三代藩主前田利常は、高岡の衰退を防ぐため、転出を禁止し、商業を保護政策をしている。
庄川・小矢部川の水運にも支えられ商業都市として発展して来ている。
高岡の5月「御車山祭」は、民俗文化財指定になっている。利長が城下に御所車を与えたと云われている。8月に夏祭り「七夕祭り」も知られている。
「高岡古城公園」は、1609年、加賀藩2代藩主前田利長が開いた高岡城は、大阪夏の陣の後廃城となる。
美しい水濠や土塁は残されて、約21万㎡の広大な城跡公園となり、四季それぞれに鮮やかな自然美を見せてくれる。
公園内には、工芸都市高岡ならではの"芸術の森"や博物館、自然資料館、動物園、市民会館、図書館、市民体育館、射水神社などがあり、豊かな自然とともに、
心なごむ憩いの場として人々に愛されている。
高岡城公園 城跡から見た市内 公園内の池



築城後6年にして廃城となった高岡城の跡、廃城に際しては、建築物は一切取り壊されたが石垣、土塁、濠など残されていた。
芝一面の公園内 緑一杯の池の周り


「前田利長」 1562-1614 二代目金沢藩主 関ヶ原の戦いの功により加賀、能登、越中国を拝領した。お家安泰の為、母を人質に。
古城の古井戸跡 広い園内の小道



一国一城令により、大坂夏の陣からの利常凱旋を待って高岡城は廃城、越中国の令制国としての城機能は火災から再建された富山城に移ったとされる。
廃城時期については1638年とする異説もある。廃城後も高岡町奉行所の管理下で、加賀藩の米蔵・塩蔵・火薬蔵・番所などが置かれ、軍事拠点としての機能は
密かに維持された。加賀藩の越中における東の拠点であった魚津城も同様。
街道の付け替えの際には、濠塁がそのまま残る城址を街道から見透かされるのを避けるため町屋を移転して目隠しにしたといわれる。
廃城後に利長の菩提を弔うために建立された瑞龍寺や周囲に堀を備える利長の墓所自体も高岡城の南方の防御拠点としての機能を併せ持つものとして配置
されたと考えられている。江戸時代の古図の中には城址を「古御城」の名称で記しているものがある。
城内におかれた米蔵等は1821年の高岡大火の際にほぼ全焼したが、その後再建され明治に射水郡議事堂が建設されるまであったという。
城主の前田利長公像



古城公園から北西5kmの場所にある二上山に二上神が降臨したのは遥か古代で詳しい時代は定かではない。
675年正月奉幣を預かったとの伝承を持って鎮座の年とされている。
慶雲3年初めて新年奉幣の例に入り、宝亀11年従五位下の神階に叙せられ、延喜の神名帳には越中唯一の名神大社に挙げられている。
射水神社は、戦国時代に兵火に罹り荒廃したが、前田利家・利長の保護により再興した。明治4年の国幣中社に列せられた。
明治維新後の神仏分離により、寺坊所管の二上を離れ明治8年9月に高岡古城公園(本丸跡)に遷座した。
射水神社入口 境内



越中国最高位の神社として朝野の崇敬を受けて、「日本文徳天皇実録」854年は、二上神の祢宜と祝が把笏に預かったことが記載されている。
「日本の神々 -神社と聖地- 8 北陸」古代に笏を把ることを許されたのは伊勢神宮と諸大社の神職のみであったと有る。
8世紀後半に成立したと言われる「万葉集 巻17」には、大伴家持によって当神社を詠んだ和歌が収録されている。
神殿内 拝殿


「高岡大仏」は、1745年 富山極楽寺(坂下町)の第15世住持等誉上人の発願により、坂下町の坂道を上りつめたところ、定塚町に建立された
木造金色の大仏が高岡大仏の起こりと云う。
現在のものは再び焼けることのない鋳銅仏にしたいとの願いから、広く各地に勧進して30年の努力の末昭和8年に完成。
原型、鋳造とも高岡工人の手によるもので、「銅器の町 高岡」の象徴であるとともに、総高18.85m、重量65tというスケールの大きさは奈良、
鎌倉の大仏とともに日本3大仏の一つに数えられている。
高岡大仏境内 大仏


「高岡城遺跡発掘調査」は、古城公園の発掘調査で、細かい石を敷き詰めた 栗石層が「貫土橋」現在の朝陽橋、周辺で見つかった。
江戸時代初期の文献や絵図でしか残っていない貫土橋の存在を裏付ける遺構の可能性が出てきた。
市教委は専門家の意見を聞いて分析を進めている。現在の朝陽橋は高岡城築城当時は存在せず、貫土橋と呼ばれる可動式の橋があったとさ れる。
栗石層は石垣を沈下させないことを目的に設置される。
貫土橋については、専門家が江戸時代の絵図をもとに、橋周辺に石垣が築かれていた可能性を指摘。市教委は橋の構造の解明と併せて、石垣の有無も調べられている。
高岡城跡の発掘調査は、国史跡を目指して昨年度から行われ期待されている。
高岡城内発掘調査現場 慰霊碑



「瑞龍寺」は、関本町にある、曹洞宗の寺で、山号高岡山、本尊釈迦如来、加賀藩主三代前田利常が、高岡城を築城した先代利長を弔う為に
造営した。
重要文化財の総門、山門、仏殿、法堂が直線上に配され、回廊がとりまく「一城同様」として有事には、城郭とする意図があったとも言われている。
仏殿の屋根は、鉛瓦で葺かれている。弾丸にして概算250万発に相当するという。山門から、八町道を挟んで前田利長墓所と相対している。
国宝( 仏殿、 法堂、 山門)
重要文化財( 総門、 禅堂(僧堂)、 大茶堂、 高廊下、 北回廊、 南東回廊、 南西回廊、 紙本墨書後陽成院宸翰御消息)
富山県指定有形文化財 (木造烏蒭沙魔明王立像、 紙本墨書近衛信尋筆懐紙、 前田家寄進の宝物)
富山県指定史跡( 石廟)
この他、絵画や墨蹟などの文化財を多数。拝観料 有料。
国宝高岡山瑞龍寺 総門 屋根瓦(実物)



利長公の菩提を弔う為三代藩主利常は、義弟になりその恩を感じ、時の名匠 山本善右ヱ門嘉広をして七堂伽藍を完備し、広山禅師を持って開山した。
造営は、利長公の50回忌の20年間1663年までを要したと云う。当時の寺域は、36000坪、で濠をめぐらし、まさに城の姿をしていた。
山門 左に東司 七間浄頭


総門、正面三間、薬医門で正保年間の物。石廊には、織田信忠の分骨廊、塔がまつられている。禅堂、座禅修業であった。
国宝山門左右に金剛力士像 仏殿前の境内



山門には、金剛力士像安置、楼上に釈迦如来、十六羅漢を祀られている。国宝の法堂は、建坪186坪の大建築物、総檜造りで利長公の位牌が安置されている。
中央の二室の格天井には、狩野安信の四季の百花草が描かれている、高岡の地名となった鳳凰が欄間に掛れている。
仏殿 奥に法堂 禅堂 向かいに茶道・大庫裏


大庫裏は、調理配膳や運営する堂で結露に配慮されていたという。大茶堂は、土蔵と同じ大壁で、内部を土天井の珍しい防火建築である。
仏殿 1659年建立(国宝) 観光客



仏殿は、1659年建立、建築山上氏が最も力を入れた建築物、屋根は鉛板で全国でも金沢城の石川門だけという。本尊は中国明代の釈迦・文殊
普賢の三尊を祀っている。
「前田利長の墓所」
1614年に没した前田利長の冥福を祈るため、3代藩主前田利常(利長の異母弟、後に養嗣子)が33回忌にあたる1646年に造営したもの。
周囲に堀を構えたその墓所の豪壮なことは武将のものとして全国的に珍しい。
江戸時代の古図には外郭は輪郭型に内郭を取り囲んで、南面を除く三面に堀を備えた姿で描かれており、有事の際には二重に堀を構えた高岡城防衛の砦
としての使用も考慮されていた。
現在、約10,000m2が残っているが、2007年に行われた調査の結果、造営当初の墓所の面積は、前田家の古文書のひとつにある1万坪という記述とも合致する
約33,000m2であることが確認された。これは現存の3倍以上の規模であり、戦国武将の墓としては国内最大級になる。
瑞龍寺から前田家墓所の参道 墓所前の鳥居



「曹洞宗 仙寿山 繁久寺」は、前田利長墓所の廟守の寺として造営されたお寺。回廊に安置された五百羅漢で知られている。
墓所管理している繁久寺 山門



次回は、能登七尾へ。