どのよう道を歩んでいる人も必ず悩みがあります。人に接すれば人間関係で悩み、仕事では、上手く行く行かないで悩み、夫婦では顔を合わせれば、何故か罵り合い悩みが尽きない方もおられるでしょうし、お金持ちも、貧乏人にも悩みがあります。
坐道とは、欲を捨て去り、内なる神を覚する道であるため、悩みは少なくなってきます。それでも、山中で孤独に生活しているのであればともかく、働き、人と交われば、誤解や中傷もあり、悩みの種は尽きません。
真に達観する者は生死の見がないと言います。つまり、生死に心を奪われないのです。
武士道とは死ぬこととを見つけたり。昔の日本人の侍は、不始末を犯したら自分で自分の腹を切りました。当時は鎖国しておりましたが一部許されいたオランダ人等はこの風習を見て、驚き、尊敬されたようです。なんせ、自分の罪は自分でつぐなうのですから。
昔の武士はいつも武士らしく腹を切る覚悟をしていました。その覚悟がある武士こそが士道を歩んだのです。
士道は卑怯を嫌い、いつでも死ねる覚悟です。言わば常に死人(しびと)です。死人に基本、痛みや恐怖はありません。これこそが常に死を覚悟する達観です。この達観を得るために禅寺で坐禅をする武士も多かったでしょう。
「真に達観する者は、生死の見が無く、本来生死がなければ、どうして苦楽があろうか、本来苦楽がなければ、どうして、好き嫌いがあろうか。故に好き嫌いの心を滅ぼすには、必ず先ず、生死の見を除かなければならない。」
人は悩み苦しみます。しかし、死ぬ気になれば、障害を排除して、新たなる道が開眼するのです。
溺れる者は藁を掴もうとするから溺れるのです。溺れたら自然に任せ、沈めば良いのです。沈めば後は浮き上がるのが天地の法則です。
士道は達観であり、常に「大死一番」なのです。
 にほんブログ村
にほんブログ村

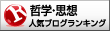
哲学・思想 ブログランキングへ
上記三カ所クリックをお願いします。
坐道とは、欲を捨て去り、内なる神を覚する道であるため、悩みは少なくなってきます。それでも、山中で孤独に生活しているのであればともかく、働き、人と交われば、誤解や中傷もあり、悩みの種は尽きません。
真に達観する者は生死の見がないと言います。つまり、生死に心を奪われないのです。
武士道とは死ぬこととを見つけたり。昔の日本人の侍は、不始末を犯したら自分で自分の腹を切りました。当時は鎖国しておりましたが一部許されいたオランダ人等はこの風習を見て、驚き、尊敬されたようです。なんせ、自分の罪は自分でつぐなうのですから。
昔の武士はいつも武士らしく腹を切る覚悟をしていました。その覚悟がある武士こそが士道を歩んだのです。
士道は卑怯を嫌い、いつでも死ねる覚悟です。言わば常に死人(しびと)です。死人に基本、痛みや恐怖はありません。これこそが常に死を覚悟する達観です。この達観を得るために禅寺で坐禅をする武士も多かったでしょう。
「真に達観する者は、生死の見が無く、本来生死がなければ、どうして苦楽があろうか、本来苦楽がなければ、どうして、好き嫌いがあろうか。故に好き嫌いの心を滅ぼすには、必ず先ず、生死の見を除かなければならない。」
人は悩み苦しみます。しかし、死ぬ気になれば、障害を排除して、新たなる道が開眼するのです。
溺れる者は藁を掴もうとするから溺れるのです。溺れたら自然に任せ、沈めば良いのです。沈めば後は浮き上がるのが天地の法則です。
士道は達観であり、常に「大死一番」なのです。

哲学・思想 ブログランキングへ
上記三カ所クリックをお願いします。
















