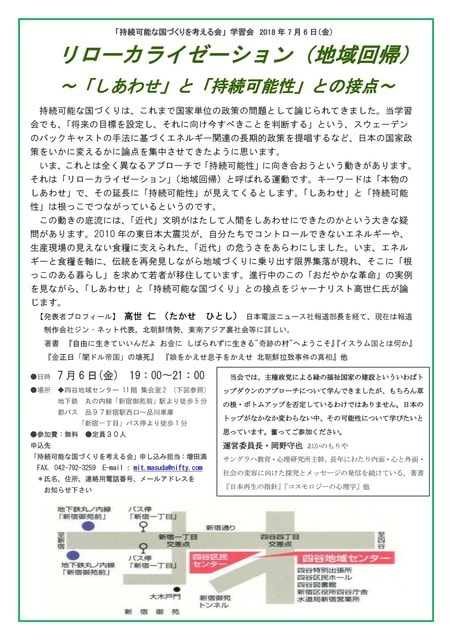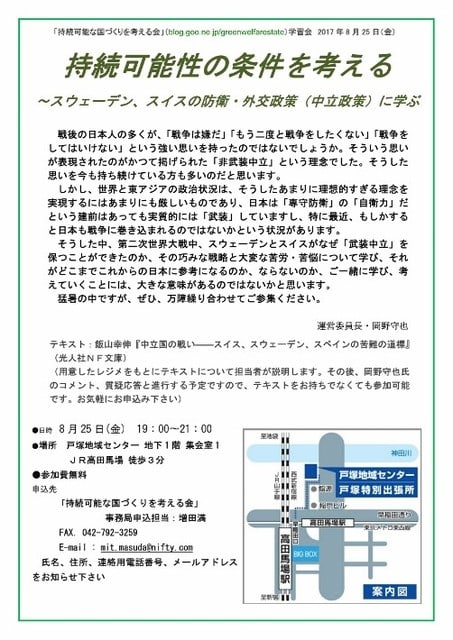年頭、安倍首相が「今年は憲法についての議論を加速化させたい」といった趣旨の発言をしていました。
憲法について議論することそのものは、特定の状況では必要だと思いますが、現政権の目指している方向と私(たち)の望んでいる方向は、残念ながらはっきり違っています。
何人ものポジティブシンキングの著者たちが口をそろえて言っているのは、まず何を実現したいと望んでいるのかはっきりしたイメージを描くこと、そしてかならず実現すると信じることです。
そこで、年頭のポジティブシンキングとして、私(たち)が何を実現したいと思っているのかを、繰り返し書いてきたことですが、もう一度改めてはっきりさせておくことにしました。
「憲法」とは目指すべき国のかたち・国家理想を表現したものだと考えますが、聖徳太子「十七条憲法」こそ、604年に発布された日本の最初の憲法です。そもそも「憲法」という言葉自体、「十七条憲法」に由来するものです。良かれ悪しかれ、これは日本という国の出発点・原点です。
……と書き始めて、ちょっと自己弁明しておきたくなりました。善意の誤解も含めて、これまであまりにもしばしば誤解されてきたからです。
私は右でも左でもありません。右の妥当な面と左の妥当な面を統合したいと思っているのです。聖徳太子以来の伝統(のプラスの面)を重んじるという意味ではいわゆる右・保守以上に右・保守だと思いますし、平等社会への根本的変革を目指しているという意味では左・革新以上に左・革新だと思っています。
戻ると、十七条憲法の第一条にはこうあります。
一に曰く、和をもって貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)とせよ。人みな黨(とう)あり。また達(さと)れる者少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず。また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ、下(しも)睦(むつ)びて、論(あげつら)うに諧(かな)うときは、事理(じり)おのずから通ず。何事か成らざらん。
第一条 平和をもっとも大切にし、抗争しないことを規範とせよ。人間にはみな無明から出る党派心というものがあり、また覚っている者は少ない。そのために、リーダーや親に従わず、近隣同士で争いを起こすことになってしまうのだ。だが、上も下も和らいで睦まじく、問題を話し合えるなら、自然に事実と真理が一致する。そうすれば、実現できないことは何もない。
ここには、日本という国がもっとも優先的に追求すべき国家理想は人間と人間との平和――そして人間と自然との調和――であることが高らかに謳われています。これは現代的に言い換えると「エコロジカルに持続可能な福祉国家」ということでしょう。
しかもそれだけでなく、争い・戦争というものは無明
*から出てくる自分たちさえよければいいという党派心(「黨(尚黒し)」の心から生まれるという深い人間洞察が、短い言葉のなかでみごとに表現されています。
無明がなくならないかぎり、戦争はなくならない、平和は実現しない、人間と自然との調和も実現しないのです。
しかし、たとえまだ無明を克服し覚ることのできていない人間であっても、心を開いて親しみの心をもって、事柄とコスモスの真理が一致するところまで徹底的に話し合うなら、たとえどんなに困難なことでも実現できないことはない、というのです。
近代的な民主主義のまったくない時代に、私利私欲ではなく理想を目指して徹底的に議論すること、話し合いによる政治を提唱し、「和の国日本」の建設という当時の状況からすればほとんど不可能に見える大国家プロジェクトをみんなで立ち上げよう、と太子は呼びかけています。
この理想、このプロジェクトは1400年を経てまだ実現への途上にあります。
この未完のプロジェクトを完成したい、というのが私(たち)の願望です。
そしてそれは、私個人だけでなく私たち日本人の立ち帰ることのできる原点、立ち帰るに値する原点、立ち帰らなければならない原点であり、向かうべき方向だ、と私は思うのです。
「十七条憲法」の第二条は、いわば仏教の国教化宣言です。
ここには、なぜ太子が仏教を国教とするのか、きわめて明快な理由が示されています。
人間の心は無明によって曲がってしまっている。そのために憎みあい、争いあい、自然の循環を乱してしまう。
しかし、本来どうすることもできないほどの悪人はいない。すべての人には「仏性(ぶっしょう)」が具わっている。
仏が存在し、その真理の教え、つまり縁起の理法、すべてはつながって1つだという教えがあり、それを体得した集団・僧伽があって、その真理を人々に教えるならば、人々は教化され真理に従うことができるようになる、というのです。
そうなれば、平和と調和に満ちた国日本を創出するというあまりにも理想的で一見不可能にさえ見えるプロジェクトの実現も不可能ではない、というのです。
二に曰く、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬え。三宝とは、仏(ぶつ)と法と僧となり。すなわち四生(ししょう)の終帰(よりどころ)、万国の極宗(おおむね)なり。いずれの世、いずれの人か、この法を貴ばざらん。人、甚だ悪しきものなし。よく教うるをもて従う。それ三宝に帰(よ)りまつらずば、何をもってか枉(まが)れるを直(ただ)さん。
第二条 まごころから三宝を敬え。三宝とは、仏と、その真理の教えと、それに従う人々=僧である。それは四種類すべての生き物の最後のよりどころであり、あらゆる国の究極の規範である。どんな時代、どんな人が、この真理を貴ばずにいられるだろう。人間には極悪のものはいない。よく教えれば〔真理に〕従うものである。もし三宝をよりどころにするのでなければ、他に何によって曲がった心や行ないを正すことができようか。
しかも、太子は、すべてはつながって1つ、縁起の理法は人間だけでなくすべての生き物のいのちの根拠でもあり、すべての国が到やがて目覚めるべき普遍的な真理であることをしっかりと認識しておられます。
「いずれの世、いずれの人か、この法を貴ばざらん」というのは、太子がただ仏教を頭から信じ込んでいたのではなく、それがあらゆる時代、あらゆる人に通用する普遍的真理であることをつかんでおられたことを示しています。
かつての原理主義的な左翼の先入見と異なり、太子は、自分は理解したり本気で信じたりしてもいないのに、「民衆の阿片」、つまり人々をだまして服従させるためのイデオロギー(虚偽意識)として、仏教を導入-利用したのではないようです。
自ら、深く理解して、その普遍性・妥当性に信頼を置かれたので、和の国日本を創るために、指導者から始まってすべての国民の心を涵養・浄化する有効な方法として導入されたのだ、と思われます。
だからこそ、仏教を排他的に採用することなく、仏教に不足している社会倫理的な教えの部分については儒教を併用し、従来の神道も十分に尊重しています。「神仏儒習合」という日本の心の基礎は、太子が作られたものだといっていいでしょう。
第一条と第二条を合わせて読むと、そこには「外面の変革と内面の変革を同時に」というきわめて妥当な変革の筋道が示されている、と私には読み取れるのですが、読者はどうお考えでしょうか。
外面だけでなく内面も、内面だけでなく外面も、というのが変わることのない私(たち)の目指すところ・実現したい願望であり、やがてかならずそれは実現すると信じています。
くわしくは、本ブログの記事全体や以下の拙著をご覧いただけると幸いです。
そして、共感・合意していただける方には、ぜひ能動的な参加もお願いしたいと思っています。