ミンス・パイ mince pie
クリスマスの時期、イギリス中で出回るおなじみのお菓子です。
10月にはいるとスーパーやコンビニ、パン屋さんで販売されはじめます。
11月に入るとティールームやカフェのメニューにあらわれます。お値段はピンからキリまで。
昔は名前のとおり、羊肉のミンチをスパイスであえたものがはいってたそうです。
今はもっぱら干したぶどう、りんご、オレンジ、レモンの皮等の果物を切り刻んで大量のお砂糖と少量のスパイスをまぜて・・・・
伝統的にはスゥィット suet(シュイットと聞こえる)でねっとりさせた具を厚いパイ皮 crusty pastry につめたものをミンス・パイとよんでいます。
甘酸っぱくてスパイスの苦味もあるし、日本の子供にはうけない味でしょう。
うちの12歳の息子は大好きで3つも4つも食べちゃいます。
スエットは、牛や羊の内臓のまわりの半透明の脂です。
私も実物を見たことはありません。
お尻の脂肪のことを言う場合もあります。
今は健康に気を使う人や、大勢いる菜食主義者(ベジタリアン)への心使いで、ほとんどの市販品は人口のベジタリアン・スエット vegetarian suet なるものを使っているということです。
それでも、うちは夫が菜食主義者なので表示には気をつけて買っています。
「伝統的な」本物の肉脂スエットを使った場合は表示の義務があるそうです。
先週行った、ウインチェスター大聖堂 Winchester Cathedral のティー・ルームで紅茶を飲んでミンス・パイを食べました。
紅茶はティーバッグ。だけどちゃんとティーポットででてきます。
二人で飲むのに適量でした。
カップとポットに有名な12世紀の蔵書、ウインチェスター・バイブル Winchester Bible に出てくる頭文字、Wと人物をモチーフにした、ウインチェスター大聖堂のロゴが焼き付けてありました。
気がきいてます。
パイの内部。
この写真は帰宅してから、スーパーで買ったパック入りのミンス・パイを包丁でていねいに切って撮りました。
手で割るとパイ皮が厚めでもろいのでばらばらになってしまいます。
↓↓↓画像を応援クリックしてくださいな。ありがとうございます

国立絵画館のある、ロンドンの中心地,トラファルガー・クエア Trafalgar Square は平日でしたが観光客でいっぱい。
大道芸人もいっぱい。
おなじみ楽器の演奏、ストリート/ダンス、チョークで描いた名画の模写( 国立絵画館の前でいい度胸です )もやってました。
注目を浴びていたのが、ヒューマン・スタチュー human statue とかリヴィング・スタチューl iving statue といわれる、銅像、石像のふりをしてじーっとしてる芸。
国立絵画館前にずらっと並んで芸をきそっていました。
中でも白眉はこの人。

あんまり真にせまってるので、名物の鳩までだまされて腕にとまってました!
広場にあるどの銅像にもたいてい1羽は鳩がとまってます。
腕を下ろしたら鳩はどこかへとんで行っちゃいいました。「手なずけられた鳩疑惑」がこれで晴れました。
鳩が飛び立つ瞬間。

後ろの宙にうく黄金像に注目。

ヒューマン・スタチューはどこの観光地でもみられます。
宙に浮くワザは他で、見たことなかったです。
ここでは何人もやっていした。しかけは謎です。
芸人さんたちはもちろん見物料目当てでやってます。
通り道でかってにやってるんだから、ちょっと足をとめて見物するぐらいなら払わなくてもいいはずです。
ただし、写真をとったら確実に支払いの義務が生じるといっていいでしょう。
まあ、常識というか心使いですよね。相場はよくわかりません。
私の連れは、ちょっと太っ腹、1ポンドあげたみたい。( 私の分も?)いっしょに記念撮影をしたらなおさら。
うまいと思ったらご祝儀。
子供連れなら子供にお金をもたせてご祝儀箱(帽子など)にいれさせるのもどうやら鉄則みたい。
私の地元、ストックポートの場合、ショッピング・センターで大道芸をやるのにはオーディションにうからなければなりません。
トラファルガー広場もそれに類したものがありそうです。かなり質がたかい。
応援クリックお願いします↓↓↓ どうもありがとう。

先週水曜日から3日間、イギリス南部の美しい古都、ウインチェスター Winchester に3泊しました。
とめてくれた日本人の友人といっしょに1日ロンドン見物をしました。
といっても、国立絵画館 National Gallery と、その裏のナショナル・ポートレイト・ギャラリー National Portrait Gallery に行っただけですが。
ウインチェスターは電車で一時間ぐらいのロンドンへの通勤圏です。。
遠くから泊りがけで来た私はおのぼりさん気分を満喫しました。
地下鉄をおりて地上に上がったら、国立絵画館がすぐ正面にあるトラファルガー広場 Trafalgar Squareです。
「絵のような」ロンドン風景に高揚しました。
上の写真は国立絵画館側から遠くに見えるビッグ・ベン Big Benです。
工事中のビルの足場がちょっと見苦しいですね。
トラファルガーの海戦を勝利に導いたネルソン提督の像(こっちにおしりをむけてます)と、モダン・アートの青いオンドリCock。

この、そもそも人物彫像をのせるために用意された4個ある台座のうちのひとつ、フォース・プリンス Fourth Plinth の上に展示されるアート作品は1年ごとにかわります。
社会的意味を持つ問題提起アートが多いようです。
この年の問題作、オンドリ!
ドイツ人のカサリン・フリッツ Katharine Fritsch という女性作家が、男性の象徴であるオンドリを創作したことにとても深長なフェミニズム的意義があるということなのです。
(この場では私が調べて理解した詳しい説明を書かないことにします。不穏当な表現が避けられません)
今日から3日間 ロンドン特集です。
↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。
また改めてご報告しますね。
あ~、ねむい。(チーズ&オニオン・パイ)


きのう、マンチェスターのピカディリー・ガーデンズでシャボン玉があがっていました。
ものすごく大きいのや、泡のように小さいのがぶくぶく無数に空にうかんだり、地面すれすれをはうようにとんでたり
人どおりもそれほど多くない平日、注目をあつめていました。
3人の若い男の人たちがシャボン玉パフォーマンスやってました。

一人は先に輪を付けた棒で、もう一人は長いひものついた2本の棒で、豪快にシャボン玉をとばしていました。
あとの一人はお手伝い。ひもの輪に顔つっこんで静かに静かにく吹いてました。
輪をゆらすと、シャボン玉が切れちゃうんですね。
もうこれ以上大きくならないというところまで膨らんでから、そおっとゆらすと巨大な玉になったシャボン玉がすっとはなれます。
絶妙のチームワーク。

輪がいくつもつながってるひもからは一度にたくさんのシャボン玉。


で、あの青年たちはどういった素性の人たちなんでしょうか。
大道芸のように見物料を徴収するわけでなし、気持ちよく晴れた晩秋の朝、周りの人たちを楽しませ自分たちも楽しんだようです。


左上から サクランボ、海老、入れ歯、目玉焼き、かめ、脳みそ、わに、スイカの切れ、「ジェリー・ベイビー」、イチゴ、牛乳ビン、コーラのビンいり、ミーアキャット(2個)、ピンクの豚の顔、ピンクのきのこ、白ネズミ、多色使いネズミ?、でんでんむし。
白いネズミは「ホワイト・チョコレート」ですが、ほかはすべて日本でいう「グミ」タイプの駄菓子です。
レトロなお菓子を売る、Mr Simm's Olde Sweet Shoppe (つづりがわざと昔風なのにご注目)

ストックポートのマーケット広場 Market Square から急な石だたみの坂を降りた角、アンダーバンク Underbank のはじまりにあります。
ノスタルジーをうりものにして、ほんの数年前にこの場所にオープンしたチェーン店です。手広く全国展開しています。
ストックポートのような古い町並みの残る町でこのごろよくみかけます。
内装も品揃えも凝っています。
手作り風のトフィー、ショートブレッド、チョコレートなどなどがきれいな古風なパッケージで、木の棚に並んで売られてるのが目をひきます。
小さなカウンターの後ろの壁を覆いつくす、瓶に入ったお菓子が目を楽しませてくれます。
量り売りです。
全部違う種類。



硬いアメは、英語で ボイルド・スイート boild sweet といいます。
日本でもおなじみの 「グミ」はガム gum あるいはガミィ gummy といいます。駄菓子の多くは、これ。
ハイチューのような、かむとねっとりタイプは、チューイー chewee。すっぱい粉のはいったのは、シャーベット sherbet。
(氷菓子のデザート、日本語のシャーベットは ソルべ sorbetといいます)。
金太郎アメみたいに、どこを切っても同じ字(観光地の名前など)や絵柄のでる長い棒アメは、ロック rock。
キャラメル、トフィー toffy、甘い、丸めた求肥のようなボンボンス bonbons。
棒つきのお菓子はすべて、ロリポップ lollipop。まだまだありそうです。
特筆すべきは、リコリス licorice タイプ。日本ではカンゾウ(甘草)というそうですが、甘くないです!
この 不気味な どす黒い、日本人にはなじみのない嗜好品に関しては 後日あらためて書くつもりです。
天井までぎっしり、形の違うリコリス・・・イギリスでは人気があります。

先月の、郵便局の駄菓子売り場の記事、3本が好評でした。リンクを下に貼りましたので、ちょっと見てみてくださいな。
イギリスの駄菓子その1
http://blog.goo.ne.jp/stockport/e/512243d8c895b9c76e7c3300bf794ef2
イギリスの駄菓子その2
http://blog.goo.ne.jp/stockport/e/efb7f75eb3fba60dd258c2a6c50d341d
イギリス、驚きの駄菓子 その3
http://blog.goo.ne.jp/stockport/e/3cd0011be225cbb7bab9adc60a3537dd
ここでも駄菓子をひとつずつ買うことに。
昔風なガラスのカウンターの下の仕切のついた木の引き出しにきっちり詰まっています。
ガラスに光が反射して写真がとれなかったので持って帰って食卓の上にセッティング。一番上の写真です。
店員さんは、嫌がらずに一つ一つピンセットでつまんで袋にいれてくれました。
「写真撮るならこれもどう?スイカ!」と協力的でした。お値段は、ニュースエージェントの倍近く!
場所や雰囲気を考えれば納得できないこともない・・・ぼったくりです!
ケースにはまだまだここにお見せする3倍もありました!
いったい何でしょう??
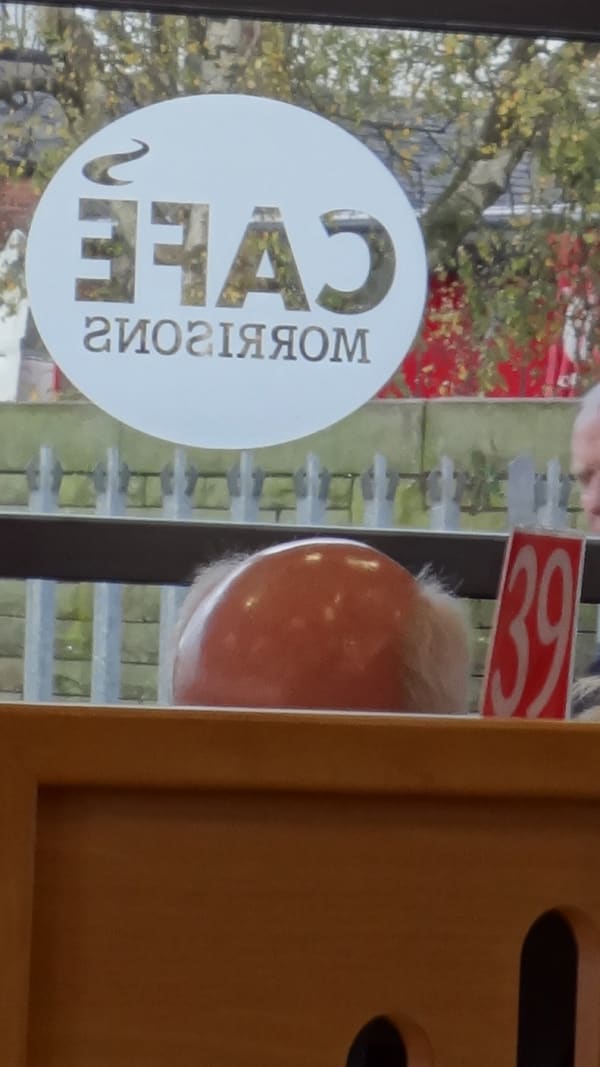
素晴らしく光るはげ頭。

弓がたのシヴィック・センター Civic Centre の左端は、1階がボルトン中央図書館、Bolton Central library。
2階が博物館 Bolton Museum と美術館 Bolton Gallery、地階が水族館 Bolton Aquarium です。
ギリシャ神殿風の入り口。

こぢんまりした博物館は郷土史、自然史(展示替えのため閉鎖中)と古代エジプト遺物、の3部にわかれています。1時間でみてまわれるこぢんまりした規模です。
郷土史の部屋で、小学校の校外学習にまざってボルトンの綿織物産業についての ためになるお話がきけました。
美術館はかなり混沌としたコレクションで、お気に入りがみつかればもうけもの。
イギリスでテキスタイルを勉強した私にはおなじみ ヴァネッサ・ベル Vanessa Bellの油絵がありました。小さな地方美術館ですが、なかなかあなどれません。
ボルトン美術館は展示室がたった2室。水族館は日本のデパート屋上の金魚屋さんの規模。
すべて入場無料です。
建物の外観が古代ギリシャ風。中には建造当時のアールデコ意匠が完璧に残っています。
図書館の読書室の天井漆喰かざり、石造りのゆるやかな螺旋階段とその手すりなどなど圧巻です!!
ロッカーに荷物をあずけてコンパクトカメラだけ提げて歩いていた 私に、若い職員が声をかけてきました。
「写真撮影には許可がいります。上の事務所から申請書をもってくるから記入してください」と言ってきました!
展示物じゃなくて、たてものも?と聞いたら、気の毒に考えこんじゃって、「上の事務所で聞いてきます」 めんどくさいので、
写真撮影一切しない約束をしてしまいました。たぶん融通のきかない職員にあたったのかもしれませんが約束は約束。写真は撮りませんでした。
水族館では若い人たちが携帯電話で写真をとりまくっていましたよ。
写真撮影に関してうるさい観光施設は、はじめてです。
博物館のあるシヴィックセンターに、裏側の1930年代古代ギリシャ風建て増し部分をむけている、市庁舎の正面を拝見するため、ぐるっと表にまわります。
ボルトン市庁舎 Bolton Town hall・・・ 横から。

正面からみたら左右対称で、両側に小ぶりの噴水と 伏せたライオン像があります。1865年建造の堂々たるネオ・クラシック様式。
正面。

今月18日のストックポート日報に載せた、「クリスマスの電光飾りを揚げている写真」をもう一度・・・
市庁舎裏側の増築部分。
もういちどクレセント(シヴィックセンターのある湾曲した道)にまわってアールデコ細部をみてみましょう。
手すりと、よく見たら一見ギリシャ風の軒飾りもアール・デコ。

ボルトン駅。
階段おりて、ホームに出たところすぐにある謎のピラミッド。
テラコッタの屋根瓦でできてます。人が柱の後ろをとおるのをとめてるんでしょうか。

その裏側。改築の際、大工さんが置いていったあまりものの屋根瓦で駅員が創作意欲を発揮したんでしょうか。
だれか由来を知ってる人、教えてください。

イギリス北部を東西に結ぶ鉄道会社, ノーザン Nothen の小さめの電車はすべて前、後ろに口ひげをはやしています。


ボルトンは、グレーター・マンチェスター Greater Manchester の北にある ボロウ borough のひとつです。
ボロウは、日本で言えば、市町村に当たるかもしれません。(ストックポートも、ボロウのひとつです)
先週、用があって行きました。
ストックポートから1時間に1本の直通電車で、マンチェスターを通って30分あまり。ついでにちょっと町見物。
駅からちょっと歩いたところに、半円形に湾曲した 長大なシヴィック・センター Bolton Civic Centreがあります。
市庁舎付属の、お役所ビルです。
大きく湾曲した道に沿ってたつ 左右ほぼ対象の 古代ギリシャ風建築です。

1930年代の建造で、細部がアール・デコ様式で装飾されています。
アーチの向こうにちょっと見えているのが市庁舎 Bolton Town hall の、うらがわです。
工事の白い仮囲いがちょっと見苦しい。湾曲した道は英語で クレセント crecentといいます。三日月という意味です。
また白黒写真です。

アーチをくぐってクレセントの内側に入ります。内側から見たシヴィック・センターのたてもの。
最初の白黒写真もそうです。
シヴィック・センターの右端はオフィス棟です。ギリシャ神殿風。

今回 用があったのは、このビルの左端、上階の、小さな博物館 Bolton Museum。一階は市民図書館、地階には水族館があります。
一階は図書館、地階は水族館。外観は右端と同じです。
続きはあした。

一定の間隔で、同じぐらいの樹齢の木が植えられているんですが、なぜか木の種類がちがいます。
だから花が咲く時期、紅葉する時期、散る時期がばらばら。11月にはいって、散りそろい始めたようです。秋もおわりです。
夏の終わりは日本よりずっと早くやってきます。9月にはいるともう朝夕の通勤に上着が欠かせません。日もどんどん短くなってきます。
日暮れ後、子供たちが仮装して近所の家々をまわってお菓子をねだる、10月31日のハロウイーン Halloween、かがり火を焚き、花火を打ち上げる11月5日の ガイ・フォークス・ナイト Guy Fawkes' Night(うちではどっちも無視しちゃったので、今年はご紹介できませんでした。)がイギリスの秋の夜を盛り上げる行事です。
これからはじまる、夜が長-いイギリスの冬に対する覚悟をきめて、意地でも楽しくやってやろうという意気込みの行事かもしれません。
クリスマス時季、午後3時をすぎると日没です。
ライトアップされたストックポート・ヴァイアダクト Stockport Viaduct。先週6時ごろの撮影。

11月の第2日曜日の戦没者追悼日(リメンブランス・サンディ Remembrance Sundayー11月10日の本欄参照 )と
11月11日の第一次大戦の終戦記念日 Armistice Day の2つの厳粛な行事が終わると、イギリスの秋は終わりって気分です。
赤いケシの花輪に囲まれた戦没者慰霊塔 war memorial。イギリス晩秋の風景。

どの町でも慰霊塔ではリメンブランス・サンデイの追悼式で花輪を捧げます。これはマンチェスター北部、ボルトン Boltonの市庁舎前。
この2つの厳粛な行事が終わるといっきに自粛していたお店やテレビのコマーシャルがクリスマス商戦解禁、ってムードになります。
(ハロウイーンが終わるとすぐクリスマスの飾りつけをする商店街や自治体もありますが。)
クリスマスの準備開始、すなわちイギリスの冬の到来!
伝統的にはクリスマス・イヴ(12月24日)の午後までクリスマスの飾りつけはしないことになってるそうなんですが。
しかもまだ11月!
家庭では、どこもだいたい12月の最初の週末にクリスマスツリーを出しちゃうようですね。
特に子供がいたらなおさら早くなる傾向らしい。商業主義につられて。
ボルトンの市庁舎前で、先週 火曜日にクリスマスの電光ディスプレイを揚げる作業をやってました。

きのう撮影した、ストックポートのマージー・スクエア Mersey Square(ザ・プラザ The Plaza があります。9月6日の本欄参照)のクリスマスツリー。

てっぺんは2階の窓にとどく高さ。栽培農家から買った、イギリスではクリスマスツリーとしておなじみの生のカナディアン・パイン Canadian pine(松の一種)です。伐って台に取り付けてあります。
ショッピングセンター、マージーウェイ Marseywayのいりぐち。


新館といっても、どちらも築80年です。
市庁舎 新館は1930年代の流行を反映した、ちょっとアールデコ調です。
図書館に面した外壁は 図書館の丸みにそって湾曲しています。
二つの建物の間の半円形の歩道は、現在 工事中で立ち入り禁止です。
改装がはじまるまでは 長くライブラリー・ウォーク Library Walk として親しまれてきました。
先の見えない、両側を高い石造りの壁で遮蔽された湾曲した道を歩くのはわくわく不思議な気がしたものです。
頭の上の平行な2本の曲線に切り取られた空を、ぬけきるまでに一回はみあげました。
図書館の4年にわたる大改装が終了した後も、ライブラリー・ウォークでは依然として 何か工事が進行中のようです。
高い仮囲いを立てて通りぬけできないようになっています。
図書館と となりの市庁舎 新館が現在、地階でつながっています。
ライブラリー・ウォークの真下に当たる地下一階部分には、天井が一部ガラスの、明るい書架スペースが増設されていました。

両側を高い石造りのビルにはさまれた細長い地下空間なのに開放感たっぷり。
上を見上げると丸いふたつの外壁の間に見える青空の見え方が、改装前の外の歩道、ライブラリー・ウォークの時とほぼ同じ。
ふたつの建物の地下の壁をとりはらった地点です。

手前が市庁舎 新館。その奥がライブラリー・ウォークの地下の、明るい書架スペ-ス、そのまた奥が、改装された旧中央図書館ビル。
中央図書館と市庁舎 新館が地下でつながったこの機会に、何の用事もない市庁舎 新館に、はじめて足をふみいれてみました。
図書館に面した壁はやっぱり丸い!

図書館に面してないサイドは直線です。

左側には 市民が申請用紙などに書き込むための投票所みたいな作りつけのブースが並んでいます。
市庁舎 新館ビルの地階、コロネード手前に、郷愁を誘う旧式の赤い電話ボックスがあります。

中に設置してある公衆電話は新式の使用可モデルでした。
携帯電話が普及した今でも、海外からの観光客のためでしょうか、観光地には公衆電話ボックスが かなりたくさん設置されています。
かつてのライブラリー・ウォークを抜けた先、図書館の裏側には、市庁舎本館 Manchester Town Hall Main Building がそびえたつアルバート広場 Albert Squareがあります。
市庁舎本館は、荘厳華麗イギリス・ネオ・ゴシック建築の代表建築にしてしかも教会ではない!建築史上稀有な好例。
・・・・とほめすぎですが、とにかく立派です。そのうち写真に撮ってきますね。
かんじんの中央図書館の周りはいまだに工事の仮囲いで見苦しいので全景写真はすべて完成して足場や仮囲いが取り払われてから撮りにいきます。
「マンチェスター中央図書館」の5回+最初の一回連載は今日でおしまいです。
また機会があれば、お見せします。
カウンター式カフェで、コーヒーとショート・ブレッドを買って座る席を探します。

談話禁止ではありませんが、しゃべってる人はあまりいません。図書館の中だからでしょうか。
コーヒー片手に会議の資料か何かをラップトップでまとめている女の人の向かいに座りました。
ただコーヒーを飲んでるのは、なぜか手持ちぶさたです。
まわりはみんな携帯電話かタブレットか、あるいは本を手にしています。ここは閲覧スペースですから。
えっ、図書館の閲覧スペースで飲食していいのかって?
そういえば、上の階の書架の間に設置してある空き缶や紙コップ用 分別ゴミ箱を見て、「こんなところで何か飲む人がいるの?」と不思議に思ってたんです。
これで判明。
この図書館は蔵書を読みながらの飲食、大奨励なのでした。
書架の間にテーブルが点在するカフェでお茶を飲むんだから、本を手にしないといけないような気がして一番手近な郷土史の棚から豪華な布張りの写真集をもってきて読むことにしました。
膝の上で本をひろげ、コーヒーを飲み、ショートブレッドをかじりました。
汚さないように気をつかいました。

日本の大きな書店に行った時、未会計の(!)本を持ち込める喫茶室があって驚いたことがあります。
人が腰を据えて読んだ、しかもコーヒーのシミやビスケットのくずがついてるかもしれない本を買う人がいるのが今でも不思議です。
だけど、どうせみんなで共有、誰の物でもない図書館の本なら納得です。
3階、用もないのに上がってみた、オフィス階の廊下。

別に一般の人は立ち入り禁止、というわけではありませんが、用のない人はわざわざいかない場所です。
やっぱり丸い。
丸の中心は下の階の読書室 Central Wolfton Reading Room の天井部分でもある、巨大ドーム(丸天井)。
入り口ロビーの吹き抜けを見下ろす2階ギャラリーの、くつろぎスペース。ここも飲食OKです。

真ん中の読書室での読書やお勉強に疲れたら、おしゃべりに出てくるための場所としても便利ですね。
改装前のこの図書館は、アカデミックで戦前の雰囲気たっぷりの、格調高く、また陰気な場所でした。(それはそれでよかったのですが・・・)
心機一転、現在のこの図書館は 市民の憩いの場、くつろげるスペースを提供しようという心づもりのようです。
明日で最終回です。
一階、ロビー奥の喫茶スペース、ライブラリー・カフェ Library Cafe 。
広いです。どこからどこまでカフェか、判別がつきません。


ところどころ検索用のコンピューターが設置されていて、周りは書架です。
書架と書架の間に低いコーヒー・テーブルと椅子が点在しています。
喫茶スペースは一階の図書閲覧コーナー全体に拡張しているようです。
丸い図書館の一回中央部分です。やっぱり丸い!
まんなかでぐるぐる回る電光文字の下は、「 アーカイヴ・プラス・コンピューター Archive Plus Computer 」という設備だそうで、古文書が検索できるようになってます。

まわりに3だい立っているタッチスクリーンの装置で操作できるみたいです。
近未来風な装置が、シブいマンチェスターの古地図の映像を映していました。
ぐるぐる回る電光文字の上は、壮大な上階の、読書室 Central Wolfson Reading Room の床、中央です。
(きのうの本欄を参照)
上階の読書室の真ん中の床が丸く くりぬいてあって、一階のぐるぐる回る電工文字の円筒の先っちょがとび出してます。

下から見上げたところ・・・
昨日より4回シリーズでお届けしています。
























