写真は拾った蹄鉄です。拾った場所は田園風景の中にある小さな神社ですが、神社のことは別の機会に掲載します。ここでは村の鍛冶屋について漱石の「二百十日」の冒頭部を引用して子供時代を懐かしみたいと思います。

一
ぶらりと両手を垂げたまま、圭(けい)さんがどこからか帰って来る。
「どこへ行ったね」
「ちょっと、町を歩行(ある)いて来た」
「何か観るものがあるかい」
「寺が一軒あった」
「それから」
「銀杏の樹が一本、門前にあった」
「それから」
「銀杏の樹から本堂まで、一丁半ばかり、石が敷き詰めてあった。非常
に細長い寺だった」
「這入って見たかい」
「やめて来た」
「そのほかに何もないかね」
「別段何もない。いったい、寺と云うものは大概の村にはあるね、君」
「そうさ、人間の死ぬ所には必ずあるはずじゃないか」
「なるほどそうだね」と圭さん、首を捻る。圭さんは時々妙な事に感心す
る。しばらくして、捻ねった首を真直にして、圭さんがこう云った。
「それから鍛冶屋の前で、馬の沓を替えるところを見て来たが実に巧み
なものだね」
「どうも寺だけにしては、ちと、時間が長過ぎると思った。馬の沓がそん
なに珍しいかい」
「珍らしくなくっても、見たのさ。君、あれに使う道具が幾通りあると思う」
「幾通りあるかな」
「あてて見たまえ」
「あてなくっても好いから教えるさ」
「何でも七つばかりある」
「そんなにあるかい。何と何だい」
「何と何だって、たしかにあるんだよ。第一爪をはがす鑿と、鑿を敲く槌
と、それから爪を削る小刀と、爪を刳る妙なものと、それから……」
「それから何があるかい」
「それから変なものが、まだいろいろあるんだよ。第一馬のおとなしいに
は驚ろいた。あんなに、削られても、刳られても平気でいるぜ」
「爪だもの。人間だって、平気で爪を剪るじゃないか」
「人間はそうだが馬だぜ、君」
「馬だって、人間だって爪に変りはないやね。君はよっぽど呑気だよ」
「呑気だから見ていたのさ。しかし薄暗い所で赤い鉄を打つと奇麗だ
ね。ぴちぴち火花が出る」
「出るさ、東京の真中でも出る」
「東京の真中でも出る事は出るが、感じが違うよ。こう云う山の中の鍛
冶屋は第一、音から違う。そら、ここまで聞えるぜ」
初秋の日脚は、うそ寒く、遠い国の方へ傾いて、
淋しい山里の空気が、心細い夕暮れを促がすなかに、かあんかあんと
鉄を打つ音がする。










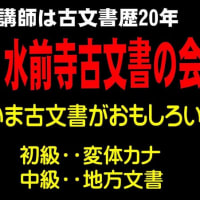

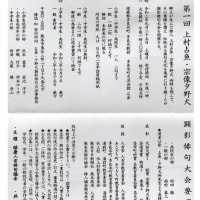





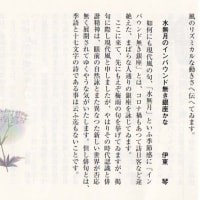
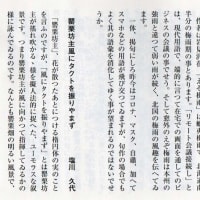
蹄鉄を取り替えるのは鍛冶屋ではないのでしょうか?
漱石の描写には少し足りないところがあります。それは爪の焼ける臭いがないことです。
蹄に合わせて鉄を整形したあと冷めてない蹄鉄をジュツと押し当てるので爪の焼ける独特の臭いが発生します。それでも馬は平気な顔をしているので熱くないのだなと感心したものです。
昭和20年代の物資の運搬手段は馬車でしたから蹄鉄馬が多かったのです。農耕馬に蹄鉄は打ちません。
現代では蹄鉄を着けた馬は競走馬くらいです。
膝栗毛に出てくる街道馬は人と同じに草鞋を履いていました。以上