さらば東京裁判史観 何が日本人の歴史観を歪めたのか(4)
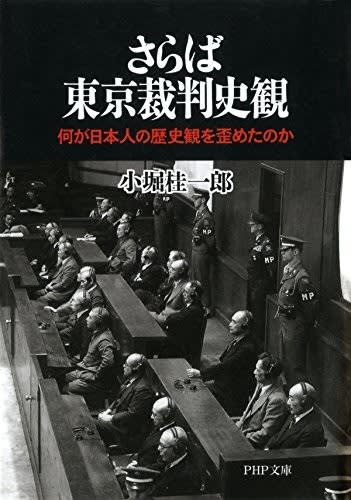
『新しい歴史教科書』問題が、かまびすしい。なぜ、韓国や中国はあんなに危険思想視するのか。小泉首相の「靖国参拝」問題に関しても、なんであれほど明白な内政干渉ができるのか。ましてや、そのような外国の理不尽な物言いに賛同して大騒ぎしている日本人の一部の精神構造はどうなってしまっているのだろうか。本書は、そのような疑問に真摯に、そして明確に答える、国民必読の評論である。大東亜戦争に敗北し、降伏した日本は、勝者である連合国の暴力的なマインド・コントロールによって、「自らの歴史に対する誇り」を傷つけられ、その痛手からいまだに回復できないでいる。この連合国のやり口とはいかなるものであったのか。そしてそれが現代日本人の精神構造にどんな影響をおよぼしているのか。著者は、つねにその検証を続けてきた。その成果として、確かに言えること、言わねばならぬことを、あらためて訴える。
昨日の続きです。P.78 から引用します。
現代にこびりついた史観の毒
イギリスの国際法学者ハンキー卿 (Baron Maurice Pascal Alens Hankey) はその著書『戦犯裁判の錯誤の中で、パル判事の意見書の中に見られる、 不戦条約と今次大戦との関係に就いて論じた一節にふれて以下の様に述べている(冨士信夫『私の見た東京京裁判」による)。
〈パル判事が絶対に正しいことを、私は信じて疑わない。 ケロッグ条約(パリ不戦条約)は私もまた熱心な支持者のひとりであるが、それが作られた経過のすべてを熟知している者として、また、この条約の計画を調整する一切の段階、および二つの大戦の間、この条約に影響を与えた一切について特別な責任をもつ者として私が確言することは、条約調印からニュルンベルク、 東京の判決と刑の言い渡しを読んだ時まで、私は、この条約を、戦争を計画し準備し遂行することを戦争犯罪として訴追する根拠として使い得るなどという暗示は、一回だに耳にしたことがないということである〉
国際法上の学術書の邦訳であるからどうしても読みにくい文章だが、要約して言えば、パリ不戦条約が戦争犯罪訴追の根拠として用いられ得るとは夢にも思っていなかった、と言っているのである。
ところが一方日本の国際法学を代表する立場にあった横田はそうは考えなかった。〈東京判決は世界の審判にほかならないから、その決定は、一般的に確立する可能性がすこぶる大きい〉という文言で、自分が国際法学者としての運命をそこにかけた東京裁判判決の普遍妥当性に望みを嘱したのである。
かくて日本人による東京裁判史観の受容とその定着の基礎は、法学上の立場からして立派に築かれたことになる。そこに運命を賭けた横田 (平成五年九十七歳で歿)が長命であった如くに、この史観もなかなかに息が長く、 老残の身ながらとにかくなお生きて呼吸をしている。 そしてその瘴気によって我国の教育界・思想界・ 歴史学界を、いや何よりも先ず社会一般に於ける国家と国際関係についての考え方を汚染し、毒し続けている。 その次第を次章以下に具体的に考察してみよう。
ここで第二章が終わります。
戦後民主主義関係資料
日本国憲法の誕生/国立国会図書館
新番組!憲法学者の闇 第1回「日本を支配する東大憲法学?」
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(1)
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(2)
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(3)
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(4)
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(5)
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(6)
戦後の民主主義を調べていてこの論文に出会いました(7)
横田喜三郎先生の記事
戦後の憲法について調べていてこのサイトに出会いました
日米地位協定 及び 関連情報 (上) 日米地位協定 及び 関連情報 (下)
新番組!憲法学者の闇 第1回「日本を支配する東大憲法学?」
歴代首相の憲法観 -せめぎ合う改憲派・護憲派・現実派-









