
太陽の光と熱は強烈だ。普通の星のようにファインダーを覗いて導入するわけには行かない。観測デッキの壁に映る望遠鏡の影を手掛かりに太陽を視野の中に導いた。そして、望遠鏡の後ろに取り付けたフリップミラーと名付けられた45度に傾いた鏡の先にアイピースを取り付けて太陽面を見る。
見えた。思ったよりはるかに綺麗に見えた。光球と呼ばれる丸い太陽の上に、小さなほくろのような黒点。光球の周辺には白斑と名付けられた薄白い斑点も分かる。太陽は今活動期の真っ最中だと言うので、もう少し大きな黒点を期待していたのだが、思ったより小さい。少しさびしいが仕方が無い。この小さなほくろを中心に置いて、倍率を上げてみた。
パソコンのモニターによってはかなり暗くなるかもしれないが、これがその写真。

三つの黒い塊は、それぞれ対になっていて、磁力線の出口と入り口だと言う。その周りは少し色が変わっていて、あたり一面海の波のような薄黒い筋が見える。さすがに米粒状斑と言う名の対流の証拠までは見分けられなかった。
太陽はその質量が1.989×10の14乗テラトン。まあ、書いてみただけで何のことやら分からない。地球の33万倍と言われてもやっぱりピンと来ない。何しろ地球を離れて見た事が無いのだから。そんなでかい光の球の上にポチッと出来たほくろをこうしてみているわけだ。そのほくろと太陽の光球の大きさを写真上で測って黒点の大きさを割り出してみた。一番大きな黒点の長いほうがおよそ8600キロメートルあった。
8600キロメートル。地球の直径の3分の2にも及ぶ、小さくて大きなほくろだ。










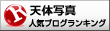
















フリップミラー=望遠鏡ののぞく所の近くに付いていて、レバーを回すと脇に隠れる小さな鏡
アイピース=望遠鏡の手元側に取り付ける、覗く所のレンズ
光球=太陽の表面
磁力線=磁石の力の同じ所を繋いだ仮想の線。本当は面になってる。
テラ=キロやメガと同じ倍率を表す言葉で元の量の一兆倍
こんなところで分かるかなぁ