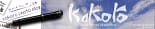|
冬至は「日短きこと至〔きわま〕る」という意味です。 |
|
|
|
|

庄内は例年だとこの時期は↑(月山)こんな風景です。
今年は雪がとても少なく、↓(鳥海山)こんな風景になっています。

白鳥が落としていった羽根がきれいに輝いていました。
日本海では海鳥たちが必死で生きています。
荒れた日本海の波に決死のダイビングで小魚を捕獲しています。
最上川の白糸の滝神社

希に風が止んだとき、深々と雪は積もります。
最上川河口の冬の風景
撮影DATA
Nikon D300s
Nikkor AF-S DX 17-55mm F2.8G
Nikkor AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G
TAMRON SP 90mm MACRO F2.8
 |
Let It Be |
| クリエーター情報なし | |
| EMI Catalogue |