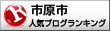風を読む
2011-10-21 | 環境
このところ、議会報告会や町会懇談会が立て続けにあって、
まちの生の声を知る機会に恵まれています。
議会報告会は、市民ネットの三人の代理人(議員)がまちに出向いて直接議会の報告をし、
逆に皆さんからも様々な問題を伺って情報交換をはかる場です。
今回は、馬立と瀬又の二か所で行いました。
どちらも共通して大きな話題となったのは、環境問題。
東京や神奈川といった大消費地からほど近く、恰好な山間部や低地がある市原市は、
「首都圏のごみ捨て場」とも言われかねない状況です。
空気や飲み水など環境の汚染が静かに確実に進んでいることを、
市原市の住民は生活の中で感じ取っています。
今回参加された方の中に、
臨海部の企業をリタイヤしたのち、大学で地球環境科学の講座を開いていた方がいらっしゃいました。
講義で使用した資料を見せていただきながら、
特に、ダイオキシンを発生するポリ塩化ビニル樹脂の危険性についてわかりやすく教えて下さいました。
ポリ塩化ビニル(塩ビ)といってもあまりピンと来ないのかもしれませんが、
日本では、電線やコード、チューブ、下水・排水管などのパイプ類に盛んに使用されています。
身近なところでは、100円傘。これは、絶対に止めなければならないものだそうです。
化学式で塩ビより塩素が一つ多いポリ塩化ビニリデンも、要注意です。
これは、有名メーカーの食品用ラップに使用されています。
現代社会では、これらを全く排除するのは現実的ではありませんが、
ラップも傘も、パイプにしても、環境を汚さない材料で作られているものが他にあるのですから、
できるだけそちらを使用することは可能です。
それから、ダイオキシンは、ゴミを燃やす時の温度が低いと発生しやすくなります。
できるだけ高温(1300度)で焼却するとよいそうです。
(ちなみに、市原市の福増は800度。)
そして、どんどん使ってどんどん捨てる生活を見直すこと・・・
環境問題は、結局私たちの毎日の生活を見直すことに繋がっているのですね。
エネルギー問題と一緒です。。
環境問題とは直接関係ないのですが、
たくさんいただいた講義資料の最初に、こんな文章を見つけたのでちょっと紹介。
学生たちへ、私(講師)からの願い・正しい努力を!
「自分は一生懸命努力したのに不遇」
これは、努力の「方向」と「時」の誤り。
この講義は、時代を読み、努力の方向性を正しく学ぶ、即ち「世の中の風を読む」勉強。
そこで、新聞記事を教材として活用する。
環境問題は、これからの研究・開発ビジネスの“宝の山”。
学生の卒論テーマ・就職決定の一助となることを願う。
『開発は時代を読む作業である』 安藤桃福
もひとつ。
公害を正当化しない
いつの世も、現実社会は
利便性と犠牲のバランス。
利便性をほどほどに・犠牲を最小化・自然と共生
対応案を創出、批判のみはダメ。
これが、みなさん技術者の役割。
この講義を受けた超有名大学の学生さん、
将来は多くが日本の未来を背負って立つ技術者になるのでしょうね。
どうか、広い視野を持って。風を読み違えてこれ以上多くの犠牲者を出さないように!!
まちの生の声を知る機会に恵まれています。
議会報告会は、市民ネットの三人の代理人(議員)がまちに出向いて直接議会の報告をし、
逆に皆さんからも様々な問題を伺って情報交換をはかる場です。
今回は、馬立と瀬又の二か所で行いました。
どちらも共通して大きな話題となったのは、環境問題。
東京や神奈川といった大消費地からほど近く、恰好な山間部や低地がある市原市は、
「首都圏のごみ捨て場」とも言われかねない状況です。
空気や飲み水など環境の汚染が静かに確実に進んでいることを、
市原市の住民は生活の中で感じ取っています。
今回参加された方の中に、
臨海部の企業をリタイヤしたのち、大学で地球環境科学の講座を開いていた方がいらっしゃいました。
講義で使用した資料を見せていただきながら、
特に、ダイオキシンを発生するポリ塩化ビニル樹脂の危険性についてわかりやすく教えて下さいました。
ポリ塩化ビニル(塩ビ)といってもあまりピンと来ないのかもしれませんが、
日本では、電線やコード、チューブ、下水・排水管などのパイプ類に盛んに使用されています。
身近なところでは、100円傘。これは、絶対に止めなければならないものだそうです。
化学式で塩ビより塩素が一つ多いポリ塩化ビニリデンも、要注意です。
これは、有名メーカーの食品用ラップに使用されています。
現代社会では、これらを全く排除するのは現実的ではありませんが、
ラップも傘も、パイプにしても、環境を汚さない材料で作られているものが他にあるのですから、
できるだけそちらを使用することは可能です。
それから、ダイオキシンは、ゴミを燃やす時の温度が低いと発生しやすくなります。
できるだけ高温(1300度)で焼却するとよいそうです。
(ちなみに、市原市の福増は800度。)
そして、どんどん使ってどんどん捨てる生活を見直すこと・・・
環境問題は、結局私たちの毎日の生活を見直すことに繋がっているのですね。
エネルギー問題と一緒です。。
環境問題とは直接関係ないのですが、
たくさんいただいた講義資料の最初に、こんな文章を見つけたのでちょっと紹介。
学生たちへ、私(講師)からの願い・正しい努力を!
「自分は一生懸命努力したのに不遇」
これは、努力の「方向」と「時」の誤り。
この講義は、時代を読み、努力の方向性を正しく学ぶ、即ち「世の中の風を読む」勉強。
そこで、新聞記事を教材として活用する。
環境問題は、これからの研究・開発ビジネスの“宝の山”。
学生の卒論テーマ・就職決定の一助となることを願う。
『開発は時代を読む作業である』 安藤桃福
もひとつ。
公害を正当化しない
いつの世も、現実社会は
利便性と犠牲のバランス。
利便性をほどほどに・犠牲を最小化・自然と共生
対応案を創出、批判のみはダメ。
これが、みなさん技術者の役割。
この講義を受けた超有名大学の学生さん、
将来は多くが日本の未来を背負って立つ技術者になるのでしょうね。
どうか、広い視野を持って。風を読み違えてこれ以上多くの犠牲者を出さないように!!