永平寺開山記 ⑤ さて、哀れにも比叡山に落ち延びた神道丸と梅王は、慣れぬ山住まいに、都の方を眺めては、
「遙かの雲井のその下は、恋しい父のいらっしゃる都だが、また、恨めしき都でもある。」と、語り嘆いて過ごしておりました。
そんな時、ようやく神道丸の行方を突き止めた、譜代の家臣「田代の源内」が、訪れました。源内は、早速に御前に罷り出ると、道忠卿の最期と、その後の一家離散の顛末について語りました。
「このことを知らせんため、彼方此方と、探し回りましたが、ようやくお会いでき本望です。これにて使命は果たしました。これ以上、何の役にも立たぬこの命、譜代の主を見捨てて出奔したからは、お暇申して、いざさらば。」
と言うと、ふっつと舌を噛みきって、その場で命を絶ちました。
二人は、あっと驚き、詰めよりましたが、時既に遅し。呼べど叫べど、源内は、帰らぬ人となりました。二人は、密かに源内を葬ると、ある決断をしました。
二人は、僧都(そうず)に、これまでのことの次第を全て語り、出家を願い出たのでした。僧都はこれを聞いて、
「そうであれば、髪を下ろし給え。」
と、血筋と撫でた御髪(おぐし)を四方浄土にお剃りになりました。二人は、墨の衣に着替えると、改めて僧都から、戒名を受けました。神道丸は、道元(どうげん)、梅王丸は、道正(どうしょう)と授かったのでした。
それからというもの、二人は、宝蔵に籠もって、昼夜と問わず学問に精を出しました。
窓の前には、蛍を集め灯火として、天台経典の円頓(えんどん:悟り)止観(しかん:正しい智慧)を修めますが、道元には、納得できないことがありました。ある時、道元は、道正にこう言うのでした。
「いかに、道正。わたしは、天台の諸経を通貫したが、現世末世の衆生成仏の願いを実現するためには、「禅法」の外に道は無いと考えている。しかし、日本は小国であり、「禅法」の極意を全うすることができない。私は、末世の衆生済度のため、命を賭けて入唐(にっとう)して、禅宗六祖(慧能大師)より直に禅法の極意を学びたいと思う。」
二人は、僧都に暇乞いをすると、旅の装束を調えて、菅笠で顔を隠し、竹の杖だけを頼りとして、まだ世も明けぬうちに比叡山を後にしました。道元は、この修業の旅立ちに、こう一首を詠みました。
「今日出でて いつかきて(来て・着て)みん 唐衣 我が立つ山の 雪の白雲」
「衆生済度の旅ではあるが、再び帰れるかどうかも分からない。」
と、振り返ると、比良の高嶺の残雪が目に焼き付いたのでした。
さて、それより二人は、京都を離れ、大阪、兵庫と、旅路を重ねて行きました。
やがて、淡路島が見えてきました。浜には、塩屋の煙がたなびいています。道元は、その煙を眺めながらも、こう詠嘆するのでした。
「浪間浪間の塩釜に
炊くや憂き身を焦がすらん
煙と消えし我々も
かかる憂き目に遭うまじと
身を恨み、世を疎み」
ここは、松の浦という浜辺です。二人は、ここで唐船が出るのを待つことにしました。 二人は、唐船は無いかと方々尋ねましたが、そう簡単にあるものではございません。道元と道正が、浜辺で休んでいますと、沖より一艘の小舟が近づいてきました。やがて、二人の前に舟を着けると、舟の老人がこう問いかけました。
「御僧達は、どこまで渡る方々ですか。もし、唐船(もろこしぶね)をお待ちの様であるならば、乗せてあげますよ。」
喜んだ二人は、二つ返事で舟に乗り込みました。すると不思議なことに、夢か現かと思う内に、唐の明星津に着いていたのです。すると老人は、
「いかに、道元、道正。我はこれ、加賀の国、白山大権現なり。御身、禅法を極めて、必ず日本に戻りなさい。その時は、私が守り神になるであろう。」
と言い残すと、光を放って忽然と消えたのでした。
(※伏線:後に道元が世話になる吉峰寺が、白山信仰の寺である)
あら有り難やと、いよいよ行く末頼もしく思った二人が、深く祈誓を掛けて礼拝していると、一人の通行人がありました。道元は、禅の霊場天童山への道を尋ねてみようと、その老人を呼び止めました。
「われわれは、粟散国(ぞくさんこく:小国の意)の者であるが、これより天童山へ上がろうと思っております。道をご存じであればお教えください。」
老人は、立ち止まると、
「なに、方々は、日本よりの僧と仰るか。天童山に上がるとは、さぞや深い願いがあるようじゃの。大変、殊勝なる志じゃ。よしよし、道しるべをいたそう。」
と、先に立って歩き始めました。老人は、歩きながらも、やれ、天童山は中国禅宗四山のひとつだとか、やれ、禅法を究むるには、天童山より外は無いなどと様々に話しをして、多くの谷、峰を越えたにも関わらず、二人は飽きる間もなく、天童山に到着しました。
老人は、
「さて、これこそ天童山。ようく拝みなされ。霊窟が沢山あり、岩滑らかに苔深く、谷は峙ち(そばだち)雲が立ちこめ、巌(いわお)からは水が滴る。八葉の峰は、八相の浄土をかたどり、月は、真如の影を映す。八つの谷には、八功徳水(はっくどくすい)。
晴嵐(せいらん)が梢を吹けば、法性、懺悔の声がする。されば、使命の第一は、心静かに拝むことじゃ。」
と、言いました。これを聞いた二人は、痛く感動して、信心を肝に銘じて感涙の涙を絞りました。すると、老人は、いきなりこう問いかけてきました。
「日本の僧よ、それ、禅法に工夫あり、座禅の公案を何と心得る。」
道元は、こう答えました。
「そこに入れば、幽玄に同じ、そこを出れば、三昧の門に遊ぶ。」
さらに、老人が、
「自身の仏とは、さて如何に。」
と問うと、
「雲深き所、金竜が踊る。」
と答えます。すると老人は、
「生死を離れるなら。」
と、聞き返しました。道元はすかさず、
「輪廻の如し。」
と、答えると、老人は、重ねて道元に向かって、同じ問いをしました。
「生死を離れるなら。」
道元は、
「潭月長閑(たんげつのどか:水面に映る月のように静かである)」
と答えました。老人は、矢継ぎ早にこう問いました。
「それで、これから、どうするつもりだ。」
そこで、道元は、問答から離れて、静かにこう答えました。
「柳は緑、花は紅の色々。」(蘇東坡の詩)
老人は、にっこりと微笑むと、
「おお、良きかな、良きかな道元。則ち、教下別伝(きょうげべつでん)の理体をよくよく悟っておるわい。」
と、呵々と大笑すると、巻物一巻と払子、柱杖(しゅじょう:正しくは手偏の主)を取り出して道元に与えました。
老人は、突然にそばの岩に上に飛び上がると、たちまち達磨大師に化身して、
「いかに、道元、道正よ。それなる巻物は、碧巌録(へきがんろく)なり。
(一夜碧巌録:石川県金沢市東光山大乗寺を指す)急ぎ日本へ帰島いたし、末世衆生を引導いたせ。さてさて、我が有様をよっく目に焼き付け、下根蚰蜒(げこんげじ:無能な)なる僧共に、よく学ばせよ。」
と、言うなり、最後に座禅の姿をお示しになって、やがて巌の向こうに消えて行きました。まったくもって、有り難い次第です。
つづく










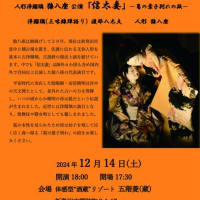


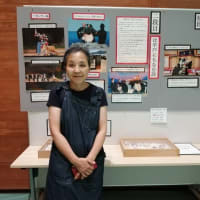
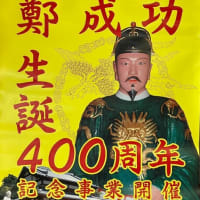




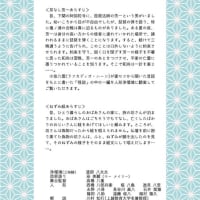
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます