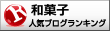今週末は台風11号の影響で、大阪にも大雨
洪水警報が…
することもないので甘いものネタをひとつ。
春休み前半、家族で訪れた京都府の北端、
天橋立(あまのはしだて)。
天橋立といえば、こちらのお店に行かねば
なりますまい…。
<勘七茶屋> ~宮津市字文殊~

日本三景天橋立の南端、智恵の文殊として
有名な知恩寺の門前にある有名店。
創業は元禄3年(1690年)と300年を
超える老舗。
もちろん元来が茶店なので、店内の席でも
いただけます。
画像でお分かりの様に両隣でも智恵の餅が
売られる知恵の餅激戦区。
<智恵の餅>


親指大の小餅をたっぷりのこしあんで包んだ
あんころ餅…
というよりあんの中に餅が埋もれている感じ。
あんころもちの代名詞、伊勢名物の赤福餅と
比べると、餅はやや柔らかく、こしあんは
少し甘くてやや素朴という感じですが、
智恵の餅には頭が良くなる?おまけ付。
その由来はこんな感じ…
鎌倉末期、文殊堂の前で餅を売るお婆さんが
ある子供に毎日餅を与えていた。
ここを訪れた京都大徳寺の大燈国師が子供の
聡明さに驚き、「智恵の文殊の力を受けた餅
を毎日食べているからに違いない」と云った
というのが由来だとか。
(ほんまかいな…)
賞味期限は翌日まで。
(10個入り \700)
私も智恵の餅をいっぱい食べたので、
ちょっとは賢くなったかな?
~おまけ~
<智恩寺>


左:山門、右:文殊堂
なんといっても、智慧の文殊「智恩寺」あって
こその智慧の餅です。
日本人なら、寺社の門前の餅や団子を見たら
迷わずにありがたく買うべし!
洪水警報が…
することもないので甘いものネタをひとつ。
春休み前半、家族で訪れた京都府の北端、
天橋立(あまのはしだて)。
天橋立といえば、こちらのお店に行かねば
なりますまい…。
<勘七茶屋> ~宮津市字文殊~

日本三景天橋立の南端、智恵の文殊として
有名な知恩寺の門前にある有名店。
創業は元禄3年(1690年)と300年を
超える老舗。
もちろん元来が茶店なので、店内の席でも
いただけます。
画像でお分かりの様に両隣でも智恵の餅が
売られる知恵の餅激戦区。
<智恵の餅>


親指大の小餅をたっぷりのこしあんで包んだ
あんころ餅…
というよりあんの中に餅が埋もれている感じ。
あんころもちの代名詞、伊勢名物の赤福餅と
比べると、餅はやや柔らかく、こしあんは
少し甘くてやや素朴という感じですが、
智恵の餅には頭が良くなる?おまけ付。
その由来はこんな感じ…
鎌倉末期、文殊堂の前で餅を売るお婆さんが
ある子供に毎日餅を与えていた。
ここを訪れた京都大徳寺の大燈国師が子供の
聡明さに驚き、「智恵の文殊の力を受けた餅
を毎日食べているからに違いない」と云った
というのが由来だとか。
(ほんまかいな…)
賞味期限は翌日まで。
(10個入り \700)
私も智恵の餅をいっぱい食べたので、
ちょっとは賢くなったかな?
~おまけ~
<智恩寺>


左:山門、右:文殊堂
なんといっても、智慧の文殊「智恩寺」あって
こその智慧の餅です。
日本人なら、寺社の門前の餅や団子を見たら
迷わずにありがたく買うべし!