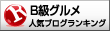11月19日(水)pm7:00から、湖西市商工会館2F研修室で開催された
中小企業会計啓発・普及セミナーを受講した。
「経営を強くする」 会計を活かした経営力の高め方
漠然としたタイトルで、話の内容はいったいなんぞや?という感じですが、
なぜ、日々帳簿を付けるのか?なぜ、決算をするのか?という普段何の疑問も
抱かずに行っている経理処理の根っこの部分に注目し、聞き慣れた遠州弁で
解りやすく話してくれた。
講師は、坂本&パートナー理事長 坂本孝司氏。
浜松市に生まれ、神戸大学を卒業後、昭和56年、25歳で浜松に会計事務所を開業。
その後勉学に励み、平成4年には東京大学大学院法学政治学研究科修士課程終了
平成9年、同大学院同科博士課程単位取得終了の経歴を持っている。
氏曰く、「会計」の歴史を、どんどんさかのぼっていくと、1673年「フランス商事王礼」
にたどりつくのだそうです。日本では、ちょうど江戸時代。当時のフランスは、大不況
の真っ只中で、企業倒産が続発していたそうです。それを見かねた国王ルイ14世が、
大蔵大臣コルベールに倒産防止策の立案を求め、商人に記帳と決算書作成を義務化。
破産時に帳簿を裁判所に提出できなければ、厳罰・死刑になったのだそうです。
もし、私が17世紀に生まれて起業し、倒産していたら間違いなく「死刑」?
人と人とを結ぶ「静岡やすま園」 <http://www.yasumaen.jp>
静岡やすま園
〒431-0427
湖西市駅南1-3-1
パレマルシェ新所原店内1F
TEL:053-577-5357
FAX:053-577-5355