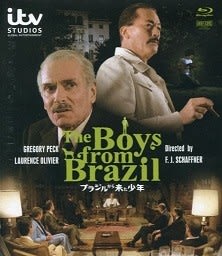日本機軍機動部隊が真珠湾を奇襲?
この情報をつかんだアメリカは真偽を確かめるべく、
ひとりの日系人をスパイとして日本に派遣する。
佐々木譲の『エトロフ発緊急電』は本格スパイ冒険小説だ。
スパイとして白羽の矢が立てられたのはケニー・サイトウ。
スペインでフランコ独裁政権と闘った元義勇兵だ。
スペイン内戦。
ここで作家ヘミングウェイは『誰がために鐘は鳴る』を書き、
ジョージ・オーエルは『カタロニア讃歌』を書き、
写真家のロバート・キャパは有名な写真『崩れ落ちる兵士』を撮った。
ピカソは空爆された街ゲルニカの悲惨を目の当たりにして『ゲルニカ』を描いた。
スペイン内戦は『自由と民主主義』のための戦いであり、世界中の耳目が集まった。
さて、こんなスペイン内戦に参加した主人公ケニー。
自由と民主主義のための闘争に裏切られて虚無的になっている。
アメリカの諜報部からスパイとして日本に潜り込むことを依頼されるが、ケニーは拒絶する。
いはく、
「おれは世界中のどの政府にも忠義を尽くすつもりはない」
「この世界はおれが真面目に怒らなくてはならないほどの価値はない」
「すべてが愚かだった。共和国の理想もデモクラシーも革命も」
こんなケニーに、彼をスカウトに来たアメリカ軍のキャスリンは反論する。
「それは安っぽい虚無主義よ。愛したものから十分な見返りがなかったからと言って、
かつて自分が何かを愛したという事実すら否定してしまうのは」
しかしケニーの心は動かない。
それどころかアメリカの批判を始める。
「貴様らの標榜するデモクラシーなどただのお題目」
「圧政と搾取を糊塗するためのきれいごとのスローガンでしかない」
「国内では黒人やメキシコ人やアジア人をどう扱っているか。
中米ではどれほど好き勝手のし放題をしているか。胸に手を当ててよく考えてみろ」
……………………………………………………………………
日本ではめずらしい骨太の冒険スパイ小説だ。
僕はこの作品をスタート地点にして船戸与一など、日本の冒険小説を読んでいった。
そして現在、僕はケニーの言葉に共感する。
「おれは世界中のどの政府にも忠義を尽くすつもりはない」
「この世界はおれが真面目に怒らなくてはならないほどの価値はない」
「すべてが愚かだった。共和国の理想もデモクラシーも革命も」
国のために。自由と民主主義のために。
政治家はきれいごとを言うけれど、裏金問題などでどうしようもない言い訳を聞いていると、
懐疑的にならざるを得ない。
この後、ケニーはカネのためにアメリカの要請を引き受けて日本に潜入する。
そこで彼が何を見て考えたのかは本作を読んで確認して下さい。
非常に面白い冒険小説です。
この情報をつかんだアメリカは真偽を確かめるべく、
ひとりの日系人をスパイとして日本に派遣する。
佐々木譲の『エトロフ発緊急電』は本格スパイ冒険小説だ。
スパイとして白羽の矢が立てられたのはケニー・サイトウ。
スペインでフランコ独裁政権と闘った元義勇兵だ。
スペイン内戦。
ここで作家ヘミングウェイは『誰がために鐘は鳴る』を書き、
ジョージ・オーエルは『カタロニア讃歌』を書き、
写真家のロバート・キャパは有名な写真『崩れ落ちる兵士』を撮った。
ピカソは空爆された街ゲルニカの悲惨を目の当たりにして『ゲルニカ』を描いた。
スペイン内戦は『自由と民主主義』のための戦いであり、世界中の耳目が集まった。
さて、こんなスペイン内戦に参加した主人公ケニー。
自由と民主主義のための闘争に裏切られて虚無的になっている。
アメリカの諜報部からスパイとして日本に潜り込むことを依頼されるが、ケニーは拒絶する。
いはく、
「おれは世界中のどの政府にも忠義を尽くすつもりはない」
「この世界はおれが真面目に怒らなくてはならないほどの価値はない」
「すべてが愚かだった。共和国の理想もデモクラシーも革命も」
こんなケニーに、彼をスカウトに来たアメリカ軍のキャスリンは反論する。
「それは安っぽい虚無主義よ。愛したものから十分な見返りがなかったからと言って、
かつて自分が何かを愛したという事実すら否定してしまうのは」
しかしケニーの心は動かない。
それどころかアメリカの批判を始める。
「貴様らの標榜するデモクラシーなどただのお題目」
「圧政と搾取を糊塗するためのきれいごとのスローガンでしかない」
「国内では黒人やメキシコ人やアジア人をどう扱っているか。
中米ではどれほど好き勝手のし放題をしているか。胸に手を当ててよく考えてみろ」
……………………………………………………………………
日本ではめずらしい骨太の冒険スパイ小説だ。
僕はこの作品をスタート地点にして船戸与一など、日本の冒険小説を読んでいった。
そして現在、僕はケニーの言葉に共感する。
「おれは世界中のどの政府にも忠義を尽くすつもりはない」
「この世界はおれが真面目に怒らなくてはならないほどの価値はない」
「すべてが愚かだった。共和国の理想もデモクラシーも革命も」
国のために。自由と民主主義のために。
政治家はきれいごとを言うけれど、裏金問題などでどうしようもない言い訳を聞いていると、
懐疑的にならざるを得ない。
この後、ケニーはカネのためにアメリカの要請を引き受けて日本に潜入する。
そこで彼が何を見て考えたのかは本作を読んで確認して下さい。
非常に面白い冒険小説です。