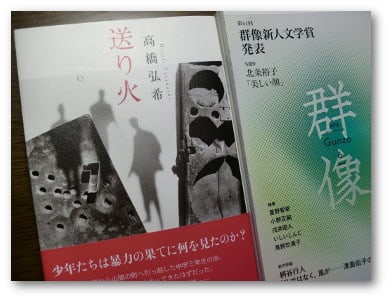俊英による芥川賞受賞作ということで、高橋弘希著『送り火』(文藝春秋社)を読んでみました。導入部は、東京から青森県の山間の町に引っ越してきた中学三年生の男の子が、新しく住まいとなった一軒家になじみ、翌年には廃校となる予定の中学校のクラスに入っていく様子が描かれます。わずか六人しかいない男子生徒たちの中で、花札でナイフを盗む役割を決める場に居合わせたことから打ち解けていく、というのは実に大きな一歩だったのでしょう。
あとは、予想通り、いじめと暴力、その暗転としての見境無しの反撃までが、気持ちの悪い「伝統」を背景に描かれます。たしかに、言葉によって描写されるシーンは凄惨で、思わず息をのむすごさがあります。ただし、こんなこともふと思ってしまうのです。
この物語は、ドーナツ化現象でやがて廃校となる予定の都会の学校へ、田舎から転校してきた中学生が、かつて巨大なスーパーだった建物が空きビルとして放置されている場所を舞台として遭遇する出来事としても成り立ちます。昔ながらの伝統として弱いものをいたぶるのは、地元の暴走族でも設定できるでしょう。作者はなぜ津軽地方を、広く言えば田舎を舞台に選んだのか。それはたぶん、作者自身が田舎の出身であり、土俗的な背景を描きやすかったのと、田舎=遅れた封建的因習にまみれた地域としてとらえるステレオタイプな通念、都会を、繁栄と虚飾の影に大きな社会悪を宿しているとはとらえていない、そういう通念に合わせただけなのではないかと思ってしまいます。
○
正直に言って、先に読み終えた北條裕子『美しい顔』にしろ本作にしろ、おそらく二度と読み返すことはないでしょう。野暮天理系人間には、芥川賞作品はますます合わなくなってきている(*1)のかもしれません。並行して読んでいる柏原宏紀著『明治の技術官僚~近代日本をつくった長州五傑』(中公新書)がおもしろいだけに、よけいに辛口になってしまいました。
(*1):アクタガワ賞とナオキ賞~「電網郊外散歩道」2012年3月
なんぴとも、悪を見て、あえてこれを選ぶわけではない。むしろ、それをより大きな悪と比べて善であるかのように思い、これに惑わされて、悪を追い求めるのである。 『エピクロス~教説と手紙』より
あとは、予想通り、いじめと暴力、その暗転としての見境無しの反撃までが、気持ちの悪い「伝統」を背景に描かれます。たしかに、言葉によって描写されるシーンは凄惨で、思わず息をのむすごさがあります。ただし、こんなこともふと思ってしまうのです。
この物語は、ドーナツ化現象でやがて廃校となる予定の都会の学校へ、田舎から転校してきた中学生が、かつて巨大なスーパーだった建物が空きビルとして放置されている場所を舞台として遭遇する出来事としても成り立ちます。昔ながらの伝統として弱いものをいたぶるのは、地元の暴走族でも設定できるでしょう。作者はなぜ津軽地方を、広く言えば田舎を舞台に選んだのか。それはたぶん、作者自身が田舎の出身であり、土俗的な背景を描きやすかったのと、田舎=遅れた封建的因習にまみれた地域としてとらえるステレオタイプな通念、都会を、繁栄と虚飾の影に大きな社会悪を宿しているとはとらえていない、そういう通念に合わせただけなのではないかと思ってしまいます。
○
正直に言って、先に読み終えた北條裕子『美しい顔』にしろ本作にしろ、おそらく二度と読み返すことはないでしょう。野暮天理系人間には、芥川賞作品はますます合わなくなってきている(*1)のかもしれません。並行して読んでいる柏原宏紀著『明治の技術官僚~近代日本をつくった長州五傑』(中公新書)がおもしろいだけに、よけいに辛口になってしまいました。
(*1):アクタガワ賞とナオキ賞~「電網郊外散歩道」2012年3月