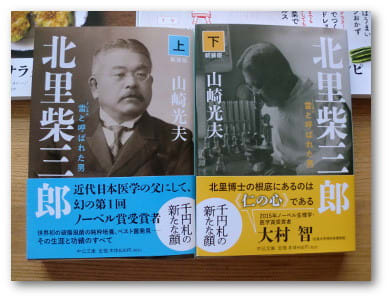千円札の顔が2024年から変わるそうで、私の記憶では伊藤博文から夏目漱石、野口英世に続き、北里柴三郎になる予定らしい。それはめでたいことですが、はて、北里柴三郎の業績はと訊かれると、破傷風だったかペストだったか、とにかく伝染病の研究をしたエライ人、くらいの認識です。
そのような世間一般の認識を商機と見たであろう出版社が、文化的意義を認識して新装版として改版刊行された文庫本、山崎光夫著『北里柴三郎〜雷と呼ばれた男』(中公文庫)の上下巻が、行きつけの書店の新刊コーナーにありましたので、いそいで手に取り購入して来ました。
上巻は、第1章「立志への道」と第2章「ベルリンの光」からなります。冒頭で、北里柴三郎は東京大学医学部長から呼びだされます。卒業を前にして少々暴れすぎたために落第を言い渡されるのか、それとも入学時の年齢詐称がバレたのかと不安になりますが、実は卒業の進路の意思確認でした。このあたり、柴三郎の経歴と当時の学生の気風が感じられるところです。
卒業後、病院勤務の道を選ばず内務省衛生局に奉職し、予防衛生の業務に携わります。エリート風を吹かす上役にペコペコせず、硬骨を貫きますが、案外こういう性格は真実を究明しようとする学者として大成する上で大事な資質なのかもしれないと感じます。衛生研究所に移った柴三郎は、顕微鏡に夢中になります。東京府下に発生した鶏コレラに対し、原因となる鶏コレラ菌を同定しますが、柴三郎の優れた手技のあらわれであり、明治18年の日本では初の業績でした。また、長崎に発生したコレラについても調査し、患者の排泄物からコッホが発見していたコレラ菌を検出して論文を発表し注目されます。
やがて、内務省からドイツ留学の命が下り、ベルリン大学でローベルト・コッホの下で研究生活に入ります。チフス菌及びコレラ菌の培養に関する基礎的研究のテーマを与えられた柴三郎の手腕と研究心を評価し、新しいテーマも与えられ、実験に次ぐ実験の生活を送ります。そんな中にやってきたのが、 森鷗外こと森林太郎。スマートですが実験室生活にはあまり熱心ではありません。それなのに、来独した陸軍省軍医監の石黒忠悳は、柴三郎に対し、コッホの下からミュンヘンへ移れと命じます。上官に従順な森と、衛生局を辞職してでも研究を続けたい柴三郎。実はコッホ本人から柴三郎への高い評価を聞いた石黒は、人事特命を撤回します。
このあたり、後に脚気病の米食原因説を唱える海軍の高木兼寛に対し、ワンマン石黒が脚気病細菌説に固執し、森林太郎は高木説を攻撃する論陣を張ります(*1)が、上司の意を受けすぎるというのか、忖度しすぎかも(^o^)/
実際には、オランダのペーケルハーリングという病理学者がバタビア(ジャカルタ)で脚気病菌を発見したという報告に対し、実験過程に疑義を呈しますが、同時にそれは同窓で同門の緒方正規に反ぱくすることとなります。
さらに柴三郎は、留学年限の三年からさらに二年の延長を認められ、破傷風菌の純培養の方法を確立しますが、同時にそれは嫌気性菌というグループの存在を明らかにするとともに、抗毒素の発見と免疫血清療法の基礎を提示する業績でもありました。
○
いやはや、すごいものです。伝染病研究のエポックメイキングな出来事が次々に登場します。柴三郎の頑固さが学問研究の上ではプラスに働いていることを感じます。
(*1):吉村昭『白い航跡』(下巻)を読む〜「電網郊外散歩道」2009年8月
そのような世間一般の認識を商機と見たであろう出版社が、文化的意義を認識して新装版として改版刊行された文庫本、山崎光夫著『北里柴三郎〜雷と呼ばれた男』(中公文庫)の上下巻が、行きつけの書店の新刊コーナーにありましたので、いそいで手に取り購入して来ました。
上巻は、第1章「立志への道」と第2章「ベルリンの光」からなります。冒頭で、北里柴三郎は東京大学医学部長から呼びだされます。卒業を前にして少々暴れすぎたために落第を言い渡されるのか、それとも入学時の年齢詐称がバレたのかと不安になりますが、実は卒業の進路の意思確認でした。このあたり、柴三郎の経歴と当時の学生の気風が感じられるところです。
卒業後、病院勤務の道を選ばず内務省衛生局に奉職し、予防衛生の業務に携わります。エリート風を吹かす上役にペコペコせず、硬骨を貫きますが、案外こういう性格は真実を究明しようとする学者として大成する上で大事な資質なのかもしれないと感じます。衛生研究所に移った柴三郎は、顕微鏡に夢中になります。東京府下に発生した鶏コレラに対し、原因となる鶏コレラ菌を同定しますが、柴三郎の優れた手技のあらわれであり、明治18年の日本では初の業績でした。また、長崎に発生したコレラについても調査し、患者の排泄物からコッホが発見していたコレラ菌を検出して論文を発表し注目されます。
やがて、内務省からドイツ留学の命が下り、ベルリン大学でローベルト・コッホの下で研究生活に入ります。チフス菌及びコレラ菌の培養に関する基礎的研究のテーマを与えられた柴三郎の手腕と研究心を評価し、新しいテーマも与えられ、実験に次ぐ実験の生活を送ります。そんな中にやってきたのが、 森鷗外こと森林太郎。スマートですが実験室生活にはあまり熱心ではありません。それなのに、来独した陸軍省軍医監の石黒忠悳は、柴三郎に対し、コッホの下からミュンヘンへ移れと命じます。上官に従順な森と、衛生局を辞職してでも研究を続けたい柴三郎。実はコッホ本人から柴三郎への高い評価を聞いた石黒は、人事特命を撤回します。
このあたり、後に脚気病の米食原因説を唱える海軍の高木兼寛に対し、ワンマン石黒が脚気病細菌説に固執し、森林太郎は高木説を攻撃する論陣を張ります(*1)が、上司の意を受けすぎるというのか、忖度しすぎかも(^o^)/
実際には、オランダのペーケルハーリングという病理学者がバタビア(ジャカルタ)で脚気病菌を発見したという報告に対し、実験過程に疑義を呈しますが、同時にそれは同窓で同門の緒方正規に反ぱくすることとなります。
さらに柴三郎は、留学年限の三年からさらに二年の延長を認められ、破傷風菌の純培養の方法を確立しますが、同時にそれは嫌気性菌というグループの存在を明らかにするとともに、抗毒素の発見と免疫血清療法の基礎を提示する業績でもありました。
○
いやはや、すごいものです。伝染病研究のエポックメイキングな出来事が次々に登場します。柴三郎の頑固さが学問研究の上ではプラスに働いていることを感じます。
(*1):吉村昭『白い航跡』(下巻)を読む〜「電網郊外散歩道」2009年8月