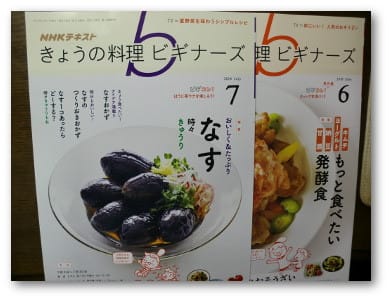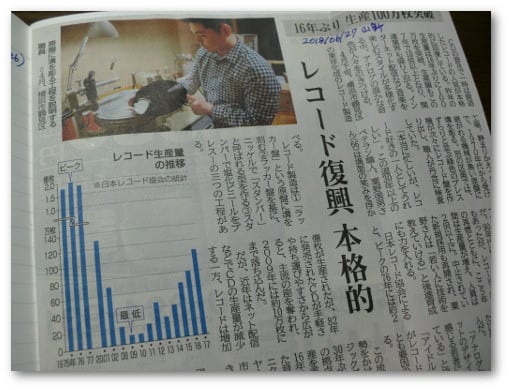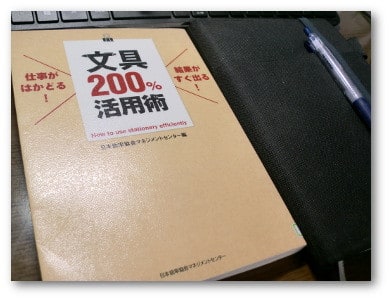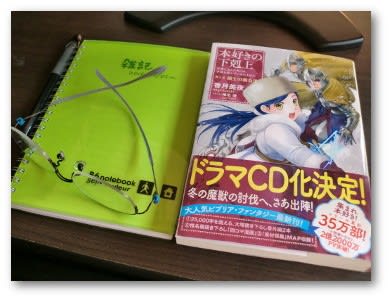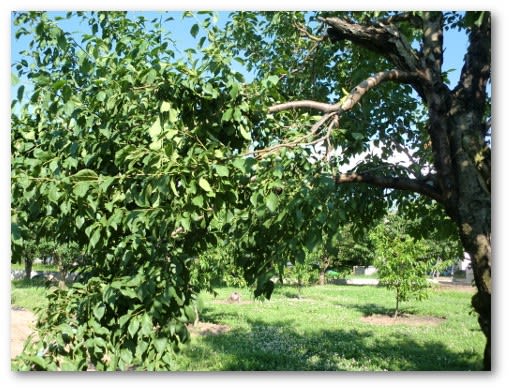海の日で祝日となった月曜日、早朝からサクランボ果樹園の褐色穿孔病対策の防除を実施し、くたびれて午前中〜昼過ぎまで爆睡、午後からハイドンの弦楽四重奏曲をいくつか聴いて予習し、演奏会に出かけました。山形弦楽四重奏団の第68回定期演奏会、ハイドンの弦楽四重奏曲全曲演奏を目標に活動してきたカルテットが、いよいよ全68曲を完奏するという記念の演奏会です。

会場となる文翔館に到着すると、議場ホール入り口にはすでに開場を待つ人たちの行列ができていました。開演前のプレコンサートは、学生さんたちを主体とする若い人の演奏で、今回は山形大卒業生の三浦奈々(Vla)と学生の佐々木杜洋(Vc)の2人による、L.V.ベートーヴェンの二重奏曲から。
続いてプレコンサート・トークは中島光之さん。初っ端から「ハイドンを全曲演奏しても今回が終わりではありません」と笑いを取ります。長男が生まれ、慣れないだっこをしているうちに腰を痛めてしまい、コルセットをして臨んだ第一回の演奏会からすでに18年、その長男もこの春に大学生になったとの感懐。今回のプログラムは「文翔館議場ホール〜ハイドン全68曲完奏記念オールハイドン〜」というもので、曲目は次のとおり。
これについては、(1)作品20-4は教会音楽とジプシー音楽を組み合わせ、教会の音楽、あるいはバロック音楽から離れていったOp.20の4曲めで、ハイドンの初期の作品、(2)モーツァルトの「ハイドン・セット」から逆に影響を受けたOp.50の4曲めで、ハイドン中期の作品、この二曲がまだ演奏していなかったので、これらに後期のOp.76-3「皇帝」を加えて三曲のプログラムとした、とのこと。前期・中期・後期の三曲にハイドンの人生の歩みを、また山形Qの18年の歩みを重ねあわせてお楽しみくださいとまとめました。うーむ、近年まれに見る、いや、聞く、出色のトークではなかろうか(^o^)/
ステージ上は、例によって左から1st-Vnの中島光之さん、2nd-Vnの今井東子さん、Vlaの倉田譲さん、Vcの茂木明人さんが並びます。今井さんのエメラルドのような青緑色のドレスが目を引くほかは、男性三人とも黒のシャツで、中島さんは腕まくりをして意気込みを示します。もしかしたら単に暑さ対策? いやいや、意気込みの現れとみました。
第1曲、ニ長調のOp.20-4。第1楽章:アレグロ・ディ・モルト。充実したハイドンの響き。第2楽章:ウン・ポコ・アダージョ・アフェットゥオーソ。短調の印象的な曲。チェロが実にいい味を出している変奏曲。第3楽章:メヌエット、アレグレット・アラ・ツィンガレーゼ(ジプシー風に)。付点リズムが特徴的な短い楽章。第4楽章:プレスト・エ・スケルツァンド。なるほど、たしかにジプシー風。しだいに速くなるところなど、チャールダーシュみたい(^o^)/
ウルブリヒ弦楽四重奏団のCDで予習をしていった影響もあると思いますが、実にいい曲を知ったなあと感じます。
続いて第2曲め:嬰ヘ短調のOp.50-4です。冷房がガンガン効く中で、第1楽章:アレグロ・スピリトーソが始まります。ハイドンにしては珍しい調性ではないかと思いますが、実際に独特の響きです。第2楽章:アンダンテ。変奏曲を奏でるチェロが、とても即応性に富んでいると感じます。第3楽章:メヌエット、ポコ・アレグレット。第4楽章:フィナーレはチェロから始まるフーガで、アレグロ・モルトの指示があります。
ここで15分の休憩です。はるばる関西から遠征して来た某さんと会い、少しだけ立ち話をしました。文翔館には何度も足を運んでおり、議場ホールもおなじみになっているようです。美味しい食べ物や温泉、音楽など、すっかり山形ファンになっていただいているようで、ありがたい限りです。知事に代わって御礼を申し上げねば(^o^)/
第3曲め:ハ長調、Op.76-3、知名度の高い名曲、「皇帝」です。実際、私もハイドンの弦楽四重奏曲をどれか一つと言われたら、「ひばり」か「皇帝」かと考えるでしょう。記憶している限りでも、山形Qの定期で1回、プレシャスQで1回、今度で三回目のナマ「皇帝」です。安定感のある4人のアンサンブルで、有名な第2楽章 Poco adagio Cantabile の、ゆったりとして伸びやかな音楽もブラヴォ!ですし、フィナーレの、ハイドン晩年の到達点にふさわしい斬新な響きにも強い印象を受けました。
実にたくさんのお客さんが入った議場ホールで、拍手に応えるアンコールは、「もう一回奏でたい曲」として選んだという、Op.76-1から「メヌエット」を。たしかに、「もう一回聴きたい曲」にも入るかもしれません。

今回は、個人的に Op.20-4 に心惹かれました。楽師ハイドンは、この曲をどんなときに作曲し、演奏したのだろう? 慶事が続く時にこの曲を選んだら、エステルハージ候から「お前、オレに何か恨みでもあるのか?」と言われかねない(^o^)/
おそらくは、エステルハージ候の周辺で何か悲しむべき事態が起こった時に、こうした音楽をさりげなく演奏したのではなかろうか? そして、候自身も、表面的には取り繕いながら、嬉しく思う面があったのでしょう。それは忖度でもゴマすりでもなくて、ハイドン自身が共感できるものだったからではなかろうか。エステルハージ侯と楽師ハイドンの関係は、ハイドンの忍耐強さはもちろんですが、両者に共感するものがあったために、長く続いた面があったのかもしれないと思えてなりません。

会場となる文翔館に到着すると、議場ホール入り口にはすでに開場を待つ人たちの行列ができていました。開演前のプレコンサートは、学生さんたちを主体とする若い人の演奏で、今回は山形大卒業生の三浦奈々(Vla)と学生の佐々木杜洋(Vc)の2人による、L.V.ベートーヴェンの二重奏曲から。
続いてプレコンサート・トークは中島光之さん。初っ端から「ハイドンを全曲演奏しても今回が終わりではありません」と笑いを取ります。長男が生まれ、慣れないだっこをしているうちに腰を痛めてしまい、コルセットをして臨んだ第一回の演奏会からすでに18年、その長男もこの春に大学生になったとの感懐。今回のプログラムは「文翔館議場ホール〜ハイドン全68曲完奏記念オールハイドン〜」というもので、曲目は次のとおり。
- F.J.ハイドン 弦楽四重奏曲 ニ長調 Op.20-4「ヴェネツィアの競艇」
- F.J.ハイドン 弦楽四重奏曲 嬰ヘ短調 Op.50-4
- F.J.ハイドン 弦楽四重奏曲 ハ長調 Op.76-3「皇帝」
これについては、(1)作品20-4は教会音楽とジプシー音楽を組み合わせ、教会の音楽、あるいはバロック音楽から離れていったOp.20の4曲めで、ハイドンの初期の作品、(2)モーツァルトの「ハイドン・セット」から逆に影響を受けたOp.50の4曲めで、ハイドン中期の作品、この二曲がまだ演奏していなかったので、これらに後期のOp.76-3「皇帝」を加えて三曲のプログラムとした、とのこと。前期・中期・後期の三曲にハイドンの人生の歩みを、また山形Qの18年の歩みを重ねあわせてお楽しみくださいとまとめました。うーむ、近年まれに見る、いや、聞く、出色のトークではなかろうか(^o^)/
ステージ上は、例によって左から1st-Vnの中島光之さん、2nd-Vnの今井東子さん、Vlaの倉田譲さん、Vcの茂木明人さんが並びます。今井さんのエメラルドのような青緑色のドレスが目を引くほかは、男性三人とも黒のシャツで、中島さんは腕まくりをして意気込みを示します。もしかしたら単に暑さ対策? いやいや、意気込みの現れとみました。
第1曲、ニ長調のOp.20-4。第1楽章:アレグロ・ディ・モルト。充実したハイドンの響き。第2楽章:ウン・ポコ・アダージョ・アフェットゥオーソ。短調の印象的な曲。チェロが実にいい味を出している変奏曲。第3楽章:メヌエット、アレグレット・アラ・ツィンガレーゼ(ジプシー風に)。付点リズムが特徴的な短い楽章。第4楽章:プレスト・エ・スケルツァンド。なるほど、たしかにジプシー風。しだいに速くなるところなど、チャールダーシュみたい(^o^)/
ウルブリヒ弦楽四重奏団のCDで予習をしていった影響もあると思いますが、実にいい曲を知ったなあと感じます。
続いて第2曲め:嬰ヘ短調のOp.50-4です。冷房がガンガン効く中で、第1楽章:アレグロ・スピリトーソが始まります。ハイドンにしては珍しい調性ではないかと思いますが、実際に独特の響きです。第2楽章:アンダンテ。変奏曲を奏でるチェロが、とても即応性に富んでいると感じます。第3楽章:メヌエット、ポコ・アレグレット。第4楽章:フィナーレはチェロから始まるフーガで、アレグロ・モルトの指示があります。
ここで15分の休憩です。はるばる関西から遠征して来た某さんと会い、少しだけ立ち話をしました。文翔館には何度も足を運んでおり、議場ホールもおなじみになっているようです。美味しい食べ物や温泉、音楽など、すっかり山形ファンになっていただいているようで、ありがたい限りです。知事に代わって御礼を申し上げねば(^o^)/
第3曲め:ハ長調、Op.76-3、知名度の高い名曲、「皇帝」です。実際、私もハイドンの弦楽四重奏曲をどれか一つと言われたら、「ひばり」か「皇帝」かと考えるでしょう。記憶している限りでも、山形Qの定期で1回、プレシャスQで1回、今度で三回目のナマ「皇帝」です。安定感のある4人のアンサンブルで、有名な第2楽章 Poco adagio Cantabile の、ゆったりとして伸びやかな音楽もブラヴォ!ですし、フィナーレの、ハイドン晩年の到達点にふさわしい斬新な響きにも強い印象を受けました。
実にたくさんのお客さんが入った議場ホールで、拍手に応えるアンコールは、「もう一回奏でたい曲」として選んだという、Op.76-1から「メヌエット」を。たしかに、「もう一回聴きたい曲」にも入るかもしれません。

今回は、個人的に Op.20-4 に心惹かれました。楽師ハイドンは、この曲をどんなときに作曲し、演奏したのだろう? 慶事が続く時にこの曲を選んだら、エステルハージ候から「お前、オレに何か恨みでもあるのか?」と言われかねない(^o^)/
おそらくは、エステルハージ候の周辺で何か悲しむべき事態が起こった時に、こうした音楽をさりげなく演奏したのではなかろうか? そして、候自身も、表面的には取り繕いながら、嬉しく思う面があったのでしょう。それは忖度でもゴマすりでもなくて、ハイドン自身が共感できるものだったからではなかろうか。エステルハージ侯と楽師ハイドンの関係は、ハイドンの忍耐強さはもちろんですが、両者に共感するものがあったために、長く続いた面があったのかもしれないと思えてなりません。