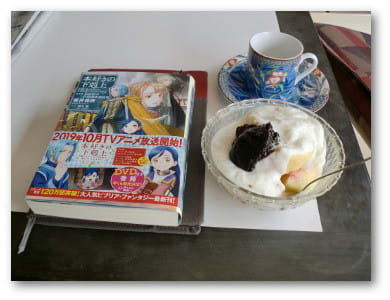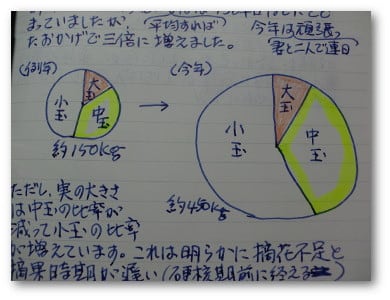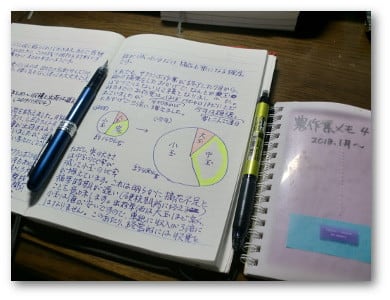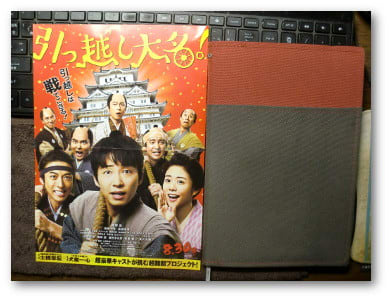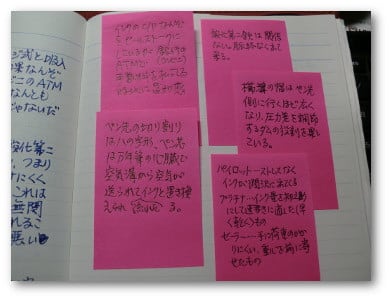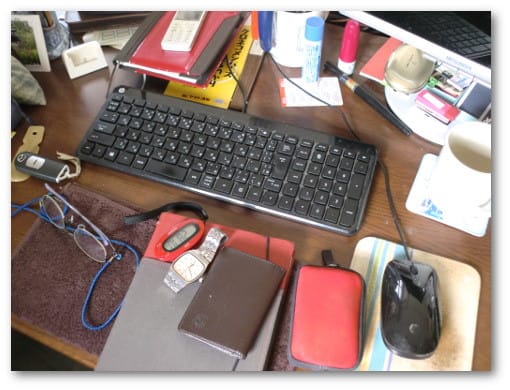ステレオ録音の初期である1960年前後の録音は、学生時代に主に各社の廉価盤LPでお世話になりました。しかしながら1968年にソ連によって制圧された「チェコ事件」の記憶も冷めやらぬ1970年代初頭、カレル・アンチェル(*1)とチェコ・フィルの録音は廉価盤シリーズに入ることもなく、さりとて学生の身分ではレギュラープライス盤を購入する財布の余裕もなく、モントゥーとロンドン響などと同様に、有名だけれど馴染みの薄いものでありました。その後1980年代に至り、たまたま入手したスメタナの「我が祖国」全曲録音をきっかけにして、これまで馴染みは薄かったけれど味わい深い演奏をする指揮者として印象深く記憶に残りました。
そして近年は、著作隣接権の保護期間が過ぎ、パブリック・ドメインの仲間入りをしたため、例えばモーツァルトの歌劇「魔笛」序曲(*2)の素晴らしさに目を開かされたように、アンチェルとチェコフィルの録音が気になります。では、ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」ではどうだろう? 例によって、「クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜」からダウンロードして、意識的に、正面から聴きました。
YouTube にもありました。
Dvořák: Symphony No. 9, Ančerl & CzechPO (1961) ドヴォルザーク 交響曲第9番 アンチェル
うーむ、テンポといいきりっとした表現といい、ばっちり好みの範囲です。俗に「手垢にまみれた」通俗名曲扱いされることもある「新世界」ですが、緊張感と集中力に満ちた立派な演奏。聴いた後に、やっぱり名曲だなあとしみじみ痛感させられる、そういう演奏です。
(*1):カレル・アンチェル〜Wikipediaの解説
(*2):アンチェル/チェコフィルでモーツァルトの歌劇「魔笛」序曲を聴く〜「電網郊外散歩道」2018年12月
(*3):もっぱら親しんできた演奏は:ドヴォルザーク交響曲第9番「新世界より」を聴く〜「電網郊外散歩道」2006年4月
そして近年は、著作隣接権の保護期間が過ぎ、パブリック・ドメインの仲間入りをしたため、例えばモーツァルトの歌劇「魔笛」序曲(*2)の素晴らしさに目を開かされたように、アンチェルとチェコフィルの録音が気になります。では、ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」ではどうだろう? 例によって、「クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜」からダウンロードして、意識的に、正面から聴きました。
YouTube にもありました。
Dvořák: Symphony No. 9, Ančerl & CzechPO (1961) ドヴォルザーク 交響曲第9番 アンチェル
うーむ、テンポといいきりっとした表現といい、ばっちり好みの範囲です。俗に「手垢にまみれた」通俗名曲扱いされることもある「新世界」ですが、緊張感と集中力に満ちた立派な演奏。聴いた後に、やっぱり名曲だなあとしみじみ痛感させられる、そういう演奏です。
(*1):カレル・アンチェル〜Wikipediaの解説
(*2):アンチェル/チェコフィルでモーツァルトの歌劇「魔笛」序曲を聴く〜「電網郊外散歩道」2018年12月
(*3):もっぱら親しんできた演奏は:ドヴォルザーク交響曲第9番「新世界より」を聴く〜「電網郊外散歩道」2006年4月