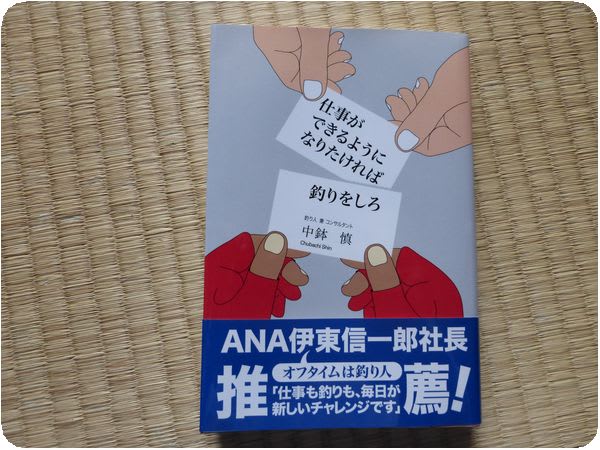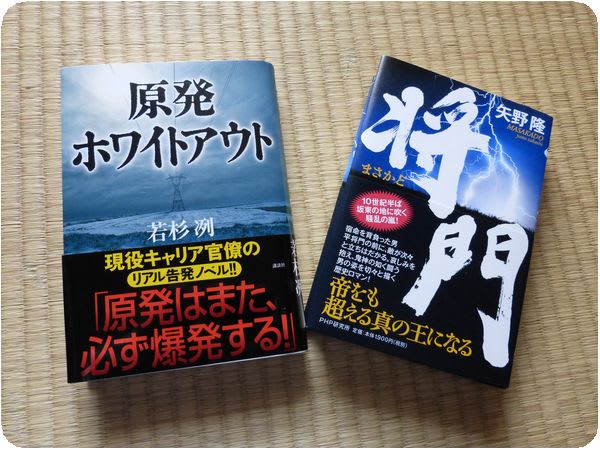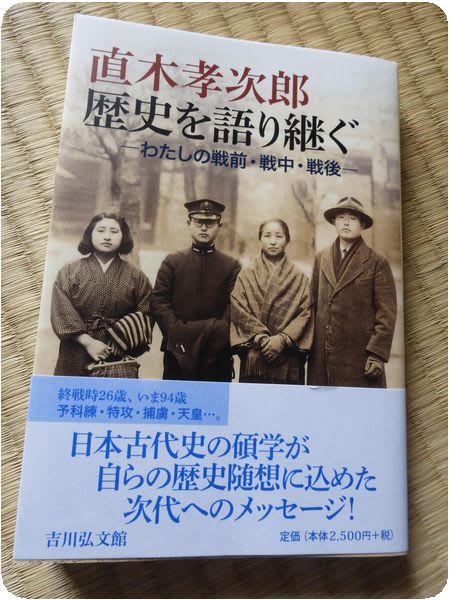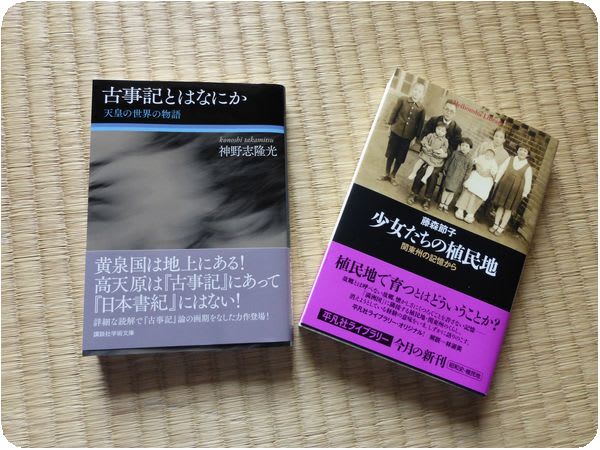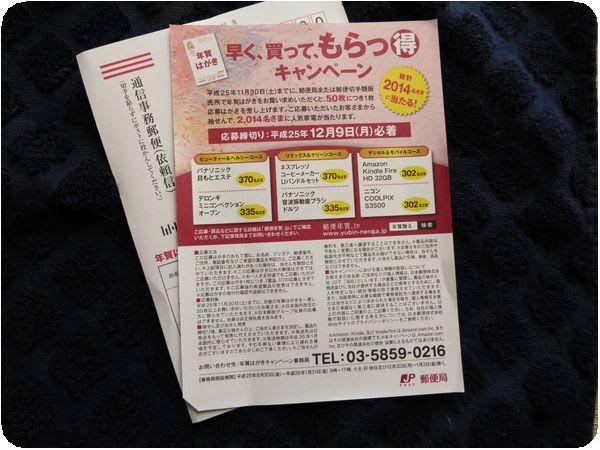大江神社の階段を降りて暫らく西へ歩くと松屋町筋に出ます。この界隈を下寺町と呼び、沢山のお寺が並んでいます。おそらく東の高台に四天王寺があるので、少し下ったこの地域を下寺町と呼ぶようになったのでしょう。今までも何度とこの松屋町筋を車や自転車で通っていますが、とりわけ関心も無く、素通りしてきましたが、歩いてみると意外な物に出逢います。


いきなり一つ目のお寺の前に『植村文楽軒墓所』の碑が建っており、墓地の北側に『文楽翁の碑』が外から見えます。植村文楽軒という人を私は知りませんが、調べてみると文楽の創業者とあり、1751年生まれですから、私より200年ぐらい前に生まれた人でした。文楽翁と言うのは文楽軒から数えて3世目にあたる人だそうです。

口縄坂に至るまでのお寺の門にこのような掲示物がありました。東儀一族墓所とあり、ミュージシャンの東儀秀樹を思い起こしたのですが、それは芸名だろうと思っていたら、母親が東儀家の人だったようでした。聖徳太子の腹心だった秦川勝を祖とする雅楽師の名家だと書かれていますが、真実はどうでしょう。江戸時代には朝廷に仕える楽師と幕府に仕える楽師、二手に分かれていたようです。東儀秀樹は宮内庁で楽師として活躍後、プロのミュージシャンになった人ですが、死んだらこのお寺に葬られるのでしょうか。

口縄坂の入り口にある掲示板、口縄坂の由来や周辺のお寺に多くの先人の墓があったと記されています。

でも曲ったところは未だ坂ではありませんでした。坂は蛇のような起伏になっているのでしょうか。

階段に辿り着くまでにあった善龍寺、門の横には再び口縄坂の由来が長文で書かれていました。“くちなわ”というのは朽ちて古くなった縄のことでヘビの古称、口縄坂の由来はやはり坂の下から見ると長く緩やかに蛇行し、階段が蛇腹のように見えたからという説が妥当だろうと書いてありました。

でも実際に坂を前にして見ると、どのようにも蛇行はしてないし、起伏も有るようには見えません。おそらく近世になって造り直したのでしょう。そうなるといつまでも口縄坂と言ってるわけにはいかないのではないかと思いますが、どうでしょう。

坂を登り切って上から見ても蛇行は有りません。

坂を登り切ったところにあった織田作之助の『木の都』という私小説のワンシーンでしょうか、“口縄坂は寒々と木が枯れて白い風が走っていた。私は石段を降りて行きながら、もうこの坂を昇り降りすることも当分あるまいと思った。青春の回想の甘さは終わり、新しい現実が私に向き直って来たように思われた。風は木の梢にはげしく突っ掛っていた。”昭和の初めにはこの坂の右の丘に夕陽丘高等女学校があり、織田作はそこの女学生に淡い思いを抱いていたらしきことが窺われます。

天王寺七坂スタンプラリーというのを何処かで聞いたことがあるような気がしますが、こうやって何処のどの寺が対応しているのかは知りませんでした。この掲示板に書かれている坂は右から順に北から南へ並んでいます。この掲示板を貼っていたのは、さんご寺だったと思います。

口縄坂を登り切り、東に向かって歩いています。突き当りに赤いお寺の塔のようなものが見えていますが、谷町筋の向こう側にある建物です。

谷町筋まで戻ってきました。南の方には阿倍野ハルカスが聳えています。ハルカスまで7~800mというところでしょうか。