京都の南に位置する天王山あたりは、豊臣秀吉と明智光秀の山崎合戦で有名な地である。「天下分け目の天王山」から戦名「天王山合戦」ともいうが、実際の戦闘は山麓、大山崎の平地や桂川べりで展開した「山崎合戦」である。いまJR山崎駅と阪急電車大山崎駅のある狭隘な地から北にかけての平野で戦闘は繰り広げられた。
山崎(やまざき)あるいは大山崎(おおやまざき)といわれるこの町は、山城国と攝津国の境界地である。JR山崎駅の木製標識がおもしろい。矢印の右が大阪府、そして左が京都府。この標示は大阪行きプラットホームの運転席寄りにある。各駅停車に乗車されたら、この駅で下車して標識をご覧になることをおすすめする。ちょうど真前でドアが開けば、発車前に車輌にもどることができる。しかし少しずれておれば、次の電車を待つことになってしまう。暇な日には、数分の遊びになるかもしれません。
昔の国境(くにざかい)はだいたいが、大きな河とか峠などで決められていたのでしょう。ところが、山崎にはそのような川も峠もない。南北境界の線引きは、幅わずか1メートルほどの小さな沢のごとき「西谷川」である。
この谷川は天王山の谷を下り、山崎駅のホームの地下を流れている。というかふだん、水量はほとんどない。小さな枯れた溝があるだけといってもよい。プラットホームの下の西谷川に沿って、駅を横断するトンネル歩道がある。天井が低いので頭上要注意だが、国境をいくこの歩道は愉快である。
ところで山崎の地はかつて、岩清水八幡宮の神人(じにん)、油座の商人たち社家が統治する自治都市であった。大阪の堺ほど大きな都市ではないが鎌倉期以来、江戸時代まで、権力から公認された油商人の町・神領である。
ちなみに堺も、摂津国、河内国と和泉国の三国にまたがる境界域にある。はじめ「境」と呼ばれたが、後に「堺」になったという。国境の山崎も、ともに自由を謳歌した自治都市である。国と国の境界には往々、治外法権の地域が誕生するのだろう。
摂津の北境、山城国南境、ともに山崎であり大山崎。離宮八幡宮に属する聖地とみなされていた。ところが明治初年、ふたつの行政区に分断され、ただの町になってしまったのである。
山崎の歴史は油業とともにあった。中世以来、大山崎の油商人たちは油座を組織し、全国の油専売権を握っていた。司馬遼太郎『国盗り物語』の斎藤道三もかつて、一介の山崎の油売商人であったされている。
次回は大山崎の油のことでも書いて、油を売ろうかと思う今日このごろ。
<2008年4月6日、JR山崎駅舎に無事帰還した燕を祝う 南浦邦仁記>










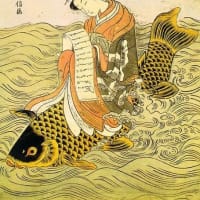



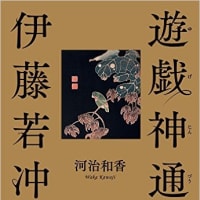





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます