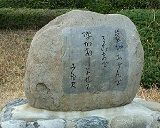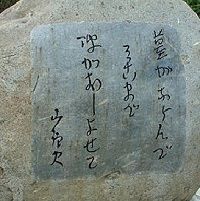前回は、なかなか終息の見えないPED/豚流行性下痢についての回でし
たが[こちら]、今回は豚コレラウイルス。8月30日に愛知県農業総合
試験場で発生した豚コレラウイルスについての話です。この発生につい
て農水省の拡大豚コレラ疫学調査チームは、道路の衛生管理区別が不十
分であったこと、そして豚舎に出入りする場合の履き物の履き換え場所
が曖昧であったこと、というその2つをウイルス侵入の原因であったと
発表しています。
ということで今回は本ブログの2018年11月分・衛生区分などについて
はなしである2018年11月に岐阜市の畜産センターでの豚コレラにつ
いての回を再掲載してみました[宮崎の鳥インフルエンザ対策例も有]。
今回の愛知県農業総合試験場と昨年の岐阜市の畜産センター、どちら
も公の施設ということも含めまして よろしかったらご参考に。
↓
『豚コレラウイルスの拡散を防ぐためにも/2018年11月』
岐阜市におけ豚コレラの問題で、11月15日に岐阜市の畜産センタ
ーの公園の豚2頭から豚コレラウイルスの陽性反応が出たのだそうで
すね。報道によれば
市畜産センター公園は、市民が動物と触れ合える憩いの場で、豚は
出荷もされている。岐阜県などによると15日午後、獣医師から
「豚の元気がなくなり、熱が出ている」と県中央家畜保健衛生所に
連絡があった。県の検査で陽性と判定され16日未明から防疫措置
に着手した
などと さらっと書いてありますが、民間よりもちからをいれておか
ねばならない、防除のお手本ともなるべき 公/おおやけの施設から
現実に2例目の感染を出してしまったわけですから、なんともびっく
りというか くちあんぐりというか、驚かざるを得ない事態になって
いるようで農業関係者のひとりとしてはじつに不安になります。
なんでまたそんなことに・・となった この岐阜市畜産センターの豚
コレラの感染の起こった原因ですが、
● 豚舎周辺だけが衛生管理区域に設定されており、関係者が行き
来する飼料や堆肥置き場が衛生管理区域に設定されていない
● 豚コレラに感染した野生猪の存在がセンター周辺で確認されて
いたにもかかわらず、公園エリアと畜産エリアで共通の機械が
使用されており、 その機械類を衛生管理区域で使用する際に
洗浄・消毒が行われていない事例もあったこと
● 飼養管理者等が豚舎に入る際に専用の衣服を着用しておらず、
作業用の長靴を消毒のみで豚舎で使用していた場合があること
などが確認されているといいますから、これなら感染しても当然とい
うか、むしろよくいままで 感染・発症しなかったなあ・・と逆に感
心してもしまいます。 なんといっても豚コレラウイルスは
● 猪だけでなく農場やたい肥置き場にいる小動物からも感染
● ヒトの履いている靴の、靴底の土からも感染する
というのはもとより
● 生肉類はもちろんハムやソーセージの加工品からも感染
[実際に日本の空港などでは探知犬も活躍していますし]
と いうのが定説であり、常識であるのですからね。・・・そうい
ったことから考えれば、
農水省のページなどで公開されている野生のイノシシの豚コレラウ
イルス感染個体数が増加し続けてなかでの この岐阜市の畜産セン
ターのとっていた対策って・・・なんとも不可解としかいいようが
ない気がします。。
たとえばですが、ウイルス病対策のいち例として宮崎県の養鶏関係
者の現場の鳥インフルザ対策では
● 鶏舎内にはいるときはその鶏舎専用の作業服や靴を用意する
● ウイルスを持っているかもしれない野生の鳥のフンが落ちて
くるのを警戒して作業服などの洗濯物を戸外で干さない
● 定期的に巡回して鶏舎への小動物の侵入防止策を徹底する
といった対策をとるのは しごくあたりまえというか、当然という
か、そんなかんじで防除している現実がありますから。
とはいったものの、でちゃったものはしかたない。・・・豚コレラ
ウイルスが日本全土に拡散していくことがないように、そしてこれ
以上のブタの生命や 野生のイノシシたちの間の感染拡大をすこし
でも減少させていくためにも岐阜の関係者のみなさまには、今後の
ウイルス対策をしっかりきっちり実行されてくださることをお願い
したいと思います。
![]() ちなみにこちらは 宮崎の口蹄疫発生時の、防疫の初動が
ちなみにこちらは 宮崎の口蹄疫発生時の、防疫の初動が
遅れた経緯をご紹介した回です。参考にしていただければ
さいわいです。
 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」
「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」











 「
「