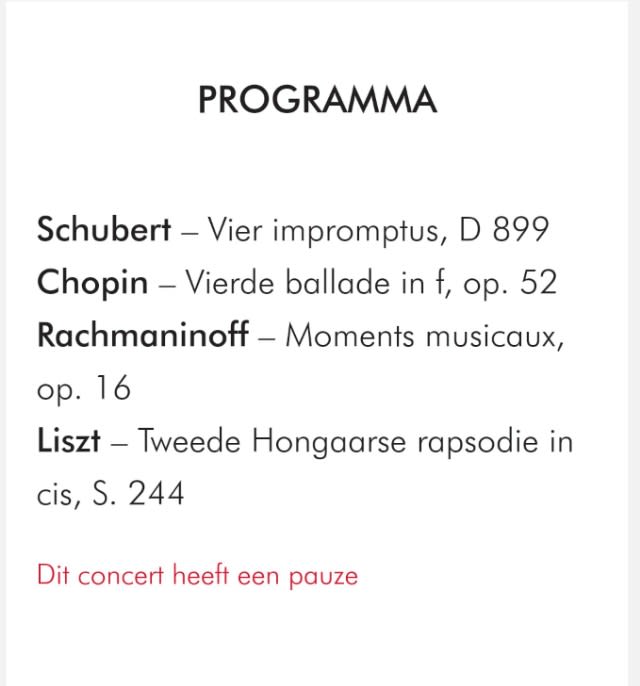アムステルダム滞在中に、たまたまベルリン・フィルがやってくる、しかも、演目がブルックナーの「9番」終楽章付きというのは、本来ラッキーなことの筈である。事実、これを知ったときには狂喜し、大いなる期待をもって、コンセルトヘボウとしては最高ランクのバルコン中央2列目の席を手配した。


朝から高鳴っていた気持ちは、夕方4時頃、楽器搬入の場面との遭遇で極に達し、あとは20時15分の開演時間に向け心身のコンディションを整えつつ臨んだものである。
しかし、今宵のブルックナー演奏への失望は、東京で聴いたヤニック・ネゼ=セガン&フィラデルフィア管による「4番」に匹敵するものであった。心が冷えてしまうのに僅か5分すらも必要なかった。
一言で申すなら、神聖なる教会のミサの最中にメタルバンドのギタリストがやってきて、ディストーション全開のプレイを繰り広げるというようなブルックナーだった。なにもエレキギターが悪いというのではなく、限りなく場違いな演奏だったと言いたいのである。
ここに、造物主への畏れや感謝もなく、永遠への憧れも祈りもない。大宇宙の鼓動や自然の美しさや厳しさがある筈もない。ただ、演奏家たちの自我ばかりが目立つばかり。もはや、ブルックナーとは言えない、ただの連続する音響があるばかり。
ベルリン・フィルの弦楽セクションは、プルトの頭から尻まで、すべてのプレイヤーが全力で弓を奮う。その姿は壮観であるし、後ろのプルトにゆくほどボーイングの小さくなる傾向にある我が国の一部のオーケストラに較べると、遥かに気持ちのよいものだし、ある意味で見習うべきものだ。
しかし、そこに鳴る音が美しいかというとそうではない。ロイヤル・コンセルトヘボウ管、シュターツカペレ・ドレスデン、ウィーン・フィルらを見れば分かるように、適切な脱力があってこそ、楽器は美しく鳴るのであり、あそこまで常に全力だと、音がギスギスして美しくないのだ。
これは音楽に限ることのない真理だ。イチローのバッティングや大谷のピッチングを見るならば、最上のパフォーマンスを得るための脱力の大事さが分かるだろう。
ベルリン・フィルのメンバーは、能力が高いばかりに、その能力の奴隷となっているようにみえた。俺たちはこんなに弾けるんだぜ、という風に楽器を鳴らしまくるうちに、目の前の楽譜が、ブルックナーでもストラヴィンスキーでも誰でもよくなってしまうのだろう。
すべては、ラトルの責任なのだと思う。まるでノーガードのブルックナーの顔面に、容赦なくパンチを打ちまくるような指揮ぶりで、大小の頂に向かっては扇情的なアッチェレランドを仕掛け、天国への階段となるべき崇高なゼクエンツでは拳を突き出しては、暴力的なフォルテで音楽を踏みにじる。
予想通り、終演後の聴衆は総スタンディングオベーション。熱狂的なブラヴォーの嵐の中、足早にホールを後にしたわたしの耳に、天国より宇野先生の声が聞こえる気がした。
「君、ラトルのブルックナーなんか、聴く方が悪いよ」。