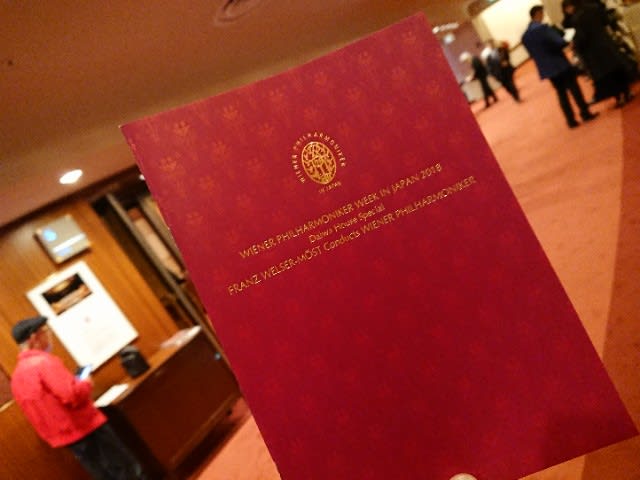
チケットを購入した時点では、さして大きな期待を抱いていたわけではなかった。
ヴェルザー=メストのブルックナーについては、以前、クリーヴランド管とのライヴ映像を観たときには、造型、サウンドや指揮姿に至るまで平凡に感じるなど、特別な感銘を受けなかったからだ。しかし、先日の「南国の薔薇」を観て、聴いて、俄然ブルックナーの素晴らしいであろうことを予感した。そして、その結果は事前の予測を遙かに上回る素晴らしいものだった。
第1楽章の冒頭から、弱音の美に胸打たれた。これは、弱音を重んじることのなかった朝比奈のブルックナーとは対極の美であり、水面に揺らめく光のように千変万化に色彩を変化させる弦のトレモロには目眩を覚えるほどであった。総じて、ピアノ以下の弱音に無限の段階とニュアンスがあり、各セクション間のバランスの絶妙さにはため息がもれるほどであった。一方、フォルテ以上にも凄まじいものがあり、総員フルボーイングから立ち上る弦の豊穣な響き、肺腑を衝く金管群の音圧にはただただ圧倒されるのみ。
第2楽章も弱音の美しさに酔った。もっと濃厚な歌心があってもよかったかもしれないが、歌いすぎない美しさもまたある、ということを教えられる。
さらに、第3楽章では、類い希な舞踊性を感じさせた。その聖と俗の綯い交ぜになったリズムの躍動は、メストとウィーン・フィル双方に通うオーストリア人の血のなせる業かもしれない。
フィナーレでは、前述の剛毅なまでの音量のほか、音楽が前へ前へと進んでゆく推進力にも秀でていた。などなど、どの瞬間を切り取っても「留まれ、お前は美しい!」と叫んでしまいたいほどの美しさに貫かていた。
何より嬉しかったことは、わたしがレコードで親しんできた50年代、60年代のウィーン・フィルの響きを彷彿とさせる瞬間が多々あったことである。ティーレマンとのベートーヴェンを聴いたときなどには、「ウィーン・フィルはもう昔のウィーン・フィルではない」と悟らされたものだが、今回の来日公演では古の良さが復活しているように思える。この件、ヴェルザー=メストの指揮がどれほど関与しているかは知らないが、ウィーン・フィルそのものが良い方向に変容してきていることを感じられたのは幸せなことであった。









