【東海三十三観音 第二十八番】



 えッ……たったこんだけ?
えッ……たったこんだけ?
弁天社
除地1段1畝6歩、字西町にあり。拝殿2間に1間半、本社は1間四方なり。神体は弘法大師護摩の灰を以て作りし像なり。長1尺ばかり是を羽田弁天の上の宮といへり。社傳云、昔僧龍海と云しもの、ある夜の夢に弁天の告ありて、いくほどなく如意宝珠を得たり。其故を尋ぬるに、当国多摩郡日原山の麓に弘法大師の草創ありし大日の堂あり。其所の霊水の中より一顆の宝珠わき出、いつしか多摩川の流に従ひて夜やまず、里人も殊にあやしみ思へり。然るに龍海ある夜不思議の夢の告ありて、かの玉を得しかば大に悦びこのまま置べきにあらずとて、まづ小祠を営みて是を祭り、傍に一宇をたてて別当所とす。後威光山龍王院と号せり。今是を上宮と云。又夫よりあまたの星霜を歴て、別当海誉が時に至り、堂舎悉く荒廃せしかば、修理を加へて旧にかへさんことを思ひたちけれど、おのが力らに及びがたければ、心にもあらでやみぬ其頃里人海老名太兵衛某と云し者、有僧の人にて、やがて本願主となりて村民等をかたらひ、又漁人など催したてて、たがひに力らを合せ幾ほどなく思ひのままに修補なれり。又海誉ある夜の夢に、一老翁来り告て云。今江戸の御家人有馬純政が家に、弘法大師の作れる弁天の像あり。汝是を請得て此所に安置せよと。まさしく告ぐると見しかば、海誉奇異の思をなし、やがて江戸におもむき、純政が屋敷を尋ね、告のままに其事の由を述てかの像をこひしかば、純政もかねて所持せしことなれば、たやすくうけかひ、やがて家人堀山孝良を使者として彼像を此社におさめしと云。是は上宮に安置す。事は詳なれど、うけがたき事多ければ、其大意をとれり。又弁天祠記といへるもの当社にあり。其記す所はまたことなり。其記に云。此弁財天は弘法大師の刻する処にして、往古より此に鎮座あり。其後建武の兵乱の時、盗賊の為に侵掠せられ、宮殿等も破壊に及び、ただかたばかり残りて、わづかの草堂の内に安ぜり。夫よりあまた年暦を経て、高橋重言と云し者夢の告ありて、新像を刻みておさめしと云。是によれば大師の刻せし像は、兵乱の時失しにや、何にも其傳ふる処詳ならねど、暫くここに記し置く。
天神社。本社へ向て左の傍にあり。小祠にて、東向なり。
別当龍王院
威光山常楽寺と号す。新義真言宗にて、高畑村宝幢院の門徒なり。開基の人を詳にせず。中興は法印融恵といひて、弘治3年入院せしよし寺の旧記に載たり。其余の事跡は傳へず。海誉法印と云ひし僧を後の中興といへり。是は尤後の世の人なれど、堂舎再建せし功あれば、かく称せるなるべし。此人は宝暦3年3月14日寂せり。本堂は4間四方なり。
(新編武蔵風土記稿より)
 や! 初めての紹介文!
や! 初めての紹介文!
 まだやんのか?
まだやんのか? そこ行ったら今日10軒目だぞ
そこ行ったら今日10軒目だぞ
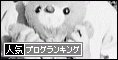
 にほんブログ村
にほんブログ村











 多摩川じゃないのな? でもこの玉川云々ってやつ、ここらに多いから。東海云々よりもメジャーみたいよ
多摩川じゃないのな? でもこの玉川云々ってやつ、ここらに多いから。東海云々よりもメジャーみたいよ












 チャイロ系ちゃんが写経もっていったら、金包まないと受け取らないってとこもあったよな
チャイロ系ちゃんが写経もっていったら、金包まないと受け取らないってとこもあったよな
















