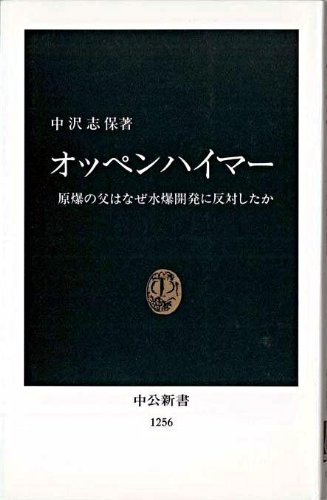猫の目に海の色ある小春かな
及川 貞
「夕方の三十分」 黒田三郎
コンロから御飯をおろす
卵を割ってかきまぜる
合間にウィスキイをひと口飲む
折紙で赤い鶴を折る
ネギを切る
一畳に足りない台所につっ立ったままで
夕方の三十分
僕は腕のいい女中で
酒飲みで
オトーチャマ
小さなユリの御機嫌とりまで
いっぺんにやらなきゃならん
半日他人の家で暮らしたので
小さなユリはいっぺんにいろんなことを言う
「ホンヨンデェ オトーチャマ」
「コノヒモホドイテェ オトーチャマ」
「ココハサミデキッテェ オトーチャマ」
卵焼をかえそうと
一心不乱のところに
あわててユリが駈けこんでくる
「オシッコデルノー オトーチャマ」
だんだん僕は不機嫌になってくる
味の素をひとさじ
フライパンをひとゆすり
ウィスキイをがぶりとひと口
だんだん小さなユリも不機嫌になってくる
「ハヤクココキッテヨォ オトー」
「ハヤクー」
癇癪もちの親爺が怒鳴る
「自分でしなさい 自分でェ」
癇癪もちの娘がやりかえす
「ヨッパライ グズ ジジイ」
親爺が怒って娘のお尻を叩く
小さなユリが泣く
大きな大きな声で泣く
それから
やがて
しずかで美しい時間が
やってくる
親爺は素直にやさしくなる
小さなユリも素直にやさしくなる
食卓に向かい合ってふたり坐る
(詩集『小さなユリと』昭森社・1960年刊)
死刑確定40年、袴田さんは今 再審取り消しの謎を追う
2020/12/12 朝日新聞
最高裁で死刑が確定してから40年間、刑が執行されないまま生き続ける死刑囚がいる。
袴田巌さん(84)。1966年に逮捕され、裁判では一貫して無実を訴えたものの、14年後に最高裁で死刑が確定。12月12日に40年の節目を迎える。
再審決定→釈放→決定取り消し
2014年3月、静岡地裁は、「犯行着衣」とされたシャツに付いた血痕のDNA型が、袴田さんの型とは一致しないとするDNA鑑定などを新証拠と認めて、再審(裁判のやり直し)の開始を決定した。同時に「拘置をこれ以上継続することは耐えがたいほど正義に反する」として、無罪が確定しないまま袴田さんを釈放するという異例の判断をした。
釈放は、逮捕から実に47年7カ月ぶり。長期にわたる収監は、「世界で最も長く収監されている死刑囚」としてギネス世界記録にも認定された。
だが、東京高裁は18年6月、袴田さんの釈放を維持したままこの決定を取り消した。
なぜ、死刑をめぐる司法の判断は正反対に分かれたのか――。
地裁と高裁で何がどのように話し合われ、何が判断の違いを分けたのか。再審請求の審理が原則非公開で行われることもあって、冤罪(えんざい)が疑われるこの事件で、重要なこの二つの決定への理解は必ずしも深まっていないように感じる。4年間にわたる高裁での審理のほぼ全てが、地裁が認めたDNA型鑑定の是非という「科学論争」に費やされたことも、理解の難しさに拍車をかけたように思う。
地裁の決定が出た5カ月後に静岡総局に配属され、その後社会部に移った後も審理の取材を続けてきた筆者自身、新聞の限られた紙面の中でこうした議論の経過を端的に伝える難しさに悩んできた。
地元の人々に見守られて
袴田さんは現在、最高裁の決定を待ちながら、静岡県浜松市内の自宅で姉の袴田秀子さん(87)と暮らす。散歩が日課で、JR浜松駅周辺の繁華街を5時間ほどかけて、ほぼ毎日歩く。半世紀近くも獄中にいて、今も死刑と隣り合わせの死刑確定囚と街中で出会うことが、地元の人には日常になった。
「こんにちは」「がんばって下さい」――。取材をしたこの日も、すれ違う人がときどき声をかける。トレードマークのソフト帽にベスト。小さな歩幅で早足に、やや前かがみになって歩いていく。
長年の拘禁生活の影響で精神を病み、日常的な会話のやり取りは難しいというが、近づいてあいさつすると、軽く帽子を取って応えてくれた。
散歩コースとなっている駅前の商業施設に入る時には、自宅を出る際に秀子さんが手渡したマスクをポケットから取り出して着け、入り口で手指の消毒もする。自動販売機の使い方は釈放後すぐに覚えたといい、この日も何度か、カルピスやエナジードリンクなどの甘い飲み物を買って、ベンチに腰掛けながらゆっくりと口に運んでいた。
4時間半ほど歩くと、あたりはすっかり日が暮れた。歓楽街を足早に通り抜け、アパート4階の自宅がみえる交差点に差しかかると、遅い帰りを心配していたのか、窓からこちらをのぞいている秀子さんの姿が小さくみえた。袴田さんは自宅に続く道をまっすぐに歩いていく。その背中を見送った。
高裁決定からまもなく2年半。最高裁の決定は、いつ出されてもおかしくはないといわれている。最高裁が高裁の決定を支持すれば、袴田さんは再び東京拘置所に収監され、刑の執行を待つことになるとみられる。
「はたからみると散歩をしているようにしか見えませんが、巌の心は獄中のままで、気ままに時間を過ごしてるようにはみえません」。秀子さんは、かつて支援者を通じて発表したコメントで、袴田さんの心の中では今も死刑の恐怖が続いているとし、こう訴えた。「食べたいときに食べ、眠りたいときに眠る。巌が長い間闘って手にした自由な時間を、続けさせてやりたいと思います」
11日に都内であった支援集会で、弁護団の水野智幸弁護士は、「袴田さんの必死の声が届かぬまま40年もの時間が過ぎた。最高裁に正しい判断をしてほしい」と話した。
生きて戻った死刑囚を目の当たりにした地域の人々の多くも、審理の行方を見守っている。(高橋淳)
「私の個人的意見は反対でありました」。日本が戦争に向かった経緯について、A級戦犯が東京裁判で語った言葉を政治学者の丸山真男が書き残している。
自らの考えを「私情」と排し、ひたすら周囲に従うのをモラルとするような指導者の言動を丸山は「既成事実への屈服」と喝破した。
天声人語 20201122
“原爆の父”オッペンハイマーは原爆投下による悲劇を予期することはできなかったのか
公開日:2016/3/12
「科学者は罪を知った。」―これは原爆製造の責任者として原爆開発プロジェクトに立ち上げ当初から関わっていたオッペンハイマーが1947年に行ったスピーチの中で語った言葉である。人類史上至高の科学技術を結集し生み出された原子力という新たなエネルギーが史上最悪の殺戮兵器として人類に牙を剥いた時、彼は一体どのような“罪”を知ったのだろうか。今回紹介する『オッペンハイマー 原爆の父はなぜ水爆開発に反対したか(中公新書)』(中沢志保/中央公論社)では、そんなオッペンハイマーの科学者としての功績、原爆計画責任者という立場のある人間としての罪、そして彼自身の苦悩に関して丁寧な考証がなされている。
1945年8月6日、そして9日。たった一発の爆弾が、人を、家を、街をも飲み込んだ。一瞬の閃光の後、訳もわからぬまま苦しみ命を落とした人が何十万人といたことだろう。そして今もなおその後遺症に苦しむ人が大勢いる。日本人にとって忘れえぬ日となった悲劇の日。オッペンハイマーこそがその日を作り出した張本人であった。これほどまでに残虐で、非人道的な兵器が、なぜこの世に生み出されたのであろうか?
それは第二次世界大戦下におけるナチス・ドイツの台頭に対する恐怖感に端を発するものであると筆者は言う。当時のナチス・ドイツの狂気に満ちた政策や軍事行動の数々は海を隔てたアメリカにもインパクトを与え、アメリカの平和を脅かすものとしてヒトラーは倒すべき存在だという認識がされていた。そして何より「ヒトラーと原爆」という、考えうる最悪の組み合わせを防ぐために科学者たちは躍起になっていたのだという。
ドイツ降伏後、原爆は対日政策の手段としての使用が考えられるようになる。原爆投下の必要性があったのか?ということはしばしば指摘されることだが、アメリカ国内においては「一人でも多くのアメリカ兵の命を救うために必要な手段」という認識がされていたようだ。オッペンハイマー自身も公の場では原爆投下に反対の立場を示すことはなかったが、彼は政府の科学顧問という立場であったから今更原爆投下を止めることなど許されなかったのだろう。本書の中に指摘はないが、自分の研究成果を世に知らしめたいという科学者としての功名心や自尊心もあったのではないかと私は思う。
一方で、原子力が軍事利用されることで人の手を離れコントロール不能なものになるというオッペンハイマーの抱える不安が、この頃の彼の様々な挙動から推察できると筆者は指摘する。そしてその心のうちを象徴するように、対日原爆投下直前の頃には彼は核の国際管理体制の必要性を度々口にするようになる。核の開発競争が始まれば世界は破滅に向かいかねないと警鐘を鳴らし、必要に応じてソ連とも足並みを揃え情報共有をすべきだと彼は主張した。しかし戦後、軍事的優位を確立し他国をリードする立場に立ちたいというアメリカ政府の思惑があり、彼の主張は受け入れられることはなかった。その後アメリカで水爆開発が始められた時、オッペンハイマーは強く反対の意を示した。原爆以上のパワーを持つ水爆は人類には統御しきれないと考えたからであるが、この時もまた政治という抗いがたい大きな波に呑まれ彼の主張が受け入れられることはなかった。
オッペンハイマーが予見した通り、その後の世界は混沌としたものになった。ソ連の核開発による米ソ冷戦突入、ベトナム戦争、冷戦が終結し一段落かと思いきやイラン・イラク戦争、中東では今もなおシリア内戦やISによる武力行使など不安定な状態が続いている。武力に対し更に強大な武力で対抗しても、新たな憎しみの種を産むだけで問題解決には繋がらない。オッペンハイマーはそのことに気付いてはいたものの、政治というしがらみから逃れられず、原爆投下を防ぐことはできなかった。もちろん原爆開発プロジェクトのトップとして彼の責任は問われ続けなければならないが、罪を知るべき人間は他にもいるはずではないのか―直接的な表現こそないものの、そのような筆者の断罪の叫びが行間からヒシヒシと伝わってくる本であった。
文=ヤマグチユウコ
https://ddnavi.com/news/291372/a/
プロミン薬禍による瀕死状態
(加賀田一さん「いつの日にか帰らん」P126~P130抜粋)
私も1949(昭和24)年からプロミン注射を始めました。主治医になられたのが、私と生年が同じで3ヶ月違うだけという若い犀川一夫先生でした。先生も若いし、私も若くて、よく話をし、友達みたいに親しくしていました。先生についてもまとめて第五章「いのち明り」で述べるつもりですが、残念なことについ先年、亡くなられました。
今思えば、先生にしてもプロミンは初めて使う薬剤なのでよくわからないわけです。それで「あんたは169センチ、68キロだから、午前中に3CC、午後2CCと2回注射を打つ」ということになりました。ところが打ち出して1週間したら寒気がして、10日を過ぎると、斑紋が潰瘍になって、頭の毛が抜けて、39度前後の高熱が出ました。衰弱は烈しく、入所者としてよく見ていたハンセン病の末期と同じ症状となり、いよいよ私も死期が近づいたと思いました。
一番苦しんだときは、夜、呼吸が困難になりました。寝ていると鼻がつまって窒息しかかるわけです。呼吸ができない苦しさから逃れるために喉に穴を開けてカニューレを差します。園内には「失明10年、喉切り3年」という言葉がありました。カニューレを差すようになると余命が3年という意味です。
私はちょうどその状態になったわけです。呼吸困難になると、家内は冷ましたお湯をヤカンから洗面器に移し、私はそのぬるま湯の中に顔を突っこんで、苦しいけれど鼻から吸うわけです。そうするとつまっている痰がぬるま湯でだんだんゆるんできて、フッと空気をやるとスポンと抜ける。そんなにスースーとはいかないけれど、ようやく呼吸ができて、これでやっと死と隣り合わせの状態から抜け出せました。
この苦しさというのは末期症状そのものです。失明後の明石海人に「切割くや気管に肺に吹入りて大気の冷えは香料のごとし」の歌がありますが、瀕死のなかで自分の状態を冷静に見つめて優れた歌にしていることに感嘆します。
その頃には足も手もものすごく臭くなっています。斑紋が潰瘍になって、そこから膿がたくさん出てガーゼや包帯をするのですが、すぐに滲み出てきます。重病棟ではハエが追っても追ってもたかります。放置しておくと、ウジがわきます。包帯を取るとウジがいるので、つまんで簡易便器に捨てるのを習慣にしている人もいました。ポトン、ポトンと断続するその音は、趣味を楽しんでいるかのごとく聞こえます。私は衰弱していますから、ほとんど家内がやってくれました。
ガーゼや包帯は洗濯して再生するわけですが、それも患者の重要な作業となっていました。洗濯は普通のお仕着せといっしょだったので、下着だけは自分たちで洗いました。すべてが付添いの仕事だったのですが、私の付添いは全部家内がやってくれました。家内には寒い時期、海に入って貝を取ってきて食べさせてもらったり、ずいぶん世話になっています。
39.5度くらいの熱が続いたときは、呼吸困難の苦しみと全身の潰瘍、脱毛、衰弱に見舞われました。ハンセン病で一番最悪の重傷状態です。喉に大きな穴が七つも開き、膿が出ました。主治医の犀川医師は、「治らなければ結核の瘰癧、治ればハンセン病」と診断され、放射線治療を受けていました。私もたくさんの病人を見てきていますから、自分でも末期症状だとわかります。
そのとき思い浮かんだのが北村くんという同年代の友達のことでした。作業からの帰り、病院に寄って、「おい、元気かい?」と見舞ったことがありました。すると彼が「加賀田くん、わしは今晩六時に死ぬわ」と言うんです。「バカなことを言うな。おまえ、何を言っとるか」と言って帰りました。ところがその夜、連絡があって駆けつけると、「六時に亡くなった」と言います。予言どおりに、本当に亡くなったのです。
それからは人間というのは死ぬ時間まで分かるのかなと思うようになりました。私の命もあと一週間か十日と思って、このままたった一人の母になにも告げずに死ぬのはよくない、最期の知らせだけはしなきゃいかんと思い、約束を破って初めての手紙を出しました。
母とは入園直前に故郷で会って、それから十三年、お互いにそのときの約束を守って音信不通で通して来ました。これまで偽名など使ったことはありません。本名で通してきたのですが、このとき初めて偽名を使って、母に手紙を書きました。1949(昭和24)年のことでした。
回復
「いつの日にか帰らん」P135~P138(一部抜粋)
最初のプロミン注射の副作用でかなりダメージを受けましたが、その後、どうにか回復することができました。犀川先生の診断で「アゴの下に開いた穴が治らなかったら結核、治ればハンセン病。しかし他の人が治ってゆくので、これを続けて行きます」と言われましたが、結果的に治ったので、やはりハンセン病でした。
体調も次第に良くなりましたが、午後は衰弱のため二百メートルある注射室まで行けなくなり、午前中だけプロミンを打つようにすると、全身の潰瘍が目に見えて治って来ました。潰瘍が乾いてきて、カサブタ状のものがはがれると中からきれいな皮膚が現れます。汚れのないその皮膚を見たときは赤ん坊の生まれたての柔らかな肌のように感じました。結局、二回の注射が多すぎたということです。私には一回で3CCの注射が適量だったわけです。過剰投与による薬禍でした。
プロミン注射によって三ヶ月くらいで陰性になった人もいますが、人によって違います。私は菌陰性になるまで四年かかりました。医師に聞くと、どんなによく効く薬でも100%の人に効果があるということはあり得ないそうです。それだけ人体とは複雑で一人一人が違うものなのでしょう。