ある韓国語の記事を見ていたら、次のようなくだりがありました。
옛날 70년대나 쌍팔년도 시절처럼 (昔70年代や双八年度の頃のように)
この쌍팔년도(双八年度) という言葉は初めて見ました。しかし電子辞書にはなく、ネット上で愛用している<NAVER辞典>にも、あるいは<DAUM辞典>や<国立国語院:標準国語大辞典>にもありません。
ハングルでgoogle検索すると約30万件のヒット数で、決して少なくはないのですが・・・。
用例を見ると、「昔」「往時」といった意味だけでなく、「時代遅れ」というニュアンスを込めて使われることが多いようです。
쌍팔년도의 패션(双八年度のファッション)とか、쌍팔년도 개그(双八年度のギャグ)等のように。
詳しく、かつ明解に説明しているのはやはり(ヌルボ愛用の)<ナムウィキ>で、まさにこの<쌍팔년도>の項目がありました。(→コチラ。)
これには、双八年度が西暦何年にあたるかについて次の3説をあげています。
①1955年説
檀紀4288年の年。「88」と8が重なっているので双八です。檀紀は檀君神話に基づく年号で、建国直後の1948年9月公用の年号として 法に定められました。(朴正煕政権下の1962年から西暦が公用となる。) ※西暦年度に2333年を加えると檀紀年度となる。
②1964年説
全然8とは関係ない数字のようですが、8×8=64なので。
③1988年説
一目でわかる「88」。ソウル五輪の開催年。
で、①~③のどれが正しいかというと①1955年。その理由は、朝鮮戦争が終わった直後から使用され始めた言葉だということ。とくに60年代~70年代後半。→コチラの記事によると、朝鮮戦争当時軍人だった人たちが昔話をする時によく使った言葉だそうです。
しかし、これで一件落着かと思ったらそうじゃないのです!
<ナムウィキ>の説明にもありますが、1988年以降に生まれた人が増えてきて(←あたりまえだ。今や全人口の4分の1だとか)、70~80年代も昔の範疇に入るようになり、上記の檀紀もボンヤリとしか知らない人もフツーになってきた今世紀になって、双八年度を1988年と認識している人が増えているということです。さらにこの説明文では、そんな状況にあって、「1955年と1988年のどちらが正しいか」と問うのは無意味で、「前後の文脈から判断すればいい」と記しています。
さらには、쌍칠년도 박통 시절(双七年度・パクトン(朴正煕大統領)の頃)=1977年や、쌍구년도 세기말 시절(双九年度・世紀末の頃)=1999年のような西暦の数字の並びによる派生的な用法も出てきているとか。
たしかに検索してみると쌍칠년도と쌍구년도のヒット数はそれぞれ約3万件と約7万件で、쌍구년도 졸업생(双七年度卒業生)
とか쌍구년도에 제가 가장 좋아했던 가요(双九年度に私が一番好きだった歌謡)といった用例がありますねー。
さて、この双八年度についてはTVのクイズ番組で出題されたこともあるのですね。2012年4月27日SBSの「1億クイズショー」です。
 問題は 「元来<双八年度>とは正確には何年度を意味するものか? ①1955年 ②1988年」です。
問題は 「元来<双八年度>とは正確には何年度を意味するものか? ①1955年 ②1988年」です。
「元来」とか「正確には」という言葉を入れているところが作問者のぬかりがないところ。回答者の表情、ちょっと自信なさそう・・・。
はたして正解できたかは私ヌルボ、番組を見てないのでわかりません。しかしこうしたクイズに出題されるということは、多くの人が一応なんとなくは知っているものの、正確には知らないというレベルだということ。
いやー、今回もちょっとした疑問から新しい知識を得て得した気がします。ふっふ。
옛날 70년대나 쌍팔년도 시절처럼 (昔70年代や双八年度の頃のように)
この쌍팔년도(双八年度) という言葉は初めて見ました。しかし電子辞書にはなく、ネット上で愛用している<NAVER辞典>にも、あるいは<DAUM辞典>や<国立国語院:標準国語大辞典>にもありません。
ハングルでgoogle検索すると約30万件のヒット数で、決して少なくはないのですが・・・。
用例を見ると、「昔」「往時」といった意味だけでなく、「時代遅れ」というニュアンスを込めて使われることが多いようです。
쌍팔년도의 패션(双八年度のファッション)とか、쌍팔년도 개그(双八年度のギャグ)等のように。
詳しく、かつ明解に説明しているのはやはり(ヌルボ愛用の)<ナムウィキ>で、まさにこの<쌍팔년도>の項目がありました。(→コチラ。)
これには、双八年度が西暦何年にあたるかについて次の3説をあげています。
①1955年説
檀紀4288年の年。「88」と8が重なっているので双八です。檀紀は檀君神話に基づく年号で、建国直後の1948年9月公用の年号として 法に定められました。(朴正煕政権下の1962年から西暦が公用となる。) ※西暦年度に2333年を加えると檀紀年度となる。
②1964年説
全然8とは関係ない数字のようですが、8×8=64なので。
③1988年説
一目でわかる「88」。ソウル五輪の開催年。
で、①~③のどれが正しいかというと①1955年。その理由は、朝鮮戦争が終わった直後から使用され始めた言葉だということ。とくに60年代~70年代後半。→コチラの記事によると、朝鮮戦争当時軍人だった人たちが昔話をする時によく使った言葉だそうです。
しかし、これで一件落着かと思ったらそうじゃないのです!
<ナムウィキ>の説明にもありますが、1988年以降に生まれた人が増えてきて(←あたりまえだ。今や全人口の4分の1だとか)、70~80年代も昔の範疇に入るようになり、上記の檀紀もボンヤリとしか知らない人もフツーになってきた今世紀になって、双八年度を1988年と認識している人が増えているということです。さらにこの説明文では、そんな状況にあって、「1955年と1988年のどちらが正しいか」と問うのは無意味で、「前後の文脈から判断すればいい」と記しています。
さらには、쌍칠년도 박통 시절(双七年度・パクトン(朴正煕大統領)の頃)=1977年や、쌍구년도 세기말 시절(双九年度・世紀末の頃)=1999年のような西暦の数字の並びによる派生的な用法も出てきているとか。
たしかに検索してみると쌍칠년도と쌍구년도のヒット数はそれぞれ約3万件と約7万件で、쌍구년도 졸업생(双七年度卒業生)
とか쌍구년도에 제가 가장 좋아했던 가요(双九年度に私が一番好きだった歌謡)といった用例がありますねー。
さて、この双八年度についてはTVのクイズ番組で出題されたこともあるのですね。2012年4月27日SBSの「1億クイズショー」です。

「元来」とか「正確には」という言葉を入れているところが作問者のぬかりがないところ。回答者の表情、ちょっと自信なさそう・・・。
はたして正解できたかは私ヌルボ、番組を見てないのでわかりません。しかしこうしたクイズに出題されるということは、多くの人が一応なんとなくは知っているものの、正確には知らないというレベルだということ。
いやー、今回もちょっとした疑問から新しい知識を得て得した気がします。ふっふ。











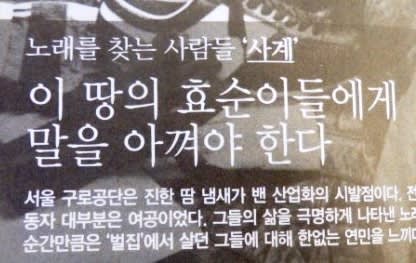
 やっと「ドリ」と「スニ」についてですが、記事中の中見出しに出てきます。
やっと「ドリ」と「スニ」についてですが、記事中の中見出しに出てきます。